たとえば、
「被投的投企」
なーんて、哲学用語を出されるとどんな気持ちがしますかね?
「被投的投企」(ひとうてきとうき)は”20世紀最大の哲学者”と言われた
マルチン・ハイデガーの哲学用語です。
「こんな難しい言葉出されたら、もうお手上げだわ」って
思っちゃいます。
だけど。
それって、分かりやすく言うとどうなの?って見ていくと、
被投的=(この世に)投げ出された(人間存在)
投企=(それを自覚した人間が人生を)積極的に(再構成して)企てる
と。
まだわかりにくいっすね。
もっと噛み砕いてみましょう。
「なんだか知らないけど生まれちゃったね。
これはもうしょうもない。けどさ、いつか死んじゃうんだから。
まあ積極的に生きてくことができるのも人間ってもんさあ」
*「いつか死んじゃう」=先駆的覚悟性(せんくてきかくごせい)
というまた小難しい用語が出てくる
これでどうでしょう?笑
だったら、最初から簡単に言えよ!
ってツッコミたくもなりますが、
まさにその通りで、これ以上の意味はないんですよ。
この程度の教訓では、心屋仁之助さんのほうがまだマシなこと言えますわね。笑
こんな感じで、
「被投的投企」なんて言われると、
もうお手上げって感じですが、噛み砕いてみると
実になんてことない。
今どき。中学生にもこんな説教通じないんじゃないかって
レベルです。
タイトルにあげた「知の陥穽(かんせい=おちいりやすいところ)」
は、まさにココになります。
つまり、哲学的・学問的な”それらしい”用語を使うと、
なんとなく知的に見えてしまうという。
学問の世界はもとより、この手のものは政治評論なんかにもいっぱい出てきます。
知がファッションになっている。
もしくは、反論をさせないための防御服(プロテクター)と言ってもいい。
僕は、真の知というものは、中学生にもわかるように噛み砕いて
説明しても、やっぱり深いもの、
だと思っています。
それができないで、用語だけこねくり回して遊んでいる輩が、
また「反知性主義者」に多いわけなんですけどね…。
カンタンにできないのは、はっきり言えば、用語を駆使している人自身が
頭があまりよくないからです。
*ただし、なんでもいつでも簡単に言えばいいってもんでもない
のも事実。専門用語はショートカットキィのようなものなので、
専門用語を使うと議論が早く進む面があります。
あるいは、中途半端な理解のまま、なーんとなく書いている。
別なところで、「僕らはマーケティングに取り囲まれている」
と繰り返し言っているんですが。
この、「知のマーケティング」にも注意したほうがいいですね。







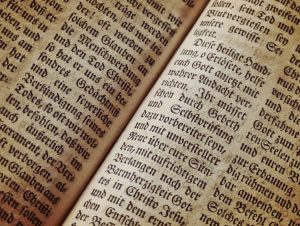

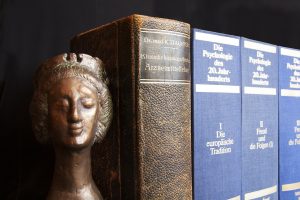

コメント