仏教では、よく”中道”という言葉を使いますが、これは簡単そうでいて、実はなかなか難しい概念です。
中道でいちばん有名なのは、釈尊(ゴータマ・シッダールタ)が成道(悟りを開く)前に発見したとされる”不苦不楽(ふくふらく)の中道”でしょう。
比丘たちよ、出家したる者は、二つの極端に親しみ近づいてはならない。その二つとは何であろうか。
愛欲に貪著することは、下劣にして卑しく、凡夫の所行である。聖にあらず、役に立たないことである。
また、苦行を事とすることは、ただ苦しいだけであって、聖にあらず、役に立たないことである。
比丘たちよ、如来は、この二つの極端を捨てて、中道を悟った。それは、眼を開き、智を生じ、寂静・等覚・涅槃にいたらしめる(『阿含経典2』増谷文雄編訳「如来所説」より)
これは、”苦楽中道(くらくちゅうどう)”とも言います。
この場合、たとえば以下のような説明が常道であるかと思われます。
「釈尊は成道される前に、”苦楽中道”に入られました。すなわち、極端な苦行・難行には悟りの因はないとし、また一方、歓楽に満ちた生活にもやはり悟りの因はない。苦と楽の中道にこそ、悟りの道はあるのだ。この修業における中道こそがまさに”不苦不楽の中道なのです」
といったふうでしょうか。
もちろん、この説明は正しいとは思うのですが、読後感としてどこか、「ふーん…」という手応えにならないでしょうか?
けっこう、「平凡な発見」というと仏陀に失礼なので、「まあ、奥深いのだろうな」となんとなく理解したつもりになってスルーしていくというパターンです。
本記事では、儒教やアリストテレスにおける”中庸”と仏教の”中道”の違いに触れつつ、「仏教でよく出てくる”中道”。難しそうな易しそうな、でも結局、よく分からない”中道”」の意味を分かるように解説していきたいと思います。
なお、”苦楽中道”については別記事で詳述していますので、興味のある方は参考になさってください。
*参考記事:”苦楽中道 ”の意味を分かりやすく説明するー ミクロとマクロの悟りへ
論語・アリストテレスの”中庸”と仏教の”中道”
”中道”と”中庸”は混同されやすい概念で、意味的には少し重なっているところもあるものの、その本質において違いがあります。
以下、儒教とアリストテレスにおける”中庸”にざっと触れつつ、仏教の”中道”について考察を深めていきます。
儒教における”中庸”
”中庸”という言葉は、儒教の四書の一書である『中庸』で説かれていますが、初出は、『論語』における下記の言葉です。
子曰わく、中庸の徳たるや、其れ至れるかな。
民鮮(すく)なきこと久し(書き下し文)孔子がおっしゃいました、
中庸(節度を守る事)の徳には至上の価値がある。
しかしそれに従う人々は近頃少ない。(現代語訳)
「どちらにも片寄らない中庸の道は徳の最高指標である」が、実践する人は少ない…と孔子は嘆いています。

要するに、”中庸”は、かたよることのない”中”をもって道をなすという意味ですね。
「考え方・行動などが一つの立場に偏らず中立であること。過不足がなく、極端に走らないこと。古来、洋の東西を問わず、重要な人間の徳目の一とされた」(大辞林より)
アリストテレスの「中庸」
アリストテレスは”メソテース”という言葉でそれを倫理学上の一つの徳目として尊重しています。

”メソテース”という言葉そのものは本来、「中間」という意味ですが、英語で、”Golden mean”と翻訳され、それが日本語では儒教を援用して”中庸”と訳されたのです。
アリストテレスによれば、倫理的な徳は「超過と不足を避けた行為」=中庸を選ぶことにあるとし、その中庸とは「バランスの取れた状態であり、釣果も不足もしていない状態。
たとえば、「無謀と臆病の中間が勇気」であるなどの例を挙げています。
「緊緩中道」を手がかりに仏教の”中道”を考える
さて、儒教やアリストテレスの”中庸”の定義から行くと、冒頭に挙げた仏教の”不苦不楽の中道”と意味的には変わらなくなってしまいそうです。
それでは、”中庸”と”中道”にはどう違いがあるのか?
結論的に言えば、”中庸”というのは「極端を離れ、ほどほどであること、その状態そのものが望ましい」ということです。「ほどほどである状態そのものが、君子(人格者)らしい在り方」ということですね。
一方、”中道”のほうは、”中庸”的な意味も結果的には含まれていますが、じつは「中道に入って得られる果実」にまずフォーカスしていくのです。
実際、”不苦不楽の中道”の発見というものは、その発見自体が目的なのではなく、「悟りを得る」ことが目的であったはずです。
その「悟りを得る」という果実を得るために、「結果的に程よい在り方」が探求され、そのポイントを”中道”と呼んでいるわけですよね。
仏典からひとつ例を挙げてみましょう。
あるとき、ソーナという僧侶が悟りを得ることができない焦燥に苦しんでいるのを仏陀が見かねて、以下のようにアドバイスしています。
「ソーナよ、どう思うか。もしあなたの琴の弦が張り過ぎたならば、琴の音色は快く妙なる響きを発するだろうか?」
「いいえ、そうではありません、大徳(釈迦)よ」
「ソーナよ、どう思うか。もしあなたの琴の弦が緩すぎたならば、琴の音色は快く妙なる響きを発するだろうか?」
「いいえ、そうではありません、大徳よ」
「ソーナよ、どう思うか。もしあなたの琴の弦が張りすぎず、緩すぎもなく、丁度よい度合いを持っていたら、琴の音色は快く妙なる響きを発するだろうか?」
「そのとおりです、大徳よ」
「ちょうど同じように、ソーナよ、行き過ぎた努力は高ぶりを招き、少なすぎる努力は懈怠を招く。それゆえソーナよ、あなたはちょうどよい努力を保ち、感官にちょうど良いところを知り、そこに目標を得なさい」(犍度大品 5,16-17)
この「琴の弦」の例で言えば、「程よい弦の張り方」ということで、これは”中庸”とまったく同じことを言っているようにも聞こえます。
しかし、そもそも、「ソーナはなぜ焦っていたのか?」「仏陀はアドバイスすることによって、ソーナに何を期待していたのか?」を考えてみると、これは、”悟り”という果実、結果にまずフォーカスしていますね。
琴の弦で言えば、「程よい張り方」という状態そのものが目的であるのではなく、「美しい音色を出す」という結果の方にまずフォーカスしているわけです。
そしてその「美しい音色を出す」という結果を得るためにちょうどよい「弦の張り方」が探求されていく、という順序になっています。

まとめてみましょう。
- 中庸:ほどほどであるという”状態”にフォーカスする。その状態自体が望ましい(君子の道/倫理学上の徳)
- 中道:ある”目的”にフォーカスし、その実現のためのほどよいベストなポイントを探る
という違いです。
上記の琴の弦の喩えは、”緊緩中道(きんかんちゅうどう)”と呼ばれています。
「不苦不楽の中道」- 中道を”弁証法”として把握する
さて、”中道”というものが、「まず結果にフォーカスし、つぎに最適のポイントを探る」ということが分かりました。
次に、「中道に入る前」と「中道に入った後」を比較して、何がどう変わっているのかをチェクしつつ、”中道”のさらに深い意味を探っていくことにします。
冒頭に挙げた「不苦不楽の中道」を例に挙げてまいりましょう。
ここには、
苦⇔楽
という緊張関係が見られます。
それでは、「悟り」という結果を得た場合、この”苦”と”楽”はすべて消滅してしまうことになるのでしょうか?
結論的に申し上げると、じつは、中道においては「苦と楽それぞれの”本質”」は保存されているのです。
より詳しく申し上げますと、
”苦”つまり、「苦行・難行」の状態を否定はしているものの、”苦”における「己に厳しくある」という”本質”は活かされていることに気づきます。
一方、”楽”つまり、「歓楽に浸っている」状態は否定されているものの、”楽”における「幸福感を求める」という”本質”は活かされていることにも気づきます。
”中道”は、左右の両極端それぞれの夾雑物=役に立たないもの=”非本質的”なものを捨象しつつ、”本質”は保存されていく、ということです。
そして本質を保存しつつ、(不苦不楽の中道で言えば)、「悟りを得る」という新しい次元に突入していくわけです。
これは、じつは西洋哲学で言うところの”弁証法”にきわめて近い、と言いますか、むしろまったく同じことを言っていることに気づきます。
*参考記事:ヘーゲルの弁証法を中学生にもわかるように説明したい
こちらの参考記事では、「ガラスコップの喩え」で解説しています。
ガラスコップは、真上から見ると円形に見えます。一方、真横から見ると長方形(あるいは台形)に見えます。断面図的には、ですね。
ここで、
円形⇔長方形
という緊張関係、矛盾が発生しています。
ところが、「ガラスコップである=円筒形である」という概念のもとでは、「上から見れば円形だけど、横から見れば長方形である」というふうに、両極端の本質概念は捨象されずに活かされていることに気づきます。

さらに言えば、円形と長方形というのは二次元の概念ですね。一方で、円筒形というのは三次元の概念です。
つまり、ここで「次元上昇」が起きているわけです。
さきほどの、不苦不楽の中道で言えば、”苦”の本質部分である「己に厳しくある」というところと、”楽”の本質部分である「幸福感を大切にする」というところを保存しつつ、”悟り”という新しい概念に次元上昇しているわけです。
このように”中道”というものを弁証法として考えていくと、すごく理解が深まります。
仏教における”中道”というのは、むしろ、”中道的発展”(=弁証法)として理解したほうが良い、ということになります。
「断常(だんじょう)の中道 」- 仏教学から永遠の生命を検証してみる
さて、では上述したことを踏まえつつ、応用問題として「断常の中道(だんじょうのちゅうどう)」を考えてみます。
仏教書を漁っていると、「釈尊は、常見(じょうけん)を否定したので、魂はありません」とはっきり書いてある本が多いことに驚きます。
”常見”とは何か?と言いますと、文字通り、「常なる見解」=「変化しないという見解」ということで、具体的には、「死後も変わらずに魂がずーっと続いていく」という見解のことです。
この”常見”の否定からすれば、たしかに一見、釈尊は死後の生命、魂を否定したともとれそうです。
しかし、実際は、仏陀・釈尊は「断常の中道」を説かれた。すなわち、断見と常見の二つの両極端を否定されたわけです。
- 断見…死ねばすべてなくなる(断たれる)という見解
- 常見…死後も変わらず(常に)存在するという見解
この2つを共に否定して、中道の立場を取られたということですね。
ここからいくと、「死後の生命、魂を否定」すると”断見”になってしまうことが分かります。
これでは仏教は単なる唯物論になってしまいます。つまり、「断見に陥っている」状態です。
この点に関して仏教学では、「魂はないけれども、業の潜性力(せんせいりょく)があって…それが輪廻して、…」と、難しい理論に取り込む方向へいきます。
業の潜性力とか、いろいろな言い方をしても、要は、「なにか、今世で作り上げた心のクセのようなもの存続する」ということですよね。
これは言い方を変えただけで、
やっぱり、「一定のアイデンティティをもった生命エネルギーが存続する」ということには変わりはないわけです。

こういう難しいことを言うよりも、単純に「魂はある」と考えたほうがスッキリと筋が通ります。
なので、”断常の中道”で言えば、
- 断見…死ねばすべて終わり(断たれるという見解)、というのは誤り
ということになります。
しかし、それなら一方の”常見”が問題になりそうです。
つまり、「永遠の生命というのは、常見になってしまうのでは?」という意見がでてくるでしょう。
しかしこれは「まったく変化せずに、常なるものとして存続する」というのが誤り、という意味であるのです。
分かりやすく言いますと、
「昨日のあなたと今日のあなたは、続いていますか?断たれていますか?」という例ですね。
これは、「あなたという一定のアイデンティティをもった存在が昨日も今日も続いている」という意味では”常見”です。続いています。
しかし…、昨日のあなたと今日のあなたでは、肉体細胞も多少入れ替わっていますし、髪や爪もちょっとは伸びていますよね。
また、今日は新しい本を読んだり、新しいニュースに接したり、友人と会ったり…で、昨日にはなかった知識があったりすることもあるでしょう。
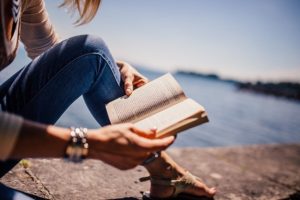
場合によっては、一日で価値観が変わってしまうこともありえます。
そのように、あなたという存在も常に変化のなかにありますので、
- 常見…まったく同じ状態が続いていく(常であるという見解)、というのは誤り
となるのです。
つまり、
「変化はしている(=常ではない)が、あなたという一定のアイデンティティを持った存在が消えてしまうわけではない(=断ではない)」
ということです。
「肉体がなくなっても(=死んでも)、あなたというアイデンティティを持ったエネルギーは存続する。つまり、いわゆる”魂”は存在する。しかし、生前とまったく同じ存在形態ではないし、住む世界も違うし、価値判断の変容を迫られることもある」
というふうに、魂やあの世を認めてもきちんと矛盾なく、”断常の中道”を説明できるのです。

もっと長期視点で考えれば、
来世・来来世と生まれ変わってまた地上に生まれてきたら、名前も肌の色も変わってしまいますからね。
長い輪廻転生の過程では、ずいぶんと価値観も変わってきますので、「あなたというアイデンティティ」も常に、変化の中にあるということになります。
先に述べた”弁証法”あるいは”中道的発展”で言えば、
”断見”からは、「常に変化の中にある」という本質を抽出し、”常見”からは「生命エネルギーが存続していく」という本質を抽出して、「死後の魂の存続」「永遠の生命」という新次元の概念をきっちり説明できる、ということになるわけです。
*参考記事:仏教は霊魂を否定していない – 無我説解釈の誤りを正す
以上、応用問題として、”断常の中道”から、仏教学のミスを指摘してみました。
八正道が”中道”と言われる理由
仏教では、「中道とは八正道である」と言われることもあります。
これはまずは仏陀の最初の説法、初転法輪(しょてんぽうりん)に根拠があります。
仏陀・釈尊は、上述の”不苦不楽の中道”を説いた後、以下のように続けます。
比丘たち、では如来がはっきりとさとったところの、人の眼を開き、理解を生じさせ、心の静けさ・すぐれた知恵・正しいさとり・涅槃のために役立つ中道とは何か。それは八つの項目から成るとうとい道(八正道、八支聖道)である。(相応部諦相応)
ここから、中道イコール八正道であることが分かります。説法どおりに理解するとそういうことですね。
それでは、なぜ中道がイコール八正道であるのか?より深く考察してまいりましょう。
さきに、中道とは弁証法もしくは”中道的発展”と理解したほうが良い、というお話をいたしました。
実際に漢訳の”中道”の原義を探ってみると、
- 中:極端の二辺を離れて矛盾・対立を克服すること(弁証法と同じですね)
- 道:そのための実践の方法
という意味であるのです。
仏教(仏法)というのは単なる哲学ではなく、やはりあくまで宗教です。宗教であるということは、理論だけではなく、実践が伴います。実際に「道をたどる」ということです。

たとえば、”不苦不楽”の中道においても、上述したように理論的・理性的に理解することも大事ではありますが、あくまで本当の目的は、「自分自身が中なる道に入り、実際に悟りを得ていく」という実践論ですね、ここに重点があるわけです。
そしてその実践論あるいは方法論の中心に位置するのが”八正道”というわけなのです。
八正道は、文字通り、8つの項目がありますが、それらはバラバラに併置されているわけではなく、1番目の正見から8番目の正定まで論理的につながっています。論理的であるということは、”縁起”でもあるということなのですけどね。
*参考記事:八正道の意味と覚え方のコツ – 一発で覚えられる語呂合わせ
一番目の正見すなわち「正しい見解」が具体的に展開していくと残りの7項目になると理解してもよいのです。あるいは、”正見”の内容が残りの7項目である、と言っても良いでしょう。
要するに、正しい見解=仏法を具体的に体得していく道、悟りの道が八正道であるということですね。まさに、”道”すなわち実践行です。
ここにおいて、八正道がなぜ中道と言われるか?お分かりになられたかと思います。
「己自身をつねに弁証法にかけて発展させていく(認識力の獲得)が中道である」と言っても良いでしょう。ここが単なる哲学・形而上学との違いなのです。
「仏教は宗教ではなく、哲学である」と主張する人もいますが、やはりそれは違います。少なくとも理論的な理性(純粋理性)という意味内の哲学には収まりません。実践的な理性(実践理性)まで射程距離に入っているということです。




コメント