今回のテーマ、「無我」については、仏教において最大に誤解されている概念のひとつだろうと思います。それは、現代でもそうですし、過去の仏教史でも幾度も出てきた問題です。
その誤解とは、「仏教は無我を説いたのだから、死後の存在、霊魂を否定した」という考え方です。
つまり、「死んだら無になる」という考え方ですね。現代のお坊さんや仏教学者でもこのような考え・立場を取る方々がたくさんいらっしゃいます。
しかし、「死んで何もかもなくなる」のであれば、それは唯物論であり、宗教ではなくなってしまいます。
世界三大宗教のひとつに数えられる仏教が、「無霊魂説」であるとすれば、これは何ともおかしな話だと言えるでしょう。
また、伝統仏教の僧侶であっても、「霊魂を信じていない」のに葬儀やお盆の先祖供養などを執り行っているとしたら、これは詐欺的なことではないかと思われます。
参考までに、PRESIDENT Onlineの「7つの仏教法人に送った質問状「霊魂は存在すると考えるか?」否定派の意外な”言い分”」記事では、7つの宗派のうち、半数以上が霊魂否定派か、霊魂について積極的に考えない立場をとっているようです。
霊魂を信じていない人は死後、どうなるか?
現実的な問題として、あの世や霊魂を信じていない人は死後、ストレートに天界へ還ることはできません。
あの世は「認識がすべて」の世界ですので、「あの世なんかない、霊魂など存在しない」という認識でいる人にとっては、実際にそのような世界が展開しているのが事実です。
つまり、あの世にすら還れずに、不成仏霊・浮遊霊になって、地上を徘徊し、場合によっては憑依霊となって、この世の人に取り憑いてさまざまな悪さをしている人も多いのです。
とくに科学万能主義に毒されて、確信的に「絶対にあの世、霊魂など認めない」と頑張っている人の魂を鎮魂するのは容易ではないのが実情です。
あるいは、「どうやら自分は死んだらしい」と認めた霊であっても、霊的次元の知識がゼロの状態では、やはり行き場がなく、仕方なくお墓や位牌、骨壷などにしがみついているパターンもあります。
そういう意味では、現代では「お葬式もお墓も要らない!」などという風潮が出てきておりますが、葬儀をきっかけに何とか霊的な自己に目覚めるケースもありますので(というか、そのぐらいしか縁(よすが)がないので)、きちんと法要を営むということも大事なのです。
また、この世の生活においても、「あの世も霊魂もない、死んだらすべてが終わりだ」と考えている人は、「では、生きているうちにやりたいように生きていこう」というふうに刹那的な快楽主義に流れるか、もしくは、ペシミスティックな悲観主義に流れるか、どちらかの方向へ行きがちなのです。
唯一なることわりを逸脱し、偽りを語り、彼岸の世界を無視している人は、どんな悪でもなさないものは無い。(「ダンマパタ」176)
そして、そうした価値観で生きた人は死後、天国的な世界に還ることは非常に難しいと言って良いでしょう。
功利主義的に考えたとしても、死後の世界を認めたほうが、より良く生きることができるのです。
そもそも来世や霊魂を前提としない思想は宗教としての前提条件を放棄している状態であると言えるでしょう。そして、そうした「実質を欠いた宗教」は決して倫理的基礎を持つことができないということを忘れてはいけないと思います。
なぜ、無我=霊魂がない、という論理にすり替わったか?
正木晃氏は著書『「空」論 空から読み解く仏教』(春秋社)において、現代における「無我=霊魂がない」説の起源をつきとめていらっしゃいます。
該当箇所を引用させて頂きます。
その背景には、1930年代前後に、当時の仏教学を主導する立場にあった東京大学インド哲学科の宇井伯寿(ういはくじゅ/1882〜1936)が「無我説」とは、「我がない」という意味であり、「我」は霊魂を意味しているので、「無我説」はすなわち霊魂の否定であると主張したのです。
なにしろ、当時における仏教学の最高権威がそう主張したのですから、その影響は絶大でした。以来、日本の仏教学では「ブッダは霊魂の存在を否定した」という学説が主流になりました。
そして、正木氏は、『サンユッタ・ニカーヤ』には、仏陀(ゴータマ・ブッダ)が死後におけるなんらかの存在を認めていたとしか思えない記述が、少なくとも2つあることを指摘していらっしゃいます。
上掲のご著書はわりあい専門性の高い本で初心者の方が読むのには難しいところが多いですが、興味のある方は一読をお勧めいたします。
現代の仏教学・仏教界に流れている毒水は、正木氏が指摘されている通りの起源であると思われます。
*ちなみに、2千数百年前、インドの部派仏教の時代にも「説一切有部(せついっさいうぶ)」という部派が中心になって、無我を実質的な唯物論に仕立て上げてしまいました。
今回の小論では、正木氏とはまた別の角度、「有無の中道」「断常の中道」から無我説をめぐる魂の問題を考えてみたいと思います。
ちなみに、社会学者の橋爪大三郎氏は、とあるサイトでこの問題について、「仏教は、一神教と違って、思想の自由があります。どう考えてもいいのです」などと書いていますが、そんなことはありません。
仏教にはたしかに教義解釈的にもおおらかなところがありますが、三法印、縁起の法、中道…など、教義の軸はしっかりとありますので、「どう考えてもいい」などということはあり得ないのです。
アートマンとアナートマン
梵我一如(ぼんがいちにょ)の思想
まず、”無我の思想”が説かれた経緯からご説明しましょう。
仏教以前のインドの思想では、バラモン教(ヴェーダの宗教)の”梵我一如(ぼんがいちにょ)”の思想が主流でした。
”梵”とはいわゆる”梵天”のことですね。”ブラフマン”といいまして、バラモン教の最高神です。
その「ブラフマンと”我”=自己とはその本質においてひとつである」、これが梵我一如の思想です。
ここの”我”というのがサンスクリット語で”アートマン”と言います。
我(自己)=アートマン、というのは、ふだんの私たちのいわゆる”自分”というのではなくて、自己意識の最も奥深いところにある真我(しんが)のことを言っています。
つまり、私たち=我の本質を掘り下げていくと、真我・アートマンに突きあたり、そのアートマンは本質において宇宙の根本原理であるブラフマンと同質であるという思想、それが梵我一如です。
釈尊はその梵我一如の思想へのアンチテーゼとして、”無我”を説いたのでした。無我はサンスクリット語で”アナートマン”と言います。
ちなみに、バラモン教は現在のヒンズー教の大本になった宗教です。バラモン教が次第にインドの土着の信仰を吸収しつつヒンズー教になっていったのです。

梵我一如は”悉有仏性(しつうぶっしょう)”と同じ!?
ところで、大乗仏教に慣れ親しんでいる私たち日本人から見ると、梵我一如の思想を釈尊が否定したのは不思議な感じがしませんか?
というのも、仏教には”悉有仏性(しつうぶっしょう)”という思想があり、これは、「私たちはその本質において、仏と同じ性質を持っている」という考えですね、これは先の梵我一如とほとんど同じ思想ではないか?と思われるからです。
このような仏教思想を”仏性論(ぶっしょうろん)”、あるいは、”如来蔵思想”と言いますが、じつは(学問的な)仏教史においては、釈尊の同時代ではなく、大乗仏教の時代に入ってから出てきた思想と言われています。
そうすると、仏教は、釈尊の仏教から部派仏教の時代を経て、大乗仏教の興隆に伴い、もともと否定していた梵我一如とほぼまったく同じ思想、仏性論に行き着いたことになります。
しかし、それでは、仏陀・釈尊は”仏性論”を説かなかったか?というと、そんなこともありません。
仏陀は「人はだれでも、修業によって自己を磨き、執着を断つことによって、阿羅漢(アラカン)になることができる」と説いていたわけですから、これは実質的には仏性論と同じことなのです。
したがって、大乗仏教において出てきた仏性論・如来蔵思想はむしろ、釈尊の真意へ立ち返るという原点回帰の意味合いが強かったと言えるでしょう。
真なる改革運動はかならず復古運動の側面を持ちます。
たとえば、16世紀ドイツのマルチン・ルターは「聖書のみ」「信仰のみ」「恩寵のみ」といったシンプルイズムで宗教改革を起こしましたが、これもキリスト教の原点回帰・復古運動の側面が強いですよね。
明治維新も、「ご一新」というイノベーションでありながら、「王政復古」を謳っていました。
大乗仏教も同様に、少なくとも運動の中期くらいまでは「仏陀の真意に帰ろう」という復古運動の側面を持っていたわけです。
なぜ、釈尊は無我を説いたのか?
さて、それでは、なぜ釈尊は無我の思想を説いたのでしょうか?
それは、当時の梵我一如の思想が形骸化して、「我は偉い!」といった(とくにバラモン=司祭階級の)傲慢さにつながっていったからです。
ちょうど、イエスの時代の律法学者たちが律法をたてに自らを高みに上げ、差別を生み出していたのと同じ構図です。
インドには今もむかしもカースト制度がありますよね。
カースト制度は、大きくは、バラモン(司祭階級)、クシャトリア(武士階級)、ヴァイシャ(平民階級)、シュードラ(使用人階級)と身分を分ける思想ですが、これらの身分は生まれながらに決まっていて変更は不可だったのです。

これに対して釈尊は、「人の偉さ・価値は生まれによって決まるのではなく、思いと行為によって決まるのだ」という、いわば”機会の平等論”を打ち出していったわけです。
因果応報(縁起の法)というものを、身分ではなく、「人としての価値」へ転換したのです。
そして、その過程で、バラモンの思想の中核であるところの”梵我一如”、アートマンの思想に対して、アナートマン・無我の思想をぶつけていったという経緯があったのですね。
「あなたががたは”自分を偉し”として自己というものを大事に思っているが、その自己というのは何であるのか?自己などというものは、それ自体では存在することもできない儚いものではないか」と釈尊は主張したのです。
これが無我の思想が説かれた経緯です。
ちなみに、ですが、仏教は13世紀頃にインドからほぼ姿を消すことになりますが、現代のインドにおいては、仏教に改宗する人が少しずつ増えているようです。
実質的になかなかカースト制度を打ち破れない状況に対して、仏教の平等思想が見直されているのが理由で、こうした運動は”ネオブッディズム”と呼ばれていますが、これは思想的になにか新しいものがあるわけではなく、ひとつの政治運動ですね。
当サイト「ネオ仏法/Neo Buddhism」とは名前は同じですが、関係はまったくありません。
”無我”か”非我”か?
釈尊としては、「自己への執われ」を打破するために無我の思想を説いていたわけなのですね。
ただし、”無我”と翻訳すると、どうしても冒頭で述べたように、
無我⇢我がない⇢霊魂はない
という流れに行きがちであることも、一見したところの論理の流れとしては成立するように思われても仕方がないところもあります。
仏教学の世界的権威である中村元氏は、「アナートマンは無我ではなく、”非我”と解釈すべきだ」と主張していらっしゃいました。
非我、つまり、「我にあらず」ということですね。
中村元氏が主張した”非我”というのは、修行の主体であるところの”自己”はむしろ積極的に認めつつ、一方では、「偽物の我」「煩悩に囚われてしまう我」を釈尊は否定したのだ、これがアナートマンの思想なのだ、という説です。
たしかに、この”非我”の解釈のほうが釈尊の真意を説明できているように私にも思われます。
ただ、非我の解釈はちょっとした妥協案といいますか、「で、結局、”非我”と言っても、霊魂はあるのか?ないのか?」の答えにはなっていませんよね。
”我”は有るのか、無いのか? – 「有無の中道」で考える
正見が点検できているか
さて、冒頭の宇井伯寿のような考え方をする人はですね、
「無我」を追求した結果、「霊魂はない」という結論に達したというよりも、「霊魂を信じられない/信じたくないから、無霊魂に結びつくような無我解釈に飛びついた」という順序なんだろうな、と思います。
ここにある態度は、まず「自分の価値観が、同時代の先入観・偏見から自由になっているか?いったん白紙に戻せているかどうか?」という点検、つまり、八正道の出発点である「正見(しょうけん)」の点検が不十分である、ということになると思います。

そして、高僧や高名な学者であっても、その「初歩」に引っかかっているケースが多いわけです。
先入観や偏見を排する方法については、また別の角度から書いた記事がありますので、下記をご参照ください。
*参考記事:”イドラ”の意味とは? – フランシス・ベーコンの英知に学ぶ
自灯明/犀の角のようにただ独り歩め
まず、出発点として、「我が有るのか?無いのか?」という論点を考えてみます。
「無我」という言葉を字句通り読めば、「我がない」というふうに読めます。
なので、単純に、「我がない」という方向に行くのも分からないでもないです。
しかし、我(われ)=自己がまったくナッシングであるのであれば、修行する主体もナッシングということなので、仏道修行そのものが成り立ちません。
釈尊の遺言(涅槃経)では、自灯明・法灯明(じとうみょう・ほうとうみょう)が説かれています。これは、釈尊亡き後は「自らを拠り所とせよ」「法を拠り所とせよ」という意味です。
無我=自己がナッシングであるならば、「自らを拠り所とせよ」などと説くはずがありません。
また、スッタニパータという経典では、「犀の角のようにただ独り歩め」という有名な一節があります。美しい詩句です。
「これは執着である。ここには楽しみは少く、快い味わいも少くて、苦しみが多い。これは魚を釣る針である」と知って、賢者は、犀の角のようにただ独り歩め。『ブッダのことば―スッタニパータ』 (岩波文庫)中村 元 (翻訳) より抜粋

*参考記事:「犀の角のようにただ独り歩め」は誤訳なのか?本当の意味は?
これも、無我=自己がナッシングであるのであれば、「ただ独り歩め」ということは成り立たなくなります。
三明を得た
仏陀は降魔成道を経て、三明(さんみょう)を得たと経に明確に書かれています。
三明とは、
- 宿命明(しゅくみょうみょう):自他の過去世のあり方を自由に知る
- 天眼明(てんげんみょう) :自他の未来世のあり方を自由に知る、
- 漏尽明(ろじんみょう):煩悩 を断って迷いのない境地に至る
の3つです。
「過去世のあり方」「未来世のあり方」ということですので、これは明確に輪廻転生を認めています。そして、輪廻するためには当然、輪廻する主体がなければいけません。
参考までに、「天眼」に該当する箇所を見てみましょう。
われは種々の過去の生涯を想いおこした。……われは清浄で超人的な天眼をもって、もろもろの生存者が死にまた生まれるのを見た。すなわち、卑賤なるものと高貴なるもの、美しいものと醜いもの、幸福なものと不幸なもの、としてもろもろの生存者がそれぞれの業に従っているのを見た。(『阿含経』)
「もろもろの生存者が死にまた生まれるのを見た」とハッキリ書かれています。
専門の仏教学者とあろうものが素人でも判断できる霊魂の存在をどうして見過ごしているのか、不思議なくらいです。
有無の中道で考える
なので、無我についても、「我が無いと書いてあるのだから、霊魂も無いだろう」と単純に考えるのではなく、ここでもやはり中道で考える必要があると思います。
全てにおいて中道で考えること。これが仏教解釈のオーソドックス(正統)です。

すでに、「ワンネス、仏教、宇宙。そしてネオ仏法の悟りへ」の記事で、「実在と現象」について考察してきました。
私たち一人ひとりは「一個の現象」ですので、時間において無常。存在において無我です。
肉体も精神も刻々と変化していきますし(無常)、肉体ひとつとってみても食べ物や空気など他の存在と相依って成り立っています(無我)ので、「実体としての存在ではない」というふうには言えるわけですね。
釈尊が無我を強調した最大の理由は、「自我意識に基づいた執着が苦しみの原因であるので、それを断ち切るため」という実践的なものです。
この場合の「自我」は、実在の一部であるという意識から離れ、かつ、他の現象とも繋がっているという意識からも離れてしまった我、ということになります。
独立した自我意識においては、かならず「存在の根源的な不安」が引き起こされます。

その「存在の根源的な不安」を一時的に緩和しようと、人は「リア充自慢」などで、他者への相対的優位を必死で求めていくわけですが、それは根本的な解決にならない。
なので釈尊は、苦しみの根本を断ち切るためには、自己というものを「全体(実在)や他者(現象)と独立した自我と捉えるべきではない」という根本的な存在論を説いたのです。
そしてそれは存在論であるとともに、強力な実践論でもあります。
このように、
- 実在の一部を担い、一定の個性・アイデンティティを持っている存在という意味では「有る」
- しかし、実在や他者から切り離された独立した実体ではありえないという意味では「無い」
という「有無の中道」ですね、これが正統の解釈だと思います。
「五蘊の仮和合(ごうんのけわごう)」についてはどう考えるか?
無我を唯物論に結びつける説のひとつに「五蘊の仮和合」というのがあります。これも仏教書によく出てきます。
五蘊というのは、色受想行識(しきじゅそうぎょうしき)の5つで、人間の構成要素を分解したものです。
- 色…肉体
- 受…感受作用
- 想…表象作用
- 行…意思作用
- 識…認識作用
この5つの要素が「仮に和合している」存在が人間なので、和合がなくなれば(=死ねば)雲散霧消する、それが無我であるという考えですね。
しかし、「仮に和合している」という意味では、今この瞬間もキッチリ和合しているわけじゃないです。
時々刻々と肉体も、心・精神の内容も変化していますよね。
なので、「五蘊の仮和合」もあくまで、「現象としての我は実体ではない」という執着を断つための実践的な教え、と捉えるべきです。
魂は有るのか?無いのか?- 「断常の中道」で考える
「毒矢のたとえ/無記」は根拠にならない
仏教書を読むと、「釈尊は死後の存在や形而上学的な論議を避けた」ということで、
- 毒矢のたとえ
- 無記(むき)
を根拠に挙げる著者が多いのです。
「毒矢のたとえ」というのは、
ある時、マールンキャプッタという人が釈尊に「死後も生命は存続するか?」「宇宙は無限か有限か?」…などを尋ねたところ、
釈尊は、「毒矢が刺さっているのに治療以外のことを考えていたら、毒が回ってしまう。まず矢を抜かなければいけない」というたとえ話をしました。
これは、「宇宙がどうした〜」とかの話は今、問題にすべきではない。そんなことを考えているうちに人生は終わってしまう。それよりも、「自己の生死の問題の解決」がまず先決である、ということなのですけどね。
これをもって、「釈尊は形而上の問題に関わらなかった」と主張している仏教書が多いのです。
しかしこれは、「釈尊があの世や霊魂を否定した」ということではなく、マールンキャプッタという人の特性を考えて対機説法をした、と捉えるべきです。

無記(むき)というのは、「記さず」ということですが、これも、「仏陀は形而上学的な論議について沈黙をした」という意味です。
この無記というのも「毒矢のたとえ」と同様で、やはり対機説法的に「無記」を貫いたこともある、という意味に解釈すべきです。
インドでは今も昔も「あの世や霊魂、輪廻」などはだいたいみな認めていたわけですよ。また、インド人は形而上的な議論がとても好きな民族なのです。
そうである以上、霊界や霊魂について、あるいは形而上の議論にあまり深入りした説法は行う必要はない、ということなのです。説法の対象者によっては、ただの趣味的論議に陥ってしまうからです。
上述のマールンキャプッタという修行者がそういうタイプであったので、仏陀・釈尊は「対機説法的に」毒矢の例えを語ったり、無記を貫いたと。そういうことなのです。
現代のスピリチュアルでも、いくらでもこういう問題があります。
「アトランティスがどうした」とか「23次元がどうこう」などと考えるよりも、まずは、自らの実存の問題として生死を乗り越えなければいけない、ということですね。
対機説法というのは、「個人の機根に合わせて説法する」というのが普通の解釈ですが、「時代や地域性に合わせて説法する」というのも大きくは対機説法の一環なのです。
施論戒論生天論がウソになってしまう
そもそも、釈尊の次第説法として、まずは「施論戒論生天論」がありました。
- 施論(せろん)…施しをして、
- 戒論(かいろん)…戒めを守れば、
- 生天論…天界に生まれることができる
というシンプルな説法です。
あの世や魂を否定してしまったら、「生天論」がまるっきり嘘になってしまいますよね。霊魂がなければ、「生天する主体」がなくなってしまいます。
いくら方便とはいえ、「不妄語戒」を説いてる仏教が基本説法でウソを説く、という解釈はあり得ないと考えるべきです。
*不妄語(ふもうご):「ウソをつくなかれ」という戒め。五戒の一つ。
したがって、仏陀・釈尊の基本教説に照らし合わせてみても、「仏教は霊魂を否定した」という断定は論理的にミスがあります。
断常(だんじょう)の中道で考える
なので、ここでもやはり中道で考えましょう。「断常の中道」です。
肉体の死を迎えると魂がなくなる、というのは明らかに断見、断滅論です。
「釈尊はいかなる意味でも死後の永遠不滅の魂などは認めなかった、常見を否定した」などと書いてある仏教書が数多くあります。
わざわざ、「常見外道」などという言葉まであります。
しかしここに言葉の微妙なすり替えがあります。「永遠不滅の魂」というところです。
魂が死後も存続しても、それは「変わらない」ということとイコールなのでしょうか?なぜ、断言できるのか?
魂も「現象」として、死後も変化していくわけです。無常でかつ無我です。
なので、死後の魂があるからイコール常見、という等式は明らかに論理的なミスがあります。
「魂は継続しつつ、変化する」という解釈で十分に断常の中道にかなっているのです。

ゆえに、結論としては、
「魂があっても無我説とは抵触しない。むしろ、霊魂を否定すると断見に陥ってしまうので、それは仏教とは言えない」ということです。
仏教、いや宗教とは倫理の基礎をなすものです。来世や霊魂の存在なくして倫理の正当性は担保できません。なんとなれば、来世がないのであれば(人生が今世限りであるのならば)、因果の理法は完結しないからです。「善行を行って何の得がある?」という世界になってしまいますよね。
霊魂・来世を信じられるからこそ、善因楽果・悪因苦果に確信を持つことができるのです。
もう一度、ダンマパタの言葉を味わってみましょう。

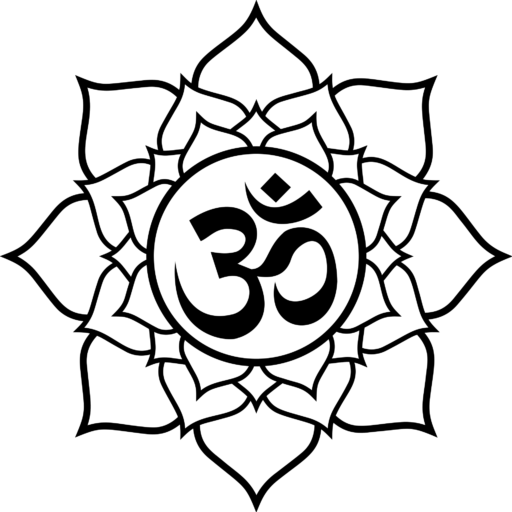











コメント
コメント一覧 (2件)
>khushさん、
コメントありがとうございます♪
よく勉強されていますね、私などよりはるかに仏教にお詳しいのではないでしょうか?
しかしながら、khushさんのご主張は、文中で言及している宇井伯寿説の繰り返しになってしまうと思います。
>中道という視点は、あくまでも、この世に存在し、相対的に対立している事象について、それらを包摂する抽象度の高い視点があるということで、
断常の中道は、断見と常見の問題を扱っていますので、やはり魂と来世に関わってきていると思われます。
魂がないとすると、やはりそれは断滅論に陥ってしまいます。
そうすると、三論(施論戒論生天論)などで主張されている、「天界に赴く主体」はいったい何であるのか?
それを魂と呼ぼうが、阿頼耶識と呼ぼうが、単に言葉・名称の問題になってしまいますが、
要は、「自己同一性を保っている(変化するものであるにせよ)何者か」を想定しないと説明がつかなくなってしまいます。
純粋形而上学的には、カントなどが主張している通り、死後の世界や生命は結局は証明ができないのですけれども、
あくまで「仏教」という範疇で見るならば、「天界に赴く」「地獄に赴く」という表現は仏典の中にたくさんありますので、
それらの説明がつかなくなってしまいます。
>釈迦は永続的な魂の存在を否定した、しかし、釈迦の死の1000年後に仏教の看板を掲げる人たちが、潜在意識の存在と、その永続性を主張した」
ということなのではないでしょうか。
初期仏典に魂と来世を肯定する文言がたくさんあります。
たとえば、『ダンマパダ(法句経)』ひとつを読んでも、そうした来世についての記述が山のようにあります。
ある人々は[人の]胎に宿り、悪をなした者どもは地獄に堕ち、行いの良い人々は天におもむき、汚れの無い人々は全き安らぎに入る。(126)
生きとし生ける者は幸せを求めている。もしも暴力によって生きものを害するならば、その人は自分の幸せをもとめていても、死後には幸せは得られない(131)
二節、引用しましたが、他にも来世に言及している箇所が他にもたくさんあります。原テクストにこのようにキッチリ書かれているのですから、やはり後世の人が勝手に主張したとは言えないのではないでしょうか。
もしこれらが方便だというのであれば、方便であることの立証が必要になります。テクスト論的にはそうなります。なので、縁起説を援用しても断滅論(断見)に抵触する無霊魂説のほうがむしろ強引であると思われます。
これらは「そのまま」受け取るべきだと思います。すなわち、魂はあり、来世もある、ということで、魂のあり方については、記事中で述べているように、「断常の中道」にて、(個人的には)解決がつけられていると確信しております。
結局、魂や来世を否定するということは、端的に言えば、「死ねば何もかもなくなる」ということですが、
そのようなことを主張する人は、そこらへんのオジサン、オバサンでいくらでもいらっしゃいます。
「アジアの光」と呼ばれた釈尊がその程度の思想であったとは到底、思えません。
少なくとも、私には信じられません。
お世話になっております。
このサイトの中観の説明は、非常にわかりやすかったです。
しかしながら、最終的にスピリチュアルな方向に行くことに
なっているからかもしれませんが、このセクションの進め方は、
少々、強引な気がします。
無我が縁起論からくるものである以上、
人が「自分だ」と思っているものは、
生まれてからこのかた、他者との因縁によって形成されたものであり
生まれる前から持っていたものではないという主張であり、
加えてアナートマンという、アートマンの否定の主張をしているのですから、
釈迦は「ありてあるもの」は存在しないという意味で、
生死を超える魂の存在を否定したと解釈するべきです。
また、「人は誰でも阿羅漢になれる」とは、誰でも「目覚めた人」になれる
という意味で、生死を超えて存在する「仏性」が人の中にあるという
根拠にはなりません。
それから、「有無の中道で考える」ですが、中道という視点は、
あくまでも、この世に存在し、相対的に対立している事象について、
それらを包摂する抽象度の高い視点があるということで、
この世に存在しない事象(存在の真偽を問う問題)、
例えば、天動説と地動説の対立などでは、
両者を包摂する視点はないのではないでしょうか。
そういう意味では、アートマンの存在の真偽も
中道的考察には適さない問題だと思います。
ただ、大乗仏教で悉有仏性と主張しているのは事実ですし、
そのための理論として、阿頼耶識や阿摩羅識の存在も主張しています。
そうなると、それらの意識は一人一宇宙なのか、共有意識なのかとか
色々な説が存在することになりますが、
結局のところ
「釈迦は永続的な魂の存在を否定した、しかし、釈迦の死の1000年後に
仏教の看板を掲げる人たちが、潜在意識の存在と、その永続性を主張した」
ということなのではないでしょうか。