ほほゑみに肖てはるかなれ霜月の火事のなかなるピアノ一臺
読み方:ほほえみににてはるかなれしもつきのかじのなかなるぴあのいちだい
作者・出典:塚本邦雄・『感幻楽』
(「羞明・レオナルド・ダ・ヴィンチに献ずる58の射祷」より)
***
僕の一番好きな歌人、塚本邦雄(つかもとくにお)の作品。
塚本邦雄は、戦後の、いわゆる「前衛短歌運動」の旗手として活躍していた方です。
***
旧仮名遣いの上に、漢字が正字(せいじ)です。
ピアノ一臺=ピアノ一台
ということになります。
って…。
いま使われている漢字は正字の簡略体で、
戦後、GHQの占領政策の一環として、常用漢字
→当用漢字(=現在の漢字)になったことを知っている人が
もう少なくなっているのでは…?
旧仮名遣い(歴史的仮名遣い)を新仮名遣いに改めたのも
同じ流れです。
GHQの狙いとしては、文字を断絶させることによって
日本の伝統・歴史を分断して、
”黄色い猿”を再教育する、という狙いだったんでしょうな。
***
僕は、「ほんとうは、美しくて、無駄なものが好き」
といつか書きました。
これ、塚本邦雄が言いそうな言葉だなーと検索してみたのですが、
見つからず。
でも、やはり掲出歌のような歌にインスパイアされてるんだな、
とあらためて思った次第です。
***
霜月(=旧暦11月)の”冷”、火事の”熱”の対比、
それから、
ピアノの”黒”と、火事の”赤”の対比。
映像としておそろしく美しい。
が、
おそろしく、無駄。笑
上の句の「ほほゑみ」は連作のタイトルから分かるんですが、
レオナルド・ダ・ヴィンチの「モナリザ」ですね。
謎の微笑。
微笑しているのか、微笑していないのか。
あるいは、なにに微笑しているのか。
微笑しているとして、
この、「おそろしく無駄で美しい」ものに、
微笑しつつ、「はるかなれ」(=永遠なれ!)
と刻印を押している、退廃の美。
(こういったデカダンスに惹かれれてしまうのが
女房との共通点のひとつか?)
***
前衛短歌というのは、いろいろな観点から
論じられますが、こうした暴力的なまでの
反倫理性も特徴のひとつとして挙げられます。
歌集タイトルの『感幻楽』も「管弦楽」を
もじりつつ、
まぼろしこそ真なるもの
と歌いあげた塚本邦雄の矜持が感じられます。



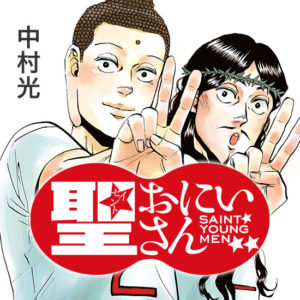
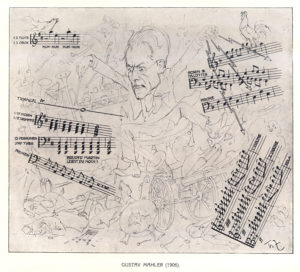






コメント