今回は、クラシック音楽の作曲家・指揮者であるグスタフ・マーラーについて論じていきたいと思います。
検索で当記事にたどり着かれた方は驚かれるかもしれませんが、マーラーは霊格的には、菩薩界上段界の存在であり、芸術家としては最高峰のひとりであると私は類推しております。
*当サイト(ネオ仏法)は、スピリチュアル的要素を加味した宗教哲学系のサイトです
マーラーの交響曲の、今日(こんにち)における演奏頻度は「ベートーヴェンを超えた」ほどの人気ぶりです。
マーラーはその巨大な交響曲において、全宇宙すなわち<全体>を音響的に把握しようとした作曲家であり、それでいて数多くの心打つ<実存>的な歌曲を残しています。
全世界が実際にそこに映し出されるような巨大な作品を考えてごらん。 ー そこでは人は、いわば宇宙が奏でる一楽器に過ぎないのだ(アンナ・フォン・ミルデンブルク宛の手紙より)
「人は、いわば宇宙が奏でる一楽器」という言葉は、”全体の中の個”としての人間。
さらに、あえて踏み込んで言うならば、「”実在”の自己展開のイチ”現象”としての人間”」という人間観を見て取ることができると思います。
第三交響曲においては、岩などの無生物から、植物、動物、人間、さらには天使まで登場させていますので、マーラーが<全体の中の一楽器>として把握している射程距離は、じつにさまざまな存在に及んでいる、と言えるでしょうね。
このように、グスタフ・マーラーという音楽家は、
- 宇宙・世界という”全体”すなわち<実在>を把握しようとした(おもに交響曲において)
- <実在>の一部である<現象>としての個の在り方を表現している(おもに歌曲において)
という意味において、真理への眼差しとトータル性を重視した「哲学者的芸術家」であると考えられます。
マーラーの音楽がなぜ偉大か?まず思いつくまま、いくつかポイントを挙げておきます。
- 交響曲で宇宙<全体>を表現した
- 歌曲で個の<実存>を表現した
- 交響曲と歌曲はモチーフ的に深い関連があり、<全体>と<実存>(ネオ仏法用語では、<実在>と<現象>)の両者を総合している
- (3.に関連しますが)分裂と総合を同時に表現している、いわば<絶対矛盾的自己同一>の音楽である
- これらのことは”意図的に”作曲されており、思索家・哲学者としての資質が高い。すなわち、ハイレベルな真理価値を芸術に込めることに成功している
- マーラー個人の資質は、強靭な精神力の持ち主であり、死をまっすぐ見つめる強さ、それを作品に昇華するしなやかさを併せ持っている
- 指揮者としては、ヴィーン宮廷歌劇場の監督を10年務めており(”帝王”カラヤンでさえ8年)、現代に続くさまざまな改革を断行した「ブレない」成功者
- ゆえに、芸術だけでなく、現実処理能力・戦略的思考能力もかなりのレベル、むしろ、「あつかましい」と言っていいくらいのレベル。
…といったふうに、べた褒め気味です(笑)。
これらのポイントについては、また後ほど、詳述してみたいと思います。
強靭な精神力の持ち主である「成功者」マーラー
このような巨大・偉大な作曲家ではあるのですが、マーラーについては長らく、
- 不遇であった
- 極度に死を怖れていた
- 分裂症であった
- ユダヤ人として、異邦人として、アイデンティティ問題に揺れていた
…等といったマイナーな捉え方をされてきました。
私はマーラーの交響曲を聴くにつけ、このようなマーラー論にずっと違和感を感じていたのです。
前島良雄氏がその著作『マーラー 輝かしい日々と断ち切られた未来』で、これらの旧来の見解を見事に論破しておりますので、興味ある方は一読をお勧めいたします(当記事の引用文は、とくに断りがない限りはこの著作からの引用です)。
本の帯には、
不遇でもなく、
死の影に脅かされたものでもない、
輝ける音楽家人生。
と書かれています。
詳しくは、前島氏の著作をお読み頂ければ、と思うのですが、まずは、マーラーについてのネガティブな先入観について、上記4つの論点に沿いつつ、簡潔に整理(反駁)しておきましょう。
マーラーは不遇ではなかった
まず、指揮者としてのマーラーは、音楽界の頂上まで登り詰めています。ヴィーン宮廷歌劇場の監督を10年務めており(”帝王”カラヤンでさえ8年)、位人臣を極めたと言っても良いでしょう。
マーラーが断行した”改革”は現代に至るまで音楽界に貢献するものとなっております。
魑魅魍魎が跋扈する、と言っても良いヴィーンの楽壇で改革を断行できるというのは、これは、強靭な精神力の証でしょう。
伝統とは怠惰のことだ。君たちが「伝統だ」と主張していることは、「今までどおりにやって楽をしたい」という意味でしかない。
作曲家としてのマーラーも、指揮者としてほどではないものの、同時代においても称賛をもって迎えられています。
多くの交響曲は、同時代において初演され、とくに第二交響曲、第八交響曲などは大成功を収めています。
マーラーは”死”をまっすぐに見つめる強さを持っていた
マーラーの交響曲は、その楽章単位まで含めると、たしかに”死”をテーマにしたものが多いのは事実です。
それをもって、「マーラーは死を極度に恐れていた」という言説がながらく常識になっていました。
しかし、”死”をテーマにできるということは、まず、”死”というものを客観的にまっすぐ見つめる必要があります。
多くの人間は、死という現実をみつめる勇気を持っておりません。ハイデガー的に言えば、”頽落(たいらく)した状態にあり、そして、日々むなしい”空談”でもってごまかしをしているのが平均的な人間なのです。
仏教の開祖釈尊も、悟りの出発点においては、”生老病死の真理”をまっすぐに受け止め、その後、これら”苦”の克服に取り組んでいます。
死をまっすぐに見つめ、かつ、楽曲のテーマとし、しかも偉大な交響曲にまとめあげられるというのは、弱さではなく、これも強靭な精神の証しであるのです。
マーラーは、分裂・矛盾を弁証法的に総合した
マーラーが分裂症気味であった、というのもよく語られるところです。
交響曲のなかでも、高貴な旋律が続いている矢先に、突如、俗っぽい旋律に変わったりします。
しかし、曲としてまとめ上げられるということは、(ましてや、演奏時間においても長大です)、単なる分裂の寄せ集めではなし得ないことです。
とても哲学的な言い回しになりますが、「分裂・矛盾を抱えたまま、より高次の統一体へと進む”絶対矛盾的自己同一」を成し遂げているのが、マーラーの作品なのです。
マーラーがそうしたことを確信的に行っていたことを伺わせる、マーラー自身の言葉があります。
*散歩中に、クロイツベルクのお祭り騒ぎにでくわしたときの言葉
聴いてみろよ。これがポリフォニーだ。ぼくはこうしたところからポリフォニーを手に入れているのさ。……まさにそのように、各テーマはまったく違った方向から聞こえてこなくてはいけないし、リズムや旋律もまるっきり違ったものでなくてはならない。ただ、芸術家がそれを互いに調和して響きあう一つの全体に組織化し、統一するだけのことだ
グスタフ・マーラー個人についても、分裂症云々と言われることもありますが、これはフロイトの診察などを受けていることに由来しているのでしょうか。
しかし、上掲の前島氏の著作には以下のように書かれています。
この時の会見は、フロイトも旅行先にことであったので、「診断」というものではなかった。ましてや、「精神分析」などと呼べるようなものではなかった。だから、フロイト自身もきちんとした形で「グスタフ・マーラーの症例」などという文章を書き残していないのであろう。(p274)
マーラーは、複雑なアイデンティティを”強み”にできた
マーラーの複雑なアイデンティティについて、よく引用されるのが、下記のマーラー自身の言葉です。
僕は三重に故郷のない人間だ。オーストリア人のなかではボヘミア人として、ドイツ人の中ではオーストリア人として、そして全世界の中ではユダヤ人として
しかし、どうもこの文句は”出来すぎ”な感じがします。
この言葉は、マーラーの妻アルマの『回想と手紙』に出てくるものなのですが、アルマのこの著作の内容が信憑性に欠けるものであることはいまや常識です。
仮に上記のとおり、マーラーが語っていたとしても、これは言葉としてあまりに劇化されすぎており、むしろ、マーラーの自己プロデュース戦略の一環なのではないか、と思われるほどです。
前島氏が前掲書で指摘しておりますが、そもそも、このような何重な意味で「故郷がない」ひとは、世界中にいくらでもいるのです。マーラーに特殊な事情であるわけはありません。
マーラー音楽の”偉大性”の分析
つぎに、マーラーの作品そのものの偉大性について、いくつかのポイントに分けて論じてみたいと思います。
芸術作品の価値を決めるのは、まず第一段階としては、当該作品に込められた「真理価値」によります。
芸術作品の価値、芸術家の”霊格”については、下記の記事をご参照下さい。
*参考記事:芸術と哲学の関係 – イデーの模倣としてのアート
全宇宙をまるごと音符に置き換える気概と作品
これは、マーラーの交響曲から明らかに聴き取れるものであり、また、マーラー自身の下記の言葉も残っています。
全世界が実際にそこに映し出されるような巨大な作品を考えてごらん。 ー そこでは人は、いわば宇宙が奏でる一楽器に過ぎないのだ(「アンナ・フォン・ミルデンブルク宛の手紙」より)
とくに、第三交響曲にこうした気概が読み取れます。
第三交響曲は、岩(無機物)→植物→動物→人間→天使、というふうに段階を追って、神の愛に至ります。
また、こうしたいわば”空間的な”宇宙と言うだけでなく、自身の潜在意識を経た集合意識への遡行の試みも見られます。
死の直視と克服(復活)
マーラーについては、死をテーマにした楽曲・楽章が多いためか、「死を過度に恐れていた」という記述がなされることが多いですが、私はそうは思いません。
上述しましたが、「死を見つめることができる」のはむしろ勇気です。
また、それを楽曲化できるのは、相当な精神力が必要でしょう。
第一交響曲の第3楽章では、死が戯画化されています。葬送行進曲を民謡『マルチンくん』(ドイツ名)の旋律を引用しつつ展開していきます。
*『マルチンくん』はフランス民謡『かねがなる』という名称で、日本でも紹介されています。一聴すれば、だれでも聴いたことがある旋律です。
本来、厳粛であるべき(とされている)葬送行進曲を戯画化する、いわば相対化することによって、死を別の角度から見つめ直すことが促されてくるようです。
第二交響曲の第1楽章は、もとのタイトルは『葬礼』でした。しかし、第4楽章以降は、”復活”の讃歌へと至ります。
じつは、キリスト教理解の最大ポイントは、まさに”復活”にあると言っても過言ではないのです。
*参考記事:イエス・キリストの”肉体の復活”は本当か?アストラル体で解読する
キリストの復活に与ることが死の克服とイコールとされているからです。
第二交響曲、最終楽章のエンディングは教会の鐘の音が鳴りひびきつつクライマックスを迎えますが、ここは聴いていると鳥肌がたつほど感動させられます。
第五交響曲の第1楽章も葬送行進曲です。
出だしのトランペット「パパパパーン!」のメロディーは、メンデルスゾーンの『結婚行進曲』からの引用とされています(これも、聴けばだれでも知っているメロディーです)。
それとともに、この「パパパパーン!」は、ベートーヴェンのやはり第五交響曲『運命」のモチーフとリズムが同じです。
生と死が裏表一体であることを表現しているように思われます。
『大地の歌』も死がテーマでありつつ、同時に”再生”をも謳っています。
『大地の歌』終局のメロディーは、第九交響曲冒頭に引き継がれています。ここにも、死と再生(復活)のテーマが見て取れるように思われます。
絶対矛盾的自己同一の音楽
私としてはマーラーを超絶に偉大な芸術家として捉えているのですが、マーラーの音楽はやはりとっつきにくいのも事実です。
- 交響曲一曲聴くのに一時間半はかかる
- 美しい旋律が続いて酔いしれていると、突然、”俗っぽい”旋律が現れ、裏切られた気分になる(かもしれない)
このように、<高貴さ>と<俗っぽさ>が一見、乱雑に同居しているがゆえに、「分裂症である」などと言われるわけですが、たんに分裂しているだけでは、音楽的カタルシスを得ることはできないはずです。
聴き手がカタルシスを感じるのは、聖と俗の二項対立を、矛盾でありながら同時に両立させるという、<絶対矛盾的自己同一>が表現されているから、というのが私の見解です。
「違う!交響曲は一つの世界のようなものでなければならない。すべてを包摂するものでなければならない。」(シベリウスとの議論より)
こうした<絶対矛盾的自己同一>の表現も、「世界をまるごと把握しようとした」マーラーに相応しいものです。
マーラーを「分裂症的だ」とのみ分析し、それに基づいてマーラー交響曲を評価していると、なぜマーラーが交響曲第8番を自身の最高傑作と考えていたのか、分からなくなってしまいます。
第8番についてマーラーは、ウィレム・メンゲルベルクに宛てた手紙で以下の通り述べています。
私はちょうど、第8番を完成させたところです。これはこれまでの私の作品の中で最大のものであり、内容も形式も独特なので、言葉で表現することができません。大宇宙が響き始める様子を想像してください。それは、もはや人間の声ではなく、運行する惑星であり、太陽です。
これまでの私の交響曲は、すべてこの曲の序曲に過ぎなかった。これまでの作品には、いずれも主観的な悲劇を扱ってきたが、この交響曲は、偉大な歓喜と栄光を讃えているものです。
このように、マーラーは多くの交響曲において、自覚的にあえて悲劇や分裂を扱ってきたことが分かります。気質に流されていたわけではないのです。
モノフォニーとポリフォニーの総合 – 実存と普遍
モノフォニーとは単旋律の音楽のことです。
イメージしやすいのは、グレゴリオ聖歌ですね。大勢で歌っていても、単旋律であればモノフォニーです。
対して、ポリフォニーとは複数の声部からなる音楽のことです。
イメージしやすいのは、バッハでしょう。複数の旋律が絡み合う面白さがありますけれど、現代の私たちからすると、「主旋律はどれ?」と若干、戸惑うところもあるかもしれません。
モノフォニーはシンプルであるがゆえに、個の<実存>を表現しやすい形式だと思います。
一方、ポリフォニーは様々な存在が五線譜のなかで自己主張しつつ、全体では調和しているような…いわば、<実在>の世界観を表現するのに適した形式でしょう。
とくに宗教改革期以降は、聖歌においては、「一般の信者がすぐに覚えられて歌いやすい」ということで、モノフォニーに戻ってまいります。
しかし、単旋律よりもう少し面白みを、ということで、主旋律に和声を載せていく形式ですね、これをホモフォニーといいます。
主旋律と伴奏ですので、主役がわかりやすく、かつ、装飾もされている美しさがあります。
バロックから古典音楽(いわゆる”クラシック”)、そして現在のポップスなどは、このホモフォニーが主流です。
ただ基本的にはモノフォニーの拡大形式ですので、<実存>を表現するのに適した形式でしょうね。
私たちが現在、耳にするのはほとんどこのホモフォニーの音楽です。
モノフォニー、ホモフォニーが<実存>を表現するのに適している、ということは、言い換えれば、「自我」の音楽形式でもあります。
この文脈からいうと、ポリフォニーは<全体>とか<神仕組みの世界観>を表現するのに適している、いわば「無我」の音楽形式ですが、存在ひとつひとつの個性が埋没してしまう傾向があるのは否めないでしょう。
前置きが長くなりましたが、マーラーの面白さは、このホモフォニーの<実存>とポリフォニーの<全体>が同時存在しているところにあるように思われます。
マーラーを聞いていると、軍楽隊のリズムやメロディーがけっこう出てきます。
これは、マーラーの幼少期に、オーストリア軍の兵舎が近くにあって、しょっちゅう軍楽が聴こえていた影響らしいのですけどね。
実に不思議なことに、こうしたマーラーの特殊的な体験を音符化したものが、それを聴く人にも、潜在意識へと遡行させる感覚を引き起こす力があると思われることです。
少なくとも、私には、「懐かしく」思われます。
個の<実存>を深堀りしていくと、むしろ<普遍>へ至るという証左であり、マーラーはこのことを知悉していたと思うのですね。
オススメの指揮者、オケについて
マーラーに限らず、クラシックの曲を紹介すると、「オススメの指揮者と交響楽団は?名盤は?」という話になりそうです。
じつは、私はプロのオケできっちり演奏されているのであれば、どの演奏でもそれなりに良いと思いますし、感動します。
これを言うと身も蓋もない話ですが、指揮者やオケの談義って、それ自体が自己表現めいているところがあると思っていまして、個人の趣味判断を、絶対の価値判断にすり替える議論が多いように思えます。
また、ポピュラーミュージックと違って、20世紀以降は20世紀以前に比べると、相対的にクラシックの新曲が少ないですよね。その上に、CDやDVDで再体験できる、というメリットもあります。
なので、指揮者やオケを問題にしないとクラシック業界が食っていけない、という側面もあるのかな、と思っています。
私個人は、作曲家と演奏者の功績は互角ではなく、作曲家が9割、残りの1割が演奏者、という割合がせいぜいではないかと。本音を言えば、ほぼ9.9割が作曲家の偉大さによっている、という意見です。
なので、プロの指揮者とオケできっちり演奏されているものであれば、何でもOKというのはそういうわけなのです。
当サイト(ネオ仏法)がオリジナル・革新を重視していますので、どうしてもクリエイター寄りに肩を持ってしまう、という面もあるのかもしれませんが。
ただ、本記事で書いてきたマーラー解釈によれば、交響曲第二番の「復活」も第八番の「来たれ、聖霊よ」も、マーラーの屈折とか妥協ではなく、本音でテーマとしていることになります。
そうすると、マーラー指揮者で有名なバーンスタインの解釈は微妙な位置づけになってしまいます。
彼は、オリジナルでユダヤ教的な主題の曲をけっこう書いていますので、キリスト教的な”普遍神”はおそらく信じていない、ゆえに、復活も聖霊も信じておらず、「これも、マーラーの屈折の一環」として捉えているのではないでしょうか?
そうであれば、バーンスタイン盤はまずはお勧めから一番に外れることになります。
しかし、「プロであればどれでもいい」で済まされるのもなんだか…ということであれば、私は、クラウディオ・アバドの演奏をベストとしてお勧めしたいです。
たとえば、交響曲第4番は、「クラシックのソナタ形式へのアイロニー」と捉える向きがありまして、たしかにそれはそうだろうと思うのですが、私には、さらにそのアイロニーを包み込む(真の意味での)「天上の愛、安らぎ」が感じられます。
マーラー自身の神理解は、ゲーテの汎神論的見解に傾倒していたようで、実はこれは、ネオ仏法的には「かなり真理」であるのです。
なので、交響曲第4番で、ペテロなどをおちょくるような歌詞があったとしても、それは伝統的なキリスト教理を超える、真の意味での抽象化された「キリスト」教理解がマーラーにあったのだ、と思うのですね。
したがって、アバドの第4番を聴いたときの「屈託のなさ」はよく聞かれるところでありますけれど、それは、アバドがこの曲に込められた真意をより深く汲み取っているということではないかと思うのです。
まあこれは一例ですけれどね。
ただアバドの演奏は好悪はともかくとして、公平に見てアバドは「中道路線」であるとも言えるでしょうから、「とりあえずマーラーを聴いていみたい」という方にとっても、最初に聴く演奏家としてお勧めできるのではないかと思っています。また、ずっと聴き続けられる演奏ではないかとお勧めしたいです。
以上、すごく書きすぎたようで、ぜんぜん書き足りず、また、駆け足で書いてしまいました。
この論考は思いついたことがあり次第、追記していきますね。

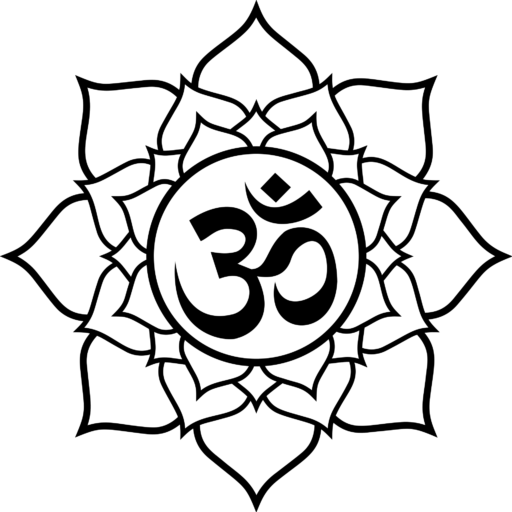


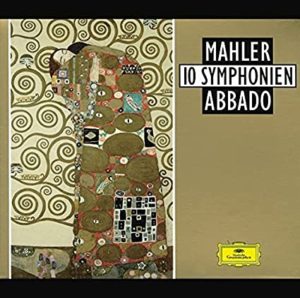








コメント