風鈴を鳴らしつづける風鈴屋 世界が海におおわれるまで
作者・出展:佐藤弓生・『世界が海におおわれるまで』
以下、掲出歌は全て同作家・同出典
掲出歌、
下の句は、ノアの洪水か、まさにこの世の終わりを思わせる情景ですが、不思議と切迫感がないですね。
それは上の句の、”昭和的とも言える風景”と”世界の終わり”を等価にしてしまっていることにもよると思われます。
多くの人類が絶望の慟哭にあるなか、詩人には風鈴の音が聞こえています。
「一水四見」(同じ水でも見る人によって違ったふうに見えること、
存在は認識によって規定されるという仏教哲学用語)とはまさにこのこと。
世界の終わり。
鎮魂歌には、風鈴屋の風鈴がふさわしい、と、詩人は観じている。
それは、アルファでありオメガである永劫の時間からみれば、地球のひとつの文明のおわりなど、なにほどのことであろうか、という問いかけであるかもしれません。
おびただしい星におびえる子もやがておぼえるだろう目の閉じ方を
初句六音。
ほんとうは恐ろしいグリムの童話、じゃあないですが、子どもの感性は私たち大人が想像するようなファンシーな世界だけではなく、本当は、世界の全体性をありのままに受け取っているのでしょう。残酷さもしかり。
しかし、いつしか私たちは、自我の目覚めとともに見ぬフリを覚え、やがてはフリをしていたことすらも忘れてしまうのかもしれません。
それは、見ていても目を閉じているのと同じこと。
真の詩人のみが、目を開けつづけていられるのです。
うつくしい兄などいない栃の葉の垂れるあたりに兄などいない
「ない」と否定されると、「ある」ように思えてしまう逆説。
平安末期の歌人、藤原定家の、
見渡せば花も紅葉もなかりけり浦の苫屋の秋の夕暮れ
「なかりけり」と否定されることによって、かえって花(桜花)と紅葉の幻影が一瞬浮かび上がってくる。
そして、幻影の宴のあとに一転、寂れた夕暮れがやってくるのです。
この幻影は、平安末期〜鎌倉初期における、王朝文化の最後の煌めきであるかのようです。
掲出歌の雰囲気、私はなぜか萩尾望都的な世界を感じてしまいます。
コーヒーの湯気を狼煙に星びとの西荻窪は荻窪の西
この歌は、友人の死への挽歌(ばんか・死を悼む歌)連作中の作品です。
星びと=友人のことです。
夜にコーヒーを入れているさりげない場面。湯気のゆくえに空を見上げると、夜空に星が見える。
星はかつての友人が自らをうたった歌詞(うたことば)であったことを、ふと詩人は思い出します。
西荻窪は、そのかつての友人が住んでいた場所なのでしょう。
しかし、今はとおい友人を思うとき、”西荻窪”はもはや地名ではなくなるのです。
”西”、とはそもそもなんであるのか?
こんな、いい大人がもう考えることもないようなことを考えてしまうのが哲学者であり、感じてしまうのが詩人です。
どこまでが”西”なのか、問いかけてみれば、子どもの頃「宇宙の果て」を想像してくらくらとしたことを思い出します。
ここにおいて、”西荻窪”はもはや地名ではなく、形而上の空間(死者の憩う場)に変化(へんげ)しています。
それはそのまま、逝ってしまった友人へのレクイエムになっているのでしょう。
空のあの青いしげみに分け入って分け入ってもう火となれ ひばり
種田山頭火の、
分け入っても分け入っても青い山
の本歌取り(本句取り?)ですね。
山頭火の句が、どこまでも続く閉塞感があるのに対して、作中主体(歌の主人公)は、「そうであるならば、いっそ火となれ」と歌いあげています。
それも、山ではなく、天上を目指して。
ひばり、は作者自身の願いの投影でしょう。
この世の苦をつきぬけた異世界にこそ真実があるのだと。
はじめての白髪すくいとりながらひかり、おまえはどこからきたの
リズム的には、白髪(=はくはつ)と読むべきでしょう。
はじめての/はくはつすくい/とりながら/ひかり、おまえは/どこからきたの
と、57577のリズムになっています。
ここで短歌の技法をひとつふたつ解説しますと。
「はくはつすくいとりながら」が自然な句のながれですが、
これを、
「はくはつすくい/とりながら」
このように、句をまたがってリズムを分断する手法を「句跨り(くまたがり)」と言います。
もっとも、ここの句跨りはそれほど不自然ではないですね。
また、四句、結句(五句)は本来、
ひかり/おまえはどこからきたの
の流れが普通です。
これをあえて、
ひかり、おまえは/どこからきたの
としており、四句のなかで意味上の「割れ」があります。これを、「句割れ(くわれ)」と言います。
さりげない情景ですが、ここでも白髪に反射している小さな光、この光は何光年を旅してきたのだろう?と、
はるかな時空間へ思いを馳せています。
根源への問いかけができる存在。
これは詩人であれ哲学者であれ宗教家であれ、できるひとは限られています。
問いかけることができる、という時点でもう”世間”をはみだしているのです。
絵空事だけが恋しい かんむりを切りぬきましょう金紙銀紙
『世界が海におおわれるまで』の歌集の表紙の裏に、この歌とともに、「高田祥さま 2004年11月14日 佐藤弓生」とサインがあります。
歌人をストップして、ビジネス/投資という効率の世界へ、そしてまた宗教哲学の世界へハンドルを切った私とは違い、佐藤弓生氏はいまも歌を作り続けているようです。
かぎりなく無駄で美しいものに生涯をささげることができるひとのみに許されるコトバのひびきがここにあるんだなあ、とあらためて感じ入った土曜の夜でした。

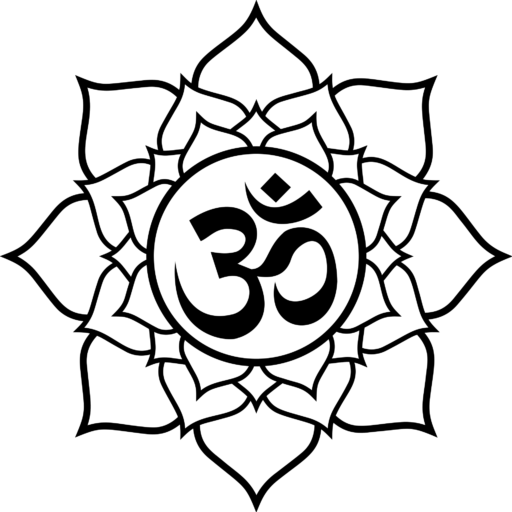
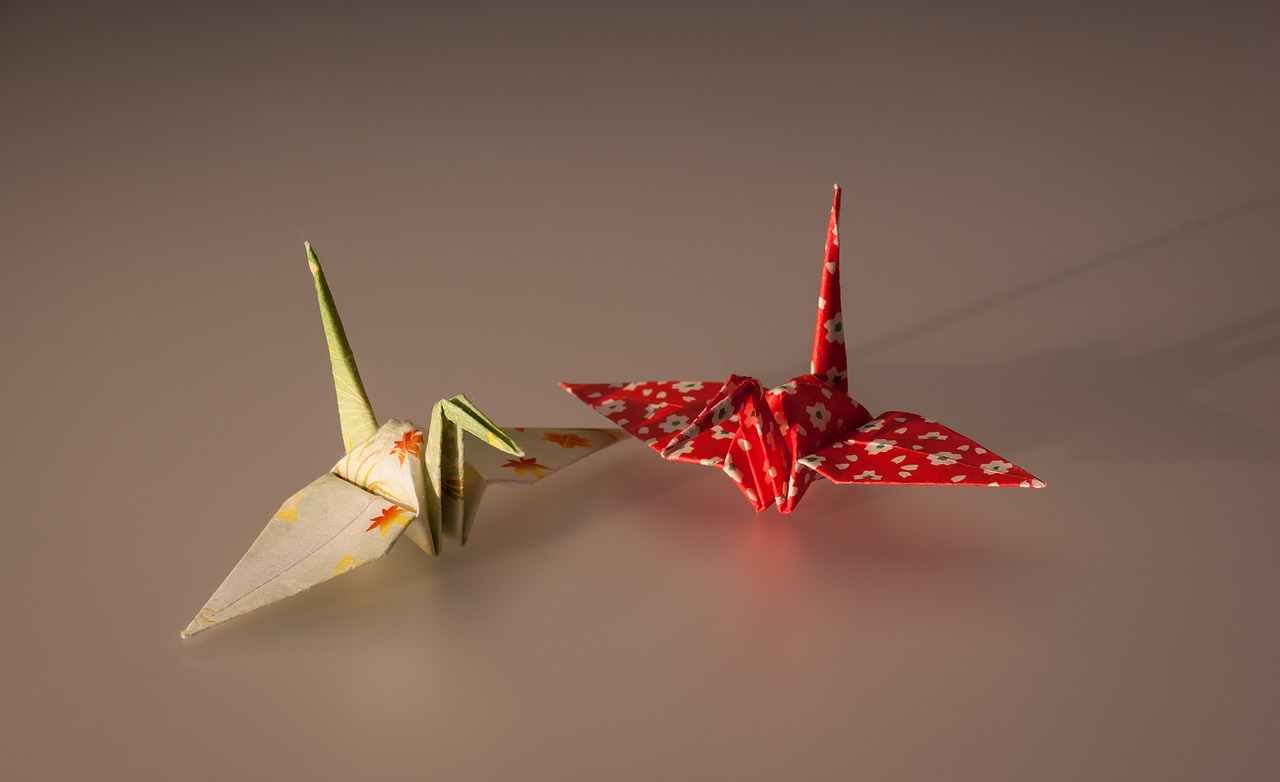









コメント