宗教の分類の仕方は色々ありますが、ひとつには一神教と多神教に分ける考え方があります。
一神教と多神教の違いは、文字通りと言いますか、「ひとつの神だけを信じるか、多数の神を信じるか」にあると、とりあえずは言っても良いでしょう。
*実際には、一神教でも、多神を認めた上でひとつの神を信じる”拝一神教(はいいつしんきょう)”、それから、他の神々を一切認めずひとつの神を信じる”唯一神教”という違いはあります。
とくに9.11以降、イスラーム原理主義・キリスト教原理主義などへの反発から、「一神教は他宗教を認めないので非寛容である」とし、多神教優位論が展開されるようになりました。
本論では、一神教と多神教の違い、多神教は本当に寛容なのか、仏教は多神教なのか…などの考察を通じて、真に世界から宗教紛争を無くす”一即多神教”の可能性について考察してみたいと思います。
*”一即多神教”はネオ仏法(当サイト)オリジナルの命名です
多神教が寛容であるとは限らない?
先に述べたように、「キリスト教、イスラム教などのセム的一神教は他の宗教を認めないから非寛容である、攻撃的である」との趣旨から、「多神教のほうが寛容で望ましい」という説があります。これが、「多神教優位論」ですね。
それに対しては、多神教が他宗教を排撃した例をいくつか出して、「そうとも言えない、多神教も非寛容な側面がある」との反論もあります。
たとえば、日本の仏教伝来にあたって、蘇我氏と物部氏が激しく争ったという歴史的事実や、日蓮宗(仏教ですね)の他宗排撃、江戸時代のキリシタン弾圧、明治期の廃仏毀釈運動、最近では、ミャンマーのイスラム教徒であるロヒンギャが仏教徒から弾圧を受けている、などの指摘もなされています。
このように、まあ確かに、多神教側が他宗教を排撃した例も探そうと思えば、いくつも見つけることができるでしょう。
しかし、一神教成立以来(とりあえず、ユダヤ教以降と考えます)の一神教による血なまぐさい戦争、異端審問や魔女狩り、植民地における宗教的理由による虐殺…などなどの歴史を考えれば、総数としては圧倒的に一神教が他宗教(他宗派)を攻撃した例のほうが多いと言えるかもしれません。
ただ、古代における中東地域はどうであったでしょう?中東は今も昔も戦争が多いですよね。
アッシリア、新バビロニア、エジプト…と思いつく限り挙げていくと、ほぼ全部が多神教なわけですよ。ほとんど唯一の例外がイスラエル人のユダヤ教が一神教であるくらいです。
「ほとんど」と書いたのはちょっとした例外もあるからなのですけどね。エジプトの新王国時代にアメンホテップ4世という王様が「アテン神」を唯一神とする一神教へ改革したことがありました。ご自分の名前も「アクエンアテン」とわざわざ変えています。
ただこの改革は一代限りで終わってしまいました。
そのアテン神信仰(一神教)が実は当時エジプトにいたヘブライ人に一神教の記憶を植え付けたのではないか、それがユダヤ教の起源なのではないか、という説もあるのですが、今回は深入りはしません。
さて、こうした考察で難しいのは、「いったいどこからどこまでがドグマ(教義)に基づいた争いなのか?」「宗教というより政治的要素が濃厚な争いなのか?」という見極めです。
代表的な宗教戦争と言われるドイツ30年戦争、これはカトリックとルター派の争いですが、これもドグマに基づいた争いとだけは言えず、多分にローマ教皇(法王)と封建領主、あるいは封建領主同士の世俗的な権力闘争の側面も大きいわけです。
さきの蘇我氏と物部氏の争いもそうですね。政治闘争の色彩が強い。なかなか見極めが難しいわけです。
逆に「政治的」と言いつつ、イデオロギー争いが先行している例もあるでしょう。イデオロギーも広い意味でドグマですからね。
というふうに色々と考えられるわけですが、ひとつ言えることは、そもそも多神教にはドグマ(教義)と言えるものがほとんどないということです。
神道の教義って思いつきますかね?おみくじに書かれてある教訓めいた言葉もほとんど儒教や仏教からの借り物ですよね。
古代ギリシャ・古代ローマ(キリスト教以前)の神々の教えって何だったのでしょう?ゼウス、ユピテルの教えとは…?
これも思いつきませんよね。
なので、多神教は寛容というより、そもそもドグマ(教義)がないので、ドグマに基づいた争いが起きようがないと言えるのです。
多神教と一神教は同じ土壌で語れるのか?
そういうわけで、ドグマ(教義)のない多神教に、そもそもドグマに基づいた宗教戦争は起きようがない、とも言えるわけです。
多神教優位論というのは、ドグマ嫌い・宗教嫌いの論者の、姿を変えた「宗教無用論」であるのかもしれない、と思ってしまいます。
なので「多神教のほうが寛容で攻撃性が薄いから、一神教に対して優位である、望ましい」という説、多神教優位論ですね、これに対しては個人的に異論があります。
私はそもそも、「一神教と多神教は同じ土壌で比べられるものなのか?」という疑問すら抱いています。
…と申しますのは、さきほどから申し上げている通り、多神教って、たいていが「教義」がないですよね。
多神教は、多分に習俗や文化、様々な通過儀礼(誕生、結婚、葬儀など)に関わるものであって、人がそれ(多神教)によって、倫理的規範を求める対象ではない、あるいはそもそもそういう役割を想定されてもいないのではないかと思えるのです。
多神教というのは、言ってみれば、民族の神話の蓄積なのではないか、と思うんですよ。
だから、たとえば、古代ギリシャ・古代ローマ(キリスト教国教時代を除く)においても、多神は礼拝の対象であったりはしましたが、人々の倫理的基盤はむしろギリシャ哲学が担っていたわけですよね。
ソクラテス(プラトン)もマルクス・アウレリウスも一応は、「神々」というふうに敬意は払っておりますが、ソクラテス(プラトン)においてはイデア説とそこから導き出される「魂の配慮」が基盤になっていますし、アウレリウスにとってはストア哲学ですね、これが彼の拠り所となっている。
ドグマ(教義)の働きとは?
もちろん、キリスト教やイスラームに見られるように、これら一神教も、人生の様々な通過儀礼に関わっています。文化・習俗の面でも深く根を下ろしています。実際はそれほど信仰心のない人にとっては、日本人にとっての法事などとあまり変わらないとも言えるでしょう。
とはいえ、一神教においては、「神との一対一の対話」にいつでも立ち返ることはできます。ドグマがあるがゆえに、そこに倫理的規範を求めることができます。
実は一神教の最大の特徴はまさにここに求めるべきだと思うのです。
「神との一対一の対話」「倫理的規範」です。
なにゆえに、これらが可能になるかと言いますと、結局のところ、世界観において人間が中心ではなくて神的実在が中心だからです。だからこそ、「規範」になることができる。
逆に、教義のない多神教においては、教義がないゆえにそもそも倫理的規範になり得ないとも言えますが、もう一つの視点は、「多神教はたやすく人間(自我)中心の世界観に陥る」ということです。
神社に礼拝に行っても、人間側の欲求に基づいた「願い事」を叶えてもらうとか、あるいは「スピリチュアルパワーを頂く」といったふうな、これはいくら礼拝していたとしても、根底にあるのは、人間が神に何かをしてもらおうとする「人間(自我)中心の世界観」です。
整理してみましょう。
- 一神教:神的実在中心の世界観
- 多神教:自我中心の世界観
つまり、一神教と多神教は、「神の数が違う」という問題ではなく、そもそも世界観が間逆なのです。まさしく、天動説と地動説のアナロジーに近いものがあります。
神的実在を中心に人間が動いているか、人間を中心に神的実在が動いているか、イメージとして、地動説と天動説で想像すると違いがくっきりと分かりますよね。

”個”の目覚めの時代には、神的実在中心の世界観が求められる
部族社会、あるいは血縁・地縁社会においては、自己と社会集団との関係性のなかに自然的な規範があります。
社会的な暗黙の掟、村社会の決まり事、風習、それから同質社会的な安心感もあります。倫理的規範としては祖霊崇拝などが中心になるでしょう。
近代社会と違って個人の自由は制限されていますが、自由が制限的だからこその快適さもあります。
ところが、近代社会、といいますか、個の目覚めが促進される帝国型社会、都市型社会においては事情が違ってきます。
帝国型社会では、様々な民族が入り乱れる状態が生まれます。商業の発展を契機とした都市型社会においても似たような状況が生まれます。それは、「隣人が異質である社会」と言えるのではないかと思います。
そうした社会においては、個の自由は促進されますが、一方では、個は文字通り個と言いますか、孤独であらざるを得なくなります。
もはや、部族社会・血縁地縁社会的な安心感や自然的な規範は期待できなくなります。
そうした否応なく個の自立が促される孤独な社会、自由に罰せられている社会において、個は心の拠り所を欲するようになります。
そして、心の拠り所は絶対的であればあるほど規範としての安心感が生まれます。
そこに先の「神的実在中心の世界観」が要請されてくるのです。
『サピエンス全史』において、ユヴァル・ノア・ハラリ氏では、時代が下るに連れて「帝国、貨幣、世界宗教という3つの装置が生み出される」という趣旨の主張をしておりますが、この3つは実に密接に関連しているのです。
*もっとも、『サピエンス全史』そのものが基本的に主張するところにはネオ仏法は同意しておりません
さて、「帝国型」「都市型」と言っても、たとえばムハンマドのイスラームは出発点が違うのでは?といった異論があるかもしれません。
よく(とりわけ以前には)「砂漠型の一神教」という物言いがなされてきました。そして、厳しい自然環境と、帝国や宗教が入り乱れる中東地域だからこそ、一神教が発達したのだ、という論の運びもありますね。
しかし、よく歴史をチェックしてみると、古代の中東〜地中海地域はむしろ多神教のほうが主流であったことがわかります。バビロニア、アッシリア、新バビロニア、エジプト、ギリシャ、ローマ…。
ムハンマドの時代はむしろ転換期の一つで。
歴史的には、ササン朝ペルシアとビザンツ帝国の争いがあり、商業・交易の中心地がアラビア半島に流れていった時代にあたるのですね。
アラブ人はもともとは部族社会ですが、そうした「商業の波」に押されるように都市型社会に移行していった時期なのでした。当時のメッカ(マッカ)はまさにそうした渦中にあったわけです。
そして従来の多神教が様々な差別や貧困問題…ひいては「心の問題」を解決できなくなっていった。
イスラームがなぜあれほど急速にアラビア半島を席巻していくことができたか、というと、やはり、神的実在中心の世界観が(無意識的にせよ)要請されていたからだと思うのです。
キリスト教もそうです。
ローマ帝国内では、反乱分子として幾度となく大迫害を受けていましたが、コンスタンティヌス帝のころはもはや押し留めようがないほどにキリスト教信者が増えていった。それはなぜなのか?
やはり、ここでも「個の目覚め」に多神教が応えることができなくなってきた、ということだと思うのです。
そして、神的実在との一対一の対話のためには、神的実在の絶対性が大きければ大きいほど安定感が強くなる。ストア哲学などではもはやその強度が不足していた、ということなのではないかと。
一方、ユダヤ教は一神教で(しかも一神教の出発点とも言えるのですが)すが、ユダヤ教は民族宗教に留まることを選びましたからね、これでは帝国民の要請に応えることができない。だから、キリスト教がもはや公認するしか道がないほどに爆発的に広がっていった、と、そういうことだと思うのです。
さて、仏教については分類としては多神教と言われることが多いと思うのですけど、まあたしかに(当時の)バラモンの神々も一応は認めていたからそうは見えるのですが。
仏陀の教えは、やはり、「法中心」なのです。
そして、「法を見るものは仏を見る」という仏典の言葉がある通り、これは結局、「仏中心」ということになり、さきの「神的実在中心の世界観」のほうへ一致してくると思われます。
仏陀の時代も商工業が急速に発達した都市型社会へ移行してった時代でした。
そしてとりわけ、大乗仏教の時代に入ると、「久遠実成の仏陀」あるいは「阿弥陀仏」は一神教的な絶対性をますます帯びていきましたね。
そういうわけで、都市型といいますか、結局は、帝国や都市は「異質な隣人」がいる社会ですから、どうしても「孤独な個の目覚め」が促進されることになる。
人は根本的には孤独には耐えられませんので、そこで心の拠り所となる「絶対の規範」を欲するようになる。そこで、一神教的な「神的実在中心の世界観」が要請されてくることになる。そういうことだと思うのです。
私たちが今、生きている社会ももはや部族的な連帯感では維持できないほどの「孤独な個」の世界ですよね。本質的には一神教的な原理が要請されているのです。
日本についてはほぼ同一民族で同質性が高く、また、さきの大戦で「一神教的な」天皇現人神的価値観が大きく否定されたために、混迷の時代になっているわけです。
そして、絶対神の代替物として、アイドル・地下アイドル、お手軽な自己啓発本が次々と消費されていっているのが現状であると、私はそう見ています。
しかし、日本においても、潜在的には、真の幸福のためには「神的実在中心の世界観」が要請されていると思います。
「神的実在中心の世界観」はいわゆる狭義の「宗教」でなくても構わないのです。要は、絶対的な原理原則中心の価値観を手に入れる、ということです。
結論として、言葉としては、やはり世界は「神的実在中心の世界観」を欲している、ということになると思われます。キリスト教とイスラームなどの一神教だけで世界人口の2/3を占めているのは偶然ではないのです。
さきに述べたように仏教も「法中心」の一神教的原理を有していますので、さらにその人口比率は上がることになります。
そして、”一即多神教”の時代へ
そういうわけで、縷縷述べてきましたように、「個の目覚め」が著しい私たち現代人にとっては、絶対的な倫理規範となりうる神的実在中心の価値観、言い換えれば、一神教的な原理が求められていると言えるのではないかと思います。
さて、そうは言っても、冒頭に述べたように、一神教の(ドグマ的)非寛容性は依然、問題として残ってまいります。
そこで、当サイト(ネオ仏法)では、多神教と一神教を弁証法的に止揚した”一即多神教”を提案してみたい。
数字の一(イチ)というのは、一(イチ)以外の何物でもないと言えるほど単純なものではありません。
一(イチ)のなかに”多”を含めることが可能なのです。
たとえば、ここに一塊の粘土があるとします。数としては一(イチ)ですよね。
ところが、その粘土をちぎっていけば、多(タ)になることができる。そして逆に、多をまとめて捏ね上げるとまた一(イチ)に戻ることができます。
このように、一(イチ)は単純な一(イチ)ではなく、「多を含むところの一」という視点があり得るのです。
これを宗教に置き換えてみましょう。
本源的な神は一(イチ)です。
ところが、一なる神であっても、時代や地域、民族性などに応じて様々に個性ある形で地上に現れてくる。あるいは、地上人が一なる神に対して様々な応答の仕方をする。
これが地上に色々な宗教が現れている理由なのです。
ところが人間の視野の狭さで、「キリスト教と仏教は違う」「イスラム教と仏教は相容れない」などとして、相争ってきたのが歴史的事実なのです。
ここで「違いは違いとして様々な宗教がある(=多)と認めつつも、本源的な在り方としては一つである」という”一即多神教”の可能性が拓けてきます。
まあ、”一即多神教”というと、そうした宗教があるかのようですが(あってもいいのですが)、そうではなく、たとえば、ある特定の宗教団体に属していたとしても、他宗教を「違うもの」として排撃するのではなく、「元は同じ根源的な創造神から分かれてきたものなのだ」と尊重する思想・精神性と言ってもいいでしょう。
この”一即多神教”こそが次代の社会に要請される神観であるべきだとネオ仏法では考えています。
ただ「一即多」と言っても、もちろんさきの粘土の例のように「ごっちゃまぜに一塊(ひとかたまり)に還元しうる」という単純なものではないでしょう。
そうではなく、違いは違いとして、個性として在りながら、より上位の観点から立体的に一(イチ)に還元することが可能である、ということなのです。
たとえば、地球は一つですが、そのなかに様々な国家がありますよね。
国レベルの視点で言えば、「Aの国とBの国は違う」ということになります。
ところが、視点の抽象度を「惑星」にまで引き上げると、様々な個性ある国家をそのうちに包含しつつも地球という一つの惑星である、というふうに、「一(地球)でありつつ、多(様々な国家)である」という在り方が成立するでしょう。

宗教も同様に考えるべきだと思うのです。
本源的な神は一つであるけれども、時代や地域・民族性などに応じて個性ある様々な宗教として現れているだけなのだと、そして、究極の神は名前は違えども同じ神なのだという考え方です。
これが「一即多神教」の思想です。
ネオ仏法では単に「元は同じである」と空念仏を唱えるだけではなく、「具体的にどのように”一つ”に還元しうるか」という立体的な構造も明らかにしつつある、という自負があります。
仏教とキリスト教でいえば、たとえば下記の記事などをご参照ください。
*参考記事:仏教とキリスト教の共通点を抽出する – “違い”を総合するネオ仏法
”一即多神教”、まあ一宗教ではありませんので、”一即多神観”と言うほうがいいかもしれませんが、こうした考え方が地球上のメジャーな宗教間で共有されるようになれば、一神教的な「神的実在中心の価値観」に由来する「絶対的な倫理規範」を担保しつつ、他宗教・他宗派を尊重する「寛容性」を発揮することができるようになるでしょう。
ネオ仏法では、こうした”一即多神観”の可能性を今後も数多く提唱していきたいと思っております。

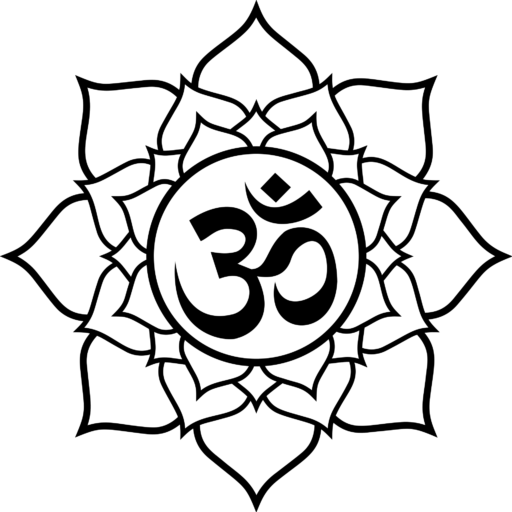










コメント