至上神は、至高神とか最高神とかいろいろな呼び方をされるときがありますが、意味的には同じことです(以下、「至上神」に統一して話を進めてまいります)。
至上神とは、かんたんに言えば、文字通り、「トップの神」ということになります。
しかし、トップの神といっても、
- 多数神がいるなかでのトップなのか
- 多神を認めないで、唯一無二の至上神ということなのか
という違いもあります。
また、各宗教で「至上神」を打ち出しているけれども、「結局、どの神が至上神なの??」という単純(しかし実は奥深い)な論点もあります。
本論考では、
- なぜ至上神にはさまざまな名前があるのか
- どの宗教の「至上神」が本当の至上神であるのか
- 至上神とはそもそもどういった存在であるのか
などなど、いくつかの角度から「至上神」についての論点を深めてまいりたいと思います。
宗教多元主義的な「至上神」理解
各宗教におけるさまざまな至上神
至上神として、まず日本人が思い浮かべるとしたら、神道の「天之御中主神(あめのみなかぬしのかみ)」でしょう。ちなみに、天照大神は「主宰神」としての位置づけです。
あるいは、ギリシャ神話のゼウスを思い浮かべる方もいらっしゃるかもしれません。「全知全能」と謳われるゼウスです。

ゼウスの神
インドのヒンズー教では、ビシュヌ神が至上神に相当するでしょう。ヒンズー教の解釈では、釈尊はビシュヌ神の「変化身(へんげしん)」という位置づけになっております。
そして、世界人口のほぼ半分がキリスト教、イスラム教(イスラーム)となっておりますので、キリスト教の三位一体の神、イスラム教のアッラーを外しては至上神を論ずることはできません。
また、この両宗教の母体になったユダヤ教の神、ヤハウェもユダヤ教成立史において、至上神、唯一神とされておりますので、ユダヤ教自体は民族宗教であるものの、ヤハウェについても考察をしていかなければならないでしょう。
まあ、古代から宗教は星の数ほどありますので、宗教ごとに、あるいは文明の数ほどに至上神は存在していた、信仰され続けてきたと言っても良いでしょう。
単一神教、拝一神教、唯一神教
さて、次に、至上神といっても、「他の(劣位の)神々を認めるのか、至上神以外の多神を認めないのか?」という論点があります。
まず、自宗教内に多神の存在を認める場合は、多神教と呼ばれますね。神道や古代ギリシャ・ローマの宗教が代表的なものです。
対して、自宗教においては一神のみを崇める場合は一神教として呼ばれます。
さらに、一神教でも、他宗教の神々を認めた上で一神を崇めるパターンを拝一神教、自宗教の神のみを唯一の神として崇めるパターンを唯一神教と呼びます。
この拝一神教、唯一神教という分類は、ユダヤ教成立史において考え出された分類法です。
旧約聖書を注意深く読むと、初期の頃は他の神々を認めていたことが伺えます。その上でヤハウェのみを信仰していたのです。これが拝一神教です。
ところが、有名なバビロン捕囚(BC6世紀頃)あたりから、ヤハウェのみを世界の創造神とするようになっていきました。これが唯一神教です。
ゆえに、「至上神」の在り方としては下記の3通りの違いがあることになりますね。
- 単一神教:多神教において、神々の中の一柱のみを至上神(主神)として崇拝する
- 拝一神教:一神教において、他の(部族・文明の)神々の存在を認めることを前提とし、至上神を崇拝する
- 唯一神教:一神教において、他の(部族・文明の)神々の存在を認めず、至上神のみを崇拝する
なぜ、至上神にはさまざまな名称があるのか
以上、ご説明してきた通り、ひとくちに”至上神”と言っても、それぞれの宗教によって意味合いが異なっております。
しかし、それはそれとして、各々の宗教に「トップの神」があり、他宗教の「トップの神」と衝突してしまうことが多いということは歴史が証明していますし、宗教の排他性のひとつの側面ではあります。
もっとも、「うちの神より、あちらの宗教の神のほうが格上です」などと説く宗教は見かけませんね。
やはり、宗教にとっては「信仰がきっちり立つ」ということが大事であって、そのためには正当なプライドとして、自らの宗教で祀っている神を”最高”とするのは当然のことであると言えるでしょう。
とはいえ、それでは結局、どの宗教が言っていることが正しいのか、あるいは、どの”至上神”が本当に”至上”であるか、という問題が出てきますね。
これに対しては、当サイト(ネオ仏法)では、いろいろな記事で答えを出しております。
どういうことかと申しますと、次のような理解の仕方をします。
神は唯一の存在であるけれども、時代性や地域性、民族性などを考慮して、様々に顕現してくる。それゆえに、宗教によって神の名が変わっているのだ、ということです。
こうした思想を、「宗教多元主義」と呼びます。代表的な思想家にジョン・ヒックという方がいらっしゃいまして、まさに『宗教多元主義』という著作があります。
「群盲象を撫でる」という諺がありますね。
象は一匹だけど、盲目な人間たちは、象の様々な箇所を撫でて、「象とは牙だ」と言ったり、「いや、象とは長い鼻なのだ」と言ったりして、互いに見解を異にしてしまう現象のことを指します。
これと同じように、神はひとつだけれども、それぞれの宗教によって把握の仕方が違うだけなのです。これが「神はひとつだけれど、様々な名前を持つ」所以です。
世界の三大宗教であるキリスト教、イスラム教(イスラーム)、仏教では、「慈悲あまねき神(仏陀)」として、それぞれ、父なる神(エロヒム)、アッラー、阿弥陀如来を立てています。
これらも上述したように、時代性や地域性、民族性を考えて違ったふうに現れているだけで、もとは一なる神(あるいは仏)と理解することができます。
このように考えることによって、世界三大宗教は相争うことなく、違いは”個性”の相違に過ぎず、もとはひとつなのだ、というふうに、相争うことなく共存していく可能性が拓けます。
もっとも、キリスト教における神とイスラームにおけるアッラーは、そもそも同一のGODではないか、少なくともイスラームの側からはそう認識されている、という反論がありそうです。
エロヒムもアッラーも固有名詞ではなく、普通名詞、つまり大文字のGODを指しますので、たしかにその通りなのです。歴史的にも、そして現在においても、両宗教は対立しております。
上述した「一なる神」というのはあくまで宗教間がコモンセンスとして共有すべきベーシック理論でありますので、宗教間の争いをこれだけで一掃するのはむろん難しいですし、実際にキリスト教とイスラームは歴史的にも血で血を洗うような争いを続けてきました。
これは、「元は同じ神なのだ」という認識がきっちり浸透してないのと、今一つは、宗教の違いというものを立体的に把握できていないのが原因である、と私は考えます。
さきの「群盲象を撫でる」のたとえで言えば、牙と長い鼻…などの位置関係を特定し、理性と対話によって、一匹の象をより立体的に把握していく努力が必要なのです。
私はまさしくそうした課題意識をもってネオ仏法を立ち上げました。
今回は「至上神」がテーマですのでこれ以上深入りしませんが、たとえば、仏教とキリスト教の関係性については下記の記事で詳述しておりますので、ぜひ参考になさってください。
*参考記事:仏教とキリスト教の共通点を抽出する – “違い”を総合するネオ仏法
とまれ、出発点としては、「一なる神が時代性や地域性、民族性を考慮して様々に顕現しているだけなのだ、人間の側の理解力の限界で違うふうに視えているだけなのだ」と考えることが第一歩になると確信しています。
ゆえにまずは、
エロヒム=アッラー=阿弥陀如来
という等式を押さえて頂ければ、と思います。これ以上のことは次項で考察してまいりましょう。
ちなみに、キリスト教における父なる神はヤハウェではないか?という疑問を持たれる方もいらっしゃるっでしょう。
その問題につきましては、下記の記事で論考しておりますので、ご一読頂ければ幸いです。
*参考記事:ヤハウェとエロヒムは別の神である – 民族神と最高神を区別したほうが良い理由
人格を超越したエッセンチア(本質)としてのGOD(根本仏)とは
さて、至上神として、ネオ仏法では、
エロヒム=アッラー=阿弥陀如来
といった等式を採用していると上述しました。「慈悲あまねき神(仏)」という意味で、ですね。
もちろん、それで間違いはないのですが、これはまず、「地球的地場」に限った場合にそうなるということなのです。そもそも、大宇宙に遍満している至上神に名前があるのがおかしいのです。
…というのも、名前というのはそれ自体で排他的・限定的な性質を持っていますよね。
「鈴木さん」という名前であれば、それは逆に言えば、「佐藤さんではない」ということになります。ゆえに、本当の意味での至上神、普遍神は、名前・名称には馴染まない、そぐわないのです。
ただ、何かしら名前を付けないと言及できない、ということもありまして、仏教では、「法身仏、盧遮那仏(毘盧遮那仏)、大日如来」といった名付けをしています。
キリスト教の神、父なる神=エロヒムですね、これも三位一体のうちのひとつの位格です。ラテン語で「ペルソナ」と言いますが、ペルソナとは「仮面」という意味です。
…ということは、仮面をかぶる以前の本質的なありかたがあることになる。これを、エッセンチア(本質)というふうに呼ぶことがあります。
イスラーム(イスラム教)で現代でも主流の哲学、「存在一性論」の基礎を築いたイブン・アラビーという方は、アッラーという人格神に至る前の本質的な有り様を「存在」と名付けました。
*参考書籍:『イスラーム哲学の原像』(井筒俊彦著)
仏教ではさきにも申し上げた通り、法身とか盧遮那仏、大日如来という名称を仮に充てているわけです。
道教では、タオ(道)と呼んでいます。
このように、人格神、仏教で言えば「報身」にあたるかと思いますが、そうした「人間に理解できるように方便的に現れる以前の本質的な存在、名称になじまない存在」というものが、本当の意味での至上神なのです。
いわば、「絶対無」こそが至上神です。
この場合の”無”とは、単なるゼロではなく、すべての存在を生み出す可能態としてゼロです。
エッセンチア(本質)としての至上神のままでは、人間などの個別的現象からは、(仮に二元論的な図式にしますと)、もう取り付く島もないような存在なわけですね。そのままでは教えを受けることすらできない。
そこで、エッセンチアとしての至上神は、まず地球的地場において人格を持ち、またさらに、時代や地域に応じて、エロヒムとかアッラー、阿弥陀如来として顕現したのです。
ここにおいて、はじめて人間と交渉をもつことのできる人格神となるわけです。
ここでも、「エロヒムとアッラーは固有名詞ではなく、普通名詞ではないか」との反論が来そうですが、それはやはりあくまで、地球的地場における普通名詞的GOD、人格神としてのGODなのです。
ちなみに、上記の等式で、「阿弥陀如来」に若干、違和感を感じられる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、この場合の阿弥陀如来は、”浄土教”の範疇に収まる阿弥陀如来ではありません。浄土教はあくまで、阿弥陀如来の本願とその成就、極楽浄土への誘いを説いたものです。
仏典の中でも最高度の抽象度を誇る『華厳経』があります。華厳経はまさに、エッセンチアとしての法身仏、盧遮那仏の働きを説いたお経です。
その華厳経の末尾、「入法界品」のさらに末尾に、「本願仏たる阿弥陀如来に帰依せよ」と説かれています。
これはつまり、盧遮那仏を人格化した存在としての阿弥陀如来が想定されていると言っても良いでしょう。
*参考書籍:『現代意訳 華厳経 新装版』(原田霊道著)
以上のように、名称を持つ以前のエッセンチア(本質)まで抽象度を上げることによって、はじめて本当の意味で「あらゆる宗教は一なる神から流れ出してきている」ということが了解されるでしょう。
文字通り「至上の命題」としては、至上神の名前、エロヒムとかアッラーとか阿弥陀如来…などなどの名称も方便として消し飛んでしまう「絶対無」としか言いようのない存在、これこそが真なる至上神なのです。

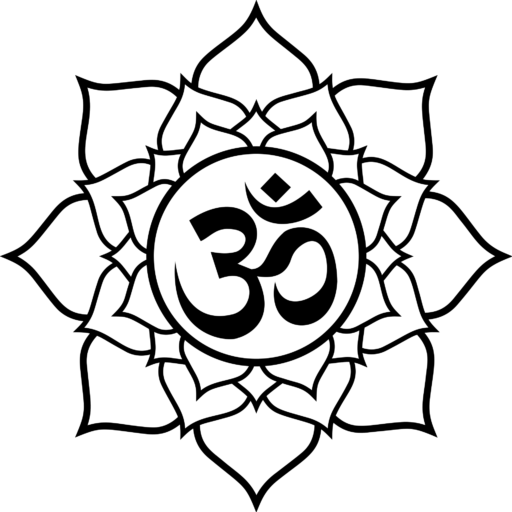












コメント