仏教とキリスト教というと、比較宗教学的にも違いばかりが強調されていく傾向があります。
異なる文明圏を理解するためにはそれも肝要なことですが、一方、宇宙時代を迎えるにあたり、”地球”という単位の文明を構築していくためには、違いを乗り越えたベーシックな共通点を探ることが今後、大事になってくると考えます。
当サイト(ネオ仏法)でよく申し上げているように、まずは少なくとも”地球”という単位でみるならば、本来の究極神はひとつです。
ひとつの神が地域や時代によって、異なる顕現の仕方をしている。あるいは、人間の側からみるならば、異なる理解(応答)の仕方をしているだけなのですね。
こうした考えは、ジョン・ヒックの『宗教多元主義』と軌を一にしております。
あるいは、大きくスケールアップしたエキュメニカル(教会一致)な運動と捉えることもできるでしょう。
本稿では、とりあえずはキリスト教神学に即して、「神論」「キリスト論」「人間論」「修道論」に分けて、キリスト教と仏教を総合する基礎理論を提示していきたいと思います。
仏教とキリスト教の接点については、ヘレニズム的世界とインド亜大陸との文化交流などからも考察できますが、今回の記事ではあくまで教理・教義の本質論に即して論じてまいります。
ちなみに、「仏教とキリスト教の違い、比較」ということでいば、『仏教とキリスト教の比較研究』(増谷文雄著)が有名です。
とくにオリジナリティのある思想を展開されているわけでもないのですが、いわゆる「著者の悟りが高い」感じがしまして、一読をお勧めしたいです。
神論
神論はその宗教を理解するためにもっともベースになっている概念です。
ここでは、
- 世界創造と自己展開
- 超越と内在
- 法前仏後と神前法後
の3点から考察しつつ、 - GODと毘盧遮那仏/阿弥陀如来
の接点を探っていきます。
世界創造と自己展開
因果の時系列で推定される「地球」の第一原因
キリスト教(セム的一神教)においては、「神は世界創造を行った」というところから、その絶対性が強調される傾向があります。

システィナ礼拝堂の天井に描かれてるこのミケランジェロの『天地創造』
一方、仏教においては、世界創造については語られていません。
これをもって、「仏教とキリスト教はまったく違う」と言われるのですね。
しかし、世界創造が説かれているかどうか?が神論においてそれほど根本的なことなのか?もう一度、白紙に戻して考えてみる必要があるように思われます。
仏教における生成論の基本は”縁起”です。「依って起こる」ということですね。ひらたく申し上げれば、(時間軸においては)「原因と結果の法則」のことです。
Aが原因となり、Bという結果がもたらされるとします。すると今度はBがひとつの原因となり、Cという次なる結果がもたらされる。
BはAからみれば”結果”ですが、Cからみれば”原因”です。そのように世界は展開していきます。
そうするとどこまで行っても、”世界創造”的な第一原因には突き当たることができない、というふうになりそうです。
しかし、「第一原因」とはそもそも何でしょうか?
聖書の天地創造で語られているのは、全宇宙の創造ではなく、あくまで地球と地球を中心とする磁場における創造に限られています。
神は4日めには「太陽と月と星を作られた」となっていますが、これも一般論・全体論としての太陽、月、星…というよりも、あくまで地球との関係性における創造ですね、その範疇における創造です。
そうすると”第一原因”と言いつつも、それは「地球にとっての」第一原因であるに過ぎません。
第一原因というのは、あらゆる根本の第一原因という意味だけではなく、あるメルクマールにおける第一原因というのも想定することができるわけです。創世記における天地創造というのは後者における第一原因です。
ひとくちに”第一原因”といっても、「それが何であるか?」を考えるならば、このように多義性を持つことが分かります。
そうであるならば、縁起ですね、今は時間軸において考えていますので、因果の法といっても良いですが、無限の因果の連なりというものがありつつも、「地球としての」第一原因というのは、想定されるうることになります。
今現在の世界を単純化してCであるとするならば、地球という磁場に限られるところの第一原因Aはどこかの時点でかならず想定されることになるでしょう。
したがって、初期仏典に天地創造が語られていないからといって、「仏は天地創造を行わなかった」とは断言できないのです。
単に、(仏陀・釈尊の時代には)「説く必要がなかったから説かなかった」というだけのことです。
「創造」というのも、ひとつの言葉に過ぎません。
ヴァッカリよ、実に法を見るものは私を見る。私を見るものは法を見る。ヴァッカリよ、実に法を見ながら私を見るのであって、私を見ながら法を見るのである。(『サンユッタ・二カーヤ』「ヴァッカリ」)
ということでいえば、生成の第一原因、これも法(存在)ですね、これは、わたし=仏そのものであるとも言えることになります。
つまり、
法=仏
です。
*法(ダルマ)には、「教え」以外に「存在」という意味があります。
自らがみずからを生成している、言葉を換えれば「自己展開」ということです。自己展開は、人や鳥、獣…などの個物の立場から見れば、「創造がなされた」ということと同じなわけです。
生成というものを、全体の側から見れば自己展開であり、個物の側から見れば「世界創造」になる。このように「どこの断面から眺めるか?」という違いに過ぎないのです。
『大日経』に確認できる「仏陀の世界創造」
さて、では仏典には一切、「天地創造」が語られていないか?というと、そんなこともありません。以下は、『大日経』の引用です。
*参考書籍:『空海「即身成仏義」「声字実相義」「吽字義」 ビギナーズ 日本の思想』 (角川ソフィア文庫)所収
私(大日)はさまざまな形の諸法と法相と諸仏と声聞と、この世を救済する聖者と懸命に努力する菩薩たちを生み出します。さらに人尊としての釈尊(あるいは等覚たる聖者)もまた同様に私が生み出したのです。一切の人々も、また彼らの住む世界も順に私(大日)が生み出したのです。そして彼らの生住異滅という変化してゆく姿、様相などの諸法もすべては私が、自然のままに常恒に生み出したのです。
(『大日経』巻五、秘密曼荼羅品第十一)*下線は高田による
これは字義通りに受け取れば、まさに大日如来による「天地創造」でしょう。
ただこの根拠に対しては2種類の反論が予想されます。
- 『大日経』および空海の意図では、「創る側(能生)と創られる側(所生)は同体」とされているので、創造神話とは異なる
*実際に、上掲書の著者はこの点注意を喚起している - そもそも、『大日経』は仏陀・釈尊の直説金口ではない
これらに対するネオ仏法の見解は以下のとおりです。
1. 能生・所生について
「創る側(能生)と創られる側(所生)は同体」というのは、要するに、「自己展開、自己生成」のことです。上述したように、自己展開と世界創造は矛盾しません。あるいは、「矛盾しつつ総合」できるのです。
2. 仏説や否やについて
初期経典の時代から、”仏説”には「法性(ほっしょう)」という基準があります。法性とは要するに「真理に適っていれば、それは仏説である」という思想です。
仏教の”仏陀”とは、釈尊の時代から釈迦仏には限定されておりません。「釈尊(釈迦牟尼世尊/ゴータマ・ブッダ)が説いた教え」という以上に、「仏陀になるための法(ダルマ)」こそが仏教なのです。
よって、対機説法を重視する仏教は、歴史的・時間的・地域的に、”仏説”そのものにダイナミズムを内包するのが当然なのです。
*参考書籍:『ブッダたちの仏教』(並川孝儀著)
ちなみに、現行の初期経典でさえ、様々な改変が施されていることが分かっており、到底、「釈尊の直説金口そのまま」であるとはもはや主張できません。
*参考記事:テーラワーダ仏教批判① – テーラワーダ仏教は部派仏教の一派の流れに過ぎない
したがって、密教経典『大日経』も仏教と銘打っており、「大蔵経(一切経)」に収録されている以上、”仏説”として認められると言って良いでしょう。
超越と内在
ここまでの「自己展開と世界創造」から敷衍すると、次のようなことが分かります。
「キリスト教(セム的一神教)においての神は絶対神、超越神であり、仏教の神観とはまったく違う」と従来から言われておりますが、これも単なる「見る角度の違い」に過ぎないということです。
神は自己展開をしてその”内部に”個別的な存在を創造しました。
なぜ”内部”なのかと言えば、もし”外部”であるならば、「神以外の領域」が存在することになり、神の絶対性が損なわれますよね。なのでやはり、”内部”と考えるのが筋なのです。
神の内部における個別的存在、Aさんとしましょうか。Aさんが神を思うとき、図式的には自らを離れた存在、というふうに二元論的に把握することになります。つまり、対象化して考えるわけですね。
自己(Aさん)→神
という二元論です。
ここにおける”神”というのは、全体としての一なる神ではなく、あくまでAさんに認識できるところの範囲の神です。
この図式においては、自己(Aさん)と神は絶対的に異質な存在であると認識されます。これがキリスト教(セム的一神教)の文脈における「超越神」です。
ところが、先の前提で考えたように、実際は、神の内部に自己意識(Aさん)は在るのですから、神は単純に超越しているのではなく、「私たち個別的な存在を含みつつ在る」ということになります。
言葉を換えれば、神は私たちを離れた別物ではない、ということです。
このように「内在の論理」で考えるならば、超越というものも単なる便宜的な”見方”、見る角度の問題に過ぎないことが分かります。
したがって、キリスト教(セム的一神教)的な超越神と仏教的な…汎神論というのですかね、「法が全体である」という考えは、じつはまったく矛盾しないのです。
後ほど、「キリスト論」のところで考察しますが、先取りして申し上げれば、
「全体が神」であり、人間(個別的存在)が二元論的に神を観想する際に現れる神が、三位一体で言うところの”父なる神”であり、あるいは、ロゴス(教え)であるところの”子なるキリスト”ということになります。
イラストで描くともっと分かりやすくなると思いますので、ぜひ脳内でイラスト化してイメージしてみてください。
唯一神を大きな丸で描き、その中に、私たち個別的な存在を(仮に存在Aとします)を小さな丸を描きます。
- 小さな丸Aから大きな丸を見れば、”超越神”に見える:現象から実在を眺める視点
- 小さな丸Aも大きな丸に包含されるので”汎神論”も正解となる:現象は実在に含まれるという視点
法前仏後と神前法後
さて、「仏教とキリスト教の違い」として、「仏教は法前仏後(ほうぜんぶつご)であり、キリスト教は神前法後(しんぜんほうご)である」と説明されることがあります。
ざっくりと定義をしてみますと、それぞれは以下のような意味になります。
- 法前仏後:仏教においては、仏陀がすでにある法を発見したのであるから、仏より法が優先される
- 神前法後:キリスト教においては、始めに絶対神が存在していたのであるから、法は事後的なものである
ということですね。
これをもって、仏教とキリスト教はまったく異質の宗教であるという論拠のひとつにもされています。
しかし、本当にそうなのでしょうか?
法前仏後と神前法後は本当に相容れないものであるのか?一度、白紙に戻して考えてみたいのです。
先に挙げましたが、もう一度、「ヴァッカリ」での仏陀の言葉を振り返ってみましょう。
ヴァッカリよ、実に法を見るものは私を見る。私を見るものは法を見る。ヴァッカリよ、実に法を見ながら私を見るのであって、私を見ながら法を見るのである。(『サンユッタ・二カーヤ』「ヴァッカリ」)
ここで”私”というのは、仏陀・釈尊のことです。
つまり、「法を見るものは仏を見る」ということになりますね。言葉を換えれば、仏と法は一体不可分であるということです。
後で「キリスト論」の項目でも取りあげますが、仏教の三身説<法身 -報身 – 応身>という図式で言うならば、応身としての釈尊の出自・本質はあくまで法身、つまり、「法そのものである」と言えるのです。
あるいは、”報身”という考え方もそうです。報身は「修行の果報として仏陀になった」という意味でありますが、これは本質論ではなく、方便論に過ぎません。
<法性法身 – 方便法身>という分類の仕方もありますが、ここから考えても、本質論としては、「仏陀の本質は法そのものである」ということが分かります。
したがって、仏教理論に従って考察しても、仏教は必ずしも”法前仏後”とは断言できないのです。これは、報身あるいは方便法身としての断面から眺めるならばそういう見方もあり得る、ということに過ぎません。
”神前法後”についても、白紙に戻して考えてみましょう。
神は全能であり、それゆえに時間をもそのうちに包含している存在であると想定されます。神と時間が別個のものであるとすれば、神は時間を支配できていないことになる、全能性に瑕疵が生じてしまいます。
ゆえに、
「神があって→その後、法ができた」という時間的経過は、絶対神の要件であるところの「神は時間をもその内に包含している」という定義に反することになります。
やはり、本質論において、絶対神と法は一体不可分のものであると見做すべきでしょう。
このように考えてみると、”法前仏後”と”神前法後”というのもあくまで、現象論・方便論という断面から見た、ひとつ分類の仕方であるに過ぎないのです。
GODと毘盧遮那仏(びるしゃなぶつ)/阿弥陀如来
さて、「仏教には超越神はない」と言われます。
しかし、上述した2ポイント「世界創造と自己展開」「超越と内在」ですね、これをベースに考えるのであれば、じつは「仏教にも”超越神”はある」というふうに主張することもできます。
真の意味での超越、絶対というのは、”全体”なのです。”全体”でないとすれば、どこかに”相対”を残してしまうことになり、それはすでに”絶対”ではなくなってしまいます。
この絶対神が大文字のGODです。キリスト教(セム的一神教)の文脈では、ですね。
この「全体にして一なる神」は仏教においては、華厳経の「盧遮那仏(るしゃなぶつ)」あるいは、「毘盧遮那仏(びるしゃなぶつ)」に相当します。

東大寺の毘盧舎那仏
歴史的な仏、釈迦仏を超えた宇宙の根本原理、法身仏(ほっしんぶつ)です。毘盧遮那仏は大毘盧遮那仏、サンスクリット語では、「マハー・ヴァイローチャナ」とも言います。また、密教では、「大日如来」と呼ばれる存在です。
さらに、法華経では「久遠実成の仏陀」とも呼ばれています。
このような”法身仏”、文字通り「法の身」ですね、「宇宙を貫く法則そのもの」。
法はダルマであり、ダルマは存在そのものです。
ゆえに、宇宙を貫く法則は、宇宙という存在そのものでもあるのです。これは究極の”絶対”でもあります。
したがって、超越神・絶対神としてのGODは、仏教における大毘盧遮那仏に相当すると言うことができます。
歴史的な文脈では、法華経の「久遠実成の仏陀」がキリスト教(セム的一神教)で言うところの唯一神として理解されてきたと言っても良いでしょう。
法華経を奉ずる団体が「これのみが真理」ということで、場合によっては強引な折伏を行うさまは、キリスト教(セム的一神教)的な強引さと軌を一にしています。
ある意味、非常に迷惑であるとも言えますが、一方、これがあるからこそ世界宗教化の原動力になったという見方もできます。
また、今ひとつ重要な視点は”救済神”です。キリスト教的に言えば、”メシア思想”です。
釈尊の時代には、救済仏という考えは全面に出ておりません。基本的には、”自力”の思想であったと言って良いでしょう。
しかし、大乗仏教の興隆に伴い、阿弥陀仏の存在がクローズアップされてきました。浄土教ですね。
この浄土教というのは、仏教の中にキリスト教的な”メシア””救済仏”的な側面を補完的に降ろされた教えであると思います。
さきの、”絶対仏”と相まってこの”救済仏”の思想こそが、仏教の世界宗教化の原動力であり、かつ、キリスト教との接点になりうる思想であろうと考えます。
また、日本の浄土教においては、中国にはない展開が見られました。法然と親鸞による”選択(せんちゃく)”および”専修念仏”の思想です。
法然以前においても、10世紀の市の聖(いちのひじり)と呼ばれた空也(くうや)を嚆矢とする学僧たちの努力により、徐々に民衆の間にも口称念仏は拡がっていました。

六波羅蜜寺 空也上人像
そういう意味では、<民衆 – 念仏>という関係だけでは、法然の独自性はないと言えます。
しかし、法然は”選択”を深化することによって、念仏を、今まで機根の劣っていた民衆向けの「方便としての口称念仏」から、諸行往生を否定しつつ、「口称念仏でしか救われない」というふうに口称念仏を一元的に最高位に位置づけました。
*諸行往生:極楽浄土へ往生するためには、様々な善根を積み、往生の因として回向していくという思想
このいわゆる”専修念仏”に法然の独自性があります。親鸞は法然の思想をさらに「末法における仏法の正統」としてさらに理論化していきました。
これにより、日本浄土宗においては、阿弥陀仏は多仏のなかの一仏という位置づけから、「唯一絶対の仏」という地位を実質的に得たと言ってもいいでしょう。
そして、阿弥陀仏は”救済神”的側面とともに、さきの法華経における”絶対神”思想と同様に、あるいはさらに徹底した”絶対神”化を推し進める結果になりました。
実際は、法然にしろ親鸞にせよ、彼らの浄土経典解釈にはかなり強引なところがあり、それは当時の旧仏教側からも批判を浴びています。代表的なものが、明恵上人の『摧邪輪(ざいじゃりん)』です。
ただ、無理筋の解釈であったとしても、法然・親鸞の打ち出した理論と実践は、結果的に、身分や富貴を問わず、「阿弥陀仏の前では全員が全員、悪人・凡夫に過ぎないのだ」という”仏の前の平等観の徹底”という、また別の宗教的真理を全面に出すことになりました。
*参考書籍:『鎌倉仏教』(佐藤 弘夫 著)
これは仏教と言いつつ、ほとんどキリスト教の思想と言えるでしょう。この点はまた別の論考で考えてみたいと思います。
妬む神と慈悲の仏
慈悲のかたまりである仏と違って、セム的一神教の神は「裁く神、妬む神」の側面を持っていると言われます。
実際、「裁く仏、妬む仏」というのは聞いたことがありませんね。なのでやはり、「キリスト教の神と仏教の仏は種類が違う」という論拠になりそうです。
この点について、どう考えるか?
私は、セム的一神教における「神理解」のなかに究極神とは違う存在が混入していると考えます。
旧約聖書にときおり見られる「裁く神、妬む神」は本当にイエスが指し示した「天の父」なのでしょうか?
新約聖書を読んでいる感覚からすると、神の性質に随分と違いがあることが感じられるでしょう。
そもそも、「絶対神であって、かつ、妬む神」というのは矛盾しています。「妬む」というのは、その時点で「他の神」を想定しているわけですよね。
彼らに言った、「我は妬む神なり。我のほかに神なし」と。しかし、こう告げることにより、彼は天使たちにほかの神も現に存在することを示したのである。なぜなら、もしほかに神がいないのならば、彼はいったい誰を妬むことがあろうか。『ヨハネの秘書(アポクリュフォン)』
この「妬む神、裁く神」というのは絶対神ではなくて、ユダヤ教の民族神なのです。旧約聖書のなかに二種類の神が混入しているのです。
パレスチナ地方で絶対神というのは、もともとは”エル”もしくは”エロヒム”と呼ばれていました。こちらのほうが本当の絶対神であり、ヤハウェ(ヤーヴェ)のほうはユダヤの民族神だと思われます。
実際に、聖書文献学でも、ヤハウェ資料とエロヒム資料があると言われています。
預言者の資質により、エロヒムとは違う神の言葉を受信してしまったことがあるということです。
この「裁く神、妬む神」が旧約に残っているがゆえに、”聖絶”の思想ですね、これが正当化されて、近世ヨーロッパ以降の植民地主義が正当化されてきた側面があるでしょう。
キリスト教が普遍宗教化していく過程で、このユダヤの民族神であるヤハウェを切り離したほうが良かったのです。
実際、”異端”とされたキリスト教グノーシス主義にはそうした主張がありました。少なくともこの点はグノーシス主義の主張に正当性があったのです。上に引用した『ヨハネの秘書』に書かれてある言葉はそのことをよく示しています。
*参考記事;キリスト教グノーシス主義と仏教の接点序説
キリスト論
三位一体と三身説
キリスト教では、神理解にあたり、三位一体論の立場をとります。
これは歴史的には、「イエス・キリストをどう位置づけるか?」を巡って展開してきた理論です。
神は唯一ですが、3つのペルソナを持つと考えます。ペルソナはラテン語的な文脈では「仮面」といった意味です。
神が神のままでいるのであれば、到底、人間の理解の及ばないところにいることになります。救いもなくなってしまいます。
それゆえ、神は「子なるキリスト」として受肉した。人類はそれによって神を知り、神の救いに預かることができた、ということです。
かんたんに言えば、「神が人となった」のがイエス・キリストである、という理解です。
一方、仏教にも近い考え方があります。それが三身説です。
- 法身(ほっしん):仏陀の本質。法そのもの
- 報身(ほうじん):修行を通して仏陀となったという方便
- 応身(おうじん):地上に顕現した仏陀
つまり、「法身が地上に顕現した存在が応身としての仏陀・釈尊である」ということですね。
先の「超越 -内在」理論を援用すれば、報身とは唯一神に相当します。
ゆえに、応身としての仏陀・釈尊は、唯一神(報身)が受肉した存在である、と考えることも可能となります。
法身は、エッセンチア(本質)としての神に相当します。
ゆえに、三身説はキリスト教の三位一体論とほぼ同じことになります。
ちなみに、「キリスト教(あるいはセム的一神教)の神は人格神である。人格神の思想はいまだ人間的な想像の枠内に執われており、仏教的な”理法としての存在”としての法身仏という思想に比べると、いまだ未熟であると言える」といった主張が仏教側からなされることもあります。
しかし、この考えは、”三位一体”をごく表面レベルでしか理解できていないことに由来します。
ペルソナとして、「父と子と聖霊」と現れる以前の”絶対神”は、人格を超越していると考えられます。
ペルソナとして、あるいは仏教的に言えば、報身・応身として現れるときに、方便として”人格”をとっているに過ぎないのです。
開祖論
キリスト教の開祖はイエス・キリストであり、仏教の開祖はゴータマ・シッダールタ(ガウタマ・ブッダ)、釈尊である、ということは常識のようではありますが、ここのところは実はなかなか一筋縄ではいかないところがあります。
よく言われているように、イエス自身には新宗教を起こすというつもりはなく、あくまでユダヤ教の改革運動だった、という認識であったと思います。
ユダヤ教の流れの中で、メシア待望論(メシア思想)というのが出てきたわけですが、その文脈の中の”メシア(メサイヤ)”として自らを位置づけていたことでしょう。
ただ、イエス自身の教えの内容は、「サマリア人のたとえ」などに見られるように、ユダヤ民族という枠を超える普遍性を有していました。
ここの普遍性を具体的に開花させていったのは、むしろ、パウロの仕事であったでしょう。「キリスト教はパウロが創った」とも言われる所以です。
一方、釈尊の方はどうであったか、ということですが、インドではもともと”宗教”あるいは”宗派”という認識の仕方そのものがセム的一神教型とは違う側面があるように思えます。
インドでは、「私は、〇〇のダルマを信じている」という言い方をするのですね。この場合の”ダルマ”とは、「法・教え」のことです。
「私は、釈尊のダルマを信じている」という言い方で、これは、いわば「私は釈迦の哲学を信奉している」というニュアンスに近いかもしれません。
なので、釈尊が仏教の開祖であるのは間違いないことにせよ、釈尊自身に”イチ宗教”を起こす、という考えがあったかどうかは疑問です。
釈尊自身も、初期の頃は、「私はいにしえの仏陀たちが歩んだ法を発見したのだ」と語っています。
ただ、イエスにしろ、釈尊にせよ、動機としてはイチ宗教を起こすつもりはなかったかもしれませんが、語られる言葉に権威があったことは確かでしょう。
人々は、その教えに驚いた。それはイエスが、律法学者たちのようにではなく、権威ある者のように教えられたからである。(「マルコによる福音書」1章22節)

『山上の垂訓』カール・ハインリッヒ・ブロッホ画
比丘たちよ、如来に対して呼びかけるのに、名前を言ったり、また、友よ、などという呼びかたをしてはいけない。如来は、供養を受けるにふさわしく、正しくさとった者であるからだ。(『『ヴィナヤ』大品)

初転法輪の地・サールナート
その”権威”はイエスと釈尊の本来的な使命・霊格に由来するものであると私は考えています。根源的な法を説ける立場にいる、という共通点です。
仏陀とイエスはその生涯のなかのいくつかの出来事についても不思議な共通点があります。
まずは、生まれ方、です。
母マリアが聖霊に満たされ、処女懐妊でイエスが生まれたというのは有名な話ですね。一方、釈尊の方は、処女懐妊かどうかは問題にされていませんが、王妃マーヤ夫人が、右脇に白象が入る夢をみて、その後、右脇から生まれたとされています。
「本当かな?」と思わないでもないですが、後世の人たちが「イエスが(釈迦が)普通に生まれるはずがない」ということで、作り上げた話かもしれませんけどね。個人的には、そうした超常現象的な生まれ方をする必要はない、と思っています。
それから、生まれたあと、
イエスのもとには東方三博士が訪れ「ユダヤの王」と拝していった。釈尊のもとにはアシタ仙人がやってきて釈尊をご覧になっては、「転輪聖王か仏陀になるだろう」と予言しました。
キリストやメシアと聞くと、「宗教的な救世主」というイメージですが、メシアにはもともと油を注がれたもの=ユダヤの王という意味合いがあります。宗教指導者兼政治家というイメージです。
そういう意味では、「転輪聖王か仏陀か」というのと何となく似ていますよね。
それから、悟りを開く前に、釈尊は魔(パーピヤス・マーラ)と戦い、ついに勝って、悟りを開きます。これを「降魔成道」と言います。
イエスの方も、40日40夜にわたり荒野で「悪魔の誘惑」を退けた話がありますね。このように、「真理への覚醒前後」の話に共通点があります。
他、聖書に出てくるたとえ話が法華経の寓話に似ているとか、……いろいろ指摘することは可能です。水の上を歩いた、などの逸話(奇跡)も共通しています。
このように共通点も多いですが、説法の仕方・弟子の教育の仕方などはだいぶ違います。
ただ、本稿のテーマでもあるのですが、「違い」というのは、唯一の神(根本仏)が、時代性や地域性、民族性などを考慮して、どのような顕現の仕方をするか、という違いだと思いますので、「違うから違う」というのは一概にいえないと思うのですね。
私たちも、大人相手と子供相手では、話題も話し方も変えるでしょう。それと同じことです。
人間論
神成の思想と仏性論
人間論においても、キリスト教と仏教ではだいぶ違いがあると言われています。
神とは絶対的に隔絶した存在として想定されているセム的一神教の人間像とは違って、仏教における人間は「仏性を宿す存在」として、本質的には仏と同一視されています。
仏教においては、人間は修業によって仏に近づいていくことができると考えれています。智慧による解脱、そして涅槃の境地を得る。
一方、キリスト教では「恩寵による救済」を一般的には強調していますが、実は原始キリスト教においても、「智慧に基づいて神と成る」という思想はもともとはあったのです。
上述した”グノーシス主義”では、「人間はグノーシス(覚知、洞察)により、神性を顕現させていくことができる」とされていました。
この点においても、グノーシス主義がまったく異端とされたことで、人間論がずいぶんと狭いものになってしまったのです。
しかし、グノーシス主義者以外の神学者でも、似たようなことを考えた人はいます。
神が人となったのは、人が神になるためであった(アレクサンドリアのアタナシオスの言葉)
この言葉はオーソドックスなキリスト教としては解釈が苦しくなってしまいますが、グノーシス的に理解すれば、スッキリ筋が通ります。
- 神が人となったのは:イエスが地上に現れたのは
- 人が神になるためであった:(その教えに啓発された)人間が神に近づいていけるようになるためである
と理解すればよいのです。
この点は、カトリック・プロテスタントではなくて、東方正教会(ギリシャ正教、ロシア正教など)の方へ(限定的な意味であるにせよ)受け継がれています。
いわゆる、「神成の思想」です。
もっとも、神成の思想においては、人間が神そのものになる、というよりかは、「神に似る、神性に与ることができるようになる」という理解なのですけどね。
ペトロの手紙二1章4節にある言葉がその直接的な根拠とされています。
この栄光と力ある業とによって、わたしたちは尊くすばらしい約束を与えられています。それは、あなたがたがこれらによって、情欲に染まったこの世の退廃を免れ、神の本性にあずからせていただくようになるためです。(「ペトロの手紙二」1章4節
この”神成”の思想、そして、それをさらにラディカルに突き詰めたキリスト教グノーシス主義をもってはじめて以下の聖句の意味が分かるようになるのです。
あなたがたの天の父が完全であられるように、あなたがたも完全な者となりなさい。(マタイによる福音書5章48節)
「あなたがたも完全な者となりなさい」というイエスの言葉には、明らかに、人間には完全に近づいていく素養がある、すなわち、神性を有し神性を開花していくことができる存在である、ということが前提とされています。
グノーシス主義をミックスすると、イエス言行録は完全に近づく
キリスト教グノーシス主義はそうした神性の思想をより明らかに主張していました。
イエスが言った、「私はあなたの先生ではない。なぜなら、私が量った湧き出づる泉から飲み、酔いしれたからである。……私の口から飲むものは私のようになるであろう。そして、私もまた彼になるであろう。そして、隠されていたものが彼に現れるであろう」。(「トマスによる福音書」より)
歴史的にはグノーシス主義は異端として抹殺されてきましたが、本来はグノーシス主義にもイエスの思想は反映されていたのです。
上述した<超越と内在>論を敷衍すれば、「ヨハネ的な信仰/超越」と「トマス的な覚知/内在」は一見、矛盾しつつも総合可能なのです。
極論すれば、正統派(オーソドックス)とグノーシス主義を総合すると、本来のイエスの教えをより完全に近い形で復元することができるのです。
また、グノーシス(=認識、覚知)によって、神性を顕現させていく思想は仏教思想とも整合性を図ることができるようになります。
修道論
キリスト教においては、神と人間は絶対的に隔絶した存在として描かれています。
人間と天使、神は本質的に違いがあり、人間はどれだけ努力しても天使や神にはなれない、というのが一般的な理解でしょう。
ただ、上述した通り、「神成の思想」あるいはグノーシス主義的な思想を取り入れると、人間には神性があり、それを開花させていくことができる、ということで、本質的には、仏教における仏性論(如来蔵思想とも言う)とあまり変わりはなくなる、と理解することもできます。
神は言われた。「我々にかたどり、我々に似せて、人を造ろう。」(創世記1章26節)
この聖句は、「肉体的にかたどり」ということではなく、本質論としてかたどられた、と理解すべきだと思います。
肉体的にかたどるのであれば、神は肉体的・物体的な存在ということになり、それはすなわち、かたち=限定あるものとして、神の全能性に齟齬をきたすからです。
この項目にも「修道論」と名付けていますが、そもそもキリスト教において、修道という思想と実践があること自体が「人間が神に近づいていくことができる」という発想が前提になっています。
修道院では、「貞潔、清貧、従順」の3つの徳目を修道する、完成することが試みられているわけですよね。
知の弁証法
さて、とは言え、キリスト教において信者に求められているのは、どちらかと言うと「隣人愛」の実践であることは間違いはないでしょう。
隣人愛はいわば、水平的な愛であり、座標軸としては”横軸”的な実践、ということになります。
一方、仏教においては、布施行の大切さなども説かれていますが、重点としては、「限りなく悟りを求める」という菩提心、これは座標軸としては”縦軸”的な実践ということになりますね。
このように、キリスト教の水平的愛(横軸)と仏教の垂直的悟り(縦軸)をどのように総合していくことができるのか?というのがネオ仏法に課されている課題です。
実はこの問題については、すでに、別の記事で回答を出しています。
*参考記事:平等性智への階梯 – 平等知→差別知→平等性智へ
この参考記事をお読みいただいても大丈夫ですが、繰り返しを厭わずにここでもまとめてみましょう。
ここでは、仏教的な「智慧の段階論」を手がかりに考えてゆきます。智慧の段階論にはいくつかのパターンがありますが、ここで取り上げるのは”平等性智(びょうどうしょうち)”です。
まずは、”平等知”の段階があります。
これは、文字通り、人々が互いに対等な存在として認識し、愛し合うことができる境地です。これは簡潔に言えば、「天国的な心境」と言えるでしょう。キリスト教の隣人愛も(愛という観点からは)この境地を推奨されていると言えます。
次に、”差別知”の段階が来ます。”差別”は仏教用語としては、「しゃべつ」と読むのですけどね。まあでも、差別知(さべつち)という読みでいきましょう。
差別知も文字通り、人々の境涯に上下の差がある、という物の見方です。これは智慧を磨いていく過程で、どうしても出てくる感情でもあります。
知恵を身に着け、さらに高みを目指していくと、「自他の区別」がとても気になる段階に入ります。「できているか、できていないか」「優秀であるか、優秀でないか」…などなど、他者との比較でいろいろな違いが気になってくるのです。
あるいは、「自分の理想と現在の自分との比較」というかたちでも現れてきます。
この差別知の段階は、優秀性を発揮しつつあるという意味で平等知にはない喜びを感じる段階であり、また同時に、相対的な比較の中で苦しんでいく段階でもあります。
今、ここのところを読んでいるみなさんにも覚えがあることと思います。差別知は「自己実現していきたい」という思いの中にどうしても付随してくる知の段階なのです。
ところが、差別知のなかで苦しみ、人生においていろいろな浮沈を繰り返していると、あるときに”悲哀”を感じ始める時期がやってきます。
優秀さや自己発揮にはもちろん段階はあるものの、それはそれとして、「人はみな自己を実現しようとして苦しんだり、悲しんだり、時には傷つけ合ったりしているのだな」といった俯瞰したものの見方が出来るようになってきます。
これが”平等性智”の段階です。
差別は差別として認識しつつも、同時に、「みな喜んだり悲しんだりしているという意味では平等なんだ」「みな、幸福になろうとして頑張ってるんだ」という新たな平等感が芽生えてきます。
平等性智は、差別知をそのうちに含みつつ、なお平等知で物事を観察できるという意味で、初期の平等知とはステージアップした智慧の段階です。
このように、
平等知 – 差別知
という一見、矛盾する概念を総合する境地として”平等性智”というものがあるのです。これがネオ仏法で言うところの「知の弁証法」です。
そして、平等性智が心境としての平均打率に達すると、それはすなわち、「菩薩の境地」ということになるのです。
ざっくり申し上げると、十界論で言えば、
- 人界:平等知
- 天界:差別知
- 菩薩界:平等性智
という対応になっております。
平等性智において、知と愛が総合されているのです。
これは先のざっくりとした宗教の分類、
- 知の宗教:仏教
- 愛の宗教:キリスト教
を総合した境地でもあるのです。知の段階が同時に愛の発現段階にもなっているのです。
このように、仏教とキリスト教を総合する修道論として、「知の弁証法」という基礎理論を提唱してみたいと思います。
無我な愛(anattā-Agape)
”無我”というと仏教的な響きがあります。また”愛”はキリスト教において中心的な教えであります。
無我は”諸法無我”とも言いまして仏教の三法印のひとつです。これは、簡単に言えば、「関係性の哲学」なのです。
「あらゆる事象はそれ自体では存在できない。相寄ってひととき現象として存在しているのだ」という思想です。それ自体では存在できない、自性なるものがないから”無我”なのです。
こうした関係性の哲学は、より積極的に理解すると、「互いに支え合って存在しているのだ。ゆえに愛し合うべきである」という愛の思想に転化していきます。
また、自我中心の世界観を手放し、神的実在中心の世界観に回心・転回(コンバート)していくこともまさしく”無我”であり、こうした神中心の世界観は、まさにキリスト教の神論そのものでもあります。
ここにおいて、仏教的無我とキリスト教的愛は総合され、「無我な愛」という修道論が完成します。
以上、本稿では、キリスト教と仏教の総合を試みてみました。
本稿の副題に即して言えば、キリスト教的な「(神の)超越/信仰」と仏教的な「(仏性の)内在/覚知(悟り)」は両立する、というのが本論の主張するところです。
もっとも、キリスト教でもグノーシス主義を視野に入れると、「内在/覚知」の思想はもともとはあった。イエスはそこも説いていた、ということになります。
論点としては、「終末論」などまだまだ語りたい論点はありますが、都度、追記していきたいと思います。

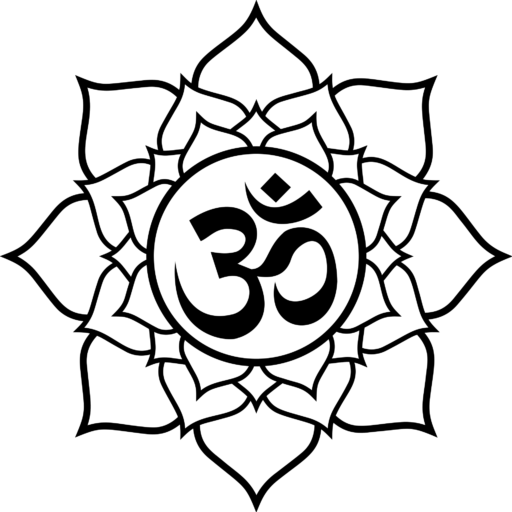





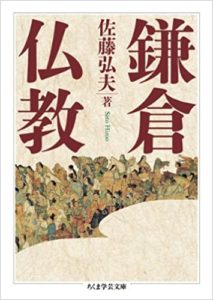









コメント