自我と無我の違い、というとまずは仏教のおける論点が気になるところです。
「自我」は心理学などでも使われている言葉ですが、「無我」はほぼ仏教用語ですからね。
そういうわけで、今回は主に仏教における自我と無我の違いはいかなるものか?について書いていこうと思います。
そもそも”我”はあるのか、ないのか? – 釈尊は自己を否定していない
近現代の仏教学では、「釈尊は無我を説いたのだから”我”は無い、ゆえに魂はない」という説がいまだ主流でしょう。
大乗の”空”の思想でも、「仏教は一切の実体的なるものを否定している」という理解が一般的だと思います。そうすると、やはり、「我なる実体的なものは存在しない」という結論に至りそうです。
…しかし、それほど単純に割り切れるものなのでしょうか?
「我がない」のであれば、そもそも修行する主体もなくなってしまうわけですから、八正道や六波羅蜜などの修行論がまったく意味をなさないことになってしまいます。
実際、お経には”自己”を強調する文言が沢山あります。一例を挙げましょう。
自己こそ自分の主である。他人がどうして(自分の)主であろうか?
自己をよくととのえたならば、得難き主を得る。(『ダンマパダ』(法句経)第12章「自己」)
これはかなり強烈ですよね。ここまで明確に”自己”を磨くことを釈尊は勧めているわけです。ゆえに、単純な「我がない」などという説はやはりどこかがおかしいと思わなければなりません。
さらに、有名なものとしては『涅槃経』に説かれている「自灯明(じとうみょう)」があります。死期が迫った釈尊の遺言ともいえる言葉です。
アーナンダよ、だからして、自己を洲とし、自己を依処として、他人を依処とすることなく、法を洲とし、法を依処として、他を依処とすることなくして住するがよい。(『涅槃経』- 『阿含経典3』増谷文雄〔訳〕)
ここでもハッキリと「自己」の大切さが説かれています。
なので、少なくとも現象としての「我は無い」というのは可笑しな説だといえるでしょう。
無我説は魂まで否定してはいない
自我について考える前に、まず、”無我”について検証していきます。
無我=無霊魂説はかなり危険な思想
冒頭で述べたように、近現代の仏教学では「無我だから、我はない、魂もない」論がいまだ優勢の状況です
しかし、私はその説に賛同しません。それどころか、かなり危険な思想と思っています。
なぜ危険と言えるかというと、魂レベルまで否定してしまう無我論は実質的に唯物論と同じになってしまい、それを信奉している人はまず死後、ストレートに天国領域に還っていくことが難しくなってしまうからです。
さきに引用した『ダンマパダ』でもつぎのように述べられています。
唯一なることわりを逸脱し、偽りを語り、彼岸の世界を無視している人は、どんな悪でもなさないものは無い。(「ダンマパタ」176)
この通りで、彼岸=あの世の世界を信じていない、つまり、「人生はこの世限りだ」と思っている人はどうしても享楽主義的な傾向に走ってしまうからです。「どうせ死ねば終わりなんだから」といった塩梅です。
あるいは逆に極端なペシミズムに陥る人もいるでしょう。
古代ギリシャにおいて、唯物論を説いたエピキュロスの学派はエピキュリアンと言いまして、今では「エピキュリアン」は”享楽主義者”という現代語になっています。
エピキュロスその人はむしろ精神的にストイックなタイプだったようですが、結局、その学説を信奉する人が”享楽主義”に流れていった経緯があるからこそ、そのように現代語として定着してしまったのでしょう。
釈尊はアートマンを否定したのか?
歴史的には、釈尊は当時のバラモン教(現在のヒンズー教の源流)にある「アートマン」の思想を否定したという流れがあります。
バラモン教にはまず「梵我一如(ぼんがいちにょ)」の思想がありました。
これは、宇宙的原理(梵/ブラフマン)と個人の魂(我/アートマン)は本質において一体なのだ、という思想です。
それに対して、釈尊は「アートマンではない、アナートマン(=無我)である」という主張をしたのですね。
そうするとやはり、釈尊は魂を否定したのではないか?となりそうですが、事はそんなに単純ではないのです。
というのも、初期経典の中に釈尊がアートマンを肯定している記述があるからです。
アートマンが存在する、と断定すると常見に陥る
アートマンが存在しない、と断定すると断見に陥る
(サンユッタ・ニカーヤ(相応部)44・10)
ポイントは(私が)下線を引いた部分です。
ここで明確に「アートマンが存在しない」という思想を否定しています。
ただ逆に、冒頭部分で「アートマンが存在する」という思想をも否定していますね。ここのところをどう考えるか?
その答えがまさに「断常の中道」なのです。
要するに釈尊は、アートマンに対して中道の姿勢を持った、ということです。決して否定する一方ではなかった。
結論から申し上げると、この問題は「我(=アートマン)なるものは変化しつつ持続する」で決着がつくのです。
たとえば、昨日のアナタと今日のアナタは同じであるのかどうか。あるいは極端に言えば、一秒前のアナタと今のアナタは同じであるのかどうか。
一秒前と比べてみると、厳密に言えば、髪の毛なども極小単位で伸びているでしょうし、細胞の生滅などもありますので、「違う」とも言えますよね。
ところが一方では、アナタはアナタとしての自己同一性(アインデンティティ)も保っているわけです。家族や友人に聞いてみれば分かるでしょう。
一秒後でも明日でも、家族・友人はアナタをアナタとして扱いますよね。
このように、アナタは「変化はしているが持続もしている」のです。変化と持続の中道を行っているわけです。これが断常の中道です。「変化しつつ(断)、持続している(常)」のです。
魂の問題もこれで解決が着きます。
来世と魂があってもそれは必ずしも「常見に陥っている」とは言えないのです。
肉体の死後、魂だけのアナタになったとしても、それはもちろん大きな変化ではありますが、アナタの個性まで奪われているわけではありません。アナタは一定のアイデンティティを保持しているのです。
このように、来世(あるいは前世)まで横断してアートマン(我)を考えるときも「断常の中道」で解決が着きます。魂は「有る」で良いのです。
逆に、「魂や死後の世界はまったくない」としてしまうと、これは断見に陥っていることになってしまいますよね。
仏典には来世(天界や地獄界など)や魂の話が沢山出てきます。一例だけ挙げておきましょう。
悪い行いをした人々は地獄へおもむき、善いことをした人々は善いところ(=天)に生まれるであろう。しかし他の人々はこの世で道を修して、汚れを去り、安らぎに入るであろう。(『ウダーナヴァルガ』第1章24節)
このように、釈尊の在家の人々に対する説法は三論、つまり、施論戒論生天論(せろんかいろんしょうてんろん)が中心でした。これは、
- 施論:施しをなし(善をなし)
- 戒論:戒めを守れば(悪をなさずば)
- 生天論:天界に生まれることができる
という単純な説法です。
これは基本説法ですので、魂やあの世が存在しないのであれば、「釈尊は嘘つき」ということになってしまいます。いくら方便を使うこともあるからといって、「妄語戒」を説いた釈尊がここまで明確に来世の話をするわけはないのです。
もっともこう言うと、仏教をかじったひとであれば、唯識説などを取り出して「輪廻する主体は阿頼耶識(あらやしき)なのだ」と反論する人もいるでしょう。
唯識説まで説明していると長くなりますのでそれは今回は省きますが、「阿頼耶識」とかムズカシイ言葉を使っても別に魂の存在とは矛盾しません。これも上述した「断常の中道」でカタがつくのです。
*ただ、唯識論についてはかなり実践的に使える内容ですので、いずれ別記事にして採り上げるつもりです。
仏教における無我とは結局、何か
さて、釈尊が
- (少なくとも現象としての)自己を肯定していること
- 無我=無霊魂説は誤りである
ということろまでご説明いたしました。
ここでもう一歩踏み込んで、「では、仏教における無我とはいかなる意味であるのか」ということを明らかにしていきたいと思います。
結論からいえば、無我は「存在論としての無我」と「作用論としての無我」の二局面から考える必要があるのです。
とくに後者の「作用論としての無我」から自我との対比が浮かび上がり、「無我と自我はどう違うのか」という問題に決着がつくことになると思われます。
存在論としての無我
存在とはいかなる様態で”在る”のでしょうか。
目の前にコップがあるとします。
そのコップはそれ自体として存在していますでしょうか?
まず、コップを乗せているテーブルなどがなければたちまち落下して壊れてしまいます。その他、空気や重力やいろいろな「関係性」のなかにコップは”在り”ます。
時間軸を入れて考えてみると、そのコップをデザインした人がいなければそのコップは「今ここ」に存在していないでしょう。
さらに、ひとつのコップを作るためには、さまざまな素材を集めたり、加工したり、企画会議や販促があったり…といった無数に近い過程があります。
そもそも、誰かが「コップというものがあったらいいな」というアイディアを出さなければ、目の前のコップはおろか、世界中にコップは存在していないことになります。
このように、空間軸、時間軸のどちらで考えても、目の前のコップはそれ自体では存在していません。いろいろな条件、関係性のなかでかろうじて「今ここ」に在ることを許されているかのようです。
そうしたさまざまな関係性のなかに存在が”在る”ことを仏教用語では「依他起性(えたきしょう)」と言います。存在は「他に依って起こる性質」を持っているということです。まさに、縁起(縁によって起こる)ですね。
また、それ自体では存在できないので、「無自性(むじしょう)」とも言います。文字通り、「自ずからなる性質が無い」ということです。
このように、それ自体では”在る”ことはできず、さまざまな関係性のなかでかろうじて”在る”こと、これを仏教では「無我」と呼んでいるのです。
それでは、「やっぱり”我”は無いのではないか?」と最初の疑問に戻ってきちゃいますよね。
かんたんに区別するのであれば、さきのコップでみたように、仮の在り方としては「有る」と言えるのですが、一方で、それ自体では存在できないという意味では「無い」とも言えます。
今風に言うならば、「現象としては有る」が「究極的な存在では無い」ということです。有無の中道です。
私たちの”自己”もやはり同じです。現象として錬磨すべき存在では有る。そこに修行論が要請されてくる。
ところが、さまざまな関係性の総体である大我から見れば、その大我の一部を構成しているところの自己は無いとも言える。繰り返しますが、ここに「有無の中道」が現れてくるのです。
本当に存在するものは総体のみ。大我のみ。これを宗教によって「根本仏」とか「創造神」と呼んでいるわけです。スピリチュアリティでは「ワンネス」などと呼びます。
ヘーゲルが言うように、「真なるものは全体である」のです。個物は現象に過ぎない。
ただし、個別であり現象に過ぎない”我”は修行により、自己拡大し、大我に近づいていくことができる。哲学的に言うならば、「実在性を高めていくことができる」のです。修行論はそのためにあります。
この「実在性を高めていく」過程を仏教では、「仏性が顕現する」と表現しているわけです。
ここの「全体と個物」の関係をさらに掘り下げてみたいのですが、相当に長くなりますので、ご興味がお有りの方は下記の記事をご参照ください。さらに「奥の奥」があり、ネオ仏法の真骨頂はここにあります。
*参考記事:ワンネス、仏教、宇宙。そしてネオ仏法の悟りへ
作用論としての無我
さて、現象としての”我”や”魂”は存在するという話をしました。
結論を先取りして言えば、その”我”の基本形が「自我」なのです。
自我はいったいどのような働きをするのか?
とくに地上に降りて肉体を持っていると、肉体と肉体を基盤とするさまざまな欲求(欲望)が生まれてきます。
そして自我はさまざまな対象に執着するようになります。
ところが地上は四苦八苦の世界ですよね。生老病死をはじめとする四苦八苦からは誰も逃れられません。
四苦八苦はつきつめていえば、「求不得苦(ぐふとくく)」に集約されると思います。「求めても得られない苦しみ」です。
なので、自我がさまざまな対象に執着しても、それは結局、求不得苦に繋がってしまうというジレンマを抱えることになります。文字通り、”苦”が生じるわけです。
ここのところは難しいことを言っているようで、じつは分かりやすいのです。
たとえば、「あの人とだけは別れたくない」と思ってもやがては別れはきますよね。そこで苦しみが生まれる。これが愛別離苦(あいべつりく)なのですが、これも結局、「愛を求めても永続できない苦しみ」すなわち”求不得苦”であると言えるのです。
その他の”苦”も同様です。すべて求不得苦に集約されてきます。
そこで釈尊は「苦しみの根源は執着にある」逆に言えば、「執着を離れれば安らぎの境地に達することができる」と喝破したのですね。
それは地上的なるものの永続性を願わないということでもあります。
ここに要請されるのが実は”無我”なのです。
ここでの無我はさきほどの存在論としての無我ではありません。
そうではなくて。「そうした現世的なさまざまな物事に執着する我は本当の我では無い」という意味での無我なのです。
現象としての”我”(=自我)はあるが、その我をいかに整えるか?”我”の作用を整えていくのです。これが作用論しての無我です。
まずは、現世的な物事を無常かつ無我なるもの(この場合は本体論としての無我です)として喝破して執着から離れる。これが第一段階です。
比丘たちよ、色(しき)は無常である。無常なるものは苦である。苦なるものは無我である。「雑阿含経1-9」
ここの「苦なるものは無我である」という場合の無我ですね。
我 →物事
という二元論で考えた場合、我は物事に対して”執着”という作用をしています。
*引用文の”色(しき)”は肉体を指しています。
その執着という自我の作用の仕方は本来の我では無い、無我である。だからそこから離れなさい、と説いているのです。
これが作用論としての無我です。
無我の理解がむずかしいのは、このように「本体論としての無我」と「作用論としての無我」がごっちゃになってしまうところにあります。
整理しますと以下のようになります。
- 存在論としての無我:真実在(一如)としての我は無い(ただし、現象としての我は有る)
- 作用論としての無我:現象としての我(=自我)がさまざまな物事に執着する、その作用の仕方は本来の我では無い。(その作用の仕方を止めよ、執着を離れなさい)
こういうことです。お分かりになりましたか?
自我とは何であるか?
順番が前後したようでありますが、つぎにようやく”自我”のほうを検証して参りたいと思います。
自我は消去すべき対象ではない
さきに「現象としての我(自己)はある」と書きましたが、ここのところがまさに自我の問題です。西洋的には、”エゴ(ego)”と言ったりしますね。
とくに仏教では自我をワルモノ扱いする傾向があります。
自我から執着が出てくる、そして苦しみに至る…というステップを踏みますので、「それでは、自我を無くせばいいのでは?」となるのは当然の成り行きであるかのようにも思えます。
ところが逆に、自我がまったく無くなったらどうなってしまうのか?
自我にはつねに基本的な欲求がつきまとっています。
代表的なものは三大欲求があります。「食欲、睡眠欲、性欲」の3つですね。
自我をまったく消去(デリート)して、これらの三大欲求を消してしまうとこれはこれで大変なことになってしまいます。
食欲と睡眠欲を絶ったら生きてはいけませんし、性欲を絶ったらこの地上に種の保存ができなくなってしまいます。
そうすると、地上にわざわざ生まれてきた意義も達成できないことになってしまいますよね。
なので、この「自我ワルモノ論」もやはりどこかおかしいのです。
結論から申し上げると、「自我は無くす対象ではなくて、整える対象である」ということです。
自我と自我を基盤にした欲求をより高次な目的に奉仕できるように整えていく、これが肝要です。
また、宗教などでもよく「赤子(子ども)のような心を取り戻す」といった物言いがありますが、これも果たして本当にそうなのか、疑いの余地があります。
実際は、赤子においては単に自我が未分化なだけであり、子どもにおいては(発達段階によりますが)「自我が確立している子のほうがそうでない子より他者への思いやり・配慮がある」という研究報告があります。
これは発達心理学が発見した重要な知見です。
つまり、人間においてはまず<自我の確立>は大事なことなのです。
自我(エゴ)→対象
という二元論的な図式があるからこそ、学びを進めることも可能になってきます。
現に今、「自我と無我の違いとは何か?」というテーマに取り組んでいますよね。
私( アナタ)→ (観念としての)自我もしくは無我
というふうにまずは二元論的に図式がないと、思考・思惟が成立しないのです。
さきに、「無我は存在論的には無自性であり、実体的なものは何もない。一切は現象に過ぎない」ということを述べましたね。
これも、「存在とは何か?」というふうに、
私(という自我)→存在(という概念)
の二元対立的図式において、思惟・思考することが可能であるから導き出せた結論であるのです。
この論理レベルの「真理の発見」があってはじめて、「では次に、一切は現象に過ぎないという真理を腑に落としていこう!」という修行レベルの段階に入ることができます。
このように考えてもやはり、ベースとなる自我が大切であることが分かります。
存在論としての自我と作用論としての自我
以上のように考察を進めていくと、結局、自我においても、無我のところで整理したように「存在論としての自我と作用論としての自我」に分けて考えたほうがよい、ということになりそうです。
まとめてみましょう
- 存在論としての自我:現象としての自我(ego)は有る。まずは<自我の確立>は必要ですらある。
- 作用論としての自我:自我が他者(or事物or概念)に働きかける、その作用の仕方で苦楽が分かれてくる。執着的な作用をする自我は本来的な自我では無い。
自我論においても、また<有無の中道>が大切であることが分かります。
結局、自我と無我の違いとは何か?
自我と無我は矛盾しない
縷々述べてきましたように、結局、無我にしても自我にしても、「存在論」と「作用論」に分けて考えないから混乱が生じているのだと思われます。
もう一度、両者を並べて整理してみましょう。
<無我>
- 存在論としての無我:真実在(一如)としての我は無い(ただし、現象としての我は有る)
- 作用論としての無我:現象としての我(=自我)がさまざまな物事に執着する、その作用の仕方は本来の我では無い。(その作用の仕方を止めよ、執着を離れなさい)
<自我>
- 存在論としての自我:現象としての自我(ego)は有る。まずは<自我の確立>は必要ですらある。
- 作用論としての自我:自我が他者(or事物or概念)に働きかける、その作用の仕方で苦楽が分かれてくる。執着的な作用をする自我は本来的な自我では無い。
このように並べてみると、釈尊の説法の本意は以下のようにまとめることができると思われます。
”自我なる存在”は現象として有る(存在論)が、その自我が他者(or事物or概念)に誤った働きかけ、すなわち執着をするときに苦が生じる(作用論)。
その苦を滅するためには、自我が真実在(一如)から見れば現象に過ぎない、本来は”無い”ということを知り(存在論)、自我が他者(or事物or概念)に執着することから離れなければならない(作用論)。
…とこのような感じで、「作用論」と「存在論」を横断しつつ、苦の克服が勧められているのだと思います。
要は、<自我>は無くすべき対象ではなく、作用論的に制御すべき錬磨すべき対象であるということ、そのために存在論的な<無我>を自らに突きつける必要がある、ということですね。
このように考えてくると、「自我と無我の違いとは?」という問いの立て方にそもそもズレがある、ということになるのではないでしょうか。
そして、無我愛へ
確立された自我は理性的な働きをします。
自我⇨他者(事物)
という二元対立のなかで文字通り対立するのではなく、他者ならどう考えるか?という客観的な視点を獲得することができます。
また、「対象をよく観察する」という哲学的・科学的な知性をも獲得することができるでしょう。
このように、自我は排除すべきものではなく(完全排除はそもそも不可能なのですが)、制御すべき対象であり、また、よく観察する主体であるべきなのです。
このような自我のあり方を唯識学派では「妙観察智(みょうかんざつち)」と呼びます。文字通り、妙なる観察する智慧です。
これがあるからこそ、自我は自らを対象化して八正道などの内省を行い、また事物の観察で哲学的・科学的知見を得て進歩していくことができるのです。
仮に菩薩・仏になったとしても、「衆生を救う」主体としての自己、自我は残ります。これは大欲(たいよく)と呼ぶべきものでしょう。
この菩薩・仏の段階では、確立された自我の上に真なる意味での無我が展開されてゆくのです。これを「無我愛」と呼ぶことにしましょう。
繰り返しますが、「真なるものは全体」であるのです。仏教用語に直せば「一如(いちにょ)」であります。
その一如の内部のおいて、まさに各々の多なる自我がひしめきあっているのです。
一如の中に多があり、また多が集まって一如となっている。まさに「一即多多即一(いっそくたそくいつ)」です。これが世界の真相です。
無我とは「あらゆるものがそれ自体では存在できず(無自性)、関係性の中にかろうじて「今ここ」にあるに過ぎない」という思想でした。
無我とはこのように「関係性」の哲学なのです。
ところが関係性というのは、「ただそのように在るのだ」という様態の説明で止まっているのであれば、「執着を断ち切る」という自利の側面しか見えてきません。いわば、受動的な無我です。
ここで、もう一歩踏み込んで、「自ら主体的に(善き)関係性を構築していく」という考え方があってもいいはずです。これは、能動的な無我です。
自ら積極的に働きかける無我、善を拡大せんとする無我、一如に奉仕せんとする無我です。
菩薩の無我とはこのように能動性に踏み込んでいく無我であるべきなのではないでしょうか。これがさきほど申し上げた<無我愛>です。
自我と無我の違いを超えて、よく調えられた自我をベースとして無我愛を展開してゆく。ここに無限の発展の余地があります。
そして主体的に関係性を構築してゆく<無我愛>は、この世における発展・繁栄をも肯定する新時代の宗教哲学的支柱になりうる、と私は信じています。

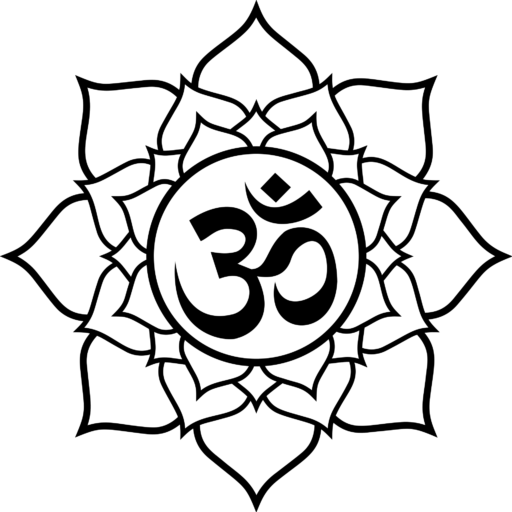










コメント