「原罪と贖罪の違い」については、定義としてはわりと簡単に整理できます。
- 原罪:アダムとイヴが「知恵の木の実(善悪の知識の木)」を食べたという過失による楽園追放により、人類は罪人とされた
- 贖罪:イエスの十字架による贖いにより、人類の罪は許された
と、シンプルに言えばこういうことですね。
順序としては、原罪があって、それに対して贖罪で解決をつけられた。つまり、原罪が先で贖罪が後、ということになります。
ところが、兄弟宗教であるユダヤ教とイスラム教では原罪の観念がありません。
後発のイスラム教はともかく、なぜ先発のユダヤ教に原罪の観念がないのか?あるいは、あっても、それほど重要視されていないのか?
これは結局、原罪→贖罪という流れは実は逆であって、
- イエスの刑死を贖罪として解釈したかった
- そのために前提としての罪があるはずで、それを楽園追放の物語に結びつけ、原罪とした
というふうに、成立としては、贖罪→原罪の順序となっていると考えて良いでしょう。
しかし、キリスト教徒でない門外漢にとっては、「イエスの刑死を本当に贖罪と考えるべきなのか?」という「そもそも論」的な疑問も湧いてきます。
いきなり話が逸れるようですが、”罪”といえば、ドストエフスキーの代表作『カラマーゾフの兄弟』『罪と罰』の両書において、ひとつの中心的なテーマになっています。
ドストエフスキーは「長大で難解でとっつきにくい」というイメージですが、今読み直してみると、やはりかなり霊格が高そうで、菩薩界でもかなり上層の存在なのだろうな、と直感しました。
やっぱり、多くの人にとって「とっつきにくい」というのは、作者の霊格が高すぎて…、当サイトでよく言っている波動理論ですね、「菩薩界の波動が高すぎて、合わない。居づらい」という面があるんだろうと思います。
*参考記事:人生の意味とミッションとは?
…ということは、ちょっと我慢して、ほんの一定の時間でも接してみる、ということを続けていくと、「少し波動に馴染んでくる→少し、自らの霊格を上げられる」ということになるのかな、と思います。
これは自らの霊格を上げるためのコツでもあります。
ドストエフスキー論そのものはまた別の機会に取り組んでみたいと思っております。
今回は、『カラマーゾフの兄弟』の一節を引用しつつ、「原罪とはなにか?」「イエスの贖罪とは?」というテーマについて考えてみます。
ドストエフスキー『カラマーゾフの兄弟』にキリスト教の核心をみる
『カラマーゾフの兄弟』の中に、とある「改心した少年」の描写が出てきます。改心後の少年の言葉に私はすごい衝撃を受けましたので、引用させてください。
その少年が母親に語っている言葉です。
ぼくたちはだれでもすべての人に対して、すべてのことについて罪があるのです。
そのうちでもぼくが一ばん罪が深いのです。
この言葉にすごい衝撃を受けまして…、私の宗教性では、感覚的にうっすらとわかるような気もする、というあたりなのですが、キリスト教的に真に目覚めると、こういう言葉がでてくるなろうなって思いました。
ドストエフスキーはこの少年に、(文学なので)あえて、理論的に語らせてないのでしょうけど、おそらく、ドストエフスキー自身が、当然、キリスト教の核心を掴みきっているのだな、と思うのですね。

<我あり>という思いからは、決して上記の言葉は出てきません。
自我を脱して<神的実在>へ溶け込むことができるから、「人類全体に責任を感じる」ことができる。
かつ、<現象>としての自我もやはり、限定的な意味では”有る”ので、「自分の罪をいちばん体感できる」ということだと思うのです。
なので、まとめますと、
- 実在側からの感覚:「ぼくたちはだれでもすべての人に対して、すべてのことについて罪があるのです。」
- 現象側からの感覚:「そのうちでもぼくが一ばん罪が深いのです」
というふうに、哲学ではなく、文学表現に(しかも舌足らずに)置き換えるとこのようになりますね。
ここまでの真理を把握し、かつ、作品化することができた。かつ、世界的に影響を与えた。今も一応は読みつがれている、ということ。ドストエフスキーは、
霊格=智慧×慈悲
がものすごく大きいということが分かりますね。
*参考記事:芸術と哲学の関係 – イデーの模倣としてのアート
学生の頃だったか、『罪と罰』を読んで、「ふーん、なかなか…刑事コロンボみたいで面白いかも、長すぎるけど」くらいの感想だったのですが、今読み返してみると、やはり、すごく深いです。
*本当に、コロンボは『罪と罰』の判事と犯人のやり取りをモデルにしている説があります
- 罪:罪は自覚によって、神の無限の愛で即座に許される(主人公は改心し、神と真実の愛に目覚める)
- 罰:しかし、因果の理はくらますことはできず、カルマの刈り取りはある(主人公はシベリア刑務所行き)
と、こんな感じです。
原罪と贖罪(イエスの贖い)はどう関係するか?
さて、上記の少年の言葉のように、「罪を引き受ける」ということと、キリスト教の教義にある”原罪”および”イエスの贖罪思想”はどう違うか?
キリスト教というと、まず信者でない人でも思い浮かぶ教義として”贖罪思想”(しょくざいしそう)”贖罪説”がありますね。
すなわち、「イエスはアダムとエバ(イブ)以来の、全人類の罪(原罪)を十字架によって贖った」という解釈です。
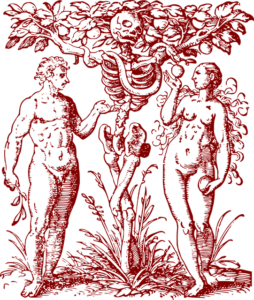
じつはこれは、かなり微妙な問題を含んでいるのではないか?と私は考えています。
まず、なによりも、使徒たちが宣教したことは、あくまでも「復活の福音」であって(「使徒行伝」参照)、イエスの贖罪ではなかった、という事実的理解が前提としてあります。
贖罪説はもともと、イエスの実弟ヤコブを中心とした初期イスラエル教会のなかで唱えられたものです。
十字架刑というのは、旧約聖書の流れから言っても、「もっとも残酷で律法的にも最大の屈辱的な刑罰」ですので、これはそのままストレートに受け取ると、イエス・キリストという存在の権威性を犯してしまうような、そうした受け取り方をなされてしまいます。
そこで、ヤコブを始めとした初期エルサレム教会の指導者は、”贖罪説”を唱えていくことになったのですね。
つまり、ユダヤ教の”過越しの祭り”で子羊が屠られますが、その”屠る”をイエスの十字架にからめて解釈したのです。
”イエスの屠り”によって、原罪は贖われた。これが旧約から預言されていた神の計画だ、という説です。
ここにはあくまでも、ユダヤ教教義の整合性に囚われている発想の一形態があります。
実際、彼ら(初期エルサレルム教会の指導者たち)は、「食事の際、異教徒と同席すべきか?」「割礼を非ユダヤ系キリスト教徒にも適用すべきか?」というような、キリスト教の世界宗教化・普遍化とは相反する意見を持っていたわけです。
ここらへんが、”異邦人”をおもに宣教の対象としていたパウロと意見を異にするきっかけとなったのでした。
もちろん、パウロの書簡にもそうした贖罪説は展開されておりますし、むしろ、パウロ神学というと、この”イエスは全人類の罪を贖った”という贖罪思想が中心であるかのように一般に受け取られております。
しかし、(今回はいちいち引用しませんが)パウロが贖罪説を展開する場合は、どうも歯切れがわるいのですね。

詳細はここでは述べませんが、どうもパウロの真意、もしくは本当に強調したかったことは贖罪説にあったのかどうか?ちょっと疑問に思うところがあります。
パウロはヤコブを中心とする初期エルサレム教会の面々に遠慮しただけではないのか…?
しかしこの点に関しては、「パウロの十字架の神学」をネオ仏法としてどう考えるか?また別の機会に論じてみたいと思います。
今回は、この「原罪とイエスの贖い」をどう考えるか?という論点です。
まず、”原罪”を文字通りに受け取ってしまうと、アダムとエバの堕落、”罪”がその後の人類すべてに及んでいる、という解釈ですね。本当にこれは真理であるのか?
この解釈に依ってしまうと、アダムとエバという、いわば”他者”の罪が、現在の人類に負わされている、ということになってしまいます。これは逆に言えば、「責任転換の論理」へと直接接続する危険性があります。
「私たちが不幸であるのは、アダムとエバの原罪によるのだ」という発想です。
この考えは、一見、さきの『カラマーゾフの兄弟』に登場する少年の言葉と同じに聞こえます。
少年の言葉は、「ぼくたちは〜すべてのことについて罪があるのです。」でしたね。
しかし、この少年の言わんとしていることは、アダムとエバへの他責ではなく、むしろ真逆の、いわば「全人類の罪を引き受ける」という発想でしょう。
これはアダムとエバよりも、むしろイエスに似ている態度です。イエスに倣った立ち位置。決して他責ではありません。

そうするとやはり、贖罪説の根本にあるところの”原罪思想”をあらためて吟味する必要が出てきます。
解決策としては、やはり、「アダムとエバの原罪と楽園追放」をひとつの暗喩として受け取る方向です。
”原罪”というのは、物語的な(あるいは事実としての)アダムとエバという”祖先”が犯してしまった罪、という事実的解釈ではなく、暗喩的解釈ですね。
つまり、人間が唯一神という<神的実在>中心の価値観から、神の真理ではなく自らの知識を拠り所としようとする<自我中心>の価値観へに染まってしまう、という暗喩です。
これは誰しも陥ってしまう陥穽ですし、また実際に過去および現代においてもほとんどの人間が陥っている罪です。
”罪”という言葉のもともとの原意は「的外れ」という意味です。
これはハイデガー的に言うと”非本来性”ということですね。本来的でない在り方。
…ということは、裏を返せば、罪から脱した状態が”本来性”を取り戻す、という状況です。
そして、罪から脱した状態への転回は、まさにさきの<自我中心>から<神的実在中心>への転回でもあります。
これは、『宗教多元主義』の唱道者ジョン・ヒックによって展開されている論理そのものでもあります。
したがって、「イエスは全人類の罪を贖った」という贖罪説も、やはり文字通りに受け取るべきではなく、暗喩的に解釈することが肝要です。
そうでないと、「自分の罪はアダムとエバのせい。だけれども、イエス様が贖ってくださった」という…、どこまでいっても”他責”の論理になってしまいます。
そうではなく、贖罪説はやはり、
「イエスは、<自我中心>の非本来的な人間の在り方(”罪”)から、「天なる父」という<神的実在>中心の価値観への大転換を主に愛(アガペー)を軸に説き、十字架という犠牲愛の実践によって自ら手本を示された」
という、象徴的解釈ですね、ここに依るべきだと思います。
そうであってこそ、<自我ー他者>という孤立化の図式から、愛(アガペー)という側面からの<神的実在と一体である>という図式へと転換し、それにより、<自他一体><全体性の回復>という”本来性”への回帰を人類は果たすことができると思うのです。

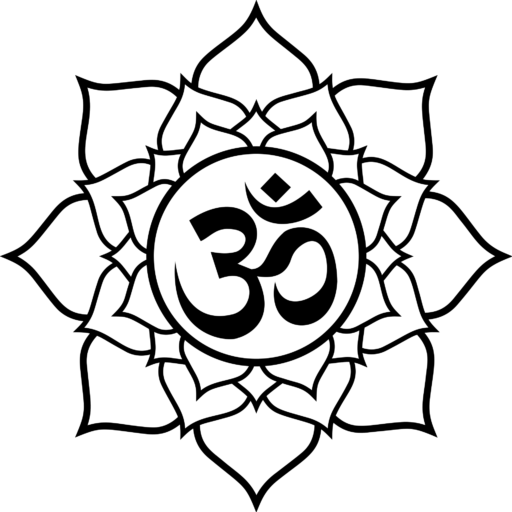











コメント