ひとくちに「グノーシス主義」と言っても、かなり広い守備範囲を持っています。新ピュタゴラス学派から新プラトン主義などの背景にもグノーシス主義の影響がうかがえますが、今回はあくまでもキリスト教グノーシス主義に絞って考察してみます。
時代背景としては、ローマ五賢帝の時代。18世紀イギリスの歴史家ギボンが言うところの「人類史上もっとも幸福な時代」を中心に展開されたキリスト教思想運動です。
「グノーシス」という言葉自体は、「知識」「認識」を意味するギリシャ語に由来します。
グノーシス主義については、1945年にエジプトで「ナグ・ハマディ写本」(「ナグ・ハマディ文書」)という大部のグノーシス文献が発見され、研究が活発になった経緯があります。
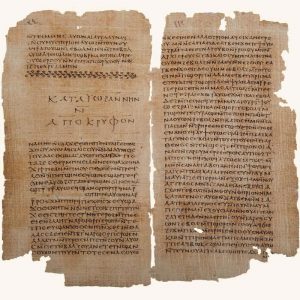
ナグ・ハマディ写本『トマスによる福音書』
なお、本論の考察にあたっては下記の書籍を手がかりにしております。
参考書籍:『グノーシス 古代キリスト教の〈異端思想〉』 (講談社選書メチエ:筒井賢治 著)
キリスト教グノーシス主義と仏教の接点については、イギリスの仏教学者エドワード・コンツェが示唆しているようです。
コンツェは、「仏教徒が南部インドで、トマス派のキリスト教徒(すなわち、『トマス福音書』のような諸文書を知り、それを用いていたキリスト教徒)と接触していた、と指摘しています。
また、グノーシス主義が隆盛をきわめた頃には、何世代にもわたって、仏教の伝道師たちがアレクサンドリアで布教していたという史実もあるようです。
*参考文献:『ナグ・ハマディ写本―初期キリスト教の正統と異端』(エレーヌ・ペイゲルス著)p18
また、コンツェは大乗仏教とグノーシス主義との共通点を指摘しています。
コンツェの8つの類似点に基づいて、ホーラーは以下のような類似点のリストを挙げています。
- 解放や救済は、解放のための洞察、すなわちグノーシスやジュニャーナによって達成される。
- 無知、すなわち洞察力の欠如は、アグノーシスまたは無明と呼ばれ、この世に閉じ込められる根本的な原因となっている。
- 解放された洞察は外的な知識ではなく、内的な啓示によって得られる。
- どちらの体系も、盲目的な唯物論から完全な精神的達成へと、精神的達成を階層的に順序付けている。
- 智慧はソフィアと般若に擬人化された女性原理として、両宗教で重要な役割を果たしている。
- キリストや仏陀は単なる歴史上の人物ではなく、原初的な存在として描かれている。
- どちらの宗教にも「反知性主義」の傾向がある。つまり、より高い精神的達成のためには、規則や社会的慣習を無視するということである。
- どちらの体系も、一般大衆ではなく精神的エリートを対象としており、隠された意味や教えがある。
以下、キリスト教グノーシス主義をてがかりに、仏教との類似点・共通点を探っていきます。
グノーシスの定義に沿ってキリスト教グノーシス主義と仏教の類似点を探る
以下は、「グノーシス主義の起源に関する国際学会」(1966年:於メッシーナ)による提言の要約です。
- 反宇宙的二元論
- 人間の内部に「神的花火」「本来的自己」が存在するという確信
- 人間に自己の本質を認識させる救済啓示者の存在
以下、この3点を手がかりに考察していきますね。
1. 反宇宙的二元論
「反宇宙的二元論」では、劣悪な物質世界であるこの世と魂の故郷である本来的世界をまずはくっきりと二元対立的な世界として分けます。
そして、この劣悪な物質世界は、旧約の「創世記」の神(グノーシス用語では”デーミウルゴス”と言います)が創造したとします。
ここから導き出されるのは、イエスが「わが父、主」と呼んだ至高神と、ユダヤ教(旧約聖書)で言う創造神(世界を創った神)は別存在である、という考え方です。
新約聖書と旧約聖書を素直に読み比べてみると、やはり違和感があります。ひとくちに旧約聖書と言っても、内容も年代も幅広いので、すべてに疑問があるというわけではないですが、
随所に出てくる「裁きの神」ですね。あるいは、「人類を試す神」、こうした有り体に言えば偏狭な神が、イエスの信じた「愛の神」と同じものと考えるには、ずいぶんと違和感があります。
このモチーフは、グノーシス主義に関わらず、疑問に思う人は多いでしょう。
かのアウグスティヌスも『告白』において、若き頃の放縦な生活とマニ教への傾倒を懺悔していますが、そもそもマニ教へ傾倒した動機が「旧約の神を論理的に信じることができない」というところにあったのです。
アウグスティヌスはその後、師アンブロシウスに出会い、旧約聖書はアレゴリー(寓話)的解釈をすればよい、というところに落ち着き、ようやくキリスト教に帰依するようになります。
ただ、やはり私は、旧約聖書に登場する「裁きの神」とイエスが信じた「愛の神」は別存在である、と解釈したほうがスッキリすると思いますね。
旧約聖書の創造神は一般に、ヤハウェ(ヤーヴェ)とされておりますが、今ひとつ、エロヒムという呼び方をされることもあります。
エロヒムはもともとパレスチナ地方では至高神とされていた存在です。
聖書学でもJ(ヤハウェ)資料とE(エロヒム)資料と分けることもありますが、私は、ヤハウェはユダヤの民族神であって、エロヒムのほうがイエスが信じた愛の神、至高神だと推測しています。
*参考記事:ヤハウェとエロヒムは別の神である – 民族神と最高神を区別したほうが良い理由
「裁きの神、妬む神(ヤハウェ)」が至高神というのはおかしな話ではないでしょうか?この点、グノーシス文書である「ヨハネの秘書(アポクリュフォン」に鋭い指摘があります。
彼らに言った、「我は妬む神なり。我のほかに神なし」と。しかし、こう告げることにより、彼は天使たちにほかの神も現に存在することを示したのである。なぜなら、もしほかに神がいないのならば、彼はいったい誰を妬むことがあろうか。(「ヨハネの秘書(アポクリュフォン)」)
新宗教を立てる際には、どうしても従来の権威を借りなければ、なかなか民衆が付いて来ないという側面はどうしてもあります。
それがキリスト教の場合は、旧約の予言であったり、アブラハム以来のイエスの系図を書いたり、というところに現れているのではないかと思われます。
これは仏教においても同様で、釈尊も初期の頃は、「私の教えは私のオリジナルではなく、過去の仏陀たちが説いていた真理を発見したものなのだ」という趣旨のことを述べています。
これが過去七仏の思想になっていくわけですね。つまり、釈尊においても初期には伝統の権威を借りていたということです。
ただし、釈尊は40数年にわたる教団運営の実績に支えられ、次第に伝統の権威から離れていくことになります。
法華経にいう「久遠実成の仏陀(くおんじつじょうのぶっだ)」。つまり、修行して覚りを開いたのではなく、自らの本当の姿は根本仏と一体なのだ、という思想に変わっていきます。
これは、キリスト教グノーシスで言う至高神(エロヒム)に相当すると解釈してもよろしいかと思います。というか、そのように解釈することによって、キリスト教と仏教を立体的に統合する契機になっていきます。
もちろん、「大乗非仏説」的には、法華経がどれだけ釈尊の直説を反映しているかについては一定の疑問がありますが、
大乗仏教のなかで超越的・絶対的な仏陀・如来が登場してきた背景には、ある程度、実在世界における釈尊自身の意思が反映されていたと見做すほうが自然だと思いますね。
2. 人間の内部に「神的花火」「本来的自己」が存在するという確信
人間やこの世については「劣悪な創造神」の産物であるが、人間の中には至高神に繋がる「神的花火」「本来的自己」がある。これを認識(グノーシス)することが大事である、という思想があります。
若干、現世否定が行き過ぎている感がないでもないですが、こうした「神的花火」「本来的自己」といった要素は、仏教で言う「仏性」とほぼ同一の思想ですね。
イエスが言った、「あなたがたがあなたがたの中にあるものを引き出すならば、それが、あなたがたを救うであろう。あなたがたの中にあるものを引き出さなければ、それは、あなたがたを破滅させるだろう」。(トマス福音書」)
正統キリスト教理では、「父と子と聖霊」と人間はまったく別物であり、人間は原罪を背負ったひたすら救済されるべき存在という解釈であるのに対し、人間観においてかなり力強い思想です。
3. 人間に自己の本質を認識させる救済啓示者の存在
グノーシス主義者のひとりであるプトレマイオスの神話では、至高神プロパトールを最上位とする「プレーローマ」なる上位世界が存在しているが、紆余曲折あって、劣悪な「裁きの神」によって、この世と人間が生み出された、とされます。
人間には、「物質的部分」「心魂的部分」「霊的部分」の3つがあり、このうちの霊的部分(2, の論点であった「神的花火」「本来的自己」)が「プレーローマ」から派遣されたキリストの啓示によって救済される、という救済論に落ち着くことになります。
神話については、グノーシス主義を正当化させる「後付け」感が否めないですが(笑)、
- 人間のなかの霊的部分(「プレーローマ」を故郷とする)がキリストの啓示によって思い起こされるということ。
- 人間にとっての救済は、自らの霊的部分の本質を認識(グノーシス)することが必須条件になる、
との教説は、正統キリスト教会の教義よりも、ずっと積極的な思想です。
むしろ、仏教思想に通底するものがあり、ほんとうの意味で普遍(カソリック)であるとも言えるのではないかと思います。
また、ナグ・ハマディ文書の『フィリポ福音書』によれば、「復活」の概念も正当キリスト教義よりもずっと精神化・内面化されていることに気づきます。
「人はまず死に、それから甦るのだ、という人は間違っている。人は、まず生きているうちに復活を受けなければ、死んだときに何も受けないだろう」(「フィリポ福音書」)
この思想も、「現象界(この世)での心境がすなわち実在界(あの世)の行き先を決めるのだ」という仏教思想とも通じるところがありますね。
ユダヤ・キリスト教に流れる<再来・輪廻転生>思想
グノーシス主義の一派であるカルポクラテース派では、「この世においてすべてを体験しておかなければ、魂は再び転生を強いられる」と信じられていました。
仏教の輪廻転生論よりもむしろラディカルなくらいですね。
輪廻転生について新約聖書から根拠を見出すとすれば、たとえば、下記の記述が挙げられます。
「ラビ、この人が生まれつき目が見えないのは、だれが罪を犯したからですか。本人ですか。それとも、両親ですか。」(「ヨハネによる福音書」9章2節)
この一節では、「本人ですか」の部分ですね、「生まれつき目が見えない」ことの原因を時系列で遡っているということは、”前世”があったことを示唆しています。
また、旧約と新約にまたがって信じられていたものに「エリヤの再来」があります。
見よ、わたしは大いなる恐るべき主の日が来る前に預言者エリヤをあなたたちに遣わす。(「マラキ書」3章23節)
エリヤは紀元前9世紀の預言者であり、この「マラキ書」は紀元前5世紀頃に書かれていますので、ユダヤ教ベースで考えても、<再来>が信じられていたことを伺わせられます。
この旧約の予言が、新約聖書においても、バプテスマのヨハネやイエス自身が「エリヤの再来ではないか」と見做される根拠になっているわけです。
そして、イエスに、「なぜ、律法学者は、まずエリヤが来るはずだと言っているのでしょうか」と尋ねた。イエスは言われた。「確かに、まずエリヤが来て、すべてを元どおりにする。それなら、人の子は苦しみを重ね、辱めを受けると聖書に書いてあるのはなぜか。しかし、言っておく。エリヤは来たが、彼について聖書に書いてあるように、人々は好きなようにあしらったのである。」(「マルコによる福音書」9章11-13節)
”三位一体”など、聖書の根拠に乏しくても、キリスト教理の中核になっているくらいですので、この引用でお分かりのように、輪廻転生のほうがむしろ聖書的根拠がハッキリあると認めても良さそうに思えます。
それにしても、こうした輪廻転生論が正統キリスト教義に取り入れられていれば、キリスト教史、ひいては世界史もずいぶん違ったものになったであろうと残念です。
神義論などは、じつは輪廻転生を入れていかないとなかなか弁証しきれないのです。今世だけでは、明らかに不公平が出てしまいますからね。
*参考記事:神義論への分かりやすい最終回答 – 全能の神が創った世界になぜ悪があるのか?
ソフィア(知恵)と般若の智慧
グノーシス主義と仏教をつなぐ共通点として、女性的原理とされるソフィア(知恵)と”仏母”と言われる般若の智慧があります。
般若の智慧、般若波羅蜜多はサンスクリット語で”プラジュナーパーラミター”と言いますが、語源的には、
- プラ:先だつところの
- ジュニャー:智慧
ということで、日常的な意味での知恵ではなく、真理を洞察する奥深い智慧を意味しています。グノーシス主義における”ソフィア(知恵)”も同様です。
実際に、欧米の学者のなかには、『般若心経』を仏教的グノーシス経典と呼ぶ学者もいるようです。
また、実は”グノーシス”と”ジュニャー”は語源的にも同根とされています。
最後に、グノーシス=知識、認識とは何を内容としているのか。キリスト教グノーシス主義者のひとりであるテオドトスの言葉を引用しておきます。
すぐれて哲学的な問いです。
我々は誰だったのか、我々は何になったのか。我々はどこにいたのか、我々はどこに投げ込まれたのか。我々はどこに向かうのか、我々はどこから解放されるのか。誕生とは何か、再生とは何か。
なお、キリスト教と仏教全般の違いを乗り越える基礎理論については、下記の記事にて詳述していますので、参考になさってください。
*参考記事:仏教とキリスト教の違いを総合するネオ仏法



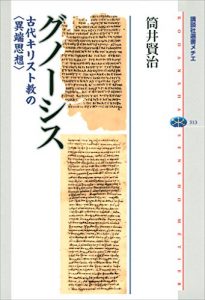


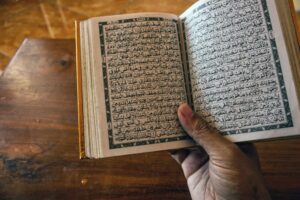







コメント
コメント一覧 (2件)
そうですね、ゴーギャンのその絵は私も大好きです。
ただ、経緯は知らなかったので、教えて頂き、感謝です。
ゴーギャンはキリスト教教理の問いを換骨奪胎して、自らの思想告白としてあの絵を描いたのかもしれませんね。
最後のテオドトスの言葉は,フランスの画家ゴーギャンの代表作「我々はどこから来たのか 我々は何者か 我々はどこへ行くのか」にそっくりですね。気になって調べてみたところ,やはりキリスト教と関連があったみたいです。以下Wikipediaからの引用です。
ゴーギャンは、11歳から16歳までオルレアン郊外のラ・シャペル=サン=メスマン神学校の学生であった。そして、この学校には、オルレアン司教フェリックス・デュパンルーを教師とするカトリックの典礼の授業もあった。デュパンルーは、神学校の生徒たちの心にキリスト教の教理問答を植え付け、その後の人生に正しい教義において霊的な影響を与えようと試みた。この教理における3つの基本的な問答は「人間はどこから来たのか」、「どこへ行こうとするのか」、「人間はどうやって進歩していくのか」であった。ゴーギャンは、後半生にキリスト教に対して猛反発するようになるが、デュパンルーが教え込んだこれらのキリスト教教理問答は、ゴーギャンから離れることはなかったと言える。