”観自在菩薩”でお経が始まる驚き
前回(波羅蜜多心経 – 般若の智慧の心髄(エッセンス)が『般若心経』)の続きです。今回でシリーズ第3回目です。
*シリーズ初回は、摩訶般若 – 仏教的グノーシスの経典としての『般若経』
今回はいよいよ本文。冒頭の、”観自在菩薩”の部分ですね。
観自在菩薩
読み:かんじざいぼさつ
現代語訳:観自在菩薩が、
じつはお経としてはですね、この「観自在菩薩…」という出だしはけっこうびっくりというか、奇異に感じるところです。
信者以外の人にとって、お経は法事などで聞くパターンがほとんどかな、と思いますが、たいていは、
にょーぜーがーもーん
という音で始まりますよね。
これは、
如是我聞(にょぜがもん)ということで、「私はこのように(仏陀から)聞いた」という意味です。
つまり、「私の勝手な考えを説くわけではなくて、(私が聞いたところの)仏陀の説法をこれからご紹介しますよ」ということですね。
そしてたいていは、この「如是我聞」の次に、仏陀が説法した場所とか、聴聞者は誰であったのか、などが書かれています。
要は、お経というのは、少なくとも建前上は「仏説」ということで、仏陀の説法を記述しているものです。
*例外的に、仏陀の高弟が説法の主役の場合もある
実際、他の般若系の経典では、仏陀が高弟のスブーティ(須菩提・しゅぼだい)の質問に答える、という形式をとっていたりします。
般若系の経典は、空(くう)の教えを説くものですから、「解空第一(げくうだいいち)」と呼ばれていたスプーティが質問役になっていることが多いのです。
代表的な般若経典としては、たとえば、『金剛般若経』などがあります。「『般若心経』以外も読んでみたい!」という方には、岡野守也著の『『金剛般若経』全講義』がお薦めです。
なので、この般若心経の出だしですね、”観自在菩薩”でいきなり始まるというのは、ちょっとびっくりするところで、
例えはアレですが、ビートルズの”A HARD DAY’S NIGHT”という曲は、12弦ギターのカッティングのジャーン!!でいきなり始まりますが、こういうインパクトですかね、
ビートルズ登場前は、なんだかんだとイントロが長かったので、「ジャーン!!で始まるのかい?」というインパクトは当時はかなり大きかったと思います。
なので(?)、なぜ般若心経の出だしが珍しいか?ということを整理しますと、
- 仏陀ではなく、観自在菩薩が説法の主体になっていること
- 他の般若系経典にはあまり縁がないと思われる観自在菩薩が主人公であること
この2点です。
1. については、じつは種明かしがありまして。
実際、私たちが親しんでいるところの『般若心経』というのは、いくつかあるバージョンのひとつで、「小本(しょうほん)」と呼ばれているものです。
小本というからには、「大本(だいほん)」が存在するわけで、大本は文字通り、経文がずいぶん長くなっているわけです。
具体的には、小本の前段、いわば、「前フリ」として、さきに挙げた、説法の主体(=仏陀)、説法の場所、聴衆の様子などが書かれています。
また、「後フリ」としては、お経ではたいてい、「聴衆はみな仏陀の説法で喜びに満たされました。めでたしめでたし」みたいな、いわば、大団円で終わりました、というエンディングがくるわけですが、大本にはそれが載っているのですね。
で、大本の立場としては、あくまで説法の主体は仏陀・釈尊でありまして。
ただし、釈尊は瞑想に入られ、そしてその威神力を受けて、観自在菩薩が説法をする、という構造になっています。
なので、説法の本当の主役は釈尊ですよ、ということで、ここで「仏説である」ということを担保しているわけです。
もっとも、成立時期としては、小本ができた後に、大本が成立した、と言われていますので、小本が大本の省略版であるかというと、そうとも言えないところもあるのですけどね。
2.については、…こんなことを書いている解説本はないかもしれませんが、
「観自在菩薩」が主人公で登場しているのは、般若心経を作成・編集した人のマーケティング的な意図があると思われます。
どういうことかというと、
当時、観音菩薩というのがすごく人気が出てきたところでして、人気の理由は現代日本でも同じですが、「観音様はとにかく慈悲深く、現世の衆生を具体的に救ってくださる」というところですね。

観音菩薩の功徳・パワーについては、法華経の「観世音菩薩普門品(かんぜおんぼさつふもんぼん)」という一章でまるまる説かれています。
内容的には一言でいえば、「観世音菩薩を念じると、どんな危機が迫っていても助けてくださる!」ということです。
刑場に曳かれて刀で切られそうになっても、観音様を念じれば、刀はバラバラに砕ける、みたいな。まあ実際、日本では日蓮上人が実体験をされている、ということになっていますけどね。
とにかく、観世音菩薩は「霊験あらたか」と言いますか、「実際に救ってくださる」ということで、これは人気がでるのは頷けるところです。
なので、そのような人気者である観世音菩薩を主役に抜擢しました、というイメージです。
これは立派な宣伝、マーケティング戦略ですね。
これから説く般若心経がいかにスゴイお経であるか…なにせ、あの観音様の登場ですよ!みたいな。
鳴り物入りの新作映画に、人気急上昇の女優を抜擢するような、というたとえは失礼かもしれませんが、しかしそれに近いものはあると思います。
こうした「経典におけるマーケティング戦略」というのは、他のお経でもけっこう見つけることができます。
また、仏教だけではなく、キリスト教の福音書も、それぞれ、「マーケティング的な意図に基づいた編集がされている」というのは、他の記事でも書きました。
*参考記事:ふしぎでないキリスト教- ②「エリ、エリ、レマ、サバクタニ」の真意を解き明かす
こういうふうに、「編集」とか「マーケティング」というと、お経や福音書のありがたみがうすれる側面があると思われるかもしれません。
しかし、古代と現代では「著作」というものに対する考え方がまるっきり違っています。著作権の概念もないですし、なにより、「事実より真実を優先すること」を重視しています。
また、匿名であるほうがむしろ真理に対する礼節にかなっている、という考え方もありました。
それから、ある程度、神話化して説得力をもたせる、ということも躊躇のないところで、
そのように考えると、「フィクションを織り交ぜながら、全体の説得力・真実性を増す」という意味では、お経には、文学的・芸術作品的側面も担っていた(少なくとも大乗経典では」)とも言えそうです。
観世音菩薩と観自在菩薩は別存在!?
さて、
本論では、私は微妙に、観自在菩薩と観世音菩薩をすり替えて語っています。
それはその通りなのですが、これは実はですね、
『般若心経』の編集・作成にあたっては、やはり人気の「観音様(観世音菩薩)を主役にする」というのがもともとの意図でありました(すみません、ここらへんは学問的には立証できません)、
しかし、みなさんが「般若心経」を一読した感覚でも、さきに挙げた「観音様の功徳と慈悲、霊験あらたか」というイメージと、観自在菩薩の性格にずいぶん違いがあるように感じられると思います。
観自在菩薩のイメージでは、「現世で救ってくださる」どころか、「一切は空(くう)であると、切って捨てよ!」みたいな冷静さ、いわばもっと理性的なキャラクター性を感じますよね。
ここのところはやはり、般若心経を漢訳する際に、「観世音菩薩」ではなく、「観自在菩薩」という訳語を採用した玄奘(げんじょう)の直感力…があると思います。
学問的には、「観世音菩薩と観自在菩薩は同一のもの」とされていると思いますが、漢字の語感でもちょっと違いがありますよね。
「世の音を観る」というのは、つまりは衆生の声を聞く、ということですので、これはやはり慈悲のイメージが強くなります。
一方、「観ること自在」ということでは、どちらかというと、観察そのものが優れている、ということで、これは智慧の側面を強く感じます。
観自在菩薩、あるいは観世音菩薩は、もとのサンスクリット語では、アヴァローキテーシュヴァラと言いまして、これは、
- アヴァローキタ:観ること
- イーシュヴァラ:自在
の合成語です。
これをどう漢訳するか?というだけの違いなのですけどね。
あるいは、むずかしくなるので省略しますが、文法的にどうとらえるか?で、「世の音を聞く→観世音」という漢訳のほうが自然である、と解釈する向きもあります。
そちらの解釈では、「世の音を聞く→観世音」は、原語の発音がアヴァローキタスヴァラになります。
整理すると、
- アヴァローキテーシュヴァラ:観自在
- アヴァローキタスヴァラ:観世音
となります。
音感が似ているので混交されてきた…ということで、
要は、「観自在菩薩も観世音菩薩も同一の菩薩である」という解釈が学問的には一般的だと思います。
実際、玄奘ではなく、鳩摩羅什(クマラージュ)が漢訳した般若心経では、”観世音菩薩”が採用されています。
しかし、玄奘の直感はそら恐ろしいレベルでして。と言いますのも、実際はどうであったか?と言いますと、観自在菩薩と観音菩薩はもともとは別存在だったと思われます。
そのほうが、上述したイメージの差をスッキリと説明できます。
それから、観自在菩薩は実在の人物がモデルになっている、とどこかで書きましたが、観自在菩薩に限らず、仏典でも目立っている菩薩というのは、実際は実在の人物であっことが多いのです。
大乗仏典に登場してくる菩薩は数多いですが、なかには、「ちょっと数合わせで創作されたかな?」という菩薩名もありますが、
文殊菩薩とか、あとは普賢菩薩とか…わりとメジャーな菩薩は、実際に実在していた可能性が高いのです。
仏典に限らず、たとえば、ギリシャ神話ではゼウスをはじめオリンポス十二神、その他の神々がいらっしゃいますね。
これらは現代では文字通り、「神話である」と片付けられていますが、もともとはこれらの神々は遠い昔に実在していた宗教的・政治的・軍事的指導者がモデルになっていると思われます。
「ゼウスが好色である」というのも、実際は、周辺諸国との友好のための政略結婚などが行われていて、これは旧約のソロモン王などと同じですね。
こういう、「妻が多い」というのを「好色である」というふうに神話化されていった。
あるいは、ゼウスと言えば、「イカヅチの神」でもありますが、これはおそらく、当時の軍事作戦のなかで、敵対国がまだ知らなかった火薬類などを用いたのだと思いますね。
その印象が強烈だったので、「ゼウスは雷を自由に操れるらしい」→「雷の神」、といった流れですかね。
まあ話は逸れましたが、このように、歴史的に時間が経つと、もともとは実在の人物であっても神話化されたり、あるいは、「観自在菩薩&観世音菩薩」のように名前が似ていると、混同されて理解されていくパターンもあります。
2000年くらい経つと、「イエスは実在しなかった」みたいな、そういうことを言いたがる人がかならず出てくるもので、遺跡でも発見されない限り、だんだんと神話化していく流れになります。









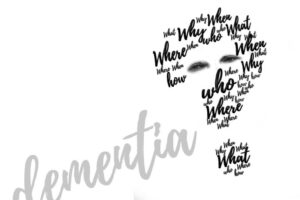


コメント