”十字架”というと、キリスト教信者でなくても、「キリスト教のシンボル」としてのイメージを喚起させられるところの、象徴的な存在ですよね。
しかし、キリスト教に慣れ親しんでいない人によっては、なぜキリスト教が十字架をシンボルにしているのか?今ひとつ分かりにくいところです。
イエスは罪人として、十字架に磔(はりつけ)になって人生を終えたわけですから、ストレートに考えれば、十字架は”敗北の象徴”と言ってもいいくらいでしょう。
キリスト教理においては、「イエスは全人類の罪を贖うために十字架につけられた」という贖罪説が唱えられています。
この贖罪説をどう考えるか?については、”復活思想”との対比で下記の論考で述べてみました。
*参考記事:贖罪思想の意味とは? – 「原罪とイエスの贖い」をどう考えるか
少し、復習してみましょう。
結論的には、ネオ仏法的には、贖罪説はそのまま受け取ることは危険である、と考えています。
贖罪説においては、まず前提として、人間は”原罪”を背負った存在であるとされています。
そしてその原罪の典拠としては、アダムとエバの楽園追放ですね。ふたりが神の禁を破って知恵の木の実を食べてしまった、そして楽園追放の憂き目にあったという創世記の記述です。
アダムとエバが人類の始祖であるので、その原罪は今もなお全人類に及んでいると。
その全人類の罪を贖うために、神はみずからの独り子イエスを遣わせて、あえて十字架につかせた。
神の子が屠られることによって、つまり供犠(くぎ)となることによって、全人類の罪は赦されたのだ。
ちょうど、祭壇で神に生け贄を捧げるように、イエスが贄となることによって人類の罪は贖われたと。
贖罪説とは、かんたんに言えばそういうことですね。
ネオ仏法が贖罪説に距離を置いているのは、これは他責の論理に転嫁する危険性があると考えているからです。
罪の根拠も、先祖とはいえ、アダムとエバといういわば”他者”です。そして、その罪の贖いも、イエスというこれも”他者”です。
神は自らに似せて人を創造されました。
神は言われた。「我々にかたどり、我々に似せて、人を造ろう。」(創世記1:26)
神はご自分にかたどって人を創造された。神にかたどって創造された。男と女に創造された。(創世記1:27)
「ご自分にかたどり」というのは、外観というよりも、「自由意志を持った存在」として人類を創造されたということでしょう。
自由意志のあるところには、かならず責任、すなわち”主体性の原理”があります。
したがって、
罪の原因と解決の両方を他者に転嫁する思想は、”主体性の原理”に反する危険性とつねに隣り合わせにあるのです。
さきに、「供犠としてイエスは十字架に架けられた」と述べましたが、実際にこの考え方は、初期キリスト教会の主流派、ヤコブ(イエスの実弟)たちによって唱えられていたものです。
これは、キリスト教の母体であるところのユダヤ教において、過ぎ越しの祭で子羊が生け贄として捧げられること、そのアナロジー(類比)として、イエスの磔刑を捉えているわけです。
十字架刑は当時において、刑罰のなかでももっとも呪わしいもの、屈辱に満ちたものでしたから、こうしたアナロジーを用いずには、彼らは到底、イエスの十字架を直視することができなかったのでしょう。
これがいわば贖罪説の起源です。
ところが、こうした初期教会のメンバー、彼らはユダヤ教の伝統を継ぐものとして、”ヘブライスト”と呼ばれていますが、
ヘブライストたちの勢力は、その後のキリスト教史のなかでは、パウロらを起源とする”ヘレニスト”に取って代わられることになりました。
「異邦人と食事をともにしてはならない」とか、あとは割礼の問題もありますね。こうした”ユダヤ教的伝統”の延長線上では、キリスト教は普遍宗教化することはできなかったのです。
実際に、その場に異邦人として私たちがいたとしても、「イエスの教えは立派であるかもしれないけど、割礼はちょっとかなわん!」ってなりますよね。
贖罪説というのも、こうしたヘブライストの思想の産物であるので、ここからは直接的に、イエスの教えを普遍化することは難しいのです。
しかし、贖罪説についてはいまだに現代の教会においても唱えられていることはけっこう不思議な現象ではあります。
私たちは原点にかえって、初期キリスト教の流れのなかでも、キリスト教を普遍宗教化せしめたところの、パウロの思想を今一度、検討してみる必要があるでしょう。
パウロの”十字架の神学”
実際に、「キリスト教を創ったのはパウロである」とも言われております。
キリスト教が普遍宗教化したのは、パウロの思想がユダヤ教の枠を超えて普遍性を備えていたから、と考えられるでしょう。
いったいどのあたりが普遍性を備えていたのか?と申しますと、一言でいえば、十字架というものを単なる”事件”としてではなく、
- 神(究極的実在)と人間(現象的存在)の関係はいかなるものか?
- 人間としての本来的な生き方とはなにか?
ということの暗喩・メタファーとして捉え直した、ということだと思うのです。
たとえば、「コリントの信徒への手紙二」に次のようなくだりがあります。
すると主は、「わたしの恵みはあなたに十分である。力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだ」と言われました。だから、キリストの力がわたしの内に宿るように、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。それゆえ、わたしは弱さ、侮辱、窮乏、迫害、そして行き詰まりの状態にあっても、キリストのために満足しています。なぜなら、わたしは弱いときにこそ強いからです。(コリントの信徒への手紙二・12章9-10)
*太字は高田
じつは、こうした逆転の論理は、イエスの説法にも見られる構図です。”山上の説法(山上の垂訓)”を見てみましょう。とりわけ、ルカによる福音書の記述に逆転の論理が顕著です。
貧しい人々は、幸いである、
神の国はあなたがたのものである。
今飢えている人々は、幸いである、
あなたがたは満たされる。
今泣いている人々は、幸いである、
あなたがたは笑うようになる。
(中略)
しかし、富んでいるあなたがたは、不幸である、
あなたがたはもう慰めを受けている。
今満腹している人々、あなたがたは不幸である、
あなたがたは飢えるようになる。
今笑っている人々は、不幸である、
あなたがたは悲しみ泣くようになる。
(ルカによる福音書 6章:20-26)
このように、パウロ神学やイエスの説法の本質を洞察していくと、
真空を作るとそこに空気が流れ込んでくるように、低いところに高いところから水が流れ込んでくるように、自我を弱くするときに、逆に神の強さを手にしている、という逆転の論理が見て取るのです。
*参考書籍:『パウロ 十字架の使徒』(青野太潮著)
こちらの参考書籍の著者、青野太潮氏によると、
パウロが手紙のなかで十字架刑につけられたキリストに言及するとき、彼は必ずこの現在完了形の分詞を用いている(同著p116)
とのことです。
現在完了形は、英語でもそうですが、「過去のある時点で行われたことが”現在も”続いている」という継続の意を表すときに遣われます。
よく読まれている新共同訳聖書では「十字架につけられたキリスト」と訳されており、現在完了形がきちんと翻訳されていない。
そうではなく、現在完了形としては、「十字架につけられたままのキリスト」と訳すべきであり、実際に、1917年訳の文語訳聖書では、「十字架につけられ給ひしままなるイエス・キリスト」と訳されている、と青野氏は述べております。
この青野氏の主張は卓見だと思います。
「弱いときに強い」が普遍性をもつ永遠の真理だからこそ、イエスの十字架も一度限りの出来事ではなく、(象徴的に)今現在も続いている、という解釈です。
青野氏によりますと、こうした「十字架につけられたままのキリスト」という解釈は、のちの偉大な神学者たちが発見した(再発見した)パウロ解釈でもあるのです。
アウグスティヌス、マルチン・ルター、カール・バルトなど、錚々たる神学者たちによって”再発見”されている。
実際に、”十字架の神学”という言葉はマルチン・ルターの学説に由来しております。
「私は弱いときに強い」
自分の弱さを自覚するときに、逆に神の強さを手にすることができる。
そう言えば、ソクラテスも”無知の知”を説きました。
こちらも、一般に解釈されている「知らないということを知る」ということだけでなく、
「(現象としての)自己の無知を自覚したときに、イデア(真実在)の英知を得ることができるのだ」という解釈が成り立つのではないか、と思います。

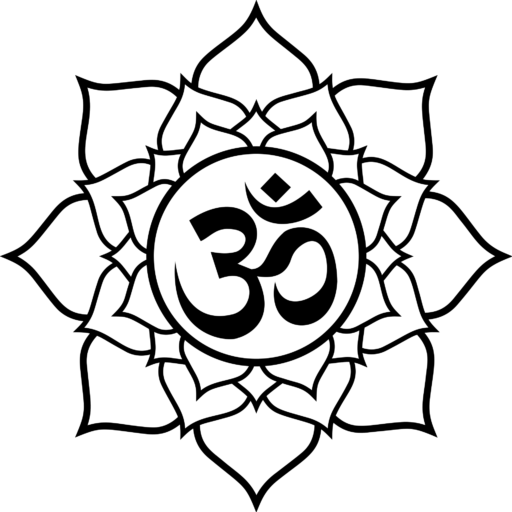










コメント