シニフィアンとシニフィエ
前回の続きで、今回はシリーズ29回目です。
*シリーズ初回からお読みになりたい方はこちらから→「般若心経」の悟りを超えて -①
*『般若心経』全文はこちらから→祈り/読誦
得阿耨多羅三藐三菩提
読み:とくあのくたらさんみゃくさんぼだい
現代語訳:最高の悟りを得ることができるのだ
主語は、”三世諸仏”です。
流れとしては、「過去・現在・未来の仏陀たちは、般若の智慧に依るがゆえに、最高の悟りを得ることができるのだ」となります。
”阿耨多羅三藐三菩提”は、字面だけでみると、摩訶不思議かつ難解で逃げ出しそうになりますが、これは、サンスクリット語の”アヌッタラ・サンミャク・サンボーディ”の音写です。
”無上正等覚(むじょうしょうとうがく)””無上正等正覚(むじょうしょうとうしょうがく)”などとと意訳するときもあります。
言葉の対応関係としては、
- 阿耨多羅:無上
- 三藐:正
- 三:等
- 菩提:覚
となります。
”正等覚”は、”正覚”とも言いますが、要は、「仏陀の悟り」のことです。
なので、無上正等覚は、直訳すれば、「この上ない仏陀の悟り」ということになります。菩薩たちは、日々、この仏陀の境地を目指して修行をしているのですね。
”無上正等覚”という立派な意訳語があるのであれば、得阿耨多羅三藐三菩提ではなく、”得無上正等覚”となぜ玄奘は翻訳しなかったのか?
単純に、”阿耨多羅三藐三菩提”のほうが有り難みがありそうな感じもしますけどね。意外にそういう側面もあるかもしれません。
ただまあ、本当のところはむしろ、「翻訳しきれない」「翻訳しないほうがベターである」と判断したのでしょう。
”近代言語学の父”と呼ばれている哲学者ソシュールは、言語を”シニフィアン””シニフィエ”という二種類に分けて考察しています。
それぞれ、
- シニフィアン:文字や音声
- シニフィエ:イメージ、概念、意味内容
ということです。
初めて聞く方は、この定義では「なんのことやら?」となってしまいますよね。
シニフィアン/シニフィエは、ひとことで言ってしまえば、「言葉と、言葉が指し示している対象に直接的な関連はない」ということです。
たとえば、”猫”という文字、あるいは音声があります。
もしこの”猫”が実際の猫そのものとイコールで、絶対的な音声・文字であるとすれば、全人類がみな”猫”という言葉を使うはずです。
ところが、英米人は”CAT”と言いますよね?
母語を異にすれば、猫そのものをなんと呼ぶか?には、それこそ言語の種類の数だけの呼び方があります。
つまり、
私たちが、文字を書いたり、発音したりするところの”猫”と、実際の”猫”には必然的な関係はないということです。
あくまで、その言語を使用している民族の合意によって、”猫”と呼び習わしているだけですよね。
- シニフィアン:”猫”という文字や音声
- シニフィエ:”猫”そのもの
という対応関係です。
話を戻しまして、
翻訳として、”無上正等覚”。私たち日本人であれば、「無上の悟り」と言ってしまうと、「なんとなく分かった気がしてしまう」という危険性があります。
「あ、無上の悟りのことね、知ってる知ってる」と、深く考えることなしにスルーしてしまう危険性です。
ところが、”阿耨多羅三藐三菩提”と漢字をずらずら並べられると、一瞬、「えっ!?」となってしまいますよね。
この「えっ!?」という驚きは、「…無上の悟りとは、そのそも何ぞや?」と改めて考察する契機になるでしょう
中国人、日本人…にとっては、”阿耨多羅三藐三菩提”という文字・音声はひとつの異化作用として迫ってきます。
これによって私たちは、「”無上の悟り”と、かんたんに分かった気になってしまってはいけないな」という知的謙虚さが生まれますね。
玄奘がサンスクリット語を意訳せずに音写する時は、そのように、「あえて異化作用を引き起こさせ、言葉が指し示している内容(シニフィエ)を考察してもらいたい」という願いもあったのだと思います。
無上の悟り、この上のない仏陀の悟りとは?
上記のシニフィアン/シニフィエで言えば、「無上の悟りとは…………〇〇である」とこれから解説しても、〇〇がまたひとつのシニフィアンになってしまうのですけどね。
しかしまあ、そう言っていてはブログが書けませんので、できるだけ接近してみましょう。
…というより、今回は”無上の悟り”の内容というよりも、「無上の悟りを得るとは、そもそもどういうことであるのか?」について考えてみたいと思います。
上述しましたが、”無上の悟り”とは、「この上ない悟り」という意味でしたね。
そして、”この上ない”と言うと、文字通り、「もう、これ以上はない」というスタティック(静的)な状態をイメージしてしまいます。
そして現実にも、多くの僧侶・修行者たちも、”無上の悟り”をそのようにイメージしていることでしょう。
しかし、考えてみれば、「この上ない」というのは、言ってみれば、「頭打ちである」というひとつの制約になってしまいますよね。
仏陀の悟りが広大無辺のものであるならば、”制約”というのは、「広大無辺ではない、限りがある」という矛盾に陥ることになってしまいます。
これはやはり、悟りというものをスタティックな状態であると誤認しているところから生じる錯覚であると思います。
もちろん、「ある一定の悟りを得た」という…、たとえば、「声聞の悟りに達した」というふうな、いくつかのメルクマール・指標は存在するでしょう。
そうした指標があるからこそ、目標設定がしやすい、というメリットもあります。
しかしやはり、”菩薩の悟り”にしても、”仏陀の悟り”にしても、常に上へ上へと更新していると解すべきではないでしょうか?
別の論考では、「大宇宙の一なる神(実在)は、自らの発展を望まれて、自己に内部に”現象”を生じせしめた」という趣旨のことを書いたことがあります。
*参考記事①「般若心経」の悟りを超えて – ⑫不生不滅 不垢不浄 不増不減
*参考記事②ネオ仏法は、小乗も大乗もはるかに超えてゆく-④ワンネス、宇宙そして空(くう)
こちらの参考記事に詳しく書いておいたのですが、「自己内部に無数の”現象”を創造した」目的は、一なる神(実在)そのものが拡大・発展を成し遂げていくのが目的です。
一の内部に、私たちや一人ひとり…無数の多があります。
一即多多即一です。
そして、たとえば今これを読んでいるあなたの認識がひとつ増えた、とすれば、言葉を換えれば、あなた(現象)が智慧をひとつゲットしたとするならば、
それは”全体”であるところの一なる神(実在)も、そのあなたが獲得した智慧の分だけ増量することになります。
この増量すなわち、発展・拡大が、大宇宙創造の目的そのものです。
ここのところは、それこそ私たち人間に許されている”無上の”認識でもありますので、「ちょっとまだ分かりにくい」という方は、上記の参考記事2つをぜひ繰り返しくりかえし読むことをお勧めいたします。
まさしくここが、「般若心経の悟りを超えて」いるところだからです。
さて、
もっと私たち一人ひとりに引き寄せて論じるとするならば、
私たちの”悟り”というのも、「これで悟ったからおしまい!」というようなスタティックなものではないのです。
江戸時代中期の禅僧、白隠禅師が「小悟は数知れず」と名言を残していますが、悟りというものは常に認識力を更新し続けているというダイナミクス(動き)そのものでもあるのです。
私たちは、ともすれば、「悟った」「悟っていない」というふうに二分法で考えてしまいます。
こうした二元論は、物事を考察するのにとても便利ではあるのですが、究極のものでないのも確かなのです。
やはり、「悟った」「悟っていない」という二分法ではなく、悟り(認識力)を常に更新している動的な状態が理想です。

習慣論などでもそうです。
すぐに習慣が破綻してしまう原因のひとつが、「私はできている」「私はできていない」という二分法の考察にあると思えます。
「あーあ…今日も出来ていない、目標をクリアできていない。もうこれ以上、努力を続けてもなあ…」という具合に、努力の習慣が破綻してしまうのですね。
そうではなく、
「昨日よりは一ミリでも出来ている、出来つつある自分」という動的な自分にアイデンティティを求めれば良いのです。
「一かゼロか」というデジタルではなく、「一へと続く限りない」アナログな動きです。ここにアイデンティティと誇りを置くこと。
これによって初めて、「継続していこう!」というモチベーションも生まれてくるというものです。
こうした「二分法の陥穽」は他にもいくらでもあります。
- 「稼げてる自分」「稼げてない自分」
- 「精神が安定している自分」「精神が安定していない自分」
…などなど。
大宇宙創造の目的まで喝破していくことももちろん素晴らしいですが、もっと身近に、
「自分もまたスタティックな状態に陥っていないか?真理とはダイナミクスにあったのではなかったか?」
と、時に自問自答してみると、幸福感は増大していきます。
幸福感も、結果ではなく、過程(ダイナミクス)に存するからです。








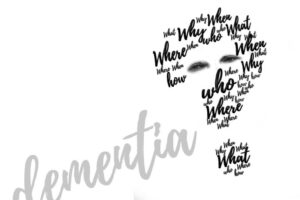


コメント