天上天下唯我独尊。読み方は、「てんじょうげんげゆいがどくそん」「てんじょうてんがゆいがどくそん」のどちらもでもいいです。個人的には、前者のほうがリズムが良くて好きです。
さて、「天上天下唯我独尊 本当の意味」でGoogle検索すると、検索1ページめにヒットする記事のほとんどが、大意、「人はみな、かけがえのない大切な存在であるという意味」と解説していることに違和感を覚えました。
そうした解釈は、安手の自己啓発本の言説と何ら変わらないのではないか?と私には感じられてしまうのです。
ちょっと言葉はキツいかもしれませんが、現代仏教が救済力を失っているのは、こういうところからも伺えると思うのです。
もちろん、近年、慣用的に勘違いされているような、「自分が一番!と自惚れている独りよがりな人」という意味ではないことは確かです。これは仏教用語の明らかな誤用です。
では、「天上天下唯我独尊」はいかに解釈すれば良いのか?
結論的に、かつ端的に言えば、ストレートに、「私(=釈尊)が一番尊い」という意味で良い、と私は考えます。
もちろん、世界四大聖人(あるいは、世界三大聖人)に数えられる釈尊が”謙虚さ”の美徳を忘れ、自惚れを表明したというわけではないことはもちろんでしょう。
そこで、今回はこの「天上天下唯我独尊」に込められた釈尊の真意を探りつつ、かつ、仏教の可能性について思いを巡らせてみたいと思います。
”天上天下唯我独尊”のポーズの意味と成立の経緯
”天上天下唯我独尊”との言葉は、釈尊がルンビニーにおいて摩耶夫人(マーヤぶにん)の右脇から生まれた後、右手で天を指し、左手で地を指しつつ発した言葉とされています。
そのときのポーズがトップ画像の仏像になっているのですね。
そうした逸話は現代人からすると、「作り話だろう」となると思いますが、はい、私も作り話と言いますか、釈尊を賛嘆するために、後世に付加された逸話だろうと思っています。
ただし、「逸話だから、事実でないから」と言って、一概に無下にすることではないと思いのですね。
やはり、そういう逸話が成立するからには、釈尊の在世当時の在り方、ひいては釈尊の思想自体に萌芽があったと考えるべきです。
この”天上天下唯我独尊”のポーズの意味は、「天上においても地上においても、私(釈迦)は最大の存在である」という自負心を表現しています。獅子吼しているわけです。
この解釈は冒頭に挙げたような他サイトの解釈と全然違っていますが、理由はのちほど述べていきますので、よければ、このままお付き合いくださいね。
”天上天下唯我独尊”には続きがある
天上天下唯我独尊の続きとしては2パターンあります。漢字は無理して追わなくていいです。
- 天上天下唯我独尊 今茲而往生分已尽(『大唐西域記』より)
- 天上天下唯我為尊 三界皆苦吾当安之(『修行本起経』より)
順番に見ていきましょう。
1. 天上天下唯我独尊 今茲而往生分已尽
今茲而往生分已尽:今ここに生まれきたのは最後の生である
これは解釈としては、「私、釈迦が今生、この世に生誕したからには、迷いの輪廻は尽きるであろう」とでもなるでしょう。
自身の「迷いの輪廻」が尽きると同様に、悟りの力によって、衆生も迷いの輪廻から解放してあげよう、という宣言ともとれます。
その「悟りの力」は釈尊自身の比類のない悟り、無上の悟りのことですので、冒頭の「天上天下唯我独尊」は、「(迷いの輪廻を断ち切る無上の悟りを説く)私は天上においても地上においても唯一人、そうした悟りの力をもつ存在なのだ」というふうに解釈できるでしょう。
多くの人々の迷いの輪廻を断つ無上の悟りを提供できるのは天上天下、釈尊ただひとりなのです。ですからやはり、「一人ひとり、みな尊いのだ」的な解釈はおかしいでしょう。
これは釈尊の正当な矜持と受け取ったほうが自然です。
2. 天上天下唯我為尊 三界皆苦吾当安之
「唯我独尊」のところが「唯我為尊」となっていますが、まあ意味は同じです。
ポイントは、そのあとの「三界皆苦吾当安之」でしょう。
”三界”は難しく言うと、欲界・色界・無色界のことですが、まあシンプルに「私たちが輪廻する世界すべて」と理解して良いです。

「輪廻する世界は皆、苦であるけれども(=三界皆苦)、私(=釈尊)がこれを安んじてみせよう」という意味であり、これもパターン1と同様に、釈尊の矜持でもあります。
このように、”唯我独尊”について「一人ひとり、みな尊い」という解釈はやはり私は採れません。
「みな尊い」ということであれば、釈尊でなくても”三界の苦”を安んじることができるはずで、すでにみなハッピーということになりますよね。釈尊が生まれる必要もなくなってしまうでしょう。
”天上天下唯我独尊”のポーズと七歩歩いた理由
それから、「誕生後すぐに七歩歩いた」というのも、そのうちの”六歩”が「六道輪廻」を指しているという説があります。
六道(ろくどう)は、「地獄・餓鬼・畜生・修羅・人・天」の6つの世界ですね。
*参考記事:十界と十界互具 ー 仏教における”世界”の階層構造論
これも、上述した”三界”と同様に、「私たち凡夫が輪廻する世界」ということです。
釈尊が「七歩歩いた」というのは、七歩目で六道から抜け出す、つまり、解脱する道を示したという解釈です。
なので、ここでもやはり、”独尊”は、「釈尊のこと」であることが分かります。この解釈のほうが全然スッキリするでしょう。
したがって、やはり、”天上天下唯我独尊”のポーズですね、右手を天に上げ、左手を地に下ろしている立ち姿は、「天界においても地上においても、私(釈尊)は比類のない悟りを得る」という自負心の表れととるべきでしょう。

正当な自負心は”傲慢さ”とは別物です。
もちろん、実際には釈尊は29歳で出家して、悟りを開いたのは35歳のときです。
なので、この誕生譚は一種の説話と受け取るべきでしょうが、ただ、「説話だから意味がない」ということではなく、こうした説話が出来上がるほどのインパクトがあったということで、事実でなかったとしても、”真実”として受け取りべきでしょう。思想的真実です。
ちなみに、上掲した釈尊の像は”誕生仏”と言うのですが、けっこう色々なお寺に安置されています。
そして、釈尊の生誕日(花祭り)の4月8日にはこの像に甘茶をかけてお祝いをします。
唯我独尊は傲慢さではなくて、”矜持”である
一方、”唯我独尊”を「人はみな尊い」と解釈してみたいという気持ちも分からないでもないのです。
実るほど頭を垂れる稲穂かな

あるいは、
下がるほど 人の見上ぐる 藤の花
という俳句がありまして、この2つは「謙虚さが大事ですよ」という教訓を示しているのですね。
そして、「釈尊ほどの方が”謙譲の美徳”を忘れるはずがないだろう」というのが、唯我独尊イコール「みな尊い」解釈の根拠になっているのです。
また、WIKIで調べると、14世紀のさる天台宗の尼僧は「この広い世界のなかで、私たち人間にしかできない尊い使命がある」と解釈しているようです。
この解釈をそのまま採用して解説しているサイトもいくつかあるようです。
しかし、やはり、これもひとつの解釈に過ぎず、昔の人がそう言ったからといって権威化して受け取る必要はないと思います。
というのも、この解釈でもやはり、”三界皆苦吾当安之”のところが説明不能になってしまうからです。
さらに、「釈尊が自らを言うときは”我”ではなくて”吾”という漢字を充てているので、やはり、”唯我独尊”は、釈尊のことではなくて「みんな」のことである」と解説してるサイトもあります。
しかし、『大唐西域記』の誕生偈の偈文の表記では、
天上天下 唯吾獨尊
というふうに、”吾”という字が充てられていますので、その解釈もやはり当たりません。
さて、
それでは、「では、釈尊が謙譲の美徳を忘れてしまったのか?」という疑問をどうするか、というところですね、ここをどう解釈するか?
答えはすでに見出しのところに書いてしまったのですが、”唯我独尊”は「傲慢さ」ではなくて、「矜持(きんじ)」なのです。
矜持というのは、この場合、「正当なプライド」という意味で申し上げています。
先に述べたように、三界・六道…といった苦しみの輪廻から解脱する道を示したのは、少なくとも仏教的には釈尊お一人なのです。
なので、「私(=ゴータマ・シッダールタ)こそが、天上界も地上界も含め、”解脱”への道を指し示すことができる唯一の存在である」という矜持、「責任感を伴った宣言」でもあるのです。
これは決して、傲慢ではなく、謙虚さの美徳とも矛盾しません。
立場を表明するというのは「リーダーとして責任をとります」ということであり、これは謙譲とはまた別の種類の美徳なのです。
実際に、天上の神々も釈尊に教えを請うています。これを”梵天勧請(ぼんてんかんじょう)”と言います。
実は、”天上天下唯我独尊”以外にも、こうした例を挙げることができます。他ならぬ、”仏陀”という称号です。
釈尊は、「私は仏陀になったのだ」と自らキッチリ表明されています。
釈尊は悟りを開く前に、5人の修行者たちと修行をしていた時期があるのですが、悟りを開いたのち、その5人と再開したときに、彼らは釈尊に対し、「おまえは」と呼びかけたのですね、
それに対して釈尊は、「おまえと呼んではならない、わたしは仏陀になったのだ」と宣言しております。
*典拠を示しておきたいのですが、該当の仏典がすぐに見つからなかったので、とりあえず、ひろさちや氏の原作の漫画『インドの聖地』を挙げておきます。
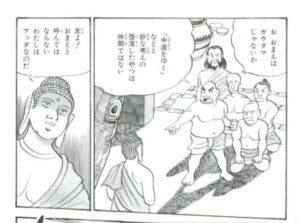
また、仏伝文学『ラリタヴィスタラ』第八章「天祠に連れてゆくこと」の箇所には釈尊の王子時代、ゴータマ・シッタールダが大意、下記の偈を詠じたとのことです。
自分が生まれたときに三千世界は振動し、帝釈天・梵天をはじめとする神々が礼拝した。あなたが自分がそこへ連れてゆくというのは何の神なのか。自分は「神々を超えた神」であり、自分に等しい神はいない、いわんや自分を超える神などいるはずがない、と。(『大乗仏教の誕生』梶山雄一著p44より引用)
この箇所はまさしく”天上天下唯我独尊”の本当の意味を裏書きしていると言えるでしょう。
繰り返しますが、このように「正当な立場」を表明することは傲慢ではなく、責任感の現れなのです。
たとえば、会社の社長が自ら社長であることを隠していたら、社員も取引先も困ってしまいますよね。
なので、しっかりと名刺に「代表取締役社長」というふうに表記するのです。
これは、「会社の事業について最大の執行権限を持つと同時に、最終的に責任をとるのは社長である私なのです」という表明です。
仏陀であること、また、天上界・地上界を含めて”解脱”の道を示すことができるのが釈尊以外にいらっしゃらない以上、「仏陀であるのだ」「天上天下唯我独尊」というのは、やはり、責任感を含めたところの”矜持”であるということです。
結局、天上天下唯我独尊を「みんな尊い」と解釈する説は、近現代に蔓延した”結果平等”的な思考ですね、
これはもちろん共産主義に淵源を持っていますが、こうした同時代的な”フィルター”を外して物事を観察することができていないことが原因で出てきているのだと思います。
それだから、現代仏教は救済力を失ってしまっているのです。

こうした同時代的な”フィルター”あるいは”レンズ”を外していかないと、真実の姿は観えてきません。
「正しく観察すること」が八正道の出発点である”正見(しょうけん)”であるのです。
正見は別名、”如実知見(にょじつちけん)”とも言いまして、文字通り、「実のごとく知って観察する」ということなのです。
*参考記事:八正道の意味と覚え方のコツ
この同時代的なフィルターの外し方のコツについては、下記の記事でまた別の角度から詳述しています。ぜひ参考になさってください。










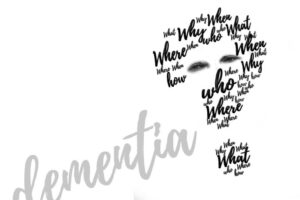


コメント