人間は心の修業によって、天使(菩薩)になることができる、とネオ仏法では繰り返し申し上げているのですけど、本来の大乗仏教理論によれば、それ以上でして、最後は仏陀になることができる、というところまで行き着きます。
釈尊の時代は、悟りを得たものを阿羅漢(アラカン)と呼んでおりました。そういう意味では、少なくとも原始仏教では、釈迦も阿羅漢のひとりである、という分類だったのですね。
修学旅行で京都などに行くと、お寺に、十六羅漢像とかいろいろありましたね。この、羅漢(らかん)さんが阿羅漢です。*原典のサンスクリット語では「アルハット」。

大乗仏教の時代に入ると、小乗仏教への批判もあって、「阿羅漢は自分の独りの悟りしか考えていないのだ、仏道を志すものは自らの悟り(自利)だけではなく、利他に生きなければならない、そして仏陀になることができる。それが菩薩である」という思想に行き着いたのです。
自分を磨きながら、その智慧でもって他者や世の中に貢献していくことを自利利他(じりりた)といいます。
この自利利他を日々の実践課題とし、実際にそのように生ききることができる存在が菩薩であるのです。
今回は、菩薩、仏陀の境地に限らず、人間が住む/赴く世界のすべての真相をできるだけ明らかにしていきたいと思います。
中国の南北朝時代〜隋の時代に、天台大師智顗(ちぎ)という方が、この人間が住む/赴く世界を十通りに分類しております。これが、いわゆる十界論(十界説)です。
以下、十界論にしたがいつつ、ネオ仏法で得た霊界情報もミックスしながら、”世界”の構造論を明らかにしてまいります。
十界論はスピリチュアルな出世の段階
実在界での境涯、いわば出世の段階論を天台教学に従うと、下記のとおり、十段階に分類されています。これが十界論(じっかいろん)です。超訳的な説明も付しておきます。
- 仏界(ぶっかい)・・・ほとけ、如来
- 菩薩界(ぼさつかい)・・・利他に生きる境地
- 縁覚界(えんがくかい)・・・自意識的な悟りの境地
- 声聞界(しょうもんかい)・・・真理の縁にふれて学ぶ境地
- 天界(てんかい)・・・自己実現の境地
- 人界(にんかい)・・・平均的な人間の境地
- 修羅界(しゅらかい)・・・喧嘩上等の境地
- 畜生界(ちくしょうかい)・・・欲望のままの境地
- 餓鬼界(がきかい)・・・貪り(むさぼり)多い境地
- 地獄界(じごくかい)・・・上記以下の地獄すべて、八大地獄などがある。最下層は無間地獄(むけんじごく)
*下線で引いた境涯は私たち真理を学ぶものが目指すべき境地です(のちほどご説明します)。
*上座仏教(テーラワーダ仏教)で言う「阿羅漢」が声聞界・縁覚界に相当すると、とりあえず考えてください。
天台教学では、上記の十分類が、死後赴く世界というだけではなく、現世、今ここにいる私たち一人ひとりの心境が上記の十段階に通じている”十界互具説(じっかいごぐせつ)”という考え方を採ります。
*十界の各々が互いに十界を具(そな)えているので、10×10=100の世界、百界になります。これが一念三千論という天台思想の基礎になっています。
たとえば、菩薩界出身の魂が、現世に生まれてきたとしますね。
そのような魂であっても、一瞬一瞬、いつも菩薩界に通じる心境を維持するのはなかなか難しいことです。
ある瞬間には、調子よく菩薩界、ときには仏界にも通じる心境であるときもありますが、また別のときには、つい修羅界に通じる心境になってしまうこともあるでしょう。
つまり、ひとつの世界出身の魂が(ときにより)十通りの心境を示すことがあることになります。
これを敷衍(ふえん)して考えると、「十通りの世界出身の魂たちは、それぞれが十通りの心境を示すことがある」ということで、合計、10×10=100ですね、合計100通りの世界が存在することになります。
十界のそれぞれがまた十界の世界を持つことができるので、これを十界互具(じっかいごぐ)と言っているわけです。
ここが、上座仏教の六道(ろくどう・りくどう)の考えでは、下から、「地獄・餓鬼・畜生・修羅・人・天」の6つだけになります。
まあ、オリジナルはこの六道なのですけどね。
それはそれで良いとしても、問題は、餓鬼とか畜生が、この世のことなのか?あの世のことなのか?イマイチ判然としておりません。
「人界」もおそらくは、いま私たちが生きているところの現象界を指しているのでしょう。
そうすると、「畜生道に堕ちるぞ!」というのは、肉体の死後、すぐ地上の動物に魂が宿ってしまう、という理解になっているかと思われます。
これはインド的な、「また人間に生まれられるとは限らない。次回は虫に生まれるかもしれない」という因果応報説が基礎になっていると思われますし、今ひとつは「生まれる」という解釈の問題もあります。
インドでは、死後、ある世界へ赴くことも「生まれる」という表現を使います。あるいは、死後の世界、たとえば天界から現世へ生まれてくることも、「天界の寿命が尽きた」という表現を使ったります。
ここが誤解と混乱を招いているところではありますね。
そういう意味では、十界論とそれを発展させた智顗の十界互具説(じっかいごぐせつ)はとても理性的で整然とした世界観を提示しております。
実在界で十段階になっており、現象界でも心のあり方において十段階になっている。しかもそれがきっちり対応しつつ、世界は、10×10=100の世界があるというのが十界互具説です。
これは、かなり真実に近い世界観だろうと私は思っています。
現世での心境が死後赴く世界を決める、というのは釈尊在世当時からありましたので、そういう意味では、釈尊オリジナルに忠実でありつつ、さらに世界の真相を深く突き詰めた思想であるということができるでしょう。
たとえば、カーっと怒ったその瞬間に「修羅界」に通じているということです。
そして、そういう心境が今回の人生の平均的な境地になったら、死後も修羅界に赴く、ということになるわけです。
上記の分類で言うと、「自己実現で喜びに満ちています!」という段階が「天界」に相当しますかね(自己実現の内容にもよりますが)。
そして、真理に目覚めて「もっと学びたい!」と決意した段階が「声聞界」ということになります。
今、この記事を読まれていてそのように思えたのであれば、”今この瞬間”は声聞界に通じていることになります。
さらに、一生を通じた平均的な心境としてそれを維持できたら、死後は声聞界という聖なる世界に還ることができるということです。
注意1) ・大乗仏教では、声聞・縁覚=おのれ一人が悟ればいいという境涯とみなし(小乗仏教=上座部仏教への反発)、菩薩界=仏法を学び利他へ生きる境涯、と広く分類している。その際、菩薩界のなかに小乗仏教で言う声聞などの段階が含まれたりしているが、説明が煩雑になるので、菩薩界は狭義の菩薩界、たとえば華厳(けごん)教学で言うところの、十地(=聖の境涯)と定義する。 ・縁覚は「独覚(どっかく)」=一人悟りの段階という定義が一般的だが、声聞より上の境涯に置かれているところから、「広く真理を学び、知識を思索と経験を経て智慧に変えることが出来た一定の悟りの段階」という意味で使う
私が、しつこく、「天使(菩薩)を目指しましょう!」って言ってるのは、天界もいいけど、もっと上を目指しましょうよってことなのです。
実際、今の日本に生まれて自己実現に夢中になっている方は天界(レベルの差はありますが)出身の方が多いのです。
そして実は、天界から声聞界へのコースはそんなに難しくないのですね。なので、目指さないのはとても勿体ないのです。
また、こうした実在界の成功の階段を知っておかないと、「この世で成功したと思っていたら、蓋を開けてみたら失敗(地獄行き)していた」とか、
あるいは逆に、「この世ではたいした成功をしていないが、蓋を開けてみたら意外に成功していた」ということがありえるのです。
この世の成功とあの世の成功をLINKさせるのがベスト
そういうわけで大事なことは、実在界と現象界の関係性を熟知して、この世(現象界)での成功が、あの世(実在界)での成功へとリンクするような生き方がベストなのです。
こうした声聞界の悟りを固める、ということに関しては、別に講座も設けますし、また、当サイトのブログを読み続けていけば数多くのヒントが見つかるはずです。
注意2)華厳教学(「華厳経入法界品」)では、善財童子(ぜんざいどうじ)が文殊菩薩(もんじゅぼさつ)の勧めにより、53人の善知識(=指導者)をめぐって修行を重ね、最後に普賢菩薩(ふげんぼさつ)に出会って悟りを開く、という経典の内容から、菩薩に52段階アリ(最後の1段階は仏界)としています。東海道五十三次の”五十三”は、この53段階から来ているという説も。ほか、経典によって、頭がくらくらするくらい、細かな分類がされています。そこらへんも面白いは面白いのでまた別の機会に書きますね。
仏界→大日如来の思想は、世界への福音になる
さて、
十界論の概要は上記のとおりなのですが、大乗仏教では、釈迦如来以外にも、時間軸(過去・現在・未来)そして空間軸(十方世界)の様々なところに如来がいらっしゃるという思想になっていきます。
そして密教では、如来の頂点に大日如来(華厳経で言う、毘盧遮那仏(びるしゃなぶつ))が座しまして、その周りに4種の如来がおわす、ということになります。
*奈良の大仏が毘盧遮那仏です。
そのうちのひとり、西方にいらっしゃるのが有名な阿弥陀如来ですね。

そうすると、菩薩の上に如来があり、最高位に大日如来(大毘盧遮那仏)、という序列になりますかね。
ただし、ポイントは、
大日如来がトップと言っても、トップの下に、だっーーーとトップダウンで並んでいるわけではありません。
大日如来が一者であり、かつ全者である、のですが、時代・地域・役割に応じて諸如来・諸菩薩の存在が<内部に>ある、という意味です。少なくとも私の解釈ではそうです。
「<内部に>ある」というところが重要で、もし他の偉い存在が外部にあったら、大日如来は一者でも全者でもなくなってしまいますね。
たとえて言えば、人間のボディはひとつですが、その<内部>に役割に応じて、肝臓や心臓などの各器官がある、というイメージです。
つまり、キリスト教のような、私たちを離れた絶対的な超越者ではなく、個別的な存在をすべて(つまり、最下層の地獄までも)包含した一者である、という思想なのですね。
ここは誤解されやすいところですが…。
要は、悪というものも時間軸を入れて考えると、それは一時的な歪(ひずみ)に過ぎないと。
川で言えば、ところどころ岩にぶつかって逆流しているところ、ですかね、悪というのは。
でもその逆流は一時的なものに過ぎないわけです。
そうした悪も方便として自らのうちに包含しつつ、自らを生成発展させていく存在、として大日如来は考えられています。
ここのところはなかなか理解が難しいところで、これが腑に落ちると、一転して、ドイツ観念論哲学の最高峰であるヘーゲルの言葉、
真なるものは全体である。しかし全体とは
、ただ自己展開を通じて己れを完成する実在 のことにほかならない。(『精神現象学』)
という言葉が理解できたことになります。
そして実は、この「多様性を包含した一者」という考え・思想こそが、次代の文明の軸になっていくのだと思います。
つまり、多民族・多国家・多宗教…を、包含しつつ総合していく思想、本当の意味での初の世界的価値観の核となる思想になりうる、と私は思うのです。
その場合、もちろん、「大日如来」という名称にこだわる必要はありません。むしろ、「名前がある」ということは、<究極の一者>ではない、というふうに受け止められてしまいます。
ある名前がある、ということは、逆から見れば、その「名前以外の何か」ではなくなってしまいますので、論理的な帰結として、「一者ではない」ということになってしまいますね。
たとえば、「これはコップである」と言ったら、それは同時に、「本でもない、椅子でもない…(ずっと続く)」というふうに捨象していくことになります。名詞にはそうした限界があります。
ただ、名前がないと呼びようがない、という不便さはありますので、そこのところは「仮に〇〇」」と呼ぼう、ということでいいと思います。
そういう意味では、大日如来は、華厳経で言うところの「毘盧遮那仏(びるしゃなぶつ」に当たりますが、毘盧遮那仏は、原語で「マハー・ヴァイローチャナ」となります。

インドの言語・思想はドイツ、ギリシャ、イランなどと同じくアーリア的な考えを基礎にしていますので、「マハーヴァイローチャナ」という呼び名は、もちろん仏教起源ではあるものの、西洋・中東にも配慮がある、ということで、意外に世界性がある名称かな、とも思っていますけどね。
地獄篇概要
さて、まずは「地獄篇」として、まあ一般に「地獄」と呼ばれる世界ですね、ここのところに焦点を当ててみます。
十界論で言うと、下記の4つの世界に相当します。
- 修羅界(しゅらかい)・・・喧嘩上等の境地
- 畜生界(ちくしょうかい)・・・欲望のままの境地
- 餓鬼界(がきかい)・・・貪り(むさぼり)多い境地
- 地獄界(じごくかい)・・・上記以下の地獄すべて、八大地獄などがある。最下層は無間地獄(むけんじごく)
仏法(真理)を学んでいて、「自分は菩薩(天使)を目指せるかな?」とか「大きな使命がある!」と思っている人であっても、意外に、蓋を開けてみれば「残念でした…」というケースがあります。
それは、「結果、地獄でした」という判定に愕然とするということなのですが。
なぜこういう勘違いが起きるかと言うと、「人々を救う」とか社会改革に夢中になっていると、「自分もずいぶん心境が上がった」と思いがちなのですが、実際はつい身近なことを忘れてしまうことがあります。
身近というのは、まず、自分自身ですね。
「自分自身の心を修められること」が、まずすべての出発点になります。これなくして、これ以降の世界は絶対にありえません。
当サイトでよく申し上げている「主体性の原理」です。
縁起(原因結果の法則)によって、まずは、「今の自分の心境や環境・立場は、過去から現在に至るまでの、自分自身の選択の結果、生じている」ということを認めることです。
これが意外に難しいんですよね。
主体性というのは、言い換えれば「自己責任論」ということになります。
自己責任を認めるのは誰にとってもキツイことで、それよりかは、「〇〇のせいでこうなった」と思うほうが、自己変革をする必要がなくなり、ラクな気がするわけです。
それから、「主体性の原理を認めなたくない」隠れ蓑として、「社会正義」を訴える方向へ行くケースもあります。
「国が/社会が/会社が/資本主義が/…悪い。だから変革の必要がある!」というふうに、社会正義を訴えていれば、それは、「自分のために怒っているのではなく、公のために怒っているのだ」と自分自身を正当化することができるからです。
もちろん、本物の正当な「公的な怒り」というのは別途あります。
見分けるのは一見、難しいですが、ひとつの目安として、やはり、自分自身を修めているということ、ですね。
感覚的には、日々の生活の中で、「穏やかでさわやかな心」が維持できているかどうか?というチェックポイントです。
もちろん、ある一定の期間をとってみれば、「全然、さわやかじゃない」というときもあるでしょうけど、内省すべきところは内省したら、心の状態をすぐに復元できることが大事です。そういうリバウンド力があれば大丈夫です。
いずれにせよ、孔子が「修身斉家治国平天下(しゅうしんせいかちこくへいてんか)」と言ったように、
「修身」なくして、また途中をすっ飛ばして、「平天下(=社会改革)」はありえないということです。
物事はすべて、基礎があって応用があります。これは経験的に誰にでも分かることですが、スピリチュアルな出世段階においても、やはり同じ順序になるということです。
修羅界
修羅は「阿修羅(アシュラ)」とも言われます。
この世界は、怒りや憎しみを心の癖として一生を過ごしてしまった人が赴く世界です。
行為としては、喧嘩、罵り、DV、モラハラ、パワハラ、諍(いさか)い…などがありますが、戦争の結果、赴く人も多いです。
修羅界についての解釈は、仏教においても多少、混乱があるところです。
修羅界と言えば、有名なアシュラがいらっしゃいますが…、

興福寺阿修羅像
超訳的に言えば、「アシュラは善玉なの?悪玉なの?」という議論です。
阿修羅像を見る限りは、仏法の外護役と言うんですかね、これは善玉的に把握されているようです。
ところが、初期仏教での定義ではけっこう揺らぎがありまして。
修羅界そのものを、かんたんに言えば、地獄的領域/天国的領域のどちらに含めるか?解釈が分かれるところなんですね。
なぜ、こういう見解の違いが生じるかと言うと、それは、上述した、「公的な怒り」か「私的な怒り」か?という論点に集約されます。
要は、
- 悪玉修羅界:自己保存のための怒り=私的な怒り
- 善玉修羅界:自己を修めた上で、正義を実現するための怒り=公的な怒り
という違いになって現れてきます。
後者(善玉修羅界)は、毘沙門天とか、そういう存在も有名ですよね。
まあ、そうすると、善玉修羅界は天界とか、あるいは霊格によっては菩薩界の住人も含まれてきます。
実際に、現象界(この世)においては、悪の勢力もあるわけで、それをそのまま放置しておくと、善の領域まで食われていくことになります。
なので、「悪を食い止める」という意味で、ときに政治・軍事方面で、毘沙門天的な働きが要請されてくるわけです。
ここで、「一切の争いは良くない!」といいうことで、絶対平和主義ですね、これで押し通そうとすると、国ごと滅ぼされるケースも出てきます。
なので、善を実現するための悪への抑止力として、善玉修羅(アシュラ、毘沙門天、不動明王…など)の存在が大事になってくるわけです。
あるいは、言論戦でもそうです。
言論戦、ということで言うと、実は、現代のマスコミ人はわりあい修羅界(悪玉修羅界)に還る人も多いです。
ブログなんかもそうなんですけど、活字というのは、1対多で影響を与えることのできるメディアですので、言っている内容が間違っていた場合、読者の量が多ければ多いほど、毒水を大量に流しました、という結果になります。
まあそういう意味では、Youtubeなどの動画なんかも含まれますね。
言論というのは、ときに「社会正義」という建前をとりますが、そういう建前でありつつ、実際には個人のルサンチマンを撒き散らしているだけだったり、
あるいは、知力の不足により、信奉している価値観そのものにミスがあるケースがあります。
人智学のルドルフ・シュタイナーも「現代の悪魔は活字を通して入ってくる」と述べていますが、悪魔から見ても活字というのは非常にマーケティング効果が高いツール、ということなのでしょうね。
そういうわけで、「戦ったら、イコール、修羅界(悪玉修羅界)行きか?というと、一概には言えないという結論になります。
怒りが、私的な怒りなのか、公的な怒りなのか?というチェックが必要、ということですね。
十界論で分類しているところの修羅界は、「悪玉修羅界」を意味しています。
餓鬼界
「餓鬼」というと、お腹がぽっこりと出ている姿を思い浮かべる人が多いかもしれません。
たしかに、物理的に食料が足りず、いつも、「お腹すいたすいた…」となっている餓鬼霊もいるのは事実です。
現代日本では、飢え死にするということは少ないかと思いますが、全世界で見ると、まだまだ食糧事情がわるいところが多く、
そういう地域では、「ご飯が食べたいのに食べれなかった」という執着のまま亡くなり、餓鬼地獄に陥るパターンはまだまだあると言えます。
ただ、広い意味での(?)餓鬼地獄というと、とにかく「欲しい欲しい!!与えられていない!」という気持ちが心の癖になってしまった人ですね、こういう人が赴く世界ということになります。
これは経済的に貧しい、ということがきっかけであるとはまったく限らなくてですね、大富豪であっても餓鬼地獄に赴くことはあります。
「欲しい」には、無限のバリエーションがありますからね。
「欲求の段階説」では心理学者のマズローのモデルが有名で、当サイトでもご紹介したことがあります。
*参考記事:マズローの「自己超越」「至高体験」とは何か? – 自己実現と自己超越の違いについて
先進国に住んでいる人であれば、たいがいは「生理的欲求」「安全の欲求」は満たされていますので、注意すべきは、「社会的的欲求」以上のところ、とくに「承認欲求」です。
ある程度、「認められたい」というのは誰しもありますし、それが魂の向上のきっかけにもなっていますので、全否定はできませんが、やはり、正当な範囲を超えて執着になると危険領域に入ってきます。
SNSなどでもリア充自慢がありますが、他人と比べたうえで、「私のほうがこれだけ満たされている」のを見てほしい、認めてほしいという欲求。
あるいは逆に、「他の人はあんなにキラキラしているのに自分は…」という惨めな気持ちですね。
こういうのも「執着の領域に入っているのでは?」としていうことで、注意するポイントになるかと思います。
あとは、「愛」に絞って言うとすると、
現代では、「愛」というと、「他者から貰うほうの愛」に重点があります。
J-POPの歌詞などでも、「私が愛されているかどうか」あるいは「男女の愛」などに偏ったものが多いですね。
が、こうした愛はやはり執着の方向へ行きがちです。
実際、仏教用語での「愛」はこちらの執着の愛のほうを指します。
キリスト教的な隣人愛に相当するのは、仏教的には「布施の精神」とか、「慈悲」ということになります。これが天国的な愛ですね。
「欲しい、欲しい」という気持ちの根底にあるものはやはり自我意識と無知です。
「私の〇〇」ということで、まずは、〇〇に執着するわけですが、たいていの〇〇は、この世の生命を終えたら、実在世界に持っていくことはできません。
お金も車も家も肩書もすべて「この世限定」で、実在界に持ち越していくことはできない無常なものです。
ところが、実在界(あの世)を信じていないと、それがなかなか手放すことが難しくなってしまいます。
したがって、やはりベースにあるのは、実在界に関する見識の不足にあると言えるわけです。
また、「私の〇〇」といったときの、「私」についても、本当に確固たるものであるのかどうか?
「私」というのも、どんどん変化していきますし(無常)、外界のさまざまな条件に支えられて、かろうじて「今・ここ」にある存在です、実体ではありません(無我)。
そのように考えると、真理の目からは何一つ執着する対象はあり得ない、ということになります。
釈尊が繰り返し、
無常なるものは苦であり、苦なるものは無我である
と説かれたのは、やはりこの「無常・無我」が根本的な智慧であり、またその智慧に基づいて苦しみから脱却しましょう、ということなんですね。
*参考記事:無常・苦・無我(三相)とは?仏教学通説の誤りを正す
ちなみに、大乗仏教で言う、「空(くう)」の思想は、いろいろとむずかしく言うことも可能ですが、
無常+無我=空
という理解でよろしいかと思います。
あえていえば、無常と無我はこの世(現象界)の観点からも説明できますが、「空」はもう少し霊的なエネルギーの循環論という視点が入っています(ネオ仏法の理解では、です)。
「ちょっと今、執着になっているかな?」と思う時は、一呼吸おいて、
「これはやがて過ぎ去っていくものではないか(=無常)、永遠不滅の実体などではないではないか(無我)」
「一切は、みな空(くう)なるものである。執着に値しない」
と考えてみるといいですね。
また、こうした無常観・無我観の実践こそが地上における強力な修行になり、自らの霊格を引き上げる契機になっていきます。
畜生界
人間が動物や昆虫に生まれてくることはあるか?
「畜生道」という言葉のほうがよく知られているかもしれません。
何度か申し上げていますが、小乗仏教で「畜生界」というと、この世に動物になって生まれ変わってくる、というニュアンスもあり、この世のことだかあの世のことだか、今いち判然としない所があります。
因果応報というのはもちろん認められているのですが、過去世の行いが悪いと畜生(=動物)として生まれてくることもある、というニュアンスですかね。
これは仏教以前からのインドの伝統的な輪廻観も反映されているでしょう。手塚治虫の「火の鳥」を読んでいても、人間が昆虫に生まれてきたり、「何に生まれてくるかまったく予想がつかない」という輪廻観になっていますね。
まあ、「お祖父様が目の前にいるてんとう虫かもしれない」と思うと、動物(昆虫)愛護の精神も湧きやすい、というメリットはあるでしょう。
ここのところ、実際にどうであるか、をまず申し上げておきます。
現象界(この世)の肉体も、実在界(あの世)のエネルギーの表現形式のひとつです。なので、人間のエネルギーであれば、この世にも人間の肉体で生まれてくるのが原則だと思います。
原則、と但し書きしているのは、若干の例外はあるということなのですが、
一種の教育効果として、動物に生まれてくることは、例外的ケースとしてあり得るのかな、と思えます。
たとえば、過去世で「人間として生まれる有りがたさ」を忘れ去った生き方をしていたり、あるいは、あまりに生物的本能のまま人生を過ごした場合ですね、
そういう場合は、「人間としての尊厳」を観察・実感できるように、比較的、人間に近い動物に生まれてくることはあり得るように思えます。
「人間に近い」というのは、少なくとも哺乳類でないと難しいかな、という意味もありますし、また、物理的に人間に近い場所で、という意味もあります。
人間に近い場所に生まれないと、そもそも、「人間のありがたさ」を観察・実感する機会がなくなってしまいますからね。
あの世の畜生道
あの世の畜生道というのは、これも昔からけっこう有名ですよね。
これは上記のケースとは逆で、あの世で動物の格好をして暮らしている霊がいる、ということなのですが。
これはどういうことかと言うと、
「人間は自分自身が何者であるか、自分で決定していくことが出来る」という精神の自由性を持っています。しかし、この自由性を間違った方向に使ってしまうと、堕落する方向へ行くわけですね。
そして、そうした精神のありように相応しい姿・カタチに変化してしまう、ということがあります。
たとえば、
- 人を騙す心:キツネ
- 執念深い心:蛇
といった具合です。
こう言うと、キツネと蛇に申し訳ない気もするのですが、これはむしろ、人間がキツネや蛇に抱いているイメージに基づいていると思いますね。
童話などでも、人を騙す役としてキツネが登場してきたり…そうした記憶が作用しているのだと思います。
なので、よく、「あなたには動物霊が憑いています」と言われた場合、
本当に動物の霊であるというよりも、「元・人間」と申しますか、畜生道に落ちて動物の姿形に変化した霊存在に憑かれているケースが多いと思います。
波動理論から言えば、そうした霊存在と同調してしまう心の波動を発しているので、結果、憑依されてしまう、ということですので、
このケースではむしろ、「動物霊に憑依されているから体調が(運勢が)悪くなっている」という方向ではなく、「生存欲求のままに自分は生きているのではないか?」という内省ですね。
このように心のあり方を振り返って修正をしていく。そして、心の波動を切り替えていく方向が真理スピリチュアルの対処法であるのは言うまでもありません。
この畜生道の近所に有名な血の池地獄などがあると思います。
近所というのは、つまり、「生物的欲求、本能に突き動かされるままに生きてしまった」という共通点があるから、ということになります。
地上に生まれてくると、当然肉体は持っていますので、肉体に基づいた欲求は避けることができません。
むしろ、そうした欲求があるからこそ、地上生命を維持できますし、また連綿と現象界を存続させていくことができます。
ここのところ、
ここ2千数百年の宗教史では、
- 地上=悪
- 欲望=悪
と極端に否定的に捉える向きが多いですし、これを読んでいる読者のなかにもこうした考えに苦しんできた方もいらっしゃると思います。
ただ、この極端な部分は今後、修正が必要かな、と思います。
欲求や欲望そのものは現象界に生きていくため、現象界を存続させていくために必要なものです。これはむしろ神仕組みであると言えます。
しかし、
- 本来、人間は精神エネルギーとしての存在である、という尊厳
- 現象界を魂(心/精神)を高めていく機会として使う
ということを中心に据えて、欲望/欲求部分を適正範囲に整えていくという調整論ですね。
ここでも、やはり中道が大事であろうと思います。
地獄界
「地獄篇」で「地獄界」というのもターム(用語)的に重なっている感がありますが、これは、「餓鬼・畜生・修羅界」の3つも広義の「地獄界」に分類しているからです。
小乗仏教で、「餓鬼・畜生・修羅界」というと、この世でそういう状態で生まれてくることを指しているのか?今いちピンとこないところがありますが、
今回取り上げている十界論では、「実在界(あの世)に10個の世界があり、現象界(この世)の心境にも10個の世界がある」という考え方を採ります。
肝心なのは、やはり、現象界と実在界はパラレルの関係にあるということで、まったく切り離された世界ではない、ということですね。
わかりやすく言いますと、この世での心境の平均値があの世のどこの世界に赴くかを決定する、ということです。
したがって、自分が死後、どの世界に赴くかは、内省によってチェックしてみればある程度のことは分かるということになります。
とはいえ、知識がないと内省のよすががそもそもありませんので、当サイトでこうした情報をお伝えしているわけです。
そして、さらに真実はどうかというと、
私たちの肉体は物質ですので、物質界(=現象界/この世)にありますが、私たちの精神は物質ではありませんので、この世ではなく、今この瞬間にも叡智界(=実在界/あの世)にある、ということが言えます。
*参考記事:現象界と叡智界(実在界)は同時存在する !?
なので、「死後、地獄に堕ちる」というよりも、「生きているうちに地獄に堕ちている」とも言えるわけで、これを通称、「生き地獄」と言いますね。
ただし、やはり私としては、「死後の地獄よりも、生き地獄のほうがまだマシ」という考えを採ります。
なぜというに、
死後の地獄界では周りが似た者同士なので、脱出するよすがが少ない状態にあります。
*参考記事:人生の意味とミッションとは? – 最勝の成功理論を明かします
ところが、この世では肉体を持っていますので、ふとした機会に心を他の領域に振り向ける機会が多いのですね。
たとえば、もちろん私にしても心境がよくないときはありまして、その時間中は地獄界にいるのかもしれませんが、
娘がトコトコとやってきて無邪気に話しかけられると、そちらに気を取られて(いい意味で)、心境が良い方にくらっと変わることがあります。
あるいは、意図的に「仕事に集中してみる」という方策でも、(人間の心は一時に一方向しか向けられませんので)、心境を変化させる手立てとして有効です。
ちなみに、ですが、
ネオ仏法サロンサロンでは、オンラインセミナーを行うときがあります。
セミナーは録画しておりまして、会員さんは会員限定ページからいつでも動画で観ることができます。
セミナーの録画を自分で観なおしてみても、一般的な悪霊を吹き飛ばすくらいの波動は出ていると思います。おそらく、漢語のお経を読み上げるよりかはよほど効果はあると思います。
要は、「波動理論」通り、波動が合わなければ同じ磁場にいることができない、ということですね。
もちろん、ブログ記事を読むだけでも一定の効果はありますが、音声や動画のほうが直接的な波動が強いですので、効果は高いと思います。
観るのがしんどい場合は、音声で流してなんとなく聞いているくらいでも大丈夫でしょう。悪霊払いとしては、そういう方法もあります。
さて、
地獄の種類については、さまざまな分類がありまして、八大地獄((WIKI)とか色々言われております。
それぞれ個別にお話しても良いのですが、かなり時間がかかりますので、今回は大事なポイントだけお話していきます。
十界論もそうなのですが、「〇〇界」というのはあくまで便宜的な分類でありまして、
「心の平均値が赴く世界を決める」という理論から行くと、実際は人間の数だけの世界が存在することになります。
ただ、あまり細かく分類しても参考や目安になりませんし、また、ある程度近い波動の魂たちは協同して(?)ある一定の霊域を作り上げているのも事実です。
「餓鬼・畜生・修羅界」を除いた地獄界というと、これら3つよりもさらに深い地獄ということになります。
どうして深くなるのか?と言いますと、つまりは、「影響力の度合いが強い」ということなのですね。
餓鬼・畜生・修羅については、あくまで個人的な心境に基づいて赴くわけです。
とは言っても、もちろん他者への影響はありますが、やはり自分の身の回りの人間に対する悪影響ということで、影響力の度合いが限られています。
一方、より深い地獄というのは、つまり、「影響力の度合いが強い=汚染の度合いが社会性を帯びている」、ということになるわけです。
そうすると、
- この世であっても影響力の高いポジションにいた
- 思想的に誤りがあり、その誤りを拡散させてしまい、多くの人に悪影響を与えてしまった
というのが、基本的な問題ということになりますね。
菩薩界へ還るための公式というのを
霊格=智慧×慈悲
という式でお話したことがありますが、
*参考記事:人生の意味とミッションとは? – 最勝の成功理論を明かします(「菩薩になるための公式とは?」)
思想の誤りがある場合、「智慧マイナス」になってしまいますので、「拡がりがあればあるほど、霊格が下がる」という努力逆転の法則に見事に当てはまってしまいます。
そして、その人がこの世で影響力のあるポジションにいるのであれば、なおさらその汚染は大きく広く拡散していくことになります。
とくに現代のようにインターネット、SNSなどが日常的なツールとして使われている時代は、私たち一般人でも用心が必要です。
たとえば、宗教書に対するAmazonのレビューなどを見ていると、「神が人間を作ったのではなくて、人間が神を作ったのだから…云々」といった書き込みを目にすることがあります。
書き込んだ人は何気なく、「自分の意見としてはこうですよ」とやっていらっしゃると思うのですが、
一度書き込んでしまうと、削除しない限りは、一種の「逆資産」として、今後、延々とそのレビューが読まれていくことになりますよね。
これ、まさに逆資産、マイナス資産で、
「資産がキャッシュフローを生む」という考えで行けば、(なぜか、「金持ち父さん貧乏父さん的な話に行っていますが)一度書き込みした内容が、思想的に重大な誤りがある場合、延々とキャッシュフローならぬ、「霊格落下フロー」を生み出していることになるわけです。
おおげさではなく、そのたった数行の書き込みだけで、一生分の普通の仕事ですね、それはそれで世の中に役立つ付加価値を生んでいたかと思いますが、それらを全部帳消しにしてさらに余りあるマイナス具合、と言っても大げさではないです。
この世の仕事というのは、たいてい、「利便性の提供」というあたりに止まっていますが、
思想というのは、人間の根本である心ですね、その心の働きのもっとも基底部分に影響を与えるものでありますので、起爆力がめちゃくちゃに大きいのです。
なので、思想的に誤りがあり、それを拡散してしまった場合の反作用はかなり甚大なものになる、ということは想像がつくかと思います。
今風にいえば、「悪がバズる」とでも言いますか。
そういうわけで、今回お話している地獄界でもっとも問題にしたいのは、(つまり地獄の最深部でもあるのですが)、こうしたいわゆる「思想犯」的な誤りを犯した人が赴く世界である、ということです。
ここは、無間地獄(むけんじごく)とも言うこともあります
また、この無間地獄に堕ちた魂が開き直って、さらに積極的に悪を拡散すべく悪魔になるケースが多いのです。
当サイトでは、開始当初から、「スピリチュアル起業には注意してください」とたくさんの記事を書いていますが、
これは、起業している人に対する警告でもあり、同時に、思想的な誤りがなるべく拡散していかないように、という配慮から記事数が多くなっているのが理由です。
スピリチュアル以外でも、ここ200−300年では、科学万能思考とか、唯物論とか、とにかく、「神や宗教、霊的な存在を否定するほうが、知的・科学的である」という発想ですね、
これは現代人であれば、程度の差はあれ、誰でも影響を受けているところがありますので、やはり、注意していきたいところです。
餓鬼・畜生・修羅界あたりでは、個人の内省で波動をチェンジしていけば、脱出することが可能ですが、
深い地獄界は、「悪が社会性を帯びていた(=影響が拡散していった)」ということで、ひろく他者・社会へ影響を与えてしまった責任も生じていますので、個人の内省だけではなかなか脱出することが叶わない状況になってしまいます。
なので、ここの「地獄界」ですね、狭義の地獄界。無間地獄と言ってもいいですが、ここだけは少なくとも堕ちないように、気をつけていきましょう。
以下、十界論の後半、天国部分に入っていきます。
人界
人界は、「人間界」ということで、文字通り、人間的な属性が主流な世界ということになります。
ただ、例のごとく、もともとの小乗仏教の「人界」は私たちが今、生きているところの現象界(地上世界)を指しているニュアンスがあります。
上述したことと話題が重なりますが、十界論が優れているのは、「現象界の心境と、実在界の住む世界はリンクしている」という思想にあります。
そうすると、スピリチュアル趣味的な話にとどまらず、十界論そのものが、実際に霊格向上の目標を立てたり、心境の進捗度合いをチェックしたり、内省の目安になったり、この現象界で今回、人生を送るにあたり、収穫の最大化を図るのに非常に便利な指針となります。
人界は一応、天国領域に入ると思いますが、しかし、少なくとも二段階くらいには分けて考えたほうが良いかな?と思えることろがあります。
人界下段階 -「死後、まず赴く世界」としての人界
この世(現象界)での生命を終えると、魂は肉体を抜け出して、あの世(実在界)へ移行することになります。
ただ、死後すぐには、実在界のどの場所に住むのか?決定できませんし、そもそも、今までずっと現象界に暮らしていましたので、まずは実在界そのものに慣れていく(思い出していく、とも言えます)必要があります。
なので、とりあえずは、「一時保留」的な世界ですね、キリスト教で言う煉獄(れんごく)などは若干、ニュアンス的に近いのかもしれませんが、そういう世界があります。
日本ではむかしから言われているように、「三途の川」を渡って、この世界に赴くとされています。
三途の川というのは、日本人に分かりやすいように視覚的・感覚的に翻訳されている光景なのですけどね。川がそもそも少ない国、地域ではまったく別の風景が見えることになると思います。
ゾロアスター教では、「チンバット橋」と言いまして、天国への橋がかかているとされています。
生前の罪の多さ/少なさによって、橋の幅が変わっており、まあ罪が重い人の場合は、橋の幅が糸のようなものになってしまい、下の地獄へ真っ逆さまに堕ちていくと。
こういう風景になっているようです。
これらの風景は、実際にある/ない、というよりも、
- 現象界と実在界の境目があるということ
- 現象界での生き方が実在界で赴く場所を予想させる
という一種の、「象徴」ですね、翻訳されてそのように視えているわけです。
三途の川を渡った後は、「今後、どの世界に赴くか?」というお裁きが始まることになると言われています。
「浄玻璃鏡(じょうはりのかがみ)」と言いまして、これはどんな鏡かというと、生前の思いと行いがまるごと映し出されるわけですね。
人間というのは、なかなか客観的な自己評価がむずかしいもので、つい、自分に有利なものの見方をしてしまいます。
ところが、鏡に映し出されることによって、はじめて、「客観的に自分はどうであったか/周りからどう見えていたのか」ということが分かります。
もっとも、「ぜんぶ映し出される」と言っても、生前の人生と同じ長さで、となると、膨大な時間がかかりますし、そもそも、この世とあの世とでは時間の感覚がまるで違います。
いわば、「ここがポイント!」的な映像ですね、自分のこころに良きにつけ悪しにつけインパクトを感じたところの心象風景、そうした、いわば「ベスト盤」的な映像を見ることになると思います。
このように客観的に振り返ってみると、だいたい、自分にふさわしい世界がどういうところか分かりそうなもので。
それでも、納得できない人のために、むかしから言われている閻魔大王ですね、いわば、裁判官的な役割をしている人が立ち会うことになると。
こんな感じだろうと思います。
人界上段階 -生存欲求に基づいて生きた魂が住む世界
上記の「一時保留場所」的な人界のほかに、居住地としての人界もあるでしょう。
ここは、天界、いわゆる狭義の「天国」と呼ぶほどではないけど、さりとて、地獄というわけでもない、という世界です。
仏教では、天界へ還るための方法論として、施論戒論生天論(せろんかいろんしょうてんろん)を説いています。
- 施論:施しをして(=善いことをして)
- 戒論:戒めを守れば(=悪いことをひかえれば)
- 生天論:天界へ生まれることができる
という、現代人が聞くと、「そんなバカな!」的な、超シンプルな説法です。
しかし、いくら馬鹿げたように感じられようと、こちらのほうが真実です。
なので、人界というのは、とりあえずのターゲットとしての天国(天界)までは至らない世界、ということになります。
つまり、
自我が出やすい現象界(この世)で、「施しをして戒めを守る」というのはシンプルでありながら、意外に難しいことで、これはやはり一定レベルの精神性をクリアしていることになります。
物理世界に生きながら精神性に目覚めていた、ということでこれはやはり結構なレベルなのですね。それゆえの天界です。
ここのところをテコに考えると、人界がどのような世界であるのか?逆に想像がつきます。
つまり、人界は、
- 地獄領域に行くほどではないけど、精神性の目覚めが不十分だった
- 肉体的自我の命ずるままに生きてきた
人々が住む世界、ということになります。
それでも、地獄領域に比べれば、ずっと明るい世界ですし、人界といってもその中でまた色々な段階がありますので、天界に近づけば近づくほど、より天国らしい風景になっていくのは当然のことです。
ただ、そうは言っても、「帰還の目標とすべき世界」というほどではないと思いますので、少なくとも、「天界に還ること」を目標にしたほうが良いかと思いますけどね。
天界
天界(てんかい)というのは、私たちが昔から漠然とイメージしているところの、「天国」だと思えば、間違いのないところであるかと思います。
キリスト教や浄土宗系で天国とか極楽という場合、実際は、ここの「天界に還ること」がターゲットになっているケースが多いですね。
視覚的には、「人々が愛し合い、草花が咲き乱れ…」という牧歌的で明るい世界です。
もっとも、「現象界と実在界がパラレルである」という理論から行くと、現象界でIT機器などを使いこなして、かつ、天国的な心境であった場合、
実在界(今回で言えば天界)に還っても、そうした生活スタイルを維持することがあるでしょう。
あの世の情報というのは、地獄界にしても、「大昔から語り伝えられているイメージ」が大部分ですので、私たち現代人から見ると、ずいぶん縁遠い感じがすることがありますけどね。
実際は、この世の生活スタイルをあの世に持ち越していくケースが多いですので、
たとえば、修羅界であっても、未だに刀や槍で戦争をやっている人もいることはいますが(つまり、その当時の時代からずっと修羅界にいるということですね)、
現代人が修羅界に還ると、もっと近代的な兵器(これも実際はイメージ/象徴なのですが)で戦争をやっていたりします。
あるいは、「人を傷つけること」が修羅界の特徴であるならば、たとえば、SNSの書き込みでトラブルを起こすとか…、
こういう今現在の地獄的なあり様が、あの世の修羅界でも形成されている可能性は高いですね。
天界の下段界
天界についても、二段階くらいには分けて把握したほうがよろしいかな?と思います。
天界下段界は上述したような牧歌的なシンプルな世界です。
さきほど、「人界は精神性の目覚めがいまだ不十分」と書きましたが、天界においては、一定レベルの精神性をクリアしていることが条件になります。
どういう精神性か?と言いますと、これはキリスト教で言うところの、
- 汝の主なる神を愛せよ
- 汝の隣人を愛せ
という黄金律ですね、ここをクリアしているかどうか?が目安になると思います。
*もっとも、この2つの言葉を「黄金律」としているのはネオ仏法の解釈です。
もちろん、キリスト教的な色彩である必要はなく、イスラム教でも仏教でもいいいですし、あるいは、特定の宗派ではないけれども、「人智を超えた存在を信じて、敬意を払う」という精神性ですね、それが天界に帰る条件になります。
そういう意味では、もっとシンプルに、「大自然に畏敬の念を持つ」とか、こうしたあり方でも広い意味での信仰心ですので、天界の条件はクリアしているのかな、と思います。
そうすると、天界の下段階に還る要件としては、
- 人智を超えた存在を信じ、畏敬の念を持っている
- 自分の周囲の人々に、無条件に優しく接することができる
という2点にまとめられることとなります。
この天界下段界はシンプルに視えて、実は現代人が見失いがちな価値観をしっかり保持している世界でありますし、
また、天界上段界以降の世界を狙うにしても、いつもいつも、「天界下段界はクリアしているか?忘れていないか?」というのが大事なチェックポイントになってきます。
物事はすべて、基礎があって初めて応用があるからです。
「基礎はマスターした」と思って、応用編に入っていっても、いつのまにか基礎が抜け落ちていることがあるのは、一般の世の中でもよくあることですよね。
イメージ的には、ふだん接する人々の中でも、「あの人、ほんとに良い人だよねー」と言われるタイプですかね。
「特に、優秀である/何かに秀でているわけではないけれども、ひたすら善人である、というタイプの方が赴く世界が天界」ということになります。
天界の上段界
下段階については、「特に何かに秀でているわけではないけれど、ひたすら善人が赴く世界」と書きましたが、天界でも上段階に移行するに従って、「優秀性」が要求されてくるようになります。
というのも、霊格=智慧×慈悲 という公式から考えますと、優秀であるということは、具体的には「智慧が優れている」ということでありますので、当然、霊格も上がっていくことになるからです。
もっとも、「智慧」と言ってもさまざまな段階と奥行きがあります。
天界における智慧は、真理の奥の奥を見通す深い智慧まではいかないかもしれません。
むしろ、もっと身近で実用的な知恵、世の中の利便性や進歩に貢献するような知恵の段階だと思います。
そうすると、私たちがふだん接している人のイメージで行けば、「良い人だし、すごい人だよねー」と語られるような人ですかね。
善人であることをベースにしつつ、知恵があり、仕事もバリバリできるようなタイプ、具体的に実績を出せるタイプです。
霊界の人口は逆ピラミッド型になっておりまして、上の世界へ行けば行くほど人口は少なくなっていきます。これは会社組織でもそうなっていますね。
ただ、霊格が高い人は概してリーダーシップや影響力に秀でていますので、一人で多数の人に影響を与えることができる、指導ができる、という特徴を持っています。
なので、そこから敷衍して言えることは、
天界上段階における霊格の違いというのは、影響力や指導力の差である、ということになります。
まとめますと、天界上段階へ還る条件は、
- 広い意味での信仰心を持ち、善人であること(天界下段界をクリアしていること)
- 何らかの分野で優秀性を示すことができること
- 影響力やリーダーシップを発揮することができること
という3点が挙げられるのではないかと思います。
補論:悪魔は天界にいるか?
ちなみに、仏典では、釈尊の成道を妨げたマーラ、まあ悪魔ですね、マーラが天界(*他化自在天という世界)に存在する、という分類をしておりますが、これは、誤りです。
少なくともネオ仏法的には認めることはできません。
波動理論に則れば、波動が精妙であるほど上の世界へ行き、波動が粗雑であれば下の世界へ行くことになります。
したがって、マーラ(悪魔)が天界に存在するということはありえません。
おそらくは、多神教にありがちな発想、
すなわち、「ちから(パワー)があれば、それは人智を超えた存在で偉いんだ。ゆえに、高い世界にいるのではないか?」という素朴な発想から来ているもので、伝承・口伝の過程で、間違って仏典紛れ込んできたのだと推定しています。
そして、天界最上段階へ
さて、
天界は上へ行けば行くほど、物質的な属性を離れた世界になっていきます。
仏教では、三界(さんがい)という区分の仕方もありまして、三界とは、欲界・色界・無色界(よくかい・しきかい・むしきかい)の3つです。
天界では、これら3つの世界がすべて揃っています。
興味のある方は、これらの分類を調べてみるのも一興かと思いますが、
要は、
「欲界→色界→無色界と進むにつれて、物質的属性を離れ(執着から遠ざかり)、精神性の比率が高くなっていく」というあたりの理解でよろしいかと思います。
精神性の高まりというのは、つまりは、奥深い真理へ接近していくということでもありますが、この段階は、天界より上の「声聞界・縁覚界」の項目でご説明いたします。
最後に、大事な論点をひとつ挙げておきます。
天界においては、「相対観が強くなる傾向がある」ということが言えると思います。
どういうことかと申しますと、
知恵の高まり、指導力・影響力で霊格が決まるということは、すなわち、「自己実現欲求とそれに伴う競争意識が高まる」という傾向がでてくるのですね。
ここのところで、「優秀である/優秀でない」「理想的である/理想的でない」といったふうな”相対観”に悩む時期にさしかかる側面があります。
声聞界
上記までのお話し、すなわち、十界(じっかい)のうち、下から「地獄・餓鬼・畜生・修羅・人・天」の6つは、六道(ろくどう)と言いまして、初期仏教からあった思想です。
この6つの世界をぐるぐると輪廻しているので、「六道輪廻(ろくどうりんね)」と呼ばれているのですね。
そして、釈尊の仏教では、あるいは、小乗仏教(テーラワーダ仏教/上座部仏教)では、「悟りを得ることによって輪廻を打ち止めにすることが修行の目的である」、と言われています。
「言われています」という書き方をしたのは、つまり、「ネオ仏法ではそうは考えない」ということなのですが、これはそもそも、釈尊の真意がキチンと伝わっていないと捉えているからです。
この論点については、下記の記事で詳しく書きましたので、興味のある方はご参照ください。
*参考記事:涅槃とは何か?本当の意味を解明する– テーラワーダ仏教批判④
短くまとめておきますと、
釈尊は輪廻そのものを否定的に捉えていたわけではなく、「迷いの輪廻」を智慧のちからで打ち破り、主体的な輪廻へ移行することを説いていた。
真理(実在)の視点から地上世界や輪廻(現象)の意味を汲み取り、それを最大限に活かしていくことが悟りであり、涅槃であるのだ。
というのがネオ仏法での理解です。
さて、
十界論のなかの、声聞・縁覚・菩薩・仏の4つの世界については、大乗仏教で付け加えられたものです。
小乗仏教のなかで、悟りを得る、すなわち阿羅漢(アラカン)になるということが、どこかしら利他行を放棄したような独善的な流れが出てきましたので、アンチテーゼとして大乗運動が起きてきたのですね。
その際に、仏陀の悟りを目指しつつ、利他行に励む存在として「菩薩」という思想がクローズアップされてきたわけです。
当サイトでもよく言っている「自利利他」(自利利他円満)という思想です。
そうして、自らの悟りのみを求めている小乗仏教の人たちを、菩薩より低い「声聞(しょうもん)」として位置づけたのでした。
そういうわけで、「声聞」という言葉はオリジナルに還ってみると、小乗仏教の人たちを揶揄(やゆ)するようなニュアンスがあったのですけどね。
「君たちは、仏陀の教学を学んでいるだけ=声を聞いているだけ=声聞、ではないか!」というわけです。
実際に、初期の大乗仏典を読むと、過剰なまでに声聞を貶めている内容が散見されます。
しかし、ネオ仏法では「声聞は必要な段階」という捉え方をしています。
菩薩の思想がちょっと危険なところは、「性急に利他行に走るきらいがある」というところで。
智慧×慈悲=霊格(仕事量)の公式に照らし合わせれば、
「利他行(=慈悲)といっても、伝えるべき智慧がなければどうしようもないんですよ」という論点があるわけです。
それどころか、マイナスの智慧を伝えてしまったら、利他行をやればやるほど害毒を撒き散らしていく結果になってしまいます。
このパターンは意外に多いのです。
また、そもそも自分さえ救えていないのに、どうして他人を救うことができるのか?という論点もありますね。
なので、まず、知識ベースでしっかりと仏法を学ぶことが大事で、そのためには、とりあえずは心静かに真理に一人向き合う時期は大切であると思いますし、また必要な段階でもあると思います。
ベストセラーの『7つの習慣』でも、「私的成功」→「公的成功」の順序になっていますが、やはり、物事には順序があるということです。
とはいっても、
利他行に行かないことを「自分は自利がまだできていないから、不十分だから」「まだ声聞なので」という言い訳に使うことは要注意です。
これもけっこうやってしまうんですよね…。
他者に関心が向かないことの言い訳で「声聞」を使ってしまうのはままあることで、これは私自身も反省することがしょっちゅうあるところです。
王道としては、「声聞界に楔(くさび)を打ち込んで、菩薩界を目指す」という順序かな、と思います。
というのも、菩薩と言えども、実際はいろいろな段階と個性がありまして、菩薩界下段界あたりでは、オリジナルの思想を説く、というのは無理というか難しいと思います。
釈尊の弟子にしても、イエスの弟子たちにしても、やはり開祖の教えを伝えたというところに仕事の力点があるわけで、まったくオリジナルの思想を発表したわけではありません。
後世の弟子たちも、「開祖の教えをベースにして、整理整頓(学問化)したり、あるいは時代に合った教え方(変化系)を作っていった」ということですね。
もっとも、今回ご説明している十界論をもとに教義を組み立てていった天台智顗(てんだいちぎ)など、「中興の祖」レベルになると、けっこう思想的に飛躍が必要で、難易度が高いと言えると思います。
こういう人たちは、菩薩界でも中・上段階以上の方でしょうね。
なので、霊格向上の原理として取り組みやすい(勝ちやすい)のは、
- 声聞界をターゲットに、真理を求める心の習慣をつけ、真理の知識を吸収しつつ、
- そこを足がかりにして、利他行に励み、菩薩界を目指す
という順序です。
そして、利他に行かない言い訳に注意、ということは上述しましたが、
コツとしては、自利と利他を相互作用的に回していくということです。
「学びつつ、伝える」「伝えたら何かしらリアクションがあるので、それを振り返りながらまた学ぶ」といったふうに、です。
一種のPDCAサイクルですね。
声聞界は、前回の記事で書いた天界上段界の、「善人+優秀性」に、「真理を積極的に求める心の習慣」を加えた境地です。
声聞界=善人+優秀性+真理を求める心の習慣
というふうにまとめることができるかと思います。
あるいは、「優秀性の真理含有率を底上げしている段階」と言っても良いでしょう。
現代の先進国、とりわけ日本にわざわざ生まれてくるような魂は、わりあいに天界出身(少なくとも出自としては)の方は数多くいらっしゃいます。
なので、上記の式で言えば、
「真理を求める心の習慣」をつけて、心の平均打率まで持っていければ、還る世界は声聞界ということになりますので、誰もが目指せる世界でありますし、目指さないともったいない世界であるとも言えます。
これに、利他行の実践を加えれば、広義の菩薩界に入っていくことになりますからね。
さて、
真理を求める心の習慣、ということで言えば、やはり生活リズムのなかに取り入れていくことが大事です。
なので、毎日の生活の中で、祈りや瞑想、経典読誦の時間を確保するのはやはり大事です。そのために、作りたてですが、「祈り/瞑想/読誦」メニューも用意しておきました。
ここに紹介しておいた3つだけでも、時間にしたら10分かかるか?という程度ですよね。
しかし、そのたった10分が「習慣化」に大きく寄与してきますので、まあココに紹介したものでなくても良いのですが、なにかしら、そうした「実在界との接触」の時間を設けるのがベストだと思います。
「真理を求める心」というのは、別の表現で言えば、「知への愛」です。
哲学は英語で「フィロソフィア」と言いますが、
- フィロ:愛する
- ソフィア:知
という意味です。
なので、「哲学」というと語感的に難しくなってしまいますが、ソクラテスが説いていたのは、シンプルに「知を愛すること」ということで、これは、「声聞を目指しましょう」ということとほぼ同じことなんです。
縁覚界
縁覚(えんがく)というのは、独覚(どっかく)とも言いまして、いわば「一人悟りの世界」です。
声聞のように、特定の教義を勉強するなどしないで、自分ひとりだけの力で悟りを開こう、みたいな世界です。
もともとは、仏陀・釈尊以外にも、真理を体得した人はいるだろう、ということで、仏教系以外の仏陀(?)を縁覚と定義していたようですが、十界論では当然、仏界という扱いにはなっていません。
「声聞界→菩薩界が王道で、勝ちやすいルート」と上述しましたが、「誰かについて学ぶのは嫌だ、自分の人生経験と思索だけで認識力を向上させていきたい」という人もいらっしゃいますよね。
実際に、思想・宗教系統でなくとも、職業経験から独自の悟り(認識力の獲得)を得る方も多く、
たとえば、松下幸之助さんなどは、事業家でありながら、PHP(Peace and Happiness through Prosperity)、つまり、「繁栄を通じた幸福と平和」という思想を展開していきましたね。
もっとも、松下幸之助さんは縁覚界というよりも、もっと偉い方だと思いますけど、ルートとしては縁覚的であるかもしれません。
過去世なども含めて考えると、「声聞的な世界も経験したけれども、今回の人生ではオリジナルの道を歩みたい」というルートを選ぶ場合もあり、なんとも言えないところはあります。
ただやはり、難易度としては、「輪廻のなかで、声聞的な経験を一切積まないで、イチからオリジナルを」というのは、難しいだろう、と思いますけどね。
なので、ネオ仏法的にお勧めとしては、声聞界→菩薩界のルート、ということになります。
菩薩界
さて、いよいよ、菩薩界です。西欧的に「天使界」と言ってもよいでしょう。
今まで十界を順番にお話してきましたが、「基礎があって応用がある」という流れは一貫しているとお気づきの方もいらっしゃると思います。
すなわち、
- 天界下段界:善人
- 天界上段界:善人+優秀性
- 声聞界:善人+優秀性+真理を愛する習慣性
といったふうに、上の世界は、必ず下の世界をクリアした上で成立している世界であることが分かります。
土台があって、柱が立って、家ができる…というふうに、必ず、基礎から応用へ進んでいくわけで、ここのところ、あまりにも常識的でかえって驚かれる方もいらっしゃるかもしれません。
それはやはり、菩薩とか天使、というと、「何か非常に特殊な神秘的な存在である」という歴史的な(あるいは芸術的な)イメージ、思い込みから来ているのですね。
仏教では、「人間は決意と実践次第で誰でも菩薩になれる、さらに仏陀にもなれる」(そもそも、仏陀の悟りを目指すのが菩薩なのですが)という力強い思想があります。
一方、キリスト教では、父と子と聖霊は三位一体だとしても、私たち一般の人間はまるで関わりがないと申しますか、たとえば、「修行して聖霊になる」という修行論は認められていませんね。
父と子と聖霊の前では、人間は救われるべき子羊の群れです。
ここらへんは、実際のところ、キリスト教の教義の幅と深さが不十分であった、というところに起因しているわけですが。
しかし、実際は、原始キリスト教、つまりカトリックが成立する以前には、グノーシス主義、あるいはグノーシス的色彩をもった福音書も作られていました。
今回は深入りしませんが、現行の聖書からは「外伝」として除外された「トマスによる福音書」などを読むと、「これはほとんど仏教思想ではないか」と思えるところがあります。
輪廻の思想はいまだ不十分ですが、
「グノーシス(知識・智慧)の獲得によって、人間は自らの神性を顕現していくことができる」という考えは、仏教の仏性論・修行論とほとんど同じ考え方です。
- グノーシス=知識・認識の獲得=悟り
- 神性=仏性
と読み替えてみれば、まったく同じことを言っているわけですね。
なので、残念ながら歴史的には異端とされてしまいましたが、オリジナルのキリスト・イエスの教えは現行の福音書に書かれているよりも、はるかに仏教にも通じる思想が展開されていたのです。
まあここを話し出すとまた別のトピックになりますので、この辺にしておきましょう。
下記の記事で若干、詳しい考察をしておりますので、興味のある方は読んでみてください。
*参考記事:キリスト教グノーシス主義と仏教の接点序説
話を戻しますと、
要は、菩薩(天使)という存在は、私たちと永遠に隔たった異質な存在ではなく、輪廻を繰り返し、魂修行をした先にあるところの、私たちのひとつの大きな目標地点/メルクマールであるというこことです。
もっとも、大乗仏教では、「仏法を受け入れて利他行を決意すればもう菩薩」みたいな性急なところもありますけれど、これは、菩薩および菩薩界という世界をいかに定義するか?によっても解釈が変わってきます。
前回の「声聞界」の延長で菩薩界を考えてみるならば、上述した「基礎があって応用がある」というところですね、これを当てはめてみると、
- 声聞界=善人+優秀性+真理への愛
- 菩薩界=善人+優秀性+真理への愛+利他
というふうにまとめることができるかと思います。
「利他」はいわゆる「隣人愛」ももちろん含まれますし、むしろそれが基礎であるのですが、天界下段界の「善人としての隣人愛」とどう違うか?というところですね。
結局、人界→天界→声聞界と段階を上がっていくにつれて、広い意味での「社会性」が増してくるのです。
天界上段階では、「優秀性・影響力が問われてくる」と書きましたが、これは別の言葉で言えば、「社会性を帯びてくる」ということでもあります。
そうすると、天界下段階における「隣人愛」との違いが浮かび上がってきます。
すなわち、天界下段界の隣人愛が、「ふだん接する人」を基本の対象としているのに対して、菩薩界の利他というのは、(もちろん、隣人愛は基礎にしておりますが)もう少し対象的に拡がりがあるということになります。
つまり、菩薩界の利他というのは、自分と直接的・日常的なつながりがない人々に対しても、愛の実践をすることができる。むしろ、その拡がりを望んでいる、ということです。
これがいわゆる「社会性」ですね。あるいは「公共性」と言っても良いでしょう。
そうすると、菩薩界を仮に下段界・中段階・上段階と分けた場合、この違いは何処にあるのかと申しますと、上の世界に行くに従って、「利他の拡がり・影響力・社会性が増してくる」と定義することが可能かと思います。
さて、
私たち一人ひとりは「個別的な存在」であるわけですが、オリジンに遡って考えてみると、大宇宙の「真実在」とでもいうべき存在からエネルギー分化してきたわけです。
エネルギー分化して、それが地上に生命を持つと、そこで個性化が起きる。個性の獲得ですね。
そして、個性を獲得しながら、他の個性と切磋琢磨しながら、魂を磨き、自らをより大きなエネルギーになれるよう努力しています。
これは、鮭の遡行ではないですけれど、やはり、作られたもの、すなわち子として、親(真実在)の元に還っていきたい、という願いに通じるものがあります。
そうであるならば、むしろ、「菩薩になりたい」というのは、実はきわめて正常な欲求であり、いやむしろ、この欲求に気づくことこそが、真なる意味での「魂の目覚め」であると言えるでしょう。
菩薩界の生活・働き
菩薩界と言っても、広義の菩薩界と狭義の菩薩界にとりあえず分けて考えたほうがいいでしょう。
狭義の菩薩界については、「実力・菩薩」ということで、けっこう認定としては厳しいところがあるかもしれません。
仕事量としてはどのくらいが必要か?はいちがいに言えませんが、後世への影響も含めて、ひとりで数万人程度の人々に魂の肥やしになるような影響を与える実績と実力が必要かな、と思います。
思想家や芸術家の場合、同時代では認められず、後世にだんだんと評価が上がっていくケースが多いです(逆パターンもありますが)。
その場合は、たとえば死後、すぐ菩薩界に還るというより、手前くらいの世界で慣らしつつ、だんだんと元の世界に還っていくイメージだと思います。
まあこれは菩薩界に限らず、どの世界出身でもそういう傾向はあり、
地上に生きていたときの垢落としというか精算と言いますか、その期間が必要で、まっすぐに元いた世界に戻るというのは稀だと思います。
また、「もともとの霊格」というのはやはり影響してきますので、過去(過去世)での実績。グループソウル全体の実績・霊格で住むべき世界が決まる、という側面はやはりありますかね。
グループソウルというのは、自分と自分の過去世の魂たちの集合体です。
また会社のたとえで恐縮ですが、会社では1年を四半期といって4つの期間に分けますよね。
4−6月までの成績、7月-9月までの成績、10月-12月までの成績、1月-3月までの成績の通しで1年間の勤務評定が決まるように、
グループソウル全体の霊格も、過去世1、過去世2、過去世3…今回の自分、といったふうに、トータルで決まるというイメージです。
*もっとも、グループソウルのなかの個々の魂も個性は保存されていまして、各々が若干、霊格が違うケースが多いかな?とは思います。
なので、狭義の菩薩界というと、過去世の実績も含めて…というふうになりますので、誰もが今から目指せる世界というのは、広義の菩薩界ということになります。
広義の菩薩界は、「声聞」の実力を持ちながら、実際に利他の実践に励んでいる段階です。
十界論の基礎理論に従って考えると、現象界と実在界の心境は一致していますので、地上生活でも霊界に還ってからも心境は一致しているはずです。
菩薩界へ還る要件は下記の通りでしたね。
- 菩薩界=善人+優秀性+真理への愛+利他
なので、生活パターンもこの通りで、「真理の学びと利他の実践」を各々、具体化していくということが課題になっています。
真理の知識を持っていると、ネオ仏法のさまざまな記事で書いておりますように、人間は「アイデンティティのあるエネルギー存在」ということを知っていますので、実際は、霊界に還ってからは物質的な仕事をする必要がない、ということになりますよね(ご飯を食べる必要もありませんので)。
なので、たとえば、自分より霊格の高い先生について真理の学びを深めつつ(=声聞の修行)、利他行に励むということになります。
それはたとえば、
- 霊界に還ったばかりの魂たちへの導きの仕事(説法など)
- 自分よりも下位霊界に住んでいる人々の先生役としての仕事
- 自分の専門分野について、地上で同じような仕事をしている人へインスピレーションを与える仕事
- 浅い地獄界に居る人々を説得して、天国領域へ引き上げる仕事
などがあると思います。
*4については、深い地獄界まで降りて説得をするというのは難易度が高いので、菩薩界下段界クラスでは行われていないと思います。
もっとも、こうした「わざわざ地獄領域へ行って…」というのもひとつの専門的な仕事になってきますので、やはり個々人の専門領域がどこにあるか?で変わってくるはずです。
以上、ざっとした説明ですが、重要部分・本質部分は語ることができたのではないかと思います。今後、追加すべきことがあれば、また別の記事で書いていきます。
以下は、話が若干、哲学的になりますが、「マクロ視点での利他」を考えるときに、今後、重要な視点になってくるかと思いますので、興味ある方はぜひお読みください。
「知の弁証法」で仏教とキリスト教・イスラム教を融合する
「天界の上段階は、非常に相対観が強くなる切磋琢磨の世界である」と上述しました。
切磋琢磨の世界であるということは、別の言い方をすると、「差別観・差別知の世界である」ということです。
この場合の、「差別観・差別知」というのは、いわゆる「差別する」といったような悪い意味ではなく、「自分と他者の違いを意識する」といった意味です。
違いを意識するからこそ、そこに学びがある、という側面が出てくるのですね。
ところが、菩薩界に差し掛かるようになると、差別知による学びはもちろんあるのですが、それはそれとして、同時に「平等観・平等知」が強くなってくる傾向が出てくることになります。
このことは、以前、下記の記事で書いたことがありますので、参考になさってください。
*参考記事:平等性智への階梯 – 平等知→差別知→平等性智へ
この記事では、菩薩の智慧の段階を「平等性智(びょうどうしょうち)」という仏教用語で説明しています。
この平等性智の境涯は、「差別知による切磋琢磨・学びを大事にしながら、同時に、生きとし生けるものに仏性・神性の輝きを認めていくことができる智慧の段階」と定義することができると思います。
これはいわば、知の段階論で、
- 天界下段界:平等知
- 天界上段階:差別知
- 菩薩界:平等性智
という順番になっているということです。
ここでも、中道・弁証法的発展ですね。
平等知(テーゼ)⇔ 差別知(アンチテーゼ)
から、
平等性智(ジンテーゼ)
↑
平等知(テーゼ)⇔ 差別知(アンチテーゼ)
という「知の弁証法」を発見することができます。
これは、「理屈のための理屈」ではなくて、実際、きわめて重要な視点です。
つまり、
平等知→差別知→平等性智は、「智慧の深まり」すなわち、「悟りの向上」を示しているわけですが、これは同時に、愛が隣人愛から社会的な愛へと質・量ともに拡大していく姿をも表していることになります。
ゆえに、「知の弁証法」は「仏教的な悟り(智慧)の獲得と、キリスト教・イスラム教的な隣人愛」を弁証法的に総合する理論になりえる、ということも示しています。
*隣人愛と言うとキリスト教的な特権のようですが、イスラム教(イスラーム)においても、「慈悲あまねきアッラーのもと、ウンマ(イスラム共同体)のメンバー同士が慈しみ合う」というのが信仰生活のスタイルですので、この点、本質においては、キリスト教もイスラム教も同じです。
*イスラム教は、「イスラム共同体以外(つまり、異教徒)に対してはテロを行うなど、排他的ではないか?」との意見があるかもしれませんが、教義的・歴史的に見ても、キリスト教よりむしろイスラム教のほうが異教徒に対して寛容です。こうした論点については、別の記事で取り上げるつもりです。
仏界
仏界(ぶっかい)については、私は語るには役不足なのですけれど、「おそらく、こんな感じだろう」と分かる範囲で書いていきますね。
今までのお話でも会社のたとえをよく使ってきましたが、その延長線上で言えば、仏界に住む方々というのは、いわば「地球の取締役」ということになります。
取締役の下に「事業部長」などがいて、これは通常、取締役の意思決定(会社の方針)の具体化、という仕事内容ですよね。
なので、菩薩界の上段階スピリットは、取締役(仏界)の意向を受けて、「具体的に文明をどう進めていくか?」などをいわば、事業部長的に指揮を執っていることになります。
もちろん、イメージ的に、ですね。
具体的に、仏界にはどういう方々がいらっしゃるか?ということについては、色々なスピリチュアル系サイトでも挙げられているようです。
また、神智学のほうでは、(もちろん、十界論とはターム(用語)が違いますが)、神の存在を重層的に説明し、どのような存在があるか、役割意識があるか?などの探求をしています。
ただ、私が考えるに、具体名をいちいち挙げたりすることは不遜な面もあると思いますし、
実際に仏界にいらっしゃる方か、少なくとも菩薩界上段階以上の魂でないと、「誰と誰がいるのか?」ということについては、本当のところは分かりようがないと思うんです。
「仏界に誰がいるのか?」という細々とした議論は、(自分が神々をセレクトしているかのような)趣味的かつ不遜な心境に陥る危険性がありますし、実践的観点からもあまり深入りすべきではないかな、と思っています。
とりあえずは、世界の四大聖人と呼ばれるような方々、「釈尊・孔子・キリスト・ソクラテス」といった文明の源流を作ったような方々ですね、そうした存在が住んでいる世界が仏界であろう、と。
そうした理解でよろしいかと思います。
毘盧遮那仏(びるしゃなぶつ)=天にまします父(エロヒーム)=アッラー
仏界にいらっしゃる存在が文明の源流になっている、ということは、別の側面から言えば、現象界(地上世界)において、さまざまな宗教・思想の対立がありますが、そうした対立は仏界の方々が望んでいることなのか?という論点があります。
この点については、ネオ仏法では、「一即多多即一(いっそくたたそくいつ)」の論理でご説明しております。
つまり、様々な偉大な霊存在がいらっしゃるということ、これはいわば「多神教」ですね。
それから、「アッラー以外に神はなし」といった「一神教」(セム的一神教)という、大きくはこの2つの流れがあります。
「神はひとつなのか?複数いらっしゃるのか?」という問いですね。
あるいは、神はひとつだとしても、宗教によって、「うちの宗派が説いている神こそが本当の唯一神」といったふうに、ここでもまた争いの原因となっております。
ここのところを、思想的・実践論的に解決していくことがむしろ大事なポイントです。
これについては、いくつかの記事で論じてきました。
*参考記事:天上天下唯我独尊の本当の意味 – なぜ七歩歩いたのか?
要は、
「唯一神と呼ばれるエネルギー存在はあるが、地域性や時代性に応じて、様々な、偉大な霊存在として地上に顕現していく」という思想です。
こうした「神は一元に帰す」といった思想はむかしから語られてきたことではありますけどね。
私たちにとって難しいのは、「唯一神がさまざまに顕現する」とか「エネルギー分化していく」、と言われると、どうしても、二次元平面的に想像してしまうところにあります。
つまり、「エネルギー分化」というと、図象的には(頭の中でイラストしてみれば分かりますが)、「元のエネルギーの外側に、分化したエネルギーがある」という図になってしまいますよね。
そうすると、「元はひとつであっても、分かれたあとは別々なんだろう」ということで、やはりこのイメージでは紛争の根本解決にならないんです。
「一即多多即一」というのは、そうではなくて、「唯一神の内部に多神がある」という思想です、かんたんに言えば。
なので、密教の曼荼羅(マンダラ)のように、大日如来の四方に諸如来が配置されている、というのもまだ誤解を生みやすいイメージではあります。
大日如来は、毘盧遮那仏を密教的に解釈した存在です。
たとえば、人間の身体が「唯一神」だと想像してみましょう。この身体ひとつが「大日如来(毘盧遮那仏・びるしゃなぶつ)」です。
そして、身体のなかで、最も重要な器官である「脳」とか「心臓」がいわば、イエス・キリストや(歴史上の)釈尊、孔子、ソクラテスに相当する、というイメージです。
さらに、動脈部分が「菩薩界人」であり…というふうにだんだん細かくなり、最後に、私たちひとりひとりが細胞である、というイメージです。
イラストが得意な方がいらっしゃいましたら、描いていただければありがたいです(笑)。
もちろん、今回のお話は「仏界」についてですので、「多神」と言っても、仏界に存在するところの、より高度なスピリットということになりますけどね。
そして、地球のトップ。代表取締役ですね、
地球的な磁場においての唯一神も、顕現した先の地域性・時代性に応じて様々な名称で呼ばれている、ということです。
少し分かりにくいかもしれませんが、結論を先取りすると、とりあえずは以下のように把握します。
ネオ仏法的な解釈では、
- 仏教:毘盧遮那仏(=久遠実成の仏陀/大日如来)
- キリスト教:天にまします父(ヤハウエ)
- イスラーム:慈悲あまねきアッラー
は同一存在であるということです。
こう考えることで、世界の三大世界宗教は争う必要がなくなる方向へ行きます。
さきほどから、毘盧遮那仏(びるしゃなぶつ)と言っていますが、これは奈良の大仏でもあり、大乗仏教では宇宙の真理そのもの、という存在です。
歴史的釈尊の法身(ほっしん)、つまり本質部分。大宇宙の理法そのもの、ですね。この存在が「地球の代表取締役」である、とネオ仏法では理解しています。

盧遮那仏(東大寺大仏)
毘盧遮那仏は、サンスクリット語では、「ヴァイローチャナ」ですが、実は、このヴァイローチャナは遠く、イランのゾロアスター教のアフラ・マズダー(最高神)に起源があるという説もあります。
そして、このアフラ・マズダーは、ユダヤ教のヤハウエの唯一神化に大きな影響を与えたのではないか?という説もあります。
*ユダヤ民族の神は最初から唯一神ではなく、歴史的にだんだんと形成されていった
この説は、『ユダヤ教の誕生――「一神教」成立の謎』(荒井 章三)で紹介されているのを読みました。
ということは、毘盧遮那仏=ヤハウエという等式も学問的にも整合性がとれる可能性があるということですね。
そして、イスラームの唯一神アッラーは、「アブラハムの神」そのものですから、以上を総合すると、
毘盧遮那仏=ヤハウエ=アッラー
ということになります。
もっとも、ユダヤ教- キリスト教の流れにある「ヤハウエ」については、民族神と普遍神の混同があると私は考えています。
ひらたく言えば、ユダヤ教的なヤハウエ=妬む神(民族神)とイエスが信じた愛の神(普遍神)は別存在であろうと推測しています。
ユダヤ民族という一民族だけを選民し、「カナンの先住民は滅ぼして良い」という神はやはり民族神でしょう。
この「民族神と普遍神の混同」が近世以降、キリスト教国の植民地支配・帝国主義の正当化につながっていると思います。
植民地どころか、インカ帝国を始め、「まるごと滅ぼされた文明」がいつくかありますよね。
こうした植民地支配・帝国主義の背景にある思想は、「異民族は殲滅しても構わない」という民族神的な発想から来ていると思います。
なので、ネオ仏法では、「キリスト教はユダヤ教との接続を解除したほうが良い」という主張をしています。
*もっとも、旧約聖書に流れている預言者たちの思想がすべて民族神由来だとは思っておりません。
そういう意味では、現在、ユダヤ教の「モーセ五書」成立史には、J資料(ヤハウエ資料)、E資料(エロヒーム)、他2つがあるとされておりまして。
2番めの、「エロヒーム」というのが、この神様はもともと、固有名詞ではなく、文字通り、大文字のGODという意味で使われていたらしいので、
ヤハウエよりもエロヒームという呼称の方が、ネオ仏法的には正統キリスト教の天の父にふさわしい、と言えるかもしれません。
そうすると、
毘盧遮那仏=エロヒーム=アッラー
という等式になります。
仏界における存在形態
私たちの本質は、「手があって足があって…」という肉体的なものではなく、「アイデンティティのあるエネルギー存在である」というふうにご説明しております。
ここで、「エネルギーとはそもそも何であるか」ということを考えてみます。
*物理学的に、ではないですが。
たとえば、菩薩界の条件である「利他(社会性をもった利他)」を考えてみましょう。
利他というのは、まずは順序として、「私という存在があり、その私が他者へ慈悲の実践をする」ということになりますよね。
前提として、「私という本体があって、利他という作用がある」という理解の仕方をしています。
- 本体:私
- 作用:利他
という図式ですね。
ところが、エネルギーというものはその本質において、絶えず作用を及ぼすものであるはずです。
ということは、
「エネルギー存在としての私」と「利他という仕事」という2つは本来的に区別されるものなのだろうか?
ということに思い至ります。
たとえば、私たち凡人であっても、(地上の)仕事に夢中になっていたり、あるいはゲームでも良いんですけどね。
そうしたときは、「私」が「仕事を(ゲームを)している」という二分化した意識ではなく、文字通り、没入していると言いますか、一体化している感覚を味わうときがありますよね。
これはなんとなく体感的にお分かりかと思います。
ただ、物体的な認識では、「私」という確固たる存在があり、それが「時々、仕事をしている」というふうになります。
この認識の仕方は、実在界に還ってから。天界上段階でも、あるいは菩薩界下段階でもそういう認識の仕方をしていると思います。
ところが、先に述べたように、
「エネルギーというものは、そもそも作用そのものではないか?作用しなければエネルギーであるとは言えないのでは?」という認識においては、「私と仕事」が一体化していくことになります。
- 本体:私
- 作用:仕事(利他)
ではなくって、
「本体即作用 作用即本体」の悟りです。
哲学的に表現すれば、こういうふうになるのですが、
実態論としてはどうかというと、
菩薩界上段階〜仏界 の世界では、人(スピリット)はエネルギー作用そのものとして存在している、ということです。
そして、そのような存在形態だからこそ、エネルギー分化も可能である、と。
たとえば、千手観音という仏像がありますね。
千手観音の姿は、本体はひとつでありながら同時に千の作用をしている、という「本体即作用 作用即本体」を象徴しているのだと思います。

法性寺 千手観音像
ここでも平たく申し上げますと、
たとえば、イエス・キリストがひとつしか身体(霊体)がないのであれば、世界中のキリスト教徒20億人が祈っても、たった一人のところにしか行けない、ということになってしまいます。
そうではなくて、イエス・キリストのエネルギーは”作用として”いくらでも分化して、祈る人の傍に赴くことができる、ということです。
したがって、
心の清い人たちは、さいわいである、彼らは神をみるであろう
(マタイ伝5章)
というのは、文学的・詩的なたとえではなくて、エネルギー論として真実である、ということです。
しかし、このように考えてみると、気軽に「仏陀になりたい」「メシアになりたい」とはなかなか思うことは難しいということが分かってきますね。
だって、
「一瞬一秒休むことなく、作用として存在し続ける」ということが想像できますか?あるいは、そうなりたいですか?
やっぱ、「土日は休みたい」とか、「仕事で疲れたので、ちょっとテレビでも」とか。
地上でもそうですが、実在界に還っても、やはりこのくらいが人間心でありますよね。
ただやはり、菩薩界に近づいていくと、「利他は正しいことだからそうするんだ」という気持ちではなく。「利他が幸せなので、欲求に従っているとどうしても利他になってしまう」という気持ちですね。
これは、
心の欲する所に従えども矩(のり)を踰(こ)えず
「論語」
という孔子70歳の心境そのものです。
自分の欲求はイコール、矩=法そのものに適っている、という心境です。
そうすると、菩薩界をずっと上がってくるにつれて、利他(=作用)が自然な状態になっていくのだと思います。
そうして、仏界では、作用そのものになってしまう。絶えず活動している利他エネルギーそのもので、もはや、人間ではない、ということです。
ただやはり、この境地に至るためには気の遠くなるほどの魂修行が必要だろうとは思います。
そういうわけで、焦らず、仏陀への道を、風景を楽しみながら歩んでいきましょう、ということが結論ということになるかと思います。



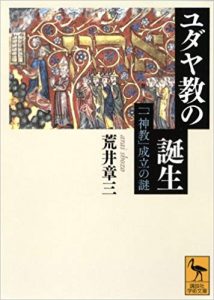





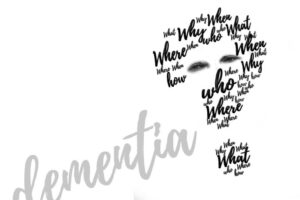


コメント
コメント一覧 (10件)
>ishigaki様
お読み頂き、また、コメントまでありがとうございます♪
>釈尊(他の聖人3人)も、キリスト(イエス)も同じ立ち位置に居るとの理解で良いのですね?
はい、私の理解の範囲内ではありますが、世界の四大聖人は仏界の住人であると把握しています。
>それはイエスは神ではなく人(被造物)として捉えているのでしょうか?
分かりやすく、<神 – 人>の二元論で説かれることもありますが、本当は、神(真理)は全体の生命エネルギーであり、
自己の内部にエネルギー分化を繰り返して、様々な現象を生み出していく、と捉えています。
*自己の外部に創造したとすると、「神以外の領域がある」ことになり、神の全能性が損なわれます
神のエネルギー分化ということは、
・あくまで神のエネルギーの分化であるという意味では、あらゆる現象(人も含めて)も神の一部であると言えます。
・あくまで、現象側から神を対象として眺めると、<神 ー被造物>であるというふうにも言えます。
つまり、視点の違いに過ぎないということですね。
とはいえ、現象にもどれだけ実在性があるか?という段階論も真理です。
ひらたく申し上げれば、イエスや釈尊のように、唯一神(大日如来)が、人々に把握できるような存在(ペルソナ)として、メシア・仏陀になって顕現しているパターンがあるということです。
これがキリスト教の論理では、「三位一体」となり、仏教の論理では、「法身(究極の仏陀)が方便として(報身として)歴史的釈尊として顕現している」と表現します。
ペルソナ(仮面/位格)として現れないと、私たち人間には絶対神を把握することが不可能になってしまうからです。
したがって、イエスも釈尊も、
ペルソナ(位格)として現れているという意味では、究極の絶対神とは違う、ということもできます。
これが「仏界に住んでいるイエス」という把握です。
一方、「究極の絶対神が方便(ペルソナ)として現れているだけなのだ、もとは同じエネルギーなのだ」という意味では、
神と一体である、神そのものである、と表現することも可能です。
これが「イエスは神である」という把握です。
要は、真理をどこの視点、断面から眺めるのか、という違いに過ぎない、ということですね。
初めまして。
友達に、このブログを勧められて読んでいます。
いくつか質問したいのですが文章が長く、数が多くなってしまうので一、二点聞かせて貰いたいと思います。
>世界の四大聖人と呼ばれるような方々、「釈尊・孔子・キリスト・ソクラテス」といった文明の源流を作ったような方々ですね、そうした存在が住んでいる世界が仏界
↑釈尊(他の聖人3人)も、キリスト(イエス)も同じ立ち位置に居るとの理解で良いのですね?
それはイエスは神ではなく人(被造物)として捉えているのでしょうか?
↑すると、キリスト教で信じる「イエスは神である」と言う事は、神ではなく「仏界に住んでる人イエス」と言う事ですか。
やる気ではなくて探究心がベースであるなら、強いですよ。
声聞って、定義を聞くと、「やってできないことはなさそうだな、いや、できそう」と思うんですけど、
100人決意して、数人でも声聞界に還ることができるかどうか…の割合だと思います。
それは結局、「一生を通じた平均打率」を求められますので、
継続がいちばん難しいっていうことですね。
継続のために一番資するのがやっぱり「習慣」です。
葉を磨くように、
「それをやっていないと(思っていないと)、なんだか気持ちわるい」
くらいの感覚まで持っていければ、勝ちは見えたって感じですね。
返信ありがとうございます♪
早く到達したいというより無知の知の自覚的な意味合い?になるかもしれません。
私の場合、感化された一時的なやる気ではなく興味と探求心がベースにあるので
習慣化するという概念がありませんでした(笑)
意図的に習慣化する視点も考えてみたいと思います。
いえいえ、そんなに遠くないですよ。
>知識がなさすぎて先が遠いです(笑)
早く到達しようとするより、「鈍くさく、たんたんと続けていく、習慣化していく」ことが大事です。
なぜなら、たいていの人は一時期やる気を出しても、次第に日常性に流されてしまうからです。
習慣化さえできれば、アベレージ声聞(これ、良い言葉ですね・笑)は難しくありません。
頑張っていきましょう!
参考記事ありがとうございます。
意味合いが違いましたね。
知識がなさすぎて先が遠いです(笑)
弁証法の総合については、分離したものを再び融合させる(溶け込んでしまうイメージ?)、というよりも、
分離は分離のままで保存しつつ、より高次な次元で総合させる、ということなんです。
*参考記事:ヘーゲルの弁証法を中学生にもわかるように説明したい
https://neo-buddhism.com/hegel-dialectic/
キリスト教、仏教、イスラム教、あるいはそれぞれのなかの各宗派は、あくまで個性を保ちつつ、
存続していく。しかし、弁証法の総合によって、「互いがより高次の立場からは喧嘩する必要がなくなる」という状態です。
>まずは菩薩界を視野に入れながらアベレージ声聞界を体現していこうと思います
すばらしいです!そのように思っていただける方がひとりでも増えるように、
私もこれからも頑張っていきますね(^^)
「知の弁証法」で仏教とキリスト教・イスラム教を融合するについて
ネオ仏法でいうところの呪術スピリチュアル?界隈のある方が
「本来の光から分離した光と闇を統合して本来の光に還っていく必要がある」
とおっしゃっていたのが自分の中で感覚的にリンクしました。
これに包含されるお話しかもしれないなと。
私のような知識のない感覚派の人間には呪術スピリチュアルは
取っつきやすくて入門的にはいいツールだと思ってます。
パズルでいうと四隅のピースのような(笑)
ただ取っつきやすい分何を選び取り入れるかは知識がない分
難しいのですが、そこは呪術スピリチュアル的に言うワクワク、
惹かれる、興味がわくみたいな直観に頼るところなのかなぁと
思いました。実際私がそうです(笑)
呪術スピリチュアルでも真理をおぼろげながら理解できてくるのですが
取っつきやすい分(ふわっとしているところが多い分)真理に迫るに
つれてモヤモヤや消化不良を起こしてきます。
(なかなかハマるピースが見つからない)
私はそのタイミングでネオ仏法的般若心経解説を拝見してスッキリして
仏教ってすげー!と感心しているところです。
個人的には神道が好きですが経典がないので一人であれこれ考えていると
やはり壁にぶち当たりモヤモヤしてきます(笑)
結局何が言いたいのか。。乱文で失礼しました。
感覚派はアウトプットが苦手なので。。
まずは菩薩界を視野に入れながらアベレージ声聞界を体現していこうと思います(笑)
コメントありがとうございます。
末法でも、鎌倉時代では、戦乱の中、民衆の教育レベルも低く、難しい教学を学ぶことができないので、
ある意味、緊急避難的に、「信心で解脱する」ということをオススメしていたと思うんですね。
そうすると、「成仏」というのが、どの程度の成仏か?ということになるのですが、
信心による解脱では、十界論でいう、「人界」のあたり、上の方でも「天界」のあたりを
目標にしているかなあと思います。最低限、地獄へ行かない、天国部分へ行く、ということですね。
法華経でいう一仏乗が真理か?あるいは、「声聞乗・縁覚乗・菩薩乗」の三仏乗が真理か?
というのは、日蓮上人以前に、最澄と(法相宗の)徳一がずいぶん論争しています。
が、厳密な意味での、成仏→仏界の悟りを得る、というのは、やはりお題目とか
信心による解脱だけでは無理で、三仏乗の修行の段階論のほうが真理だと思っています。
初めまして。興味深く拝見させて頂いております。
末法では、日蓮大聖人が説いた南無妙法蓮華経のみが仏の境界につながる修行で、他の方法では返って毒になるという日蓮大聖人の教えについては、どう思われますか?
仏界より上の次元に、この世界の衆生も修行なしに行けるのでしょうか?