「存在と時間」と言いますと、20世紀最大の哲学者と呼ばれているハイデガーの『存在と時間』を思い出しますよね。
今回は深入りしませんが、ハイデガーの『存在と時間』は非常に仏教思想に通じるところがあると思っております。
ハイデガーは同著で「存在の意味を問う」という意義を明らかにしていきましたが、「存在」というのは仏教用語で言えば、「ダルマ」ということになります。
「ダルマ(dharma)」は原義では「保つもの」という意味であり、そこから大きくは、
- 存在
- 教え
という意味で使われるようになりました。
そして、実は今回のテーマである「縁起の理」もしくは単純に「縁起」ですね、これはまさしく、仏教の存在論、教えの両面における中核と言っても過言ではありません。
つまり、縁起の理とは「ダルマ」そのものであると言ってよいのです。
ということは、「縁起の理とはなにか?」と問うことは「存在とはなにか?」と問うこととほぼ同義なのですね。
ネオ仏法では、今まで、縁起の理=原因結果の法則、と、とりあえずご説明してきました。
その理解のほうが分かりやすいから、というのが理由ですが、今回は仏教思想における”縁起の理”について、もっと深く考察していこうと思います。
縁起の理を”存在と時間”に分けて考える
結論から申し上げておきますと、縁起の理は下記の通り、存在という観点、時間という観点の2通りに分類することができると思っています。
縁起の理を理解する順序としては、「存在と時間」よりは「時間と存在」の順序のほうが分かりやすいので、以下、それぞれを”時間論的縁起”と”存在論的縁起”に分類して定義しておきますね。
- 時間論的縁起…原因・結果の法則
- 存在論的縁起…依他起性(えたきしょう)
依他起性というのは、ちょっとむずかしい言葉ですが、これは要するに、存在は相互依存にて在ることができる性質を持つ、という意味です。
さて、では、それぞれを考察してみましょう。
1. 時間論的縁起
”時間論的縁起”は今までご説明してきた縁起ですね。物事には原因があって結果があるという法則です。
いわゆる、原因結果の法則です。これは、今までご説明してきた、簡略化した”縁起の理”の理解の仕方でもあります。
ところで、”縁起”は、より具体的には、因縁生起(いんねんしょうき・いんねんせいき)という言い方がされることもあります。
これは、原因を直接原因=【因】と間接原因=【縁】に分けて考えているわけです。
たとえば、花が咲くには、
- 種を蒔く【因】
- 水・養分・太陽【縁】
- 花が咲く【生起】
といった順序になりますね。

すなわち、【因】と【生起】を媒介するのが【縁】ということになります。【生起】のところを【果】と言うこともありまして、
3. の「花が咲く」というのは、私たち観察者が得られるところの果実・報いでもありますので、流れとしては、因⇢縁⇢果⇢報となり、つなげて、因縁果報と表現したりします。
ここから、縁起の理を”因果の理法”と言うときもあるのです。
いずれにしても、過去→現在→未来の時間軸の流れのなかで、物事が原因と結果の連鎖にしたがって生起していくこと。これが”時間論的縁起”ということになります。
さらに言うならば、”時間論的縁起”は智慧に繋がってくるということも敷衍して考えることができます。
時間を、過去・現在・未来に分けてそれぞれ考えてみましょう。
過去→現在
現在の自らの(あるいは他人・社会・国家でも)状態を作り出しているものとして、過去に【因】と【縁】がある、と考えます。
そうした原因・結果のリンクを塾考していくと智慧が得られるわけですね。これは八正道の内省や十二因縁でも使われている縁起の理です。
現在→未来
これは、現在に良き【因】を蒔いておけば、未来に良き【果】を生むというふうな自己実現理論にも使えますね。
実際に聖書の「蒔いた種は刈り取らねばならぬ」という言葉から、プロテスタンティズム以後、アメリカにてニューソートやクリスチャンサイエンスの運動が起きております。
そうした運動の結実が、たとえば、ナポレオン・ヒルの『思考は現実化する』といった書物に繋がっているわけです。
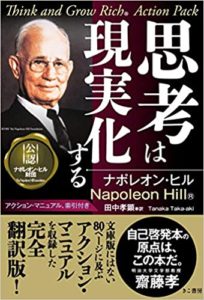
つまり、米国流の自己実現理論も、仏法の広大な理論体系の一部に収まってしまうというわけです。
過去⇢現在、現在⇢未来、のいずれにおいても、原因と結果の連鎖を観察することによって、智慧を獲得することができますよね。
ゆえに、時間論的縁起は智慧の思想につながっていくというわけです。
「知は力なり」というフランシス・ベーコンの言葉がありますが、智慧は自己確立に必須の要素であるというだけでなく、下記の慈悲の発揮におけるベースになっているパワーでもあります。
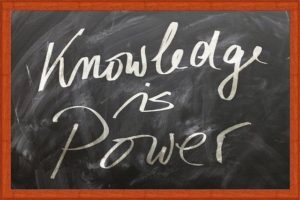
2. 存在論的縁起
2.の「存在における縁起」は依他起生(えたきしょう)、すなわち、あらゆる存在は互いに依存(いそん)して仮に存在しているという考え方です。
たとえば、今あなたが存在していられるのも、空気(酸素)があるからです。
そしてその酸素はまた植物の炭酸同化作用によって生み出されています。さらに、その植物は水や太陽を縁として炭酸同化作用を起こしていますね。
このように、あらゆる存在はそれ自体では存在できず、相依って、依存し合いながら”在る”ことが許されている。
こうした相互依存の状態は、愛にとても似ています。仏教的に言えば、慈悲ですね。
ゆえに、”存在論的縁起”は慈悲の思想に繋がっていくことになります。
ここまでの論点をまとめますと、
- 時間における縁起の理=時間論的縁起:原因結果の法則→智慧の獲得(知)
- 存在における縁起の理=存在論的縁起:依他起生→慈悲の発揮(愛)
ということになります。
智慧の獲得と慈悲の発揮は、宇宙の二大原理であるとともに、私たちの人生の意味とミッションにも当てはまるとネオ仏法では考えております。
*参考記事:人生の意味とミッションとは? – 最勝の成功理論を明かします
三法印と縁起の理
そして、ここで、仏教の教えの旗印であるところの三法印(さんぽういん)に従って、さらにまとめてみましょう。
三法印とは、
- 諸行無常(しょぎょうむじょう)
- 諸法無我(しょほうむが)
- 涅槃寂静(ねはんじゃくじょう)
の3つでした。
諸行無常(しょぎょうむじょう)は、「一切の物事は変転・変化していく」、という時間論のことですよね。
そして、「諸法無我(しょほうむが)」は、上述の依他起性で述べたように、「一切の物事はそれ自体では在ることができず、相依って仮に在ることができる」という存在論のことです。
ということは、今回の学びをまとめてみると結局、
- 諸行無常:時間論的縁起→智慧の獲得へ
- 諸法無我:存在論的縁起→慈悲の発揮へ
ということになりますよね。
さらに、三法印の最後には、涅槃寂静があります。
これは私たち一人ひとりの”実存”に、なにゆえに智慧の獲得と慈悲の発揮が要請されているか?ということに関わってきます。
智慧の獲得と慈悲の発揮というのは、言葉で言えば易しいかもしれませんが、実際にこの世において実践していくのはとても労力の要ることではあります。
それでも、何度でも生死を繰り返し、輪廻の過程にある理由は、やはり、私たち一人ひとりも、”智慧の獲得と慈悲の発揮”を根本的に求めている、ということであると思うのですね。
つまり、これは真実の意味での幸福論なのです。
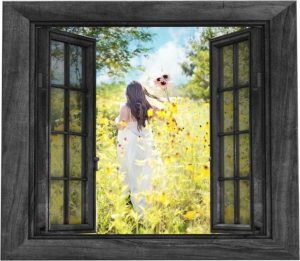
私たちひとりひとりの実存は最終的には、やはり幸福であることを欲しているだけではなく、かつ、宇宙の二大原理からも要請されてもいるのだ、というのは大きな福音だと思いませんか?
ただし、人間は現象界に生きていると、どうしてもその幸福の内実・内容を見失いがちです。肉体的な自我意識の影響で、上で述べたような諸行無常・諸法無我を忘れ去ってしまいます。
ゆえに、その大切な内実をキチッと意識して生きること。
つまり、「智慧の獲得と慈悲の発揮」を内実とするところの幸福論こそが、じつは”涅槃寂静”ということになります。
死んでから涅槃があるというよりも(それも涅槃論の一部ではありますが)、智慧の縦軸と慈悲の横軸が交差する”今ここ”に幸福論を求めるのが涅槃寂静です。
一般的な仏教の涅槃解釈とだいぶ違っていますが、やはり、従来のような「輪廻からの解脱(げだつ)が涅槃である」という解釈では、あまりにも後ろ向きだと思います。
そうではなくて、むしろ、輪廻の意義を読み込んで、積極的に活用していく”涅槃”解釈であるべきだと思います。
そして、この涅槃解釈がネオ仏法がいわゆる狭義の「仏教」を乗り越えていく契機になると思っています。
*参考記事:上座仏教(小乗仏教)と大乗仏教の違い・対立を乗り越えるネオ仏法
従来の仏教学における”涅槃論(解脱論)”に対する反駁として、いくつかの記事を書いておりますが、とりあえず下記の記事をご参照ください。
*参考記事:涅槃の解釈に誤りがある– テーラワーダ仏教批判④
以上、縁起の理を「存在と時間」に分けて哲学的に考察してまいりました。
仏教は非常に哲学的な宗教であると言われておりますが、”哲学的”というよりも、むしろあらゆる哲学の源流に位置しているのが仏教なのです。



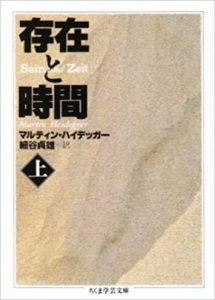





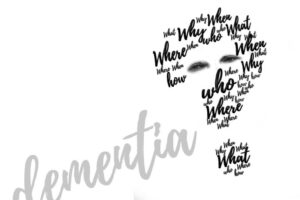


コメント