最近、親類で法事があり、お葬式について改めて考えるところがありましたので、今回は、「戒名・葬式・読経」をテーマに書いてみますね。
関連する話題として、「仏壇・お墓」については別記事で書いていますので、参考になさってください。
*参考記事:お墓・仏壇にはスピリチュアル的に意味があるのか?
【戒名】戒名は馬鹿らしいので、必要ないか?
何十万あるいは何百万円もの高額なお金を払って、戒名を授かる価値があるのか?現代では、私たち一般人も疑問に持ち始めています。
それで、「戒名なんて馬鹿らしいのでは?意味ないのでは?」とか「自分で戒名を付けても良いのでは?」などといった疑問が当然、出てきます。
そこで、ここでは戒名の成り立ち・起源を探りつつ、現代では戒名はどの程度有効なのか?を考えてみたいと思います。
戒名の構成は?
戒名については、宗派によって違いますが、基本は「院号+道号+戒名+位号」という構成になっています。
そして、戒名のランクというのは、「どれだけ仏法流布にお布施して貢献したか?」の目印になっています。
- 院号:寺院を一つ建てるくらいの貢献した場合に付けられる
- 道号:通称名
- 戒名:僧名
- 位号:通常は、「信士/信女」。お布施額が大きいと「居士(こじ)」「大姉(だいし)」となる
なので、「〇〇院」といった院号をつけると、戒名のお布施額が急に上がるのですね。

「お布施の金額によって戒名がランク付けされるのはけしからん!」となりそうですが、もともと、”檀家”という言葉は、サンスクリット語の”ダーナ”から来ていまして、「施す、与える」という意味なのですね。
現代の女性に言うと叱られそうですが、”旦那”も同じ語源です。ご主人が「施す人」という位置づけからそう呼ぶようになりました。
なので、「私は施しを受けてるわけでない!」と主張したい方は”旦那”と呼ぶのはやめましょう(やめなくてもいいですが)。
ちなみに、戒名(法名)を頂いたからと言って、俗名(本名)を捨てるというわけでもないのですけどね。ただ、戒名の由来も意味も知らなければ、当然、霊界において戒名を名乗るわけもありません。
*浄土真宗では”法名”、日蓮宗では”法号”と言います。
戒名の由来と現代的な意義
ただやはり、生きている時に戒名がピンとこないようなら、やはり、死んでも(くどいようですが、肉体の死、です)やっぱりピンとこないのは当然です。
戒名とはもともと、出家するときに”受戒”と言いまして、戒を授かるわけですね。その際にいただく法名のことです。
「戒を守ると霊的パワーが身につく」と考えられていましたので、むかしは病気のときに受戒して「病気を治そう」という動機もあったようです。
それが次第に、「臨終にあたって来世の幸福・安寧を願う」という方向へ転換していきました。いわゆる、臨終受戒です。これが現在の、”戒名”の流れへ連なっています。
*参考書籍:『浄土思想論』(末木文美士著)
ただ”「戒によって霊的パワーがつく」というのは、「自主的に戒を守っている」というのが実は前提なのです。
私たちの日常でも、ストイックに真面目に生きている人、というのは、スキがないと言いますか、どこか悪人も近寄りがたい雰囲気を発しています。
これが戒を守ることによって得られる力で、仏教用語では、”戒体(かいたい)”と言います。
しかし現在では、単なる習俗としての戒名ですので、ここのところ、まったく意味をなさなくなっているのはお分かりですよね。
俗人ではなく、「出家の僧侶」としてあの世に送り出す、というのが戒名の趣旨ですが、戒名をつけられるご本人もそのような趣旨をまったく理解・承諾しているわけではないので、”戒体”の効果はやはり、「ない」と言って良いのです。
同様に、「戒名を自分で付ける」というのも、上述の趣旨を理解した上でないと意味がないのは当然のことです。
ちなみに、”位牌”も本来、仏教とは関係ありません。中国の禅宗が道教や儒教の影響を受けて作ったもので、それが日本に伝わってきているのですね。
【葬式】原始仏教は葬式には関わっていない?
お葬式というと、一般的には仏式というパターンが多いかと思いますが、実際は、釈尊の時代は葬儀も含めて、祭事にはほとんど関わっていませんでした。
これは、釈尊以前のバラモン教(今のヒンズー教のベースになっている宗教)が、「天界へ生まれるためには祭事が大事」という教えを説いていたのですが、
それに対するアンチテーゼとして、釈尊は、「天界へ生まれるのは儀式によるのではなく、思いと行為による」という考えを打ち出していったわけです。
仏教用語で言えば、「施論・戒論・生天論(せろん・かいろん・しょうてんろん)」ということになります。
ざっくり申し上げると、
- 施論=良いことをして
- 戒論:悪いことをしなければ、
- 生天論:天界へ生まれることができる
というシンプルな説法です。
そういうわけで、釈尊の時代においては、やはり、個の自立ですね。外部からのスピリチュアルパワーによって、一気に!というのではなく、
自立→自律と言ってもいいですが、やはり他力と言うよりは、自己責任論を中心に説いていたのは間違いがないです。
ただ、祭事に関わらない、というのは、一方では、バラモン(伝統宗教)の祭官の人たちの職業まで奪ってはいけない、という釈尊特有の慈悲の配慮が働いていた側面もあるでしょう。

まあ、こういうことは、仏教を勉強している方であれば、常識的に知っていることではありますし、
また、仏教界からも、「今の葬式仏教はいかがなものか?堕落ではないのか?」といった真摯な問いも出ていますので、あまり私が言う必要もないかもしれません。
ただし、
- 小乗涅槃経では、釈尊は自らの葬儀方法を事細かに指定している
- 初期仏教以降は、仏教は葬儀・お墓の管理にも伝統的に関わってきた
という論点は別途あるのですが、
1.については、侍者の阿難(あなん)の問いに答えているだけであり、また、実際にそこまで細かく指示していたかどうか?は疑問です。おそらく、後世の付加があるものだと思われます。
そもそも、釈尊の教団は在家者の葬儀に関わることはできませんでした。
仏教教団は、「カースト制度」を真っ向から否定(あるいは無視)しておりますが、葬儀に関わってしまうと、必然的に、カートスト的なものに関わらざるを得ない、というのが理由です。
2. については、たしかにそういう面もあるのですが、
葬儀ができることと、実際に死者に引導を渡せること、はまったく別問題です。また、葬儀自体が本職のメインであったわけではありませんからね。
【読経】釈尊は漢文(中国語)で説法していたわけではない
まあ方言というとあれですけど、インドは今も昔もとても広いので、都市部であっても、地域によってずいぶん言葉が違っていたのは事実です。今でもインドは公用語がたくさんありますよね。
原始仏教そのものは、ガンジス川流域の(当時の)強国の地域でおもに活動していましたので、仏教というのは実際は、当時の都会型宗教、先進宗教として登場したわけです。
先にでたバラモン教などは、当時の雅語(がご)、雅(みや)びな言葉ですね、サンスクリット語を使っていまして、
釈尊の弟子のなかにも、「こんなに素晴らしい教えなのだから、ぜひサンスクリット語でまとめましょう」という人たちもいたのですが、釈尊はそれについては、叱責レベルで退けています。
「真理はその地域地域の言葉で語られるべきである」という考えです。
要は、「わかりやすく、実践的なものでなければならない」「権威主義に陥ってはならない」ということですよね。
そういう意味では、「大乗仏教はサンスクリット語を言語にしているじゃないか」という反論もあるのですが、まあ、サンスクリット語がわるい、という極論でもないわけで。
紀元前後にはやはり、書写にふさわしい言葉で書いたほうが広がりが出る、という(良い意味での)マーケティング志向があったのです。

まあそれでもやはり、現代日本の読経ですね、これは中国語を呉音(ごおん)で発音しているわけですが、
釈尊は当然に、中国語で説法しているわけはないですし、「現地の言葉で真理は伝えられるべき」という原則でいえば、「なんで、日本語でお経=教えを読み上げないの?」という疑問は当然、出てきます。
そして、その疑問はかなりの部分、正当性があります。
やっぱり、「死」ですね、これはつまり肉体の死ですが、「魂が本体である」という原則からいうと、「死んでも実は死んでいない」わけでして、
いわば、潜水服を脱いで陸地に上がっていったようなものです。
そして、親族は、潜水服を眺めて悲嘆にくれているわけですが、本体のほうはちゃんと生きている、という構造になっています。

なので、原則的には、本体(=魂)は肉体という服を脱いだだけですので、服(=肉体)を着ている時に分からなかったお経が、服を脱いだからと言ってわかるか?というと難しい部分はありますね。
そういう意味では、本当に中国語で読経する必要はまったくなくて、亡くなった方のためにも、参列している方のためにも、きちんとわかりやすい日本語で説法したほうがベターなのは確かです。
まあそうすると、「ありがたみがなくなる」感じがしそうですが、これは要は、お坊さんの説法に内容があるかどうか、感動させる力があるかどうか、ということですよね。
【焼き場】お墓よりも焼き場のほうが不成仏霊が多い
これはちょっとびっくりというか、今まで考えたことも意識したこともなかったのですけど。
お墓はまあたしかに、この世とあの世の接点のようなところがありますしね、
また、「死んだらお墓に入るんだろう」と思っている人がまだけっこういますので。
いわゆる、”思い=存在”の図式で言うと、お墓が住処と思っている人はやっぱりお墓に居たりするわけです。
ただ、お墓にいるのは凶悪な悪霊というほどではなく、いわば、ぼんやりと、「ここにいるべきなのかな」とか「子孫がくるかな」という感じで、わりとのんびりした感じではありますね。
一方、火葬場というのは、ほんとに死んでから(肉体の死、です…)まもなくですからね、文字通り生々しいというか、
また、最近は、「通夜も何も省いて焼いちゃえ」という人も多いですので、ほんとに死んで間もなくですか、いわゆる、「直葬」というのが増えてきたようですね。
直葬はですね、以前書いたこともあったかと思いますが、まず、肉体の死後、24時間以内に焼くのは止めたほうがいいです。
肉体の死を迎えても、スムーズに肉体から抜け出していくような魂は、よほど優秀か、よほど一直線に地獄行きか、どちらかですので、
ほとんどのケースでは、もとの肉体に戻ったり、うろうろしている状態です。
また、病気の延長で死を迎えることになるケースが多いと思いますけど、そうした状態から、ささっと、「魂としての自覚」を持てるひとはやはり少ないんですね。
はっきり言うと、「まだ自分は死んでいない」と思っている人がほとんどなんです。
なのに、火葬場に直行されたりすると、怒り狂うわけですよ。あるいは、混乱の極み。それが火葬場の不成仏霊のイチパターンです。
しかしこれはまだ良い方で。
もっとひどいのは、肉体から抜け出しきれないままに焼かれちゃうことですね。
今まで、便宜的に、「魂と肉体」と書いてきたところもあり、それはもちろん事実なのですが、実際は、魂というのも幾重(いくえ)もの霊的な衣をまとっているのが真相で。
肉体の死を迎えた直後では、まだ、人間のかたちをとり、また、肉体の各器官を模した(というより、原型なのですが)部位が霊体にあり、痛みも感じてしまうんです。
なので、「通夜を行う」というのは、やはりそれなりの知恵というか、経験知ですね、「どうも、死後すぐに焼くのは良くない」という経験知が働いているんです。
もっとも、直葬と言っても、「火葬場の予約が翌々日以降で…」ということもありますので、とりあえずは24時間はおいて、
その間に、地上からも天界からも助け舟を出して、引き上げていくということですね、そういう時間稼ぎが必要です。
そして、その「地上からの助け舟」が本来はお坊さんの役目なんですけど、実際は、役に立っていないケースが多い、ということになります。
それは、現代のお坊さん御本人の悟りが浅い…というレベルならまだしも、そもそも、あの世も魂も信じていないお坊さんがけっこういるから、なのですけどね。
実際は、お経を中国語で読んでも、読む人が内容を理解して、かつしっかり届けようという念を込めれば伝わっていくものなのです。さっきと言っていることが違うようですけどね。
言葉は”念い”が現象化したものなので、念のほうがしっかりしていれば、それは(少なくとも霊界においては)ストレートに伝わっていくんです。
これね、むかし悪霊払いになるかな?って、例の般若心経を読み上げたことがあるんですけどね、私が。
そのときは、まったく効きませんでした。あちらさんに笑われるレベルだったかもしれません(エクソシスト系の映画でよくそういう場面ありますよね)。
それは、要は当時の私が、「意味は分からないけど、有名なお経だから」で読んでるので効かないわけでして、
今の私が読むと、これはやっぱり効くんです。
…というか、冒頭の、「観自在菩薩 行深…」あたりでもう効きます。「おいおい、まだ読んでないというか、これからがいいとこなんだけど?」ってあたりで。
これは、やはり念の問題ですね。
結局、戒名・葬式・読経は馬鹿らしいのか?意味あるのか?
それでは、「戒名・葬式・読経」は馬鹿らしいと片付けていいのか?
実際は、実感としては、「戒名・葬式・読経にはやっぱり意味がある」というのが現場の感覚です。
というのも、
「亡くなった方が、意味があると思っているから」です。先に述べた、思い=存在の図式ですね。

認識が世界を作っている!
なので、逆に言えば、ハッキリと真理を悟っている人にとっては、まあやはりほとんど意味はないですね。
むしろ、そこにいる坊さんに説法したいくらい、こちらがお布施を頂きたいくらいです(まあ冗談ですが)。
やはり、「なんで、告別式をやってくれないのか」「戒名はどうなっとる!?」などとひっかかりを持つ死者もいますので、そうであるならば、世間的に常識的なことはひと通りやることによって気を悪くしないでいただくと。
その上で、「実は本当の仏法はですね…」という流れのほうが話がスムースにいくことになります。
それから、「時間稼ぎ」的な意味もあり、
実際に葬儀が執り行われて、いくたりかの縁のある人が悲しんでいる様子、自分の写真がなぜか黒い枠で飾られている様子、
お坊さんが読経をあげている様子…などを見て、「あ、自分は死んだのかな」と悟り始める人も多いわけですね。
【法事で避けるべきこと】 ”24時間以内の直葬”と”臓器提供”は避けるべし
まあ最後にここですね、この「24時間以内の直葬」と「臓器移植」。このふたつだけは避けましょう。
直葬については上述しましたが、臓器提供についてもほぼ同じ論拠です。
脳死の段階ではまだ死んでいません。痛みを感じています。なので、その段階で臓器を摘出されるというのは、生身にメスを入れられるのとまったく同じことになります。
それを知った上で、なお「提供したい」というのなら、まだ良いですけどね。
以上、お葬式関係のことは今まで書いたことなかったかな?ということで。
また、私の親類がきっかけのことでありますので、その人にとっても記事を書くことによって、功徳を積む機会になるだろうと、書いてみました。
参考になれば幸いです。



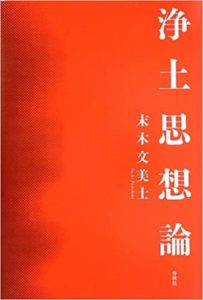





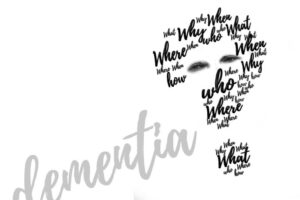


コメント
コメント一覧 (4件)
>mika様
コメントありがとうございます^^
俯瞰的に、実在界(あの世)的価値観から現象界(この世)を見直してみると、まったく違った風景が見えてきますね。
神道の場合、判断が難しいところがあるんですよ。
つまり、生きているときに「この人はすごい人だ!神のようだ!」ということで、死後、神として祀られるわけですが、
その「すごい!」が実在界的価値観からみて、本当に真理価値を含んでいるか?含んでいるとしてもどの程度のレベルか?
というのが、なかなか判別がつかないからです。
基本的には、狐や蛇(龍神)系は避けたほうが無難…と別記事に書いておきましたが、
あとはそうですね…伝統的に長く残っているところはだいたい大丈夫かとは思います。
意味深い記事をありがとうございました。
私も、子供の頃から根本で疑問に感じていた事の数々を、大変分かりやすく説いて下さり、安堵感と確信を感じました。やはりいつも深い俯瞰的な物の見方が必要ですよね。
神社やお稲荷さんからこちらに出会わせて頂き、コロナ関連記事もとても為になりました。ちなみに、霊格が高い神がいらっしゃる神社とそうでない神社の特徴がありましたら、いつか教えて頂けますとありがたいです。私の住まいの近くに神社があり、感謝を込めてできる時に参拝しています。
これからも応援しております。よろしくお願いします。
コメントありがとうございます。
記事がお役に立てて本当に良かったです。
「肉体は仮のものであり、生き通しの生命です」「肉体ではないので、もう痛みはないと思えば、痛みはなくなります」
「お迎えに来た人たちの言うことをちゃんと聞いてくださいね」「もう地上のことは執着する必要はないです」
こういったことを、ふだん通り話しかける感じでお話してみてくださいね。
100%通じます。
タイムリーな内容でしたので非常に参考になりました。本日祖父の葬式、火葬予定ですので、祖父には肉体から離れるよう語りかけてみます。