犀の角のようにただ独り歩め –『スッタニパータ』(蛇の章)より抜粋 —
「犀の角のようにただ独り歩め」は『スッタニパータ』のなかでも有名な箇所で、ずいぶん愛読している人も多いようです。
まずは、いくつか抜粋してみます。
三六 交わりをしたならば愛情が生ずる。愛情にしたがってこの苦しみが起る。愛情から禍いの生ずることを観察して、犀の角のようにただ独り歩め。
三七 朋友・親友に憐みをかけ、心がほだされると、おのが利を失う。親しみにはこの恐れのあることを観察して、犀の角のようにただ独り歩め。
三九 林の中で、縛られていない鹿が食物を求めて欲するところに赴くように、聡明な人は独立自由をめざして、犀の角のようにただ独り歩め。
四二 四方のどこにでも赴き、害心あることなく、何でも得たもので満足し、諸々の苦難に堪えて、恐れることなく、犀の角のようにただ独り歩め。
四六 しかしもしも汝が、〈賢明で協同し行儀正しい明敏な同伴者〉を得ないならぱ、譬えば王が征服した国を捨て去るようにして、犀の角のようにただ独り歩め。
四七 われらは実に朋友を得る幸せを讃め称たたえる。自分よりも勝れあるいは等しい朋友には、親しみ近づくべきである。このような朋友を得ることができなければ、罪過(つみとが)のない生活を楽しんで、犀の角のようにただ独り歩め。
五四 集会を楽しむ人には、暫時の解脱に至るべきことわりもない。太陽の末裔(ブッダ)のことばをこころがけて、犀の角のようにただ独り歩め。
六一 「これは執着である。ここには楽しみは少く、快い味わいも少くて、苦しみが多い。これは魚を釣る針である」と知って、賢者は、犀の角のようにただ独り歩め。
六九 独座と禅定を捨てることなく、諸々のことがらについて常に理法に従って行い、諸々の生存には患(うれ)いのあることを確かに知って、犀の角のようにただ独り歩め。
七五 今のひとびとは自分の利益のために交りを結び、また他人に奉仕する。今日、利益をめざさない友は、得がたい。自分の利益のみを知る人間は、きたならしい。犀の角のようにただ独り歩め。
『ブッダのことば―スッタニパータ』 (岩波文庫)中村 元 (翻訳) より抜粋
「犀の角」は、”主体性の原理”の象徴
『スッタニパータ』 は最古の仏典のひとつと言われています。
最古と言っても、仏典は釈尊の直弟子が書き記したものはひとつもないのです。
その理由は、
- 当時のインド人がおそろしく記憶力がよくて、説法の内容を暗記できた
- 大事なことは文字ではなく口伝で伝えるという習慣があった
いうところにありまして、文字で記されたのは、釈尊没後数百年後なんですね。
この点、世界の四大聖人、釈迦・イエス・ソクラテス・孔子を比べてみると、
- ソクラテス・孔子は高弟が思想を書き残している
- イエスの思想は、直弟子ではないが、直弟子系統の人たちが100年を経ずに編集している
ということで、仏典に比べると、祖師の生な言葉がそのまま生かされているケースが多く、羨ましいところではあります。
いくら記憶力が良いと言っても、説法は言霊で出来ていますので、助詞ひとつ違っていても、言葉のちからが薄れると思うのです。
これは詩歌をやっている人なら、痛いほど分かることでしょう。
そのなかでも、今回抜粋した<犀の角のようにただ独り歩め>の一連は詩としても味わい深いです。リフレーンがとても効いていますね。
また、この一連はとても人気があって、ちょっと検索してみると、プロの僧侶から素人まで、さまざまなひとが採りあげています。
そうしたなか、
<ただ独り歩め>の解釈では、犀の角は一本だから、という理由で、「孤独に徹するべし」という解釈もあり、この点、若干違和感がありました。
というのも、
仏・法・僧の三宝帰依(さんぽうきえ)を説いた釈尊が独り悟り(=独覚)を勧めるはずはないと思うのです。僧帰依は仏陀教団への帰依でありますよね。
そもそも釈尊は、1,000人以上の出家教団という「組織」を作ったわけですから、歴史的事実から鑑みても、物理的な意味での「独り悟り」を勧めるわけはありません。
また、釈尊は、「自ら灯りを照らせ」という<自灯明>を勧めていたわけですが、それは同時に、<法灯明>でもあったわけです。
なので、<ただ独り歩め>の解釈としては、これは前提としての「精神的自立」「主体性の原理」を説いたもの、と理解するべきでしょう。
この点、仏教は本来、他力救済の宗教ではない(少なくとも釈尊オリジナルでは)のは明らかです。
が、それは自力と言っても、自我力ではなく、仏法に依った自力であったのだと。
つまり、ネオ仏法でよく言っている、絶対軸ですね。自分軸でも他人軸でもない、絶対軸です。
*参考記事:”自分軸”で生きるのが難しい人へ – 真理スピリチュアルが提唱する”絶対軸”とは?
他人軸ではないことは、三六、三七を読めば分かりますし、自分軸でもないことは、五四、六一を読めば明らかです。
「犀の角」は誤訳なのか?
ところで、「犀の角」という翻訳がそもそも誤訳である、という説があるようです。
いろいろ調べてみると、どうも、アルボムッレ・スマナサーラ長老が言い出したようですね。
「犀の角」の部分はパーリ語で”khaggavisaana”となるようです。
この言葉を分解すると、
- Khagga:剣(つるぎ)
- visaana:角(つの)
ということで、
そうすると、「角が剣である動物」ということで、”khaggavisaana”だけで”犀”という意味になるそうです。
だから”khaggavisaana”を「犀の角」と翻訳するのはおかしい…中村元教授の誤訳である、ということらしいのですけどね。
ただ、詩的表現として、「犀のように独り歩め」よりは「犀の角のように独り歩め」のほうが優れていると思いますね。情景が思い浮かべやすいですし、そのほうが「独り感」がでます。
また、スマナサーラ長老への異論としては、「独覚・仏陀を”犀角”と喩(たと)えることがあるのだから、この意に沿えばやはり、”犀の角”で良い」というものがあるようです。
私もこの意見に賛成です。
しかし、「独覚=犀の角」論で行くと、上述した「犀の角=独覚のススメではない」と一見、ぶつかってしまうようです。
まあこれはですね、”孤独”というものをいかに解釈するか?という問題でもあると思うのです。
つまり、”孤独”を「物理的に世間から孤立して」という意味に採るのではなく、やはり、上述したように「精神的な独立」「主体性の原理」と把握すべきだと思うのですよ。そういう意味での「犀角=独覚」です。
『7つの習慣』で説かれているように、他者と協力して相乗効果を発揮するためには、その前提として、個人個人が「主体性の原理」を確立している必要があります(第一の習慣)。
「私的成功があってこその公的成功」ということです。
なので、犀角=孤独=主体性の原理というふうに把握すれば、孤独であることと組織論はまったく矛盾しないのです。
そもそも、仏陀・釈尊が教団をつくっておられますしね。

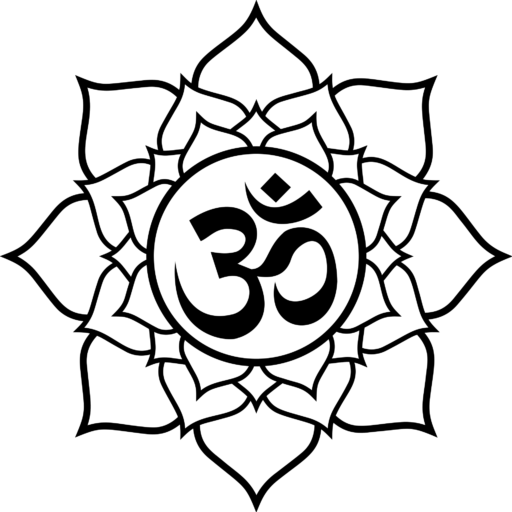











コメント