「第一の矢、第二の矢」と言っても、アベノミクスの話ではありません(笑)。これは、仏陀・釈尊のたとえ話に根拠があります。
第一の矢、第二の矢の意味とは?
まずは該当の仏典を引用してみましょう。全文を読むのが面倒なひとは太字のところだけでも読んでみてください。
比丘たちよ、まだわたしの教法を聞かないひとたちは、
苦受にふれられると、憂え、疲れ、悲しみ、胸を搏って泣き、なすところを知らず。
彼らは二種の受を感ずる。見に属する受と、心に属する受である。
比丘たちよ、たとえば、第一の矢をもって射られども、さらに第二の矢をもって射られるがごとし。
それとおなじく、比丘たちよ、すでにわたしの教法を聞いた弟子たちは、
苦受にふれられるども、憂えす、疲れず、悲しまず、胸を搏ちて泣かず、
なすところを知らざるに至らず。(雑阿含経『箭経』第十七)
比丘(びく)というのは、男性出家修行者の呼び名です。ちなみに、女性の出家修行者は、比丘尼(びくに)と呼びます。
現代におきかえると、比丘・比丘尼=出家修行者は、「真理の智慧の獲得に日々精進している人」と、意味を広くとってもよろしいかと思います。
この法話の趣旨は、
- 修行者(仏法を学んでいる者)と凡夫(ぼんぷ)の違いは、どこにあるのか?
- 修行者であっても苦しみのきっかけは受けるが、それを心に深くとどめることはない
というところにあります。
実は、あの世(実在界)は住む人の心境・境涯により、幾重もの階層構造になっております。
*参考記事;十界と十界互具 ー 仏教における”世界”の階層構造論
その中でも、まずは智慧の獲得を重点に据えている境涯を”声聞(しょうもん)”といいます。
したがって、「真理の智慧の獲得に日々精進している人」は、十界説でいえば、声聞(しょうもん)の段階にある人ということになります。
それでは、そうした声聞ですね、仏道修行を実践している人、あるいは広く、真理の智慧の獲得に邁進している人は、この世の苦しみからまったく自由でありえるのでしょうか?
この”「第一の矢、第二の矢」の法話から読む取れる結論をさきに申し上げておきます。
結論的には、声聞であっても、苦しみを受けることはあります。
それは、「生まれてくることは苦しみである」という釈尊の、実に冷静なものの見方に根拠があります。
有名な四諦八正道(したいはっしょうどう)の初めは、”苦諦(くたい)”です。「苦しみであるという真理」です。
たとえば、声聞であっても、嫌な人と会ったり、大切な人と別れたり、病気になったり、あるいは、他人からの批判を受けることもあり…で、さまざまな苦しみのきっかけに直面することはあります。
そういう意味で、この世の現象界で生きてゆくことそのものに、”苦しみ”は付随するものなのです。苦しみを受けることはあるわけです。
この、何人(なんびと)たりとも逃れることのできない苦しみが”第一の矢”に相当するのです。
ところが、”第二の矢”を受けるかどうか、で修行者と凡夫は分かれてきます。
上記の「他人からの批判」という例で言いますと、受けた批判をそれを心のなかで反芻することにより、さらに様々な心の苦しみを自ら拡大再生産してしまうケースがあります。
この「苦しみの拡大再生産」を、”第二の矢”と呼んでいるわけです。
そういう意味では、第二の矢どころか、矢を十本くらい受けてしまうこともあるかもしれません。
しかし、第一の矢を受けたあと、その矢をどのように解釈し、さらに、どのように反応していくか、ということに関しては、各自、自由に選んでいくことができる、という事実があります。
声聞の段階では、真理を学んでおりますので、第一の矢が自らの価値を損なうものではない、ということを、まずは知識として知っております。
「自らの価値は、仏法に即して生きているか?にかかっている」という智慧を持っております。
ゆえに、心が乱されることなく、さらに積極的な心の態度としては、「この第一の矢をも加工して、自分の武器にしてしまおう」という積極思考(Positive Thinking)もありえますよね。
上の例で言えば、他人からの批判を受けても(第一の矢)、「その批判のどこかに正当性はないか、学びはないか、それを魂の糧に変えることはできないか」と考えていくわけです。
つまり、
第一の矢は外部からやってくるものであって、逃れることはできないけれど、その第一の矢に対して、「どのように自分が反応していくか」については各自に決定権があるということですね。
苦しみのきっかけは誰しも直面することであるけれども、そこで「心をかき乱してしまうかどうか?」には選択権がある、という思想です。

ここまで解釈した上で、もう一度、冒頭の法話を読むと、よく意味がとれるはずです。
第一の矢は受けても、自らの選択権を行使して、「第二の矢は受けず」ということです。
ストイシズムとしての仏教
美しいものはそれ自身において美しい
この「第一の矢、第二の矢」の思想は、西洋でいえば”ストア哲学”にとてもよく似ています。仏教とストア哲学はとても相性が良いのです。
”ストア”は「ストイック」という言葉の語源でもあります。
ストア哲学の代表的な著作をひとつ挙げておきますと、古代ローマ帝国の皇帝でもあったマルクス・アウレリウスの『自省録』がお薦めです。
『自省録』からひとつ引用してみます。
美しいものはすべてそれ自身において美しく、自分自身に終始し、賞賛を自己の一部とは考えないものだ。実際人間は誉められてもそれによって悪くも善くもならない…エメラルドは誉められなければ質が落ちるか。(『自省録』)
アウレリウスの言葉こそ、文学としてもとても美しいですよね。
「賞賛を自己の一部とは考えない」とは、先の例で言えば、「他者からの批判も自己の一部とは考えない」ということでもあるでしょう。
ここには、「自らの価値は外部にあるのではなく、内部にある」「自分がどういう思いを持っている人間であるか?に自己価値の全てはかかっている」という思想があります。
これは、仏陀の「第一の矢、第二の矢」とまったく同じことを言っているのです。
刺激と反応の間には選択の自由がある
さらに現代の成功理論の決定版とも言える『7つの習慣』(スティーブン・コヴィー著)をみてみましょう。
コヴィー氏は、ナチスの強制収容所においても心の自由を守り通したヴィクトール・フランクルの例を挙げながら、下記のように述べております。
彼のアイデンティティは少しも傷ついていなかった。何が起ころうとも、それが自分に与える影響を自分自身の中で選択することができたのだ。自分の身に起こること、すなわち受ける刺激と、それに対する反応との間には、反応を選択する自由もしくは能力があった。
この、「刺激と反応の間(スペース)」という思想ですね、これは、
- 刺激:第一の矢
- 反応:第二の矢
に相当することがもうお分かりでしょう。まったく一致しております。
結局、
自らの価値が何に由来するものであるか、それを知っているかどうか、が「第二の矢を受けるかどうか」の分岐点になるということです。
自らの価値が他人の評価に決定される、という価値観であれば、第二の矢、いやいや、第十の矢くらい受けてしまうかもしれませんね。
”自分軸”の危うさ
それゆえに、価値の軸というものを真理(仏法)におく”絶対軸”がここでもやはり有効になってくることが分かります。
永遠の真理の軸、仏法の軸、絶対軸は揺るぎのないものだからです。
そういう意味では、”他人軸”ではもちろん心の安定を得られませんが、最近流行りの”自分軸”でもやはり心の安定は得ることはむずかしいでしょう。
自分軸ではいまだに「自分 – 他者」という相対観から抜け出せてはおらず、これは結局、他人軸の裏返しに過ぎないからです。
*参考記事:”自分軸”で生きるのが難しい人へ – 真理スピリチュアルが提唱する”絶対軸”とは?

そうではなく、不変の揺るぎない真理、絶対軸を基準にしつつ、「それを相対の世界にどうやって当てはめていくか?現実の場面で応用していくか?」ということですね。
ここに智慧の発生ポイントがあるのかな、と思います。



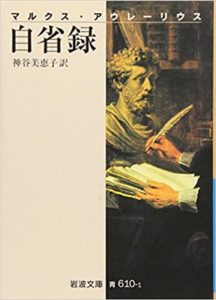






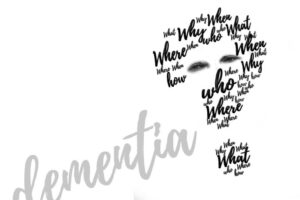


コメント
コメント一覧 (2件)
コメントありがとうございます。
まず、ご自身の症例を知り、かつ、「どうしたら良いか?」と思えるのであれば。
それはご自身を客観視するだけのちからがあるということです。
医学では、一昔にはなかった病名・症状名がどんどん生まれています。
これは、ある程度は、「病名・症例名をつけることによって、社会的認知度を増し、治療費を稼ぐことができる」
という利権意識も、ある程度は入っている側面があると思います。
また、こうした病名・症例名に限らず、あらゆる現象(起きている物事)は、本来は、”無い”という立場をとるのが仏教です。
より正確に言えば、現象としては”ある”のですが、究極の真理の実在性から見れば、”無い”と言えるということですね。
あくまで、「今・現時点での」現象に過ぎない。
ここのところ、「自分の病気は絶対的に存在する」と認識すると、その認識の程度に応じて、”ある”という現象がむしろ強化される方向へ言ってしまいます。
なので、「現象としてはそのように現れているが、実際はそれらは本来的な”実在”ではないのだ」と、意識の上で抑え込むことが肝要です。
その上で、「現象としても消し去るのはいかにしたら良いか?」という対処法に入ります。
この点は、別記事「マインドフルネスで、うつ・不安障害を解消する効果的なやり方」をご参照ください。
https://neo-buddhism.com/sinkeisho-utubyo-gekitaitaizen/
マインドフルネスの呼吸法自体で、今・ここを書き換えることができますし、
また、瞑想中の”気づき”で、すなわち、悩みを冷静に外化・対象化することによって、
それらを、都度、消し込んでいけるようになります。
マインドフルネスは、とてもシンプルで、かつ効果性・即効性がある瞑想法です。
ぜひお試しください。
また、当サイト(ネオ仏法)が解き明かしている”真理”を深く学ばれることをお勧めいたします。
大人の発達障害、LD 自閉症スペクトラム症です。
どう生きて行けば良いのですか?