前回の続きで、今回はシリーズ15回目です。
*シリーズ初回からお読みになりたい方はこちらから→「般若心経」の悟りを超えて -①
*『般若心経』全文はこちらから→祈り/読誦
無色声香味触法 無眼界乃至無意識界
読み:むしきしょうこうみそくほう むげんかいないしむいしきかい
現代語訳:かたちも音も香りも味も手触りも存在も無い かたちの認識もなく、以下同様であり、意識すらもないのである
前々回の、「是故空中」を受けています。
「かくなるゆえに、空の悟りにおいては、かたちも香りも〜無い。〜意識もない」と続いているわけですね。
前々回、前回、今回で仏教の認識論が1セットで説かれています。前回すこし予習をしましたが、ここでもキチンとご説明いたします。
認識をするためには、認識の主体と認識の客体が必要です。
たとえば、コップを眺める、という行為においては、
- 認識の主体:眼
- 認識の客体:コップ
というふうになっておりますね。
前々回に申し上げたとおり、認識の主体を六根(ろっこん)と言うのでした。これは人間の感覚器官にあたります。
それに対して、認識の客体も対応するように6つあります。これを六境(ろっきょう)と言います。これは前回のお話でした。
まとめますと、
- 認識の主体(六根):眼耳鼻舌身意
- 認識の客体(六境):色声香味触法
と、このようになります。
眼には色(物体)が、意(心)には法(存在)が、それぞれ対応しているわけです。残りの4つずつは漢字でお分かりですよね。
少し分かりにくいのは、意(心)と法(存在)の関係でしょう。
この場合の、法(存在)というのは、外界の事物のことではありません。
そうではなくて、「法」は私たちの心のなかに浮かんでくるところの様々な概念・イメージのことです。
私たち人間は、かたちや音、匂いなど外界の事物を認識の対象とすることはできますが、これは動物たちも同じです。
人間は考える葦である (『パンセ』パスカル)
という言葉もございますが、人間の人間たるゆえんは、心のなかにさまざまな概念やイメージなどを思い浮かべることができる、というところにあります。
*動物にも原初的なものはあるでしょうが、それでも本能の枠組み内であるはずです
たとえば、「自分は菩薩になりたいなあ」という場合、
- 認識の主体:心
- 認識の客体:菩薩のイメージ、菩薩とはこれこれこういうものだという概念
という構造になっておりますね。
心のなかのイメージや概念について、あれこれ思いをめぐらせることができます。
これが、意(心)と法(存在)の関係です。
この認識の主体(六根)と認識の客体(六境)を総称して十二処(じゅうにしょ)とも言います。
ここまではお分かりですよね。若干、漢字が多く出てくるだけで、構図としてはとてもシンプルだと思います。
仏教の認識論が面白いのはむしろここからです。
たとえば、私たちがひとつのコップを眺めるとします。そうすると、図式的には、
- 認識の主体:眼
- 認識の客体:コップ(”色”に相当)
ということになりますが、実際のところ、たんに眺めているだけではなくて、そこに”関係性”が生じます。
「コップに天然水でも入れて飲もうか」とか、こういう思いもまたひとつの”世界”になりますよね。
また、そもそも、私たちは対象であるところのコップをどれだけまっさらに認識できているのでしょうか?
ここはカントの認識論にとても近くなりますが、
私たちは、コップを眺めるときに、対象であるコップそのものというよりも、私たちの感覚器官に飛び込んできたコップの影像とでも言うべきものを見ているのではないでしょうか?
そう考えると、「眺める」という行為ひとつとっても、一筋縄ではいかないことがわかります。
かならず、感覚器官と対象との間にひとつの”世界”が形成されてくることになるからです。
この世界のことを「識(しき)」と言います。
六根と六境の間、それぞれに世界=識が形成されますので、合計6つの世界があることになりますね。なので、「六識(ろくしき)」と言います。
先の「コップを眺める」という行為でいけば、世界は、
- 認識の主体(六根):眼
- 認識の客体(六境):色(コップ)
- 主体と客体との関係性で作り上げる世界(六識):眼識(コップの影像)
の3通り形成されています。
それぞれがひとつの世界とも言えますので、おのおのを、眼界・色界・眼識界と呼びます。
それでは、六根、六境、六識を”世界”として分類・整理してみましょう
- 眼界ー眼識界ー色界
- 耳界ー耳識界ー声界
- 鼻界ー鼻識界ー香界
- 舌界ー舌識界ー味界
- 身界ー身識界ー触界
- 意界ー意識界ー法界
という、合計18通りの世界があることになります。これを十八界と言います。
仏教がいかに高度な哲学体系を備えているか、感嘆するばかりですね。2千数百年前にこのようなことが考えられていたのですから、カントも真っ青です。
さて、ではこのように”認識の世界”を分類していったいなんの効能があるのか?と疑問に思われる方もいらっしゃるかもしれません。
実はここでもやはり、「執着を断つ」ということ、もうひとつは「できるだけ物事を白紙に戻して観察できるようにする」ということ、大きくはこの2つの効能があると思われます。
たとえば、綺麗な人を見て「美人だなあ、いいなあ」と思うとき、私たちは美人さんそのものを見ているというよりも、
私たちの感覚器官の影像を見ているだけ、ということになります。決して対象まるごとを見ているわけではないですよね。
なので、「これは相手そのものではなくて、私の心に映じているところの影像に過ぎないのだ」と思うことにより、過度の執着を断つことができます。
また、「相手の言葉に傷ついた」という場合。
「本当に、相手の言葉そのものを受け取っているのだろうか?」という反省も入ります。
この場合でも、自分の感覚器官(耳)と、飛び込んできた相手の声の間にひとつの世界ができているわけですね(耳識界)。
さらに、「音としての声」だけではなく、相手が言わんとしていること(法)に対して、「自分はこの言葉をこう解釈する」という心の働きの世界(意識界)がまた生まれてきます。
このように考えていくと、「相手の言わんとしていることをそのまま受け止められているのだろうか」とか、
仮に相手に悪意があるにしても、それは相手の問題であって、
「”自分ごと”として傷つく必要はあるのだろうか?」「どのように受け止めるか、は私の自由ではないか」というふうに、ストア主義的に切り返していくことができます
なので、この十八界の思想は、
- 世界をキチンと分類して把握することそのものの喜び
- 物事を白紙に戻して考え、かつ、執着を断つことのできる喜び
という2つの効能(?)があるのです。
私たちはともすると、「体系的な哲学なんてなんの役に立つんだか!」とか、あるいは逆に、「人間どう生きるべきかなんて説教は勘弁!」といったふうに、
自分の得意分野に応じて、”体系哲学”と”実存哲学”を分けて天秤にかける傾向があります。
しかし、仏教では、少なくともネオ仏法では、体系哲学と実存哲学の両者を総合していくことができます。
体系的であるからこそ、幅広い実存的な発想を持つことができますし、実存的に考えられるからこそ、体系的に把握する喜びをより味わうことができるわけです。
さて、般若心経に戻りましょう。
般若心経では、上で解説したような「せっかくの認識論」を「無である!」と切り捨てています。
何ともったいない…?
無色声香味触法 無眼界乃至無意識界
”乃至”は、「途中も同様である」との意味です。なので、ぜんぶ丁寧に書き出すと、ちゃんと6つになります。
眼識界 耳識界 鼻識界 舌識界 身識界 意識界
というふうに。
「無眼界」は実際には「無限識界」だと思います。そうしないと揃わないですからね。
おそらく、リズム的に「無眼界」と読んだほうが滑らかなので、省略バージョンを用いたのでしょう
で、「無い!」という、バッサリ!の話でしたね。
この件はもう何度かお話したように、
空(くう)という、さらに高度な悟りからみると、せっかくの(?)仏教の認識論(十八界)も仮のものであり、本来無いとも言える
ということですね。
これは、空の悟りが一段も二段も上なんだ!というアピールもありますが、もうひとつは、「修行論へこだわりへの戒め」かと思われます。
十八界は素晴らしい思想ですが、どんな立派な思想であっても、あまりにこだわり続けていると、文字通りの執着になってしまいます。
「良いものに対する執着ならいいじゃないか」という説もありますが、まあそれは執着の仕方にもよりますよね。
もう頭がパンパンになって、眼が三角になるほどであるならば、やっぱり行き過ぎであり、中道からはハズレている、という判定になるかと思います。
なので、実践論的な見地からは、
十八界の思想で
- 物事を多角的に眺める練習
- 物事を白紙に眺める練習
- 物事の”受け取り方”を選択する練習
などを行っていくと、とても霊的にプラスになるのは確かですが、
「なんか執着になってきたな…」と疲れてきたら、「一切皆空!」とバッサリと切り捨てて、スッキリした中道の気分を取り戻すと。
そういうバランスかと思います。
実在、真理にも段階性がありますので、それを使いこなしていくということですね。
今回も相当に高度なお話になっていると思います。ここまで飽きずに読めるだけでも常人ではないです。

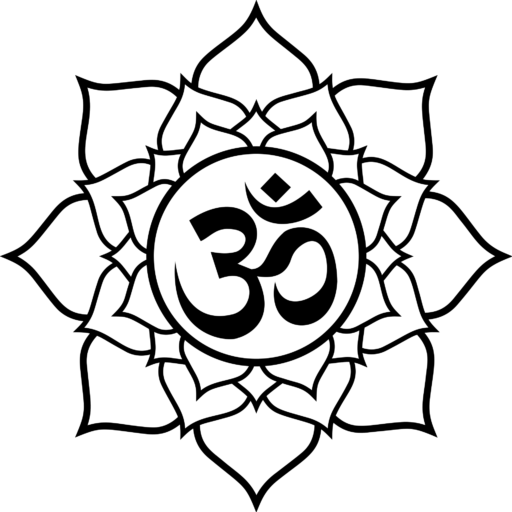









コメント