現代、とくに日本では、宗教というと「怪しい」「怖い」「弱い人が縋るもの」あるいは「金儲けのためだろう」という偏見がまかり通っています。
「宗教は怖いのか」というテーマについては、別記事で詳述していますので参考になさってください。
*参考記事:宗教は怖いと思う理由とは? – 宗教を信じないほうが怖いという真実
いきなり結論めきますが、「お金をたくさん集めているから邪教である」という判断は単純にすぎるのです。
たとえば、イエスが昇天したあとの初期キリスト教団は信者になると「全財産没収」がデフォルトでした。いったん全財産を没収しておいて、教団内部で必要に応じて再配分するというやり方です。
「お金をたくさん集めているから邪教である」ということを判断基準にすると、キリスト教は(少なくともその出発時点において)邪教であることになってしまいます。
やはり、ことはそう単純ではないのですね。
そこで今回は、特に「宗教とお金」の問題にフォーカスして考えてみたいと思います。
お金とはそもそも何であるか?
いつもの当サイトの流儀で「そもそも論」から始めてみましょう。
お金は「付加価値の現世的表現形式」
私たちがお金を払うときはどのような場面でしょうか?それは、モノ・財・サービスのいずれにせよ、「価値」を感じているからですよね。
りんご1個を百円で買う場合、りんごを食べた(あるいは家族に食べさせた)ときの美味しさ、あるいは健康への貢献などの「効用」を感じて百円を支払っているはずです。
効用を信じられると言うことはそこに百円分の「価値」を感じているということでもあるのですね。
あるいは、より正確に表現するとするならば、そこに「付加価値」を見出しているからこそ、私たちはお金を支払っているのです。
りんご1個を食べるためには、(自分一人だけの世界であれば)リンゴの木を植えて育てることから始めなければなりません。そこには膨大な労力と時間コストがかかります。
ところが売っているリンゴであれば、その労力・時間コストを省くことができる。私たちはそこに付加価値を見出していると言うわけです。
このように考えていくと、お金は「付加価値の現世的表現形式である」と定義することが可能となります。
さらには、お金そのものに付加価値が込められていますので、それは「交換価値」の働きもすることになります。
お金そのものは「価値中立的」である
さて、価値には「良い価値」と「悪い価値」が存在します。
たとえば、明らかに健康に悪いけれどもそこに依存性があるときにも、人は「価値」を感じてお金を支払う時がありますよね。
逆も真なりで、そこに明らかに善なる価値が込められている時もあります。
いずれにせよ、お金そのものは付加価値を表現してはいるものの、善悪の判定という観点から言えば「価値中立的」であるのです。
ひらたく言えば、お金そのものは善とも悪とも言えない、ということです。それが「価値中立的」であるということなのですね。
では、善悪はどこで分かれるかというと、そのモノ・財・サービスが「真理に合致しているかどうか」で決まってくるのです。
あるいは、購入後に、そのモノ・財・サービスを「どのように使うか」でも決定されてきます。
たとえば、果物ナイフは本来は「果物を剥くために便利なもの」という善なる価値を含んでいます。
しかし、果物ナイフを使って人を殺傷することもできます。もし人が果物ナイフを購入後にそのような反真理価値のために使ったのであれば、その時点で(本来、善であったものが)悪に転化していったと言うことができます。
なので、繰り返しになりますが、やはりポイントは、お金そのものは善でも悪でもなく、価値中立的であるということです。あくまでも、そのモノ・財・サービスをどのように使うか?という「用途」において善悪が発生することになるわけですね。
「お金を集めているからその宗教は怪しい」は間違い
お金を集めている時点ではまだ善悪の判断を下すことはできない
前項の結論部分でじつは本稿の結論も見えてきました。
繰り返しますが、「お金そのものは価値の現世的表現形式であり、それ自体は価値中立的である。その使用用途によってはじめて善悪が決まる」ということです。
それゆえに、「お金を集めている」時点ではまだ善悪の判定を下すことはできないのです。
あくまで、その宗教団体が「お金をどのように使用しているか?」によって善悪が決まる。言い換えれば、「その宗教が怪しいか怪しくないかが決まる」ということになります。
お金の使用用途における善悪はどのように判定されうるか?
それでは。ある宗教団体がお金をどのように使用しているか?その使途によって善悪が決まるのであれば、その「使途とは何か?」が次の問題になってきますね。
それは大きく言えば、「集めたお金をある用途に使うことによって人類の幸福が増進されるかどうか?」がポイントになると思うのです。
ネオ仏法では、幸福論こそが最高価値であるという立場をとっています。もちろん、「幸福」の内実をまた問題にすることもできるのですが、ここでは深く立ち入らないようにします。
なにゆえに幸福論が最高価値と言えるか?というと、それは仏教の三法印解釈に関わってきます。
それは、
- 諸行無常:時間論→智慧の獲得
- 諸法無我:存在論→慈悲の実践
- 涅槃寂静:(智慧と慈悲に立脚した)幸福論
という解釈です。
この点については下記の記事で突き詰めていますので、興味ある方はぜひお読みください。
*参考記事:三法印の究極の到達目標とは?- 三法印の発現段階と新時代の三法印
ただ、仏教や三法印を持ち出すまでもなく、「幸福が最高価値」というのはわりと一般に賛同が得られるところかと思います。
さて、それでは、「ある宗教団体が集めたお金を人類の幸福のために使えているか否か」はどのように判定できるのかが次の問題になってきますよね。
でも、それは結局、「その宗教団体の教義と教義に基づいた行動原理が人類の幸福に寄与するものであるか?」という視点で判断するしかないのだと思います。
あるいはもっとひらたく言えば「その宗教団体の説いている教えが真理であるかどうか」ここにかかっているということになります。
難しいことを言っているようですが、人に置き換えてみるとわかりやすいです。
善人は善人であるが故に善なるお金の使い方をするでしょう。逆も然りです。
なので、善人がクラファンでもなんでもいいですが、お金を集めて何か事業をすれば、それは(その事業が成功すれば)人類の幸福に寄与することになりますよね。
だから結局、「その人が善人であるかどうか?」が根本の判断基準になるはずです。決して、「お金を集めてるから善人、あるいは悪人」という発想の順にはならないはずです。
このことは団体に置き換えてもやはり同じなのです。
宗教団体に限らず、ある団体が善なる団体であれば、お金も善なる使い方をされるはずです。だから、まずはその団体が善であるか悪であるかを判断することが先決になってくるというわけです。
ここが大事なポイントで、ここで本論の結論が出ていると言えます。
つまりは、「お金を集めているから宗教は怪しい」「宗教は金儲け目的である」という判断はあまりに早計に過ぎる、ということです。
そして早計に走ってしまう原因は、お金以前に「宗教とは怪しいものだ、怖いものだ」という特に現代日本に蔓延している価値観に起因するものでしょう。
その発想自体が、ワールドスタンダードでないことは参考記事で論じた通りであるのです。もう一度、掲載しておきます。
*参考記事:宗教は怖いと思う理由とは? – 宗教を信じないほうが怖いという真実
宗教団体の善悪はどこで判定されうるのか?
さて、前項で「お金を集めてるから宗教は怪しいとは言えない」「結局は、その宗教団体の教義・行動様式などの内実を見ることが先決である」という結論を出しました。
これは世界宗教に限らず、新宗教、新興宗教にも当てはまることです。
それでは、ある宗教団体の教義・行動様式の善悪はどのように判定されうるのでしょうか。
行動の前提には、教義があるわけですから、結局のところ、「教義が善なるものか」あるいは「教義が真理であるか」が最初にして最終の判断基準になると言っても良いでしょう。
しかし、ここのところは難しいですよね。何をもって善とするか、真理とするか?
難しいですが、一応、目安的なものを2点挙げておきます。
- 教義で「主体性の原理」を説いているかどうか?
- その宗教団体に所属している人が人格的に向上しているかどうか?
とりあえずは、この2点がチェックポイントになると思います。それぞれ見ていきましょう。
教義で「主体性の原理」を説いているかどうか?
「主体性の原理」というと何やら難しそうですが、実際はそんな難しいことを言っているわけではありません。
要は、幸不幸の原因を外部転嫁せずに、その人本人の心のあり方を問うているかどうか?ということなのです。
幸不幸の原因を外部転嫁するのは宗教に限らず、「広き門」であり、楽な道なんです。そして楽であるが故に、地獄へ通じている道でもあります。
たとえば、「あなたが不幸であるのは先祖が迷っているせいだ」といった責任の外部転嫁がよくあるパターンです。
これはその言葉を聞いた側も「オレの(私の)せいじゃないんだ」ということで気が楽になりますよね。まさに「広き門」です。
ところが、「外部」というのはいくらでも持ち出すことができますので、「まだお布施が足りない、迷っている先祖はまだまだ居る」というふうにキリがなくなってくるわけです。
*参考記事:「先祖の因縁を断ち切る」はスピリチュアル的にあり得ない理由
そしてもっと重要なことは、幸不幸の原因を他人や環境のせいにしている限り、その人の霊性向上はあり得ない、ということなのです。
霊性向上は現世的に言えば、「人格の向上」ということになりますが、これが伴うからこそ、古今東西で説かれてきた真理と合致してくるのです。
よって正しい宗教は、かならず主体性の原理を説きます。
キリスト教や浄土宗のような救済型の宗教に主体性の原理はあるのか?と疑問に持たれるかもしれませんが、「信仰のみ」であっても、これは主体性になっているのです。
信仰するのはその人自身の主体性に関わってくるからです。
もっとも、親鸞的には、信心ですら「如来より賜りたる信心」となるのですけどね。
ここのところは判定が難しそうですが、こうした他力(絶対他力)であっても、じつは自力と矛盾しないのです。この点については別稿で論じていますので、興味のある方はお読みください。
*参考記事:聖道門と浄土門の意味と違い – 自力と他力を総合する絶対力とは?
その宗教団体に所属している人が人格的に向上しているかどうか?
これは教義の判定に比べれば、直感的・経験的にチェックしやすい項目だと思います。
聖書にもこの基準が書かれています。
「悪い実を結ぶ良い木はなく、また、良い実を結ぶ悪い木はない。 木は、それぞれ、その結ぶ実によって分かる。茨からいちじくは採れないし、野ばらからぶどうは集められない。 善い人は良いものを入れた心の倉から良いものを出し、悪い人は悪いものを入れた倉から悪いものを出す。人の口は、心からあふれ出ることを語るのである。」(「ルカによる福音書」6章43-45節)
- 良い木:宗教の教義
- 良い実:実践者の霊性向上
ということになります。逆も真なりです。
社会学の巨人、マックス・ウェーバーも「宗教とはエートスである」と述べています。エートスとは「行動様式」のことですね。
仏教徒であれば、解脱を願って悟りを目指しますし、儒教の徒であれば忠孝に生きるでしょう。某カルト教団であればサリンを撒いてしまうというふうに、かように行動様式(エートス)に直結しているのが宗教なのです。
まあ、広く哲学や思想もそうですね。




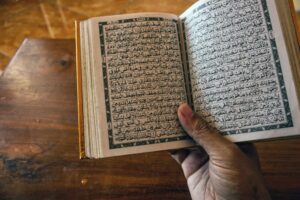


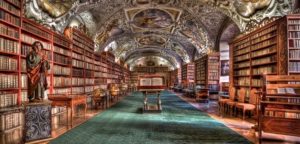

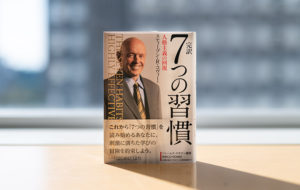

コメント