ユダヤ人の”選民思想”については、よく知られていると同時に、歴史上さまざまな軋轢を生んできたところでもあります。シオニズムから現代のパレスチナ問題まで波及しています。
ユダヤの選民思想は、簡単に言えば、
「神(ヤーヴェ)は、ユダヤ民族と独占契約を結び、その契約を守れば、メシア(救世主)の到来によって、ユダヤ人は救われる。エルサレム(イェルサレム)が世界の中心になる」
と、おおよそこういう思想で、これは「律法主義」という言われますが、文字通り、律法(トーラー/モーセ五書)にまずは根拠があります。
今、もしあなたがたが、本当に私の声に聞き従い、私の契約を守るなら、あなたがたは全ての国々の民の中にあって、私の宝となる。全世界は私のものだから。あなたは私にとって祭司の王国、聖なる国民となる(「出エジプト記」19章5-6節)
主があなたがたを恋い慕って、あなたがたを選ばれたのは、あなたがたがどの民よりも多かったからではない。事実、あなたがたは、全ての国の民のうちで最も数が少なかった。しかし、主はあなたがたを愛されたから、また、あなたがたの先祖達に誓われた誓いを守られたから(「申命記」7章7,-8節)
このユダヤ教的な「メシア」の定義にイエスがそぐわなかった、という判断から、ユダヤ教ではイエスを「キリスト」(「キリスト」はギリシャ語で、ヘブライ語になおすと「メシア」となる)と認めていないわけです。
*ユダヤ人は、他からはヘブライ人と呼ばれ、自らはイスラエル人と称していました
*参考記事:メシアとは何か? ーユダヤ教、キリスト教、イスラム教におけるメシア思想
「神がわるいんじゃない。我々ユダヤ人がわるいのだ」
この、「唯一神ヤーヴェ(ヤハウェ)から選ばれた、いわばエリート民族であるにも関わらず、ヘブライ王国のダビデ・ソロモンの治世を除いては、いっこうにイスラエルが世界の中心になるという展望が開けなかったのです。
ヘブライ王国の分裂後は、北イスラエル王国はアッシリアに、ユダ王国は新バビロニアに滅ぼされ、さらにバビロン捕囚までされてしまった。
新バビロニアがペルシャ帝国に滅ぼされるとBC538年にバビロン捕囚から解放され、第二神殿を建設することになりますが、その後も、ペルシャ帝国、アレクサンドロス大王、セレウコス朝シリアの支配下に置かれることになりました。
そうした抑圧のジレンマにも関わらず、皮肉なことに、
「これは神(ヤーヴェ)が契約を守っていないのではなく、われわれユダヤ人が契約を守っていないせいなのだ」「神がわるいのではなく、我々ユダヤ人がわるいのだ」
という摩訶不思議な方向へ行きます。
そして、バビロン捕囚を機に離散(ディアスポラ)したユダヤ人は、各地にシナゴーグ(集会所)を作って、かえって結束を固めていったのです。
これは実に珍しいケースで。
ちょっと考えてみれば分かることですが、
古代において、神様をたてて政治・軍事的闘争を行い、結果、負け続けているのであれば、「この神様は力不足である」ということで、神が見捨てられる方向へ行くのが普通です。
そして、もっと強そうな神様に乗り換えると。
ところが、ユダヤ人は、
「負け続けているのは、神がわるいのではなく、われわれが契約の内容(律法の遵守)を履行していないせいだ、われわれユダヤ人がわるかったのだ」
と考えたわけですね。
*もっとも、ユダヤ人はけっこう浮気(=他の神を拝む)していますが、まあしかし、これこそが「契約を守っていない」最たるもの、ということでしょう。ヤーヴェは「妬む神」なので、これがいちばん許せないことなのです。
まさに、おどろくべき逆転の論理です。他の世界史では起こり得なかった発想です。
真理スピリチュアル的観点から言えば、この「神的実在中心の世界観・宗教観」こそがユダヤ民族が人類に遺した最大の功績であると思います。
では、なぜこのよううな発想の大転換が可能になったのか?
いろいろ理由は考えられていますが、ポイントは、「たまに、勝つこともあった」というところがミソで、
さきのダビデ・ソロモン王の時代がそうですし、また、紀元前2世紀から約100年ほど反乱戦争(マカバイ戦争)に勝利して、ハスモン朝という王朝が成立していた時期もあります。
*もっとも、ハスモン朝もBC1世紀にはローマの支配下に置かれ、AD6年、パレスチナはローマの属州になります。
あるいは、出エジプトももちろん成功体験です。

このように、下手に(?)たまに勝って”約束の地”に帰還できるので、「ほら、やっぱりヤーヴェは偉大だ」ということになり、アブラハム〜出エジプトの民族の記憶と相まって、「バビロン捕囚」などの屈辱的事件があっても、なんとか希望を持ち続けることができた。という微妙なバランスです。
さて、
なぜここのところを若干詳しく書いているか?と言いますと、それは、「真理スピリチュアル」の誕生に関わってくるから、なのです。
*参考記事:「神の名をみだりに唱えてはならない」(十戒)のはなぜか?
この参考記事を読まれた読者の方の多くも、「え!神中心の世界観!?」と、若干でも抵抗感を持たれたかもしれません。
しかしこの、「神中心の世界観」こそが、上述のユダヤ民族の「摩訶不思議な選択」によって世界史上はじめて獲得されたのです。
こういう、発想における「土俵際うっちゃり」があるから、ユダヤ教成立史は面白いのですけどね。
神が民族を選ぶ(選民)とはどういうことか?
それから、旧約聖書を読んでみると、ダビデ・ソロモンなどの政治指導者だけではなく、優秀な宗教家、つまり預言者を多く輩出しているのも、民族のプライドの一因となっているでしょう。
もっとも、同時代では預言者はけっこう迫害されているのですけどね、ユダヤ人みずからが迫害しています。
こんなふうに、「他の神に目移りするわ、預言者は迫害するわ」で、旧約聖書は、いわば、「契約を守らないユダヤ人と神の懲らしめの歴史書である」とも言えそうです。
さて、
ここまでのところは、マックス・ウェーバーが『古代ユダヤ教』のなかで洞察している内容です。
問題は、今回「ユダヤ教の選民思想の背景〜」とタイトルにしたように、「本当に、唯一神ヤーヴェはユダヤ民族を(排他的に)選んだのか?ユダヤ人の選民思想はどの程度、妥当性があるのか?」というところでしょう。
学問だけでは立証できない範囲になりますので、ここに切り込める人はあまりいないと思います。
「神の世界計画」の特徴
じつはここのところは、「神の世界計画」に関わってきます。
神の世界計画については、本質的なところは下記の記事で書いたとおりです。
*参考記事:ワンネス、仏教、宇宙。そしてネオ仏法の悟りへ)
唯一神(地球のトップ)にとっては、
- 地球レベルでの智慧と慈悲のエネルギー総量を増やしていく(無常・無我)
- エネルギー総量を増やす過程そのものに幸福論を見出していく(涅槃)
という目的があります。
そのためには、どうするか?
特定の時代・地域に集中して天使(菩薩)を送り込むという方法が取られます。天使(菩薩)には、「神の世界計画の実行部隊長」の役割があるからです。
天使はユダヤ的な文脈では地上に”預言者”として現れることもあります。
*これはユダヤ教の解釈ではなく、ネオ仏法で再解釈した理解です。
また、天使(菩薩)までいかなくても、ある程度、優秀な魂たちも「学び」のために、その特定の時代・地域に生まれてくることになります。
なので、その特定の時代・地域の文明度がグーっと上がっていくわけです。
そして、その「選ばれた国」が一定の使命を終えたな…と判断された時点で、また別の地域に文明の力点が移っていきます。
さまざまな分野に偉大な足跡を残した古代ギリシャが、中世以降、現代にいたるまではサッパリふるいませんよね?これは地上的な観点からだけ考えると、じつに不思議なことです。
現代のギリシャは、古代当時の遺産を使った観光業で知られているくらいでしょう。こういったことは、地政学だけではとうてい説明がつきません。
ちなみに、今ですね、現代においては、「日本が選ばれている」ということを何度か申し上げています。日本に数多くの天使(菩薩)・天使(菩薩)予備軍たちが生まれてきています。
長くもって、パクス・ジャポニカは100年くらいは続くだろうな、と見ております。
そういう事情もありますので、
今この記事を読んでいるあなたも天使(菩薩)候補生であるかもしれない。むしろ、天使を目指しましょう!
と、私はネオ仏法を更新し続けているのです。
話を戻しまして、
こうした「神の世界計画」に則って、古代イスラエルの一時期にも、天使たちが連綿と生まれていた時代があったということなのですね。
なので、そういう意味では、「イスラエルの民は選ばれていた」とは言えます。選民思想はこのような限定的な意味では、正解です。
もっとも、「神の世界計画」とか「天使(菩薩)が多数、生まれてくる」というとまた抵抗を感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、
哲学者ヘーゲルが言うところの、
- 世界史は、「絶対精神」が弁証法を通して自己の本質である「自由」を顕現させていく過程である
- 特定の国家に「世界精神」が現れる
この二点ですね、ここのところを、
- 絶対精神=神
- 自己の本質である「自由」を顕現させていく過程=世界計画
- 世界精神=天使(菩薩)が生まれてくる
と言い換えれば、これはまったく同じことを言っているわけです。
ちなみに、ヘーゲルがナポレオンを見送りながら、「世界精神が行く…」と述懐したのは有名な話です。

*参考記事:ヘーゲルの弁証法を中学生にもわかるように説明したい
文明の力点(地域・場所)は時代によって移り変わる
上の考察に従えば、「ある一時期にある国、ある人種が選ばれることはあっても、それがずっと続くわけでない。文明の力点は次第に、また別の地域・国へ移動していく」ということが言えます。
なので、ユダヤ民族にしても、ある特定の時代にダビデやソロモンなどの偉大な為政者、あるいは優秀な預言者が現れていたとしても、それがずっと永遠に続くわけではないのです。
地上的な観点だけでは、「いまこの時代に、我が国は覇権国家としての使命があるのだ」という矜持(きんじ)は、容易に右翼的なものに流れていくのはおわかりだと思います。
ヒトラーの「アーリア人優越主義」などもそうですが、選民思想が危険なものに流れてゆくパターンです。
しかし、上述の通り、「神の世界計画の一環として、それぞれの時代に、文明の頂点を作るためにある国や民族が選ばれることがある」という観点では、
- 今、選ばれていてもずっと選ばれるわけではない。順繰りに覇権は移動していくものだ
- そもそも、「選ばれている」というのは、単なるエリート意識ではなく、自国を繁栄させることによって他国にも余徳を与える、という自利利他の精神を期待されているのだ
ということになり、偏狭な民族主義・国家主義というのは発生する余地がなくなるわけです。ここが大事なところですね。
*お断り 本記事では、議論の流れを分かりやすくするために、「ユダヤ人」「ユダヤ民族」「イスラエルの民」など、各タームを厳密に区別しないで使用しています。



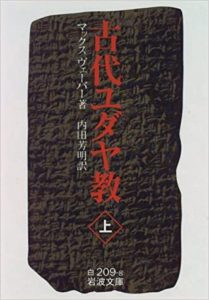
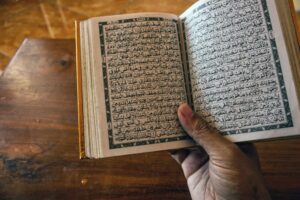







コメント