「最後の審判」(英語:Last Judgement)とは、世の終わり、ハルマゲドンの後に死んだ人間も復活、そしてキリストが再臨し、裁きを行うというキリスト教の思想です。
- 世の終わり
- 復活
- 審判
という3点セットになっております。
審判の結果、有罪となって地獄(ゲヘナ)へ堕ちるもの、永遠の生命を得るものに分けられます。神=キリストによる裁判により、正義(神の義)が実現されることになります。
システィーナ礼拝堂の祭壇に描かれたミケランジェロの絵画が有名ですね。

中央には再臨のイエス・キリストが右手を上げて裁きを行っています。向かって左側には地獄へ堕ちるもの、右側には天の国へ昇るものが描かれています。
ちなみに、「最後の審判」はキリスト教オリジナルと思っている方が多いのですが、キリスト教成立よりずっと以前のゾロアスター教でも説かれています。
善の神アフラ・マズダと悪の神アンラ・マンユ(アーリマン)の最終闘争が行われ、善が勝利を収めた後に最後の審判が行われるという流れです。
「最後の審判」はおそらく、ゾロアスター教がオリジナルで、セム的一神教(ユダヤ教・キリスト教・イスラム教)に引き継がれていった思想と考えてよいかと思いますね。
イスラム教でも、世の終わりにアッラーによる最後の審判があるとされています。
さらに意外なことに、ゾロアスター教の最後の審判は、大乗仏教とりわけ浄土教にも影響を与えているという説もあります。
ヨハネの黙示録では、神の国が到来する前に、この世に淫蕩・悪がはびこるように、<無量寿経>においては、阿弥陀仏の救済の前に五濁悪世(ごじょくあくせ)が描かれている、とった具合です。
*参考文献:『大乗仏教の誕生 「さとり」と「廻向」』(梶山雄一著)
今回は、「最後の審判 いつ来るのか」という、意外に、みな「信じ切れてはいないがすごく気になる」というテーマに切り込んでみます。
黙示文学はなにを象徴しているのか?
「最後の審判」といえば、まずは、『ヨハネの黙示録』を思い浮かべる方が多いでしょう。
パトモス島のヨハネが幻視した内容を綴ったものです。
ところが、『ヨハネの黙示録』を読み進めても、イメージと寓意だらけで、具体的に「いつ、どこで、なにが起きるのか?」についてはハッキリと分からないように書かれています。
たとえば、
第一の生き物は獅子のようであり、第二の生き物は若い雄牛のようで、(中略)それぞれ六つの翼があり、その周りにも内側にも、一面に目があった。(ヨハネの黙示録4:7-8)
こういう書き方ですね。
「生き物」「獅子」「雄牛」がなにかを象徴しているのでしょうが、具体的にそれが何なのか?解読の面白さはあるかもしれませんが、具体的な情報はなかなか読み取れないように(あえて)書かれています。
それから、「最後の審判はいつ来るのか?」ということについては
この黙示は、すぐにも起こるはずのことを、(後略)
(ヨハネの黙示録1:1)
と、いきなり冒頭に書かれていますが、”すぐ”といっても、どのくらい”すぐ”なのか?
「神の目から見れば1万年でも”すぐ”ですよ」と言われても、なかなか複雑な心境になってしまいますよね。
ただ、あえて寓意を読み解いていくとするならば、これらの記述は、ローマ帝国支配の終焉を意味している、というのが一般的な解釈でしょう。

たとえば、「忌まわしい生き物が地上にもたらされ〜最初の四つの封印からは、馬に乗った四人の騎士が〜」という記述もありますが、
これらはなぜ”4”という数字かというと、ローマ帝国の皇帝の乗る馬車が四頭立てだったから、という解釈がなされております。
それから、「大淫婦が裁かれる」という話が第一七章からでてきます。
あなたが見た女とは、地上の王たちを支配しているあの大きな都のことである。(ヨハネの黙示録17:18)
ここのところですね、この”女”はやはり、ローマの都の擬人化ととらえてほぼ間違いないでしょう。
じつは旧約聖書のなかにも、いくつか、黙示録的な記述が散見されまして、これらは「黙示文学」と言われております。
たとえば、『イザヤ書』『ダニエル書』『エゼキエル書』にも黙示録的な記述があり、それらに描かれているイメージは、「獣」とか「角」とか…ヨハネの黙示録と共通するものがかなりあります。
イザヤ、ダニエル、エゼキエルが対象としているのは、アッシリアであったり、バビロニアであったり、で時代背景が異なっているだけです。
つまり、黙示文学というのは、ユダヤ・キリスト教の流れの中で、その時々に支配者であった帝国に対する「終わりの警告」が問題になっている、ということがひとつ指摘できるでしょう。
もう一つは、そうした支配のなかで生きている一人ひとりが「神の前で義とせられるか」が問題になっている、と言えるかと思います。
神は、ひとりひとりに、その人の行いに従って報いをお与えになります。(「ローマ人への手紙」2章6節)
このように考えていくと、最後の審判とは、実際に(絶対的に)この世の終りが来る、というよりも、
- その時々の支配者(帝国)に対する審判
- その渦中に生きる個人個人の生き様が神の義にかなっているか?という意味での審判
が実際のところテーマになっている、ことが分かります。
相対的終末と実存的終末
上記のように解釈していくと、結局、最後の審判は、必ずしも「実際にこの世の終わりが来て、神の国が実現する」という意味での”最後”と受け取る必要はない、と言ってもよろしいかと思います。
では、どのように考えるか?と言いますと、
- については、ひとつの帝国支配の終焉ということで、まあエポックメイキングなことですね、ある「時代の区切り」としての終末を問題にしている。つまり、絶対的な終末ではなくて、いわば、「相対的終末」が問題になっているということが分かります。
- については、結局、「終末」といっても、ひとりひとりの関心事は、煎じ詰めれば、「自分の人生はどうなってしまうのか?」ということですよね。つまり、個人的・実存的な終末が関心事になっているということで、いわば、「実存的終末」が問題になっています。
では、これを踏まえて、「最後の審判はいつ来るのか」を整理してみましょう。
- 相対的終末:自らが生きている時代・国家ががいかなるエポックメイキングを迎えようとしているか?という「社会的な最後の審判」
- 実存的終末:自分自身が今回の人生において、どれだけ神の義にかなっていたのか?という「個人的な最後の審判」
と、このようになるかと思います。
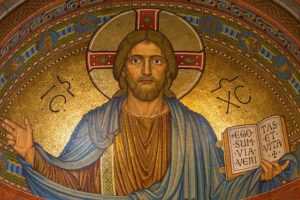
”最後の審判”を幸福論に転換する
さて、上記の通り、「相対的終末」「実存的終末」というふうに分けて考察してみても、やはり、「怖いな」という感覚は払拭できないですよね。
これはなぜかと言うに、最後の審判というものを、「外部から自分に襲いかかってくる災難」として捉えているからです。
そうではなく、最後の審判も、幸福論の基礎であるところの「主体性の原理」から捉え直してみることをお勧めいたします。
たとえば、2.の「実存的終末」です。
これは言い換えれば、「神の目、真理スピリチュアルの観点から、自分の人生はどうであったのか?これからどうあるべきか?」を振り返っていく、ということになるかと思います。
このように自らを振り返りつつ、未来設計を行っていくことは、すなわち、「智慧の獲得」につながっていきます。これは、仏教的に言えば、「自利」に相当すると言えると思います。
また、1.の「相対的終末」については、
「自らが今、地上に生きていて、その時代や共同体(家庭、社会、国家、文明)に対していかなる貢献ができるのか?」という観点で対処していくことです。
こうした貢献の行為は、いわば「慈悲の発揮」であり、仏教的に言えば、「利他」に相当するでしょう。
このように、「最後の審判がいつ来るのか?」と受け身になって震えているのではなく、主体性を軸にしていくことで幸福論へと転換していくことが可能になってきます。

仏教の方へ話が行ってしまったので、もう一度、キリスト教的な文脈で再解釈してみましょう。
「自利利他」の思想は、キリスト教的に表現すると、
「『心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。』これが最も重要な第一の掟である、第二も、これと同じように重要である。『隣人を自分のように愛しなさい。』律法全体と預言者は、この二つの掟に基づいている。」(マタイ22:36-40)
ここに該当すると思われます。
そうしますと、以下の図式が成立します。
- 相対的終末⇢利他=隣人愛
- 実存的終末⇢自利=神への愛
このように考えれば、黙示思想というものが、単なる恐怖や趣味的な議論に終始せず、まさに自らの霊格向上および社会のユートピア化の原理と合致してくることになります。
また、このように「最後の審判」を捉え直すことにより、キリスト教的世界観と仏教的世界観の橋渡しをすることができます。
「神の国」と「地の国」
さて、『ヨハネの黙示録』に戻って、結局、最後の審判はどうなったか?ということを考えてみますと、世俗権力であるローマ帝国は、結局、のちにキリスト教を公認、さらには国教にせざるを得なくなりました。
そして、西ローマ帝国滅亡後も、カトリック教会は延命し、のちに「西ローマ帝国の再興」として、フランク王国のカール大帝が戴冠しましたね。
これはローマ教皇の権威に基づいての戴冠でありますし、中世を通じて、のちの神聖ローマ帝国においても事情は同じです。
「教皇は太陽、皇帝は月」(インノケンティウス3世)と言われたように、世俗権力に対する宗教権力の優位が続きます。
ここのところは見方はいろいろありますが、
とりあえずは、罪人として十字架刑に処せられたイエスの蒔いた種が、結局は、ローマ帝国を飲み込み、「神の国」の礎が築かれた、という意味でははっきりと「キリストの勝利」と言えるでしょう。
この、「神の国」思想はアウグスティヌスに依っていますが、彼の考え方も、黙示思想をそのまま受け取るのではなく、解釈学として捉えるべきである、という考え方ですね。
*参考書籍:『神の国』(アウグスティヌス著)
社会的(マクロ視点)には、
「神の国」が地上において絶対的・排他的に実現するということではなく、あくまで、「地の国」と争いつつ実現していく過程、というダイナミクスにおいて捉えていること。
これは、個人の内面(ミクロ視点)においては、
一人ひとりの心のなかに「神の国」と「地の国」があって、相争いつつ、次第に「神の国」が実現していく。悪を知ることによって、善とはなにか?神の義とはなにか?を知っていく、ということですね。
これは、私たち人間が、なにゆえに地上に生まれてくるか?という「人生の意味とミッション」にも合致すると言えるでしょう。
*参考記事:人生の意味とミッションとは? – 最勝の成功理論を明かします
世界規模での”世紀末現象”についてどう考えるか?
さて、1999年7の月に人類は滅びるというノストラダムスの予言は外れたと思われています。ノストラダムス以外でも様々な世紀末的な予言がありました。
ただ、「予言が外れたからもう大丈夫!」とホッとするのもまだ早いかもしれません。
予言というのはなかなかに難しいもので、当たるにしても、時期や地域などがズレていくことがあります。
これは、実在界と現象界における時間の流れにズレがあることが原因のひとつですし、あとは、地上の人間にも自由選択の余地がありますので、すべてが運命のままに展開するわけではないのですね。
今この記事を追記しているのは2022/08/21で、世界はコロナパンデミックのなかにあります。これはひとつの警告です。
さまざまな天変地異や疫病の流行などがなぜ起きるのか?ということについては、仏教の”共業(ぐうごう)”の理論でご説明したこともあります。
*参考記事:共業、不共業とは? – 仏教に学ぶ天災・疫病の原因
共業というのは「共なる業」と書きますが、これは文字通り、ある特定の集団に共有されている業、カルマのことです。
逆に、個人の業・カルマのことを”不共業(ふぐうごう)”と言います。
個人の運命は、過去世から現世にかけての思いと行いの集積である程度決まってくる部分があります。これは原因と結果の法則です。仏教的には、縁起の理と言います。
それと同様に、人類が21世紀までに積み重ねてきた業・カルマというものがあります。
これは実際のところなかなかに大きなもので、たとえば欧米列強の植民地支配や、世界大戦、原爆の使用、冷戦、そして無神論や唯物論など、マイナスのエネルギーがかなり集積されています。
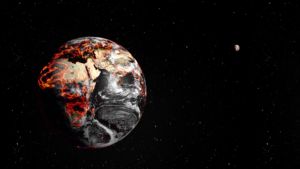
このカルマ、共業がどのように解消されるのか?
一番良いシナリオは、人類が悔い改めて真実の価値観に目覚め、自主的に文明を立て直す、というものですが、残念ながらそうした努力はあまりに不十分でした。
上述したローマ帝国の滅亡などは、ごく限られた地域のものです。特定の文明が滅びるという「相対的終末」です。
ただ、現代のように情報ネットワークや国際政治というものが文字通りグローバル化して地球レベルで展開している状況を考えると、「滅び」というものもやはり地球規模で起こりうることが予測されます。
大規模な地震などというレベルではなく、たとえば大陸が陥没していくとか、極移動が起きるなど、あたかも、「絶対的終末」がやってきたかのような観を呈するかもしれません。
それから、太陽と月と星に徴が現れる。地上では海がどよめき荒れ狂うので、諸国の民は、なすすべを知らず、不安に陥る。人々は、この世界に何が起こるのかとおびえ、恐ろしさのあまり気を失うだろう。天体が揺り動かされるからである。(「ルカによる福音書」21章25−26節)
ただ、心しておかなければいけないことは、どのようなことが起きようとも、人類すべてが滅びるわけではないということです。
こうしたことは過去、規模は違えど、何度も何度も繰り返してきました。
この地上世界は霊性進化の場として用意されているわけですが、地上があまりに乱れていると、修業の場どころか「地獄霊養成所」のようになってしまいます。
そうなるくらいなら、一度グレートリセットして文明づくりをやり直したほうが、長い目で見て魂のためになる、と判断されることがあるということですね。
だから、「この世はあくまで現象に過ぎない。無常で無我なものである」と知りつつ、
人の子の前に立つことができるように、いつも目を覚まして祈りなさい。(「ルカによる福音書21章36節))
ということが肝要なのです。





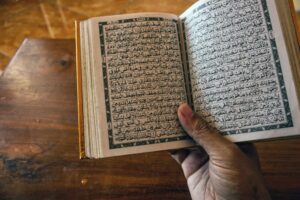







コメント