今回は、キリスト教における地獄論です。
地獄については、古ギリシャ語の日本語読みである”ゲヘナ”あるいは”ハデス”という名称で呼ばれることもあります。
おおざっぱには、
- ゲヘナ:永遠の地獄
- ハデス:不信仰な者が最後の審判を待つ場所(黄泉、陰府)
と分けられおりまして、そうしますと、
- ゲヘナ:地獄(永遠)
- ハデス:煉獄(れんごく/一時滞在所)
という概念分けがされているということですかね。
*英語訳聖書ではhellに統一されて訳し分けはされていないようです。
地獄の描写についてはダンテの『神曲』が有名です。
各々の地獄についてとくに聖書に根拠を持っているわけではないのですが、ダンテはある程度の霊能力を持っていたと思いますし、文学的に香り高い作品ですので、「地獄篇」のところだけでも一読をお勧めしたいです。
さて、しかし、私たち生きている人間にとっては、「地獄は現実にあるのか?」「あるとしたらどんな場所なのか?」「永遠の業火に焼かれるというのは厳しすぎるのではないか?」など、いろいろ気になるところがありますよね。
そこで今回は、キリスト教における地獄とはいかなる場所なのかについて考察していきたいと思います。
天国・地獄がはっきりしていないキリスト教
要は、「あの世はどうなっているか?」ということですが、天国/地獄以外にも、キリスト教特有の「煉獄(れんごく)」の思想もありますね。
*ただし煉獄はプロテスタントでは認められていません。
実際のところ、聖書の情報からは、天国・地獄・煉獄については、ハッキリした記述がほとんど見当たりません。
とくに「煉獄」についての直接の言及はない、と言ってもよろしいかと思います。
聖書で、天国/地獄について語られる場合、たいていは、「終わりの日」、つまり、「最後の審判」と関連して語られています。
*参考記事:最後の審判はいつ来るのか? – 相対的終末と実存的終末

たとえば、
(「終わりの日(最後の審判)」に、)
「人の子は栄光に輝いて天使たちを皆従えて来るとき、その栄光の座に着く。(中略)羊飼いが羊と山羊を分けるように、彼らをより分け、羊を右に、山羊を左に置く。そこで、王は右側にいる人たちに言う。『さあ、わたしの父に祝福された人たち、天地創造の時からお前たちのために用意されている国を受け継ぎなさい。(中略)
それから、王は左側にいる人たちにも言う。『呪われた者ども、わたしから離れ去り、悪魔とその手下のために用意してある永遠の火に入れ。(中略)』こうして、この者どもは永遠の罰を受け、正しい人たちは永遠の命にあずかるのである。」(「マタイによる福音書」25章31-46節)*太字は高田
このように、ストレートに読む限りでは、
- 天国・地獄は「終わりの日」「最後の審判」に関連付けられているらしい
- 天国・地獄が果たして、「あの世」のことなのか、ハッキリしていない
- 祝福された人は永遠の命で、呪われたものは永遠の罰、ということで、けっこう極端
というのが第一印象ですね。
特に、3番めの、「永遠の罰」(=永遠の業火)がなんとも厳しすぎる、「これは、神の無限の愛に照らし合わせてどうなのか?」ということが歴史的にも議論されてきたところで、
ココが厳しすぎるがゆえに、信者は罪の意識で苦しみ、一般の人は「とても信じられない!」という方向へ行きがちでしょう。
結果、「中間領域」としての「煉獄(れんごく)」が登場することにもなったわけですけどね。
煉獄は、「地獄へ行くほどの罪ではないが、天国へ行くために火の浄化が必要な魂」のために設定された場所です。
ここで罪を償えば、魂が浄化され、天国へ昇っていけるようになるわけですね。
ちなみに、煉獄の他には辺獄(へんごく/リンボ)という場所も考えられました。
辺獄は、イエス・キリスト以前に生きていた人たちのための場所です。
徳が高い人達であっても、当然、洗礼は受けていないわけで、でもかといって、「地獄へ落とすのは忍びない…」ということで、辺獄が設定されました。
*あるいは、受洗前に亡くなった幼児たちも辺獄へ赴くとされました。
なので、旧約に登場するアダムやイブ…などのイエス以前の有名人たち(長老たち)は、ここの辺獄に住んでいると思われたわけです。
そして、イエスが、十字架刑のあと3日後に復活するまでの間、冥府に下っていたのは、辺獄の住人たちを天の国へ引き上げるためであった、という理解の仕方もでてきました。

キリストがアダムとイブを天国へ引き上げようとしているところ
話を戻して、煉獄ですね。
煉獄については、聖書の記述の中には根拠が見つからないんですよね。「ここだ!」という人もいるのですが、ちょっとこじつけっぽいと言いますか…。
煉獄の根拠として挙げられているものに、たとえば、次の文章があります。
(前略)なぜなら、かの日が火とともに現れ、その火はおのおのの仕事がどんなものであるかを吟味するからです。(中略)その人は、火の中をくぐり抜けて来たもののように、救われます。(コリント1:10-14)*太字は高田
ここの箇所では、「火」というのは、「永遠の業火」ではなくて、「くぐり抜けて…救われる」という文脈になっています。
なので、「永遠の業火ではない、浄化の過程としての火がある」ということで、これが煉獄の根拠になっているわけです。
しかし、この解釈は無理くりと言いますか、ちょっと分かりにくいですよね。
また、じゃあ「煉獄」という中間領域が設定されたから、上述の「酷さ」が解消されたかと言うと、そうでもなくて、「呪われたもの」(つまり、イエスを信じない者)は、やっぱり、「永遠の罰」「永遠の業火」ということで、
やはりどうしても、「神の無限の愛に反しているのでは?」という疑問点は解消されていません。
そういうわけで、また別の考え方として、
「地獄というのは、つまり、煉獄である」と解釈したほうが良いのではないか?という思想も出てきました。
いわば、仏教で言うところの地獄が、キリスト教で言う煉獄に相当する、ということです。
仏教の地獄は、「六道輪廻」というくらいで、地獄に堕ちてもまた輪廻して別の世界へ赴くとされていますので、「永遠の罰」ではないわけです。
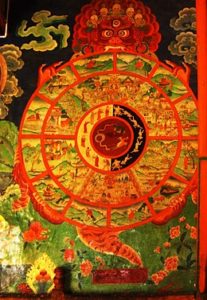
結論的には、この解釈が一番スッキリすると思います。本当は、ですね。
つまり、
天国 – 煉獄 – 地獄
ではなくて、
天国 -煉獄
の二元論の考え方です。
この考えの方が、ネオ仏法的にもスッキリします。
煉獄は火の試練はあるけれども、それは魂の浄化の過程であって、いつかは天国へ戻れる。ということなので、希望が持てますよね。
しかしやはり…上に引用したとおり、イエスの言葉として、「永遠の罰」というのがハッキリと言われていますからね、聖書に基づく限りは、やはり、「地獄」も認めざるを得ない、ということになるでしょう。キリスト教の文脈では。
で、結局、キリスト教においては、人は肉体の死後、どうなるのか?ということを纏めてみますと(まあ、これはひとつの纏め方です。”キリスト教”と一口にいっても宗派によって解釈が異なります)、
- 死後、”一時保留的”な天国・地獄・煉獄・辺獄のいずれかに赴く
- 「終わりの日」にイエスが肉体を持って再臨する
- 死者に肉体がふたたび与えられる
- 天国に入る人と入らない人を分ける(審判)
- 天国に入る人(救われる人)は「イエスを信じ、イエスの復活を信じた人」、および、「煉獄で魂の浄化を済ませた人」である
- 天国に入る人は、永遠の生命を与えられる。入れない人は永遠の死が待っている。天国へは肉体のまま赴く。中間領域としての煉獄は(役目を終えて)解消される
と、こんな感じになるでしょう。
「肉体のまま」というのがなんとも抵抗のあるところで、これは、「イエス・キリストの”肉体の復活”は事実か?アストラル体で解読する」の記事でもやはりそうでしたね、肉体としての復活という解釈です。
「肉体のまま」とか「肉体を与えられて」では、これは結局、「この世のことでは??」ということになりますので、
じゃあやっぱり、あの世がよく分からない…、というふうに、疑問点がぐるっと一周回って同じところに来てしまいます。
それから、別の論点として、
「そもそも、イエスの受難で全人類の罪が贖われたはずなのに、なぜまた罪が問われる?」というのもありますね。
こんな感じで、キリスト教の教義というのは、理性に照らし合わせてみると、なんとも面妖と言いますか、スッキリしないものが実に多いですよね。
で、こうした疑問を神父さんや牧師さんに聞いても、最終的には、「被造物である人間では、神の全能性・超越性は理解することはできない」ということで、「ただ、信ぜよ!」という世界に行ってしまいます。
もちろん、私にしても、人間の理性で全能の神(ネオ仏法的には、「真実在」)は把握しきることはできない、ということには賛成なのですけどね。
イエスの対機説法
なので、「天国/地獄論」からはちょっと離れるようではありますが、「なにゆえに、聖書および聖書から解釈されている神学が難しくなるのか?」ということを考えてみたいと思います。
文学者・詩人としてのイエス
キリスト教がこれだけ全世界的に拡がっているのには、単純に、近現代では欧米圏が政治・経済的に力を持ったから、というのもありますが、
もうひとつは、「イエスの言葉が感性にひびく」「生きづらいこの世においてなぐさめになる」という面が大きいかな、と思います。
実際、仏典やクルアーン(コーラン)に比べても、イエスの言葉は、詩的と言いますか、感性にとても響いてくる美しさがありますね。
一方、詩的表現にありがちな「極端な表現」がどうしても多くなり、結果、誤解を招きやすいというデメリットもあります。
地獄の永遠性についても、聖書にいくつかの記述があります。
もし片方の手か足があなたをつまずかせるなら、それを切って捨ててしまいなさい。両手両足がそろったまま永遠の火に投げ込まれるよりは、片手片足になっても命にあずかる方がよい。(「マタイによる福音書」18章8節)
呪われた者ども、わたしから離れ去り、悪魔とその手下のために用意してある永遠の火に入れ。(「マタイによる福音書」25章41節)
これらの、「永遠の火」も詩的表現という側面から考えたほうが良いと思います。
まあ、恋愛の場面でも、「永遠に愛します」とか言ったりしますよね。「ほんとかな?」みたいな。
しかしこれは、文字通りの「永遠」というよりは、「ずーっとあなたと一緒にいたい」という”今”の実存的な感情を詩的に「永遠」と表現したものでしょう。
言われる方も、そういうことは了解済みの上で、かつ、「詩的に言われたほうがひびく」ということで感動するわけですよね。
それと同じこと、と言ったら聖書に失礼かも、ですが、
やはり、「永遠の火に入れ」とか「永遠の命にあずかる」というのも、やはり、詩的に解釈すべきで、
神・キリストの尺度によって測られる「魂の喜び」、その反転形としての「罪」というのは、実存としての人間にとって、「永遠とも思われるくらい」の差がでてくるのだ、ということなんです。
仏陀・釈尊も似たようなことをおっしゃっています。
耳ある者どもに甘露(不死)の門は開かれた。(南伝・相応部経典:6-1 勧請)
これは、「(縁起の)真理を悟ることによって不死を得られる」ということであるのですが、
かといって、「じゃあ釈尊が悟る前は、不死じゃなかったの?」ということにはならないわけです。
あくまで、個の実存として、「人生の生老病死の苦しみの渦中にあるときは、”死”は文字通り死と思われて恐怖におののいていたが、仏法を悟ることによって、この苦しみを克服することができる」という意味ですよね。
要は、対機説法の一種として、(極端にも思われる)詩的表現が使われることがある、ということです。
*対機説法(たいきせっぽう):相手の機根に合わせてさまざまな説き方をすること
禅の問答でも、
- 問い:「仏とはなんぞや?」
- 答え:「糞をかき取るヘラだ!」
という問答があります(無門関第14問)が、
まあ、”美しい”表現ではないですけど(笑)、こういうふうに「極論に思えること」を相手にぶつけて、真理を悟らしめるという方法がとられることがあります。
この例では、「仏」とか「真理」というと崇高で美しいものばかりを思い描くけれども、世の中には一見、悪とか汚いものもあるわけですよね。
しかし、仏が実在であるならば、文字通り、「実在はすべてをおおう」ということで、「糞をかき取るヘラ」もやはり、仏=実在の現れのひとつ、ということになるわけです。
なので、「真実在は、現象的な”きれい/きたない”という分別智を越え、かつ総合した存在であるのだ」と、悟らしめるために、あえて、「糞をかき取るヘラだ!」と対話者にぶつけているわけです。
ただ、文字通り、仏=糞をかき取るヘラ、という図式にしてしまうとまた変な世界に行ってしまいますけどね(笑)。まあ、対機説法の一環としてこういう説き方があるということです。
なので、宗教家と同時に詩人・文学者としての資質が高かったイエスの説法の仕方として、こうした対機説法的な方法ですね、
「極論に聞こえるような言葉をあえて対話者にぶつけることで、真理を悟らしめる」という説法がよくなされていた、ということです。
やはり、逐語的にいちいち「そのまんま」受け取るとおかしなことになる表現が聖書には他にも沢山あります。
まあこういう解釈の曲がり方は、宗教が耐用年数を迎えるときによく起きる現象でもありますけどね。
釈尊は無我を説いたのだから、「我はない」イコール「魂はない」というふうに曲がって解釈されるのも同じ原因です。
*参考記事:仏教は霊魂を否定していない – 無我説解釈の誤りを正す
「言葉のまんま」受け取って、真意を読み解こうとしない、あるいは、「魂はないと思いたい」という意識からそういう解釈がでてくるわけです。
ほぼ3年しか時間がなかったイエス
上記のことにも関連しますが、イエスの場合は、体系的な教えを説けるだけの時間もなかった、という側面もあります。
伝道期間がほぼ3年しかありませんので、45年間も法を説いた釈尊のように体系化された教えを説くのは難しいでしょう。
ゲッセマネの園で、イエスは以下のように祈っています。
父よ、できることなら、この杯をわたしから過ぎさらせてください(マタイ26:39)

これも、「人間イエスが垣間見れる」と解釈する人もいますが、そうではないのです。
いまさら死を恐れているわけではなくて、
「旧約の預言との連続性を実現する」あるいは「アガペー(神の愛)。犠牲愛のひとつの手本を示す」ために、あえて十字架にかかるとはいえ、本当にそれで真理が伝わっていくのだろうか?という問いかけ、と解釈すべきです。
実際、イエスに付き従う群衆は多かったものの、「病気を治してほしい」とか、「奇跡を見たい」という人がほとんどでしたからね。教えそのものがどれだけ伝わっているのか?後世に本当に残るのか?
また、イエス在世中には十二弟子たちの信仰と理解度も心もとなかったわけですから。
「本当にこのシナリオでよろしいのでしょうか?」という問いかけがあったのです。
もちろん、イエスは上記の言葉に続けて、
しかし、わたしの願いどおりではなく、御心のままに。(マタイ26:39)
と続けていますので、当然、「父なる神への不信」であるわけはありません。
”聖書解釈”は当然に認められて良い
ここまで、「解釈、解釈」と何度か述べてきましたが、「そもそも聖書を解釈するなんて!」と思われるクリスチャンもいらっしゃるかもしれません。
しかし、カトリック教会・聖公会・ルーテル教会・正教会・非カルケドン派において”聖人”に列せられている、古代の教父アウグスティヌスは、主著のひとつである『告白録』のなかで、
彼の師であるアンブロシウスの「文字は殺し、霊は生かす」という教えに感激し、
文字通りに取れば、邪悪なことを教えているように見える聖書の箇所を霊的に解釈して、神秘の覆いを取り去り、そこの意味をあきらかにしてくれた(『告白録』第6巻第4章-6)
と、ハッキリ”告白”しております。
天国- 煉獄の二元論/魂の復活で良い
そういうわけで、今回は、「天国/地獄論」にとどまらないところまで話が行ってしまいました。
トピックのまとめとしては、
- キリスト教で言うところの”煉獄”が、実際の地獄の真相に近い
- 「永遠の業火」ではなくて、あくまで「魂の浄化の過程としての地獄」があり、「悔い改め」によって魂は天国へ還っていくということができる
ということです。
この点、イザヤ書の聖句をそのままに受け取るべきです。
わたしは、とこしえに責めるものではない。永遠に怒りを燃やすものでもない。(「イザヤ書」57章16節)
それから、
「肉体による復活」というのはですね、別の記事でお話したように、エジプトの復活信仰が混じり込んできたもので、実際は、「魂としての復活」が正解です。
*参考記事:イエス・キリストの”肉体の復活”は本当か?アストラル体で解読する
こうした「霊的生活への移行」ということは、キリスト教を正しく思惟した人(あるいは体験した人)には分かるもので、
たとえば、カール・ヒルティは『幸福論 第3部』のなかで以下のことを言っています。
人格の復活ということは、キリスト教の与える最も決定的な約束の一つである。(中略)もちろん、それは、キリスト教の信仰箇条にいうような言葉どおりの意味での「肉体の復活」ではない。(超越的希望:3節)
私は永生を確信している。(中略)ただしそれはこの世の生活の最も清純な瞬間に似ているであろう。そして、全然ちがった精神状態へいきなり飛躍するようなものでは決してなく、一種の継続というべきものであるのは確かであろう。そこでは各人は、現世においてそれを受ける資格を得たものだけを受けることができるのである。(同上:4節)
これらはおそるべき洞察と言えると思います。
このように考えてこそ、キリストが同じ十字架刑にかかった犯罪人のひとりに言った言葉の意味がはっきりと分かるようになります。
「イエスよ、あなたの御国においでになるときには、わたしを思い出してください」と言った。するとイエスは、「はっきり言っておくが、あなたは今日わたしと一緒に楽園にいる」と言われた。(ルカ23:42-43)*太字は高田
この「犯罪人」は”肉体として今日”復活するわけはないので、文脈としてはやはり、魂としての復活ということです。
すなわち、この「犯罪人」の心境が天の国にふさわしいものになったので、ヒルティ的に言えば、「この世の生活の最も清純な瞬間に似ている」来世へ移行する、ということですね。
もっとも、「わたしといっしょに」の部分は、まあ、イエスと同じ天国の階層にまで還れるとは思えませんので、ここも一種の誇張といいますか…、イエスの説法はどこまでも詩的・文学的なのですけどね…。
今回はずいぶん長文になりましたが、キリスト教の文脈ではなく、「とにかく、この世とあの世はどういう関係になっているのか?」を、かんたんに知りたい方は、ぜひ、人生の意味とミッションとは?をお読みください。



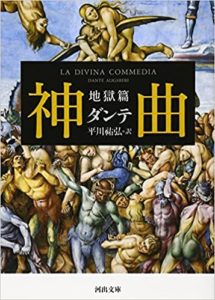
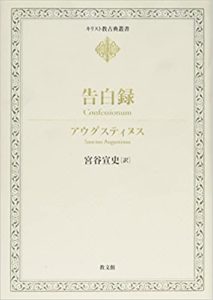
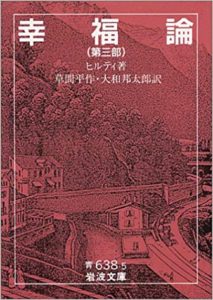
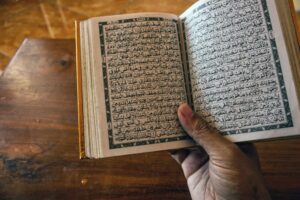







コメント