「”南無阿弥陀仏”と唱えるだけで救われるのは本当なのか?」という身も蓋もないテーマを掲げてみました。
”南無阿弥陀仏”と唱える宗派は、浄土宗・浄土真宗・時宗などの文字通り浄土系ですね。仏教の中でも、浄土系は”信者数”では圧倒的にトップです。
葬儀・法要・仏壇前の読経などでもよく唱えられますので、日本人には馴染みの深い念仏でしょう。
*令和元年の宗教統計調査結果でも、仏教系信者数4793万人のうち、浄土系が2221万人と、約半数近くを占めていました。
ちなみに、仏教の唱名(しょうめい/仏の名を唱えること)は、宗派によって違います。まとめると、下記のとおりです。
- 南無阿弥陀仏(なむあみだぶつ):浄土宗・浄土真宗本願寺派・真宗大谷派・天台宗など
- 南無釈迦牟尼仏(なむしゃかむにぶつ):曹洞宗・臨済宗
- 南無大師遍照金剛(なむだいしへんじょうこんごう):真言宗
- 南無毘盧舎那仏(なむびるしゃなぶつ):律宗
- 南無妙法蓮華経(なむみょうほうれんげきょう):日蓮宗・日蓮正宗
浄土系は宗派によって微妙に解釈の違いはありますが、一言でいえば、「”南無阿弥陀仏”と唱えることで極楽へ往生できる」というシンプルな教えに集約できると言っても良いでしょう。

問題は、「それ、本当ですか?効果あるんですか?」ということで、まあこの問い自体が身も蓋もないところではありますが、「嘘八百」であれば宗教としてマズイだろうということで、今回のテーマとしてみました。
「結論だけ知りたい」という方のために、当サイト(ネオ仏法)の結論だけをさきにお伝えしておきますと、
- 真正な信心(信仰心)をもって”南無阿弥陀仏”と唱えれば、ほぼ救われる(=極楽往生できる)と言っても良い
- 極楽浄土といっても、実はいくつか段階がある
と考えています。
以下、「”南無阿弥陀仏”と唱えれば救われるのか?」というテーマで、ある程度、歴史的・学問的な側面と、今一つは霊的な側面から考察していきます。
”救われる”とは何か? – 極楽浄土と天国は同じなのか?
浄土教の文脈で「救われる」というのは、「来世に極楽浄土へ往生すること」です。
そうすると、「極楽(浄土)と天国って同じなの?」と疑問に思われる方もいらっしゃるでしょう。
結論的には、「ほぼ同じ」と考えて良いと思います。このように結論づけると、多少とも仏教の勉強をした方からお叱りを受けそうですが。
大乗仏教の理想は、「仏陀になって衆生を救済すること」
”仏教学的・宗教学的”には、じつは「極楽浄土と天国は違う」のですけどね。
浄土教も大乗仏教の一派ですので、少なくとも名目的には大乗仏教の理想を追求しているわけです。
で、大乗仏教の理想というのは、一言でいえば「自らも仏陀を目指し、さらに衆生救済にいそしむこと=菩薩になること」です。いわゆる、”自利利他(じりりた)”です。

菩薩像
仏陀になるためには、仏陀から「あなたもいつかは仏陀になりますよ」というお墨付き(記別(きべつ)と言う)が必要とされています。
ところが仏陀・釈尊はもうこの世界にはいらっしゃらないわけですから、どこか別の世界を想定してその世界の仏陀からお墨付きを受けようと考えたわけですね。
その「どこか別の世界」のひとつが極楽浄土なのです。極楽はいくつかある浄土のうち、阿弥陀仏(あみだぶつ)が主宰している浄土です。
他にも阿閦如来(あしゅくにょらい)の妙喜国とか色々ありますが、阿弥陀如来が一番人気なので、「浄土といえば、極楽」というイメージになっているわけなのですね。
ちなみに、鎌倉の大仏は阿弥陀仏です。

鎌倉大仏
「仏陀になるための”特進クラス”」が極楽浄土
要は、「(末法の世では)この世で仏陀になるのはほぼ無理筋なので、極楽浄土という”仏陀になるための特進クラス”に行きたいです」というのが、本来の”極楽往生”であり、その特進クラスの場が”極楽浄土”なのです。
しかし、現実問題として、”南無阿弥陀仏”と唱える一般信者が「仏陀になろう(いわゆる、俗語としての”成仏”とは違う意味で)」と真剣に考えているとは思えません。
やはり、「来世で美しい安らぎのある世界に還りたい」ということで、極楽浄土を想定していらっしゃることでしょう。
極楽が”特進クラス”であるかどうかは別として、世界としては「美しい安らぎのある国」であるのは事実と思われますので、冒頭の結論、「極楽と天国は同じ」ということになるわけです。
私が観るかぎりでは、極楽浄土に行って「仏陀になるためのスパルタ教育(?)」が始まっているか?というと、そんなことはない、という感想です。
実際は、極楽浄土にもいくつかの段階があり、その点は後述しますが、一般民衆が還っていく極楽浄土は、ほぼキリスト教的な天国のイメージに近いと言っても良いと思います。

だだ、阿弥陀経に書かれているような風景、これは現代からみると随分古い情景ですね、「善福寺」のサイトに読み下し文が記載されていましたので、リンクを貼っておきますが、
*和文の阿弥陀経(「善福寺」サイト)
このような情景が現代でもそのまま…というわけでもないと思います。
霊界というのは、価値観や想念が”情景”として翻訳されてくる世界ですので、現代人が極楽に往生するとしたら、まあUSJがあるのかどうかは分かりませんが、もっと現代的な風景になっていると思います。
”南無阿弥陀仏”とは何か?
次に、そもそも”南無阿弥陀仏”とは何か?ということについてお話してみたいと思います。
南無阿弥陀仏をサンスクリット語から解釈してみる
”南無阿弥陀仏”をもともとのサンスクリット語に直すと、”namo amitaayus(ナモ・アミターユス)”もしくは、”namo amitaabha(ナモ・アミターバ)”となります。
”ナモ”は、尊敬・敬意を表す言葉です。ここから、「帰命します、帰依します」という表明を意味するようになったのですね。
”アミターバ”は「無量光」、”アミターユス”は「無量寿」という意味です。無限の光明と無限の寿命、どちらも如来の属性です。ここから”アミター”の部分が「阿弥陀」と音写されたわけです。
なので、原語から意味を探ると、
- 南無阿弥陀仏:阿弥陀仏に帰依します
となります。
いわば、「信仰告白」ですね。
阿弥陀仏の起源は?
学問的な起源
阿弥陀仏とはなにか?その起源については諸説あり、学問的・文献学的には確定していないようです。
おおまかには、
- 西方起源説
- インド内部起源説
があります。
西方起源説はなかなかロマンをかきたてる面がありますね。ゾロアスター教の善神(光明神)アフラ・マズダーが原型になっているとか。あとは、ミトラ教・キリスト教の影響を指摘する学者もいます。
インド内部起源説では、さらに
- ビシュヌ神などヒンズー教(バラモン教)に起源を求める説
- 仏陀・釈尊に起源を求める説
があるようです。
梶山雄一教授は、ゾロアスター信仰の”最後の審判”論と浄土教の”末法思想”の類似点などに言及しつつ、
ゾロアスター教との多くの類似は、本来は同根であったインドとイランのアーリア文化に潜在的にあった共通要素が、西暦紀元前後の両文化の激しい交流を経て、後一世紀のインドにおいてめだって顕勢的になった、というのがおそらくもっとも妥当な見方であろう。(『大乗仏教の誕生』梶山雄一著)
と結論づけていらっしゃいます。
いわば、先の西方起源説とインド内部起源説の折衷案ですが、私もこのあたりが妥当であろうと思っています。
霊的な起源
霊的な起源についてはもちろん学問的に実証できません。
浄土系に関わった学僧、日本では空也、源信、法然、親鸞、唯円、一遍、蓮如などが有名ですが、私は、これらの方々は魂の出自としてはキリスト教の霊人だと思っています。
仏教の流れは大まかに、聖道門(しょうどうもん)と浄土門に分かれます。これは中国の学僧、道綽(どうしゃく)による分類です。
分かりやすい言葉で言えば、
- 聖道門:自力
- 浄土門:他力
ということですね。
釈尊の時代はやはり、自力による修行論が中心であったことは間違いないと思います。そして、釈尊没後、部派仏教の時代を経て、大乗仏教が登場してきました。
ネオ仏法では、大乗仏教の興隆については、根本には実在界の釈尊による計画・指導が働いていると考えます。
ここらへん、繰り返しますが、まったく学問的には実証できないところなのですけどね。
ただ、釈尊が般涅槃(はつねはん)をしたあとに、釈尊の魂がどこにいらっしゃるのか?生命体として存続しているのか?ここの涅槃論が仏教者および仏教学の流れではほとんど顧みられることはありません。

*般涅槃:生前に悟りを開いた(涅槃の境地を得た)人が肉体の死を迎えること
一応は、”仏身論(ぶっしんろん)”として、まずは法身・色身(ほっしん・しきしん)という分類はなされています。
- 法身:仏陀・釈尊の本来のあり方、永遠の理法としてのあり方
- 色身:歴史的に地上に現れた釈尊
ということですね。
般涅槃後の釈尊は、地上にはおりませんが、”法身”としての存在になっているわけです。
ただどうも、”法身”というのが、理法そのものであり、「意思を持った生命体であるのか?」という論点が欠けているように思われます。
ここは涅槃論に関わるところです。今回はここのところ、深入りしませんが、当サイト(ネオ仏法)では、「法身としての仏陀は理法としての存在であるだけではなく、意思をもった生命体である」と考えています。
そして、仏陀が慈悲の存在であるならば、般涅槃したあとも、当然、地上の仏教の動向にも関心を持たれ、指導を行っておられるはずです。
歴史的釈尊の時代には力点としては自力中心でしたが、仏教が世界宗教化する流れの中で、いわば、キリスト教的な絶対神・他力・救済という流れを補完的に作ろうとされたのですね。
この流れのひとつが、浄土教なのです。
法身としての仏陀、これは名前としては宗派によって違うふうに呼ばれています。法華経における”久遠実成の仏陀”、華厳経における”毘盧遮那仏(びるしゃなぶつ)”、密教における”大日如来”などです。
この”久遠実成の仏陀”が大乗仏教のなかで、他力的側面を先鋭化して現れたのがまさに”阿弥陀如来”ということになります。
もっと有り体に言えば、阿弥陀如来はイエス・キリストのことであると思います。
なので、キリスト教に関わった霊人が東方(中国・日本など)に転生して、浄土教として教えを弘めたという経緯です。私はそのように観ています。
ですから、実質的には以下の等式が成り立ちます。
南無阿弥陀仏=主よ、信じます
なのです。
結局、”南無阿弥陀仏”と唱えて救われる?
それでは、結局、”南無阿弥陀仏”と唱えて救われるのか?
根拠となる経典とその解釈をチェックしつつ、さらに、ネオ仏法ではどのように観ているのか、順に述べていきます。
『無量寿経』の第十八願が救いの根拠
救い(極楽往生)の根拠は浄土三部経のひとつ『無量寿経』の第十八願を中心に解釈されています。
阿弥陀仏がまだ修行中の法蔵菩薩(ほうぞうぼさつ)の時代に下記の誓願を立てたのです。
<読み下し文>
たとひわれ仏を得たらんに、十方の衆生、至心信楽して、わが国に生ぜんと欲ひて、乃至十念せん。 もし生ぜずは、正覚を取らじ。 ただ五逆と誹謗正法とをば除く。
<現代語訳>
わたしが仏になるとき、すべての人々が心から信じて、わたしの国に生れたいと願い、わずか十回でも念仏して、もし生れることができないようなら、わたしは決してさとりを開きません。ただし、五逆の罪を犯したり、仏の教えを謗そしるものだけは除かれます。
で、今実際に、悟りを開いて”阿弥陀仏”になっているということは、その誓願が本願(=叶ったということ)になったということである、という解釈です。
そうすると、「心から信じて、わたしの国に生れたいと願い、わずか十回でも念仏」すれば、極楽浄土へ往生できる、ということになるのですね。
もっともここに微妙なすり替えといいますか、解釈の余地はあります。
元もとの読み下し文では「至心信楽して、わが国に生ぜんと欲ひて、乃至十念せん」と書かれています。
それが現代語訳、これは法然や親鸞などの解釈を経たあとの翻訳ですが、「すべての人々が心から信じて、わたしの国に生れたいと願い、わずか十回でも念仏して」となっています。
ここで問題になるのが、大きくは、
- 「心から信じて」がどの程度のものなのか?
- 乃至十念せんというのは、”南無阿弥陀仏”という口称念仏(くしょうねんぶつ)のことであるのか?
という論点です。
とくに、「十念」とはなんぞや?というところですね。
”念”はたしかに”念仏”で良いのですが、じつはもともとの念仏は口称念仏(口で唱える念仏)のことではありませんでした。
ここのところの歴史的経緯について語っていると、ものすごく長くなってしまいますので、今回は詳述しませんが、要はもともとの念仏とは観想念仏(かんそうねんぶつ)が中心である、という解釈だったのですね。
観想念仏とは、「仏の相好や浄土の様子を心にこらし、その姿や相を想い描くこと」という定義です。
これはもう瞑想の範疇に入りますので、けっこうな自力といいますか、難易度が高くなりますよね。
一方、口称念仏も認められていはいたのですが、それは機根の劣った人のいわば「入門編」(加行(けぎょう)と言います)と位置づけられていたのです。
それが、中国は唐の時代の善導(ぜんどう)という僧が、いろいろと理論を操作して、「念仏とは口称念仏のことである」としたのです。

その善導の解釈を踏襲したのが法然です。
法然は「偏依善導(へんねぜんどう)」というくらい善導に傾倒し、善導の解釈を踏襲しつつ、さらに深めました。
どのくらい「深めたか」というと、
- 口称念仏が最も優れている(勝劣の義)
- 口称念仏が最も易しい(難易の義)
という判定です。
「勝(すぐ)れていてかつ易しい」という…なんだかネットビジネスの「かんたんに月収100万稼げます!」みたいな語感がないでもないですが、要は口称念仏が「ベスト中のベスト」ということですよね。
このように次々と判定して絞り込みをかけていく手法を”選択(せんちゃく/せんじゃく)”と言います。なので、法然の主著は『選択本願念仏集』となっているわけです。
然ればすなわち弥陀如来、法蔵比丘の昔、平等の慈悲に催され、普く一切を摂せんが為に、造像起塔等の諸行を以て、往生の本願としたまわず。ただ称名念仏の一行を 以て、その本願としたまえるなり」(『選択本願念仏集』第三章)*太字は高田
「ただ称名念仏の一行を以(もっ)て」と書かれていますよね。念仏だけに専念する、これを”専修念仏(せんじゅねんぶつ”と言います。
*法然、親鸞、日蓮…など、鎌倉期の新宗教はこの”専修”、つまり、「仏道を絞り込み、それだけに専念すること」だと言っても過言ではありません。
もっとも、”南無阿弥陀仏”の口称念仏をどのように位置づけるか?については、法然・親鸞・一遍…などで微妙に解釈が違います。
もともとの第十八願では、念仏の前に「すべての人々が心から信じて、わたしの国に生れたいと願い」と入っていますので、素直に読めば、ここもまた自力の要素が入ってきて、難易度が高くなりそうです。
その問題については、かんたんに言えば、
- 法然:口称念仏すれば、そうした”心”、”信”は自ずと備わる
- 親鸞:”信”の時点ですでに往生が決まっている。口称念仏はいわば感謝の表出である
- 一遍:南無阿弥陀仏という六字の”名号(みょうごう)に往生の功徳が込められている
という解釈の違いはあります。
親鸞の解釈では、現代的に言えば、「救いは信仰のみによる」ということで、これはパウロやルターとほぼ同じことを言っています。
また、この「信仰」すらも阿弥陀仏の賜物であるということで、徹底的に自力の要素を排除していきます。
一遍まで行くと、ほとんど真言といいますか、言霊信仰に近いものがありますけどね。
信仰による救いは仏陀・釈尊の時代にもないでもなかった
こうした信心による極楽往生というのは、オリジナルの釈尊の教えではないではないか…というと、それはその通りなのかもしれませんが、初期仏教にもそうした考えの萌芽はあります。
執着を絶ち、苦しみ・迷いの娑婆世界におサラバすることを”解脱”と言いますが、この解脱にもいくつかの種類があるとされていました。
そのうちの一つが”信解脱(しんげだつ)”と言われるものです。
これは文字通り、「信心による解脱」という意味です。
実際に、信心だけで仏陀(もしくは阿羅漢)になれるのかどうか?という論点は別にありますが、少なくとも、仏陀への道に入ることはできるのですね。
そうすると、これは大乗仏教的に翻訳しなおせば、立派な菩薩であるということになりますので、来世は極楽(的な世界)へ往生することは可能だと思われます。
極楽にはいくつかの段階がある
さきに、「極楽はほぼ天国と同じ」と申し上げました。
来世(あの世)の世界については、当サイト(ネオ仏法)では、十界論(じっかいろん)という分類を採用しております。
詳しくは下記の記事を参考になさってください。
*参考記事:十界と十界互具 ー 仏教における”世界”の階層構造論
要は、「天国と地獄」と一口にいっても、実はいろいろな段階に分かれている、ということです。
さきに、「極楽浄土は実質的には天国と考えて良い」と申し上げましたが、…ということは、「極楽にもいくつか段階がある」ということになるわけですね。
やっぱり、ふつうに考えても、法然や親鸞のような高僧と、悪行はけっこうあったが臨終間際に「南無阿弥陀仏」と改心して唱えて、ギリギリセーフでという人が同じ極楽に、というのは、あまり公平ではないですよね。
さきの十界論で行けば、人界のあたりから一応は天国領域に入りますので、少なくともこの世に比べれば美しく、快適な世界ではあります。
なので、往生した側からみても「文句なし」ということにはなると思います。
しかしやはり、「口だけ念仏」では駄目だと思います。
法然の思想にしても、「南無阿弥陀仏と唱えていれば、信心は備わってくる」というふうに、これはいわば、「行為が思いに影響を与える」ということですよね。
なので、いまだ”思い”に影響がない段階ではやはり極楽往生は無理筋だと考えたほうが良いです。
悪の限りを尽くしてきたが、「まあ一応、唱えておきますか」くらいではやっぱり無理です。
浄土宗ではとくに、”悪人正機説(あくにんしょうきせつ)”という思想がありますけどね。
善人なおもて往生をとぐ,いはんや悪人をや
という『歎異抄(たんにしょう)』に収められている親鸞の言葉が有名です。
ただ、この”悪人”というのは、「自分は、自力では戒律を守りきるなどは到底不可能な凡夫である」という深い内省、その自覚を持っている人のことを言うのです。
これは、聖書でイエス・キリストが述べている
わたしが来たのは、正しい人を招くためではなく、罪人を招くためである(「マタイによる福音書」9章12-13節)
という言葉とまったく同じ内容なのです。
これはまさに悪人正機説ですよね。
このイエスの言葉も、文字通りに「罪人のほうが天国に有利」という意味ではなく、「自分は善人である」という一種の道徳的傲慢さにある人よりは、「神の物差しからみれば自分は罪人である」という内省がある人ですね、こういう人のほうが天の国に入る資格がある、という意味です。
なので、悪人正機説というのは、「悪人のほうが有利だし、まああとで”南無阿弥陀仏”と唱えればオッケーなんだから」ということでは全然ないのですね。
少し深い話になりますが、「悪をなし得る」というのもまたひとつの道徳的傲慢さである、という考えも成り立ちます。
「悪をなし得る」という考えの根底にあるのは、「自分は意志の力で善も為せるし、悪も為せる」という一種の”自由意思万能論”ですよね。
そうではなく、この世において、「善をなしたいと思いつつも、ついに、罪なくして生きていくことはできない平凡な自分」というフラットな自覚が大事だということです。
ただ、そうは言っても、話を戻しますが、法然・親鸞などの高僧と、「土俵際うっちゃりでギリギリ極楽」という人とでは、”極楽度”に差があるのは当然です。
仏教では「差別(しゃべつ)と平等」という言い方をしますけどね。
- 平等:仏性を有しており、それを顕現させていく機会の平等
- 差別:どれだけ智慧の獲得と慈悲の発揮をなしたか、という結果
この2つの視点が必要なのです。「差別知と平等知」ということです。
なので、仏陀の意思をトータルで見れば、やはり、”自力”も大事ということになるのですけどね。
ここの「自力と他力は矛盾するのか?両立するのか?」という論点についてはまた別の機会に論じてみたいと思います。
結論としては、
- 「自分は絶対善(仏陀)の物差しからみれば、悪を犯しつつ生きている凡人である」という自己省察をもち(凡夫の自覚)つつ、絶対善(阿弥陀仏)の慈悲力を信じきる心境に至れば、最低限の極楽には行くことができる
- その信心の表明(信仰告白)が浄土系においては”南無阿弥陀仏”であり、口称念仏を繰り返すことによって、また自己省察と信心が深まるという好循環に入ることができる
- 上記の意味では、他力信仰も真実ではあるが、しかし一方、この世において智慧の獲得と慈悲の発揮をどの程度なし得たか?という自力の要素によって、還るべき極楽世界にも段階差がある、という平等知と差別知の2つの視点が大事である
ということになります。

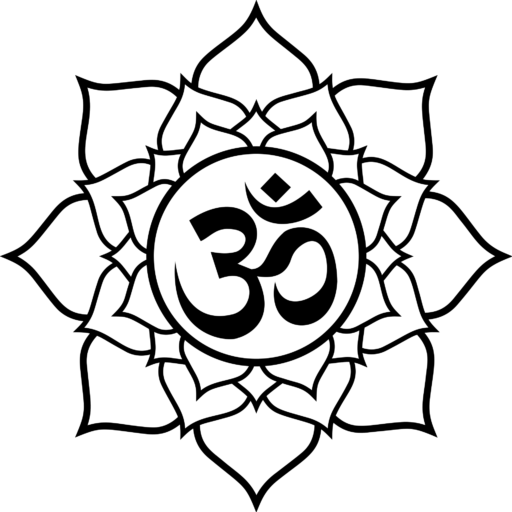


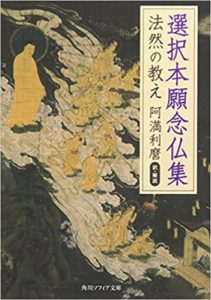









コメント